今週一週間をふりかえって
修正削除 移動 傑作(0)2011/4/3(日) 午前 11:33無題その他災害 Yahoo!ブックマークに登録
今週一週間の原発関連ニュースを振り返って
すごいことが起こってる。
プルトニウムが漏れて微量だから問題ないとかテレビの解説者が話しているがだいじょうぶなのだろうか。続々と出てくる恐ろしい情報が、なにごとも無いように小出しに流れている。
はっきりいって事象が起きていたのは、今ではないことくらいだれも気付いている。東京電力が原因不明と言っていたところを補完する事実が、後追いで少しずつ明らかになっている。
それを隠蔽というのか、今測ったら分かったので已む無いとしていいのか分からないが、事態が深刻となり、汚染の広がりが関東全域に達し、政府・東電が情報をコントロールできないところに来ているからなのか、また、自らの手で事態を収束できなくなり、海外の手を借りるには第3者にも正確に情報開示せざるを得ない状況になりつつあるからなのだろうか、それとも国民を驚かせないようにするためか、情報が小出しに出ている。でも水素爆発という公式発表からあと現場には、多くの政府・東電関係者が、長いこと現場から退避していたわけでもなく、この状況を目の当たりにしていたはずである。
日本人は、忍耐づよいとか、平和ボケかもとかの評を通り越して思考停止に陥っているのだろうか。
建屋のコンクリートを吹き飛ばしても、頑丈な格納容器は2?号機の一部破損を除いて、ほとんど損傷していないというのが、水素爆発という公式発表後の政府見解であり、通電していくらか修理し、冷却機能の回復さえできれば、メルトダウンも防ぐことができ、放射能も封じ込めることができるというのが、楽観的ではあるも期待すべきストーリーであったはずだ。
しかしながら、後追いで出てくる写真や映像は損傷が激しすぎてポンプも何もかも一から新設しないと、どうにもならない状況や、非常用の冷却装置がお釜の中で生きていたとして、かつ通電し、うまく動き出したとしても、3発ともお釜がひび割れて高レベルの放射能を垂れ流していることが分かった現在においては、非常用の冷却装置で冷やすことができても汚染水は垂れ流し放題、根本的に放射能を封じ込めることなど、とうてい出来やしない。
いまいろいろピット?のひび割れをなおしたり、幌を原発にかぶせる?土に樹脂を散布する等なんとなく対策が進んでいるように見えるが、根本的な封じ込めには程遠いように感じる。
政府発表は数ヶ月を目標(←訂正:この時点では、細野補佐官がテレビ番組で発言したようで、その後、官房長官が公式見解でないような訂正をしてました。)になんとか出来るとしているので、僕らが知り得ないミラクルな手法(高レベルの放射能の中で、格納容器や配管の亀裂などを塞いで、放射能をクローズドした状態で冷却ができる?!)を持っているのか、何か確からしい根拠やマイルストーンにもとづいて、それを発表していると信じたいが、もし復旧作業が数年にわたり続くようなら、その間、毒を吐き続けることになるのだろう。
長期にわたり汚染が続くのであれば、CTスキャン一回分やら、レントゲン一回分との被曝量の比較は意味をなさない。レントゲンやCTスキャンは1時間に1回、数年に渡って浴び続けて大丈夫なわけはないであろう。低レベルの放射能によって内部被曝が累積されていく。政府は何の防備も周辺住民に求めず、農家を補償するのを拒否したいためか風評対策にやっきになっているが、その被曝の影響について、知りたくもないが、何の防備もしない人々は人体実験ともよべる医学的には有益なデータを今後提供することになってくる。農業・漁業を止める補償の費用と被曝補償の費用を、天秤に掛けてコストミニマムの計算でもしているのだろうか?すべて場当たり的で、目の前の汚染野菜の農家の補償を回避する火消しにやっきになり、そこまで頭がまわってない気もする。
現在進行形であるが、外部からの冷却作業も止まれば、再臨界や爆発が起こるとも報じられている。なぜ政府は、もっと広範囲の住民を避難させたり関東全域を含め、被曝対策(大気汚染・水・食料)を徹底させないのだろうか。不思議なことだ。
風評被害の補償も大変であるが、近い将来?被曝者による集団訴訟?の補償についても、政府はよく考えないといけないと思う。もし被曝により、もっとも早く影響を受けやすい子供が亡くなることが、万が一あれば、全国の親から相当の恨みを、関係者は生涯買うことになるのだろうか。東電、政府関係者、テレビで大丈夫と合唱する専門家たちは、原告団から厳しく追求されはしないのだろうか。
次の政権であろうが、裁判で一部その責任を国が認めたとしても、その膨大な補償の負担は、最終的に原告でもある国民の増税や、関東の電気料金の値上げという形で賄われるのかもしれない。悲しいことだ。
東京電力は、現場で起こっていることをすべて発表したら、実は人が入ることなどできない汚染エリアで、復旧作業が継続できないと考えて、今まで公表を控えていたのだろうか。関東全域を大汚染させない為に本爆発を防ぐことは、すべてにおいて優先されると思う。そういう理由ならば、いくぶん理解できないこともない・・・・。
でも、それなら、最初から事実をしっかり発表して、逃がせる人を少しでも逃がして被曝する住人を減らすべきだろうし、関東全域の汚染の進行を防ぐ為に、現場の作業員については、国家としても基準値を越えた環境でも作業できるように緊急避難措置として、装備面において作業者の被曝を少しでも減らせるように全力を尽くした上で、どうどうとこれを許容すべきだ。
ロボットを含め、装備を持つ外国に頼ることも必要だろう。作業員やその家族への保障を手厚くし、少しでも安心して作業できるように、決死の英雄たちを、国を挙げてバックアップするべきなのではなかろうか。
海外からも英雄と言われている現場の方々は、国の為に死ぬ覚悟があるかもしれないが、実際は線量の高さも知らされず、劣悪な環境で昼夜問わず働かされているとの報道がされている。大臣が命を掛けている消防士を恫喝したり、むちゃくちゃなことを言ったので、都知事が激怒してクレームしていたが、なにかとてつもなく、おかしなことがおこっているように感じる。
事実とニュースの推移を見守っていても、いろいろなニーズがあって悪い情報を積極的に開示したくない、させないという力学がいろいろな方向から働いているように感じた。
まずは、国民は、関東が汚染される可能性について当然ながら受け入れたくない。自分らが実は被曝し、被害者になる可能性など受け入れられるわけがないという気持ちが、原発推進派の専門家たちの言う安全、たいしたことはないという風評防止?パニック防止?原発推進?を目的とする解説に説得されてしまう。これは、もちろん原発周辺の農業・漁業従事者も汚染で生活ができなくなるので、このような事態は理解できないし、受け入れがたいと思うのは当然であり、考え方は似たようなものとなるだろう。
想定しうるリスクについて説明すれば(いまのところ現実となっているが)風評として切り捨てられる。
一方、東電や政府にしても、最初の爆発で汚染の真実を知らせれば、国の定めた基準に照らせば、現場で復旧作業ができなくなる。すなわち危険だから作業員が現場を放棄すれば、更なる爆発や危機的状況が続く、現在進行形の話であるが。きっと見なかったことにして、損傷の度合いは分からないが、復旧作業に従事させたかったのではないかと想像してしまう。
数年後?10年後に、結果的に逃げ遅れて万が一癌になった関東在住の被害者は、福島原発被曝訴訟を起こすのだろうか。そうなれば、電力会社、政府、専門家も含めて被告になるのだろう。汚染が長期にわたって続くことが確定しつつある。もう下手に安全だとか、問題ないとか言えなくなるように思う。
現実問題として、今後関東の放射能汚染が長期的なものとなるのなら最近触れられなくなったが、大気汚染による内部被曝の蓄積を抑える必要があろう。マスクの徹底、エアコン停止等である。
でもこれから夏場に向けて計画停電も続き、また放射能の大気汚染が続くことになれば、空調を使えなくなる。とてもじゃないがオフォス、家庭問わず猛暑にでもなったら暮らしていけるのだろうか?被曝は、問題先送りで、だましだましいけるとしても、関東で生活することに、電力不足であることは、すぐにでも、いろいろなところで破綻がくるような気がしてならない。
もちろん、現時点で判明している農業、漁業従事者への補償、立ち入り禁止区域の住民への補償、数年後の被曝訴訟への補償、そして何よりも恐れるべき、冷却失敗や想定外?の事象による再臨海や再爆発による更なる汚染の拡大による上記の追加補償(関東全域になれば、もう負担しきれない?!)すべての費用について、税負担や関東の電力料金の値上げに跳ね返ってくるとするならば、関東で暮らすことのリスクと費用が尋常なものでなくなることにならないか。
企業としても、原発問題が政府の宣言どおりに数ヶ月で収束しないのであれば、経済性や社員の安全という観点からも、今後について、いろいろ考えていかなくてはならないのだろう。企業や工場が、いくらかでも西へ引っ越せば電力消費も減って、夏場の計画停電を減らせていいのかも・・・・!?
農家もノウハウや技術があるのなら政府の補償を原資に、思い切って西日本の耕作放棄地へ大移動させるのはどうだろうか?若くないとだめだろうけど
修正削除 移動 傑作(0)2011/4/3(日) 午前 11:33無題その他災害 Yahoo!ブックマークに登録
今週一週間の原発関連ニュースを振り返って
すごいことが起こってる。
プルトニウムが漏れて微量だから問題ないとかテレビの解説者が話しているがだいじょうぶなのだろうか。続々と出てくる恐ろしい情報が、なにごとも無いように小出しに流れている。
はっきりいって事象が起きていたのは、今ではないことくらいだれも気付いている。東京電力が原因不明と言っていたところを補完する事実が、後追いで少しずつ明らかになっている。
それを隠蔽というのか、今測ったら分かったので已む無いとしていいのか分からないが、事態が深刻となり、汚染の広がりが関東全域に達し、政府・東電が情報をコントロールできないところに来ているからなのか、また、自らの手で事態を収束できなくなり、海外の手を借りるには第3者にも正確に情報開示せざるを得ない状況になりつつあるからなのだろうか、それとも国民を驚かせないようにするためか、情報が小出しに出ている。でも水素爆発という公式発表からあと現場には、多くの政府・東電関係者が、長いこと現場から退避していたわけでもなく、この状況を目の当たりにしていたはずである。
日本人は、忍耐づよいとか、平和ボケかもとかの評を通り越して思考停止に陥っているのだろうか。
建屋のコンクリートを吹き飛ばしても、頑丈な格納容器は2?号機の一部破損を除いて、ほとんど損傷していないというのが、水素爆発という公式発表後の政府見解であり、通電していくらか修理し、冷却機能の回復さえできれば、メルトダウンも防ぐことができ、放射能も封じ込めることができるというのが、楽観的ではあるも期待すべきストーリーであったはずだ。
しかしながら、後追いで出てくる写真や映像は損傷が激しすぎてポンプも何もかも一から新設しないと、どうにもならない状況や、非常用の冷却装置がお釜の中で生きていたとして、かつ通電し、うまく動き出したとしても、3発ともお釜がひび割れて高レベルの放射能を垂れ流していることが分かった現在においては、非常用の冷却装置で冷やすことができても汚染水は垂れ流し放題、根本的に放射能を封じ込めることなど、とうてい出来やしない。
いまいろいろピット?のひび割れをなおしたり、幌を原発にかぶせる?土に樹脂を散布する等なんとなく対策が進んでいるように見えるが、根本的な封じ込めには程遠いように感じる。
政府発表は数ヶ月を目標(←訂正:この時点では、細野補佐官がテレビ番組で発言したようで、その後、官房長官が公式見解でないような訂正をしてました。)になんとか出来るとしているので、僕らが知り得ないミラクルな手法(高レベルの放射能の中で、格納容器や配管の亀裂などを塞いで、放射能をクローズドした状態で冷却ができる?!)を持っているのか、何か確からしい根拠やマイルストーンにもとづいて、それを発表していると信じたいが、もし復旧作業が数年にわたり続くようなら、その間、毒を吐き続けることになるのだろう。
長期にわたり汚染が続くのであれば、CTスキャン一回分やら、レントゲン一回分との被曝量の比較は意味をなさない。レントゲンやCTスキャンは1時間に1回、数年に渡って浴び続けて大丈夫なわけはないであろう。低レベルの放射能によって内部被曝が累積されていく。政府は何の防備も周辺住民に求めず、農家を補償するのを拒否したいためか風評対策にやっきになっているが、その被曝の影響について、知りたくもないが、何の防備もしない人々は人体実験ともよべる医学的には有益なデータを今後提供することになってくる。農業・漁業を止める補償の費用と被曝補償の費用を、天秤に掛けてコストミニマムの計算でもしているのだろうか?すべて場当たり的で、目の前の汚染野菜の農家の補償を回避する火消しにやっきになり、そこまで頭がまわってない気もする。
現在進行形であるが、外部からの冷却作業も止まれば、再臨界や爆発が起こるとも報じられている。なぜ政府は、もっと広範囲の住民を避難させたり関東全域を含め、被曝対策(大気汚染・水・食料)を徹底させないのだろうか。不思議なことだ。
風評被害の補償も大変であるが、近い将来?被曝者による集団訴訟?の補償についても、政府はよく考えないといけないと思う。もし被曝により、もっとも早く影響を受けやすい子供が亡くなることが、万が一あれば、全国の親から相当の恨みを、関係者は生涯買うことになるのだろうか。東電、政府関係者、テレビで大丈夫と合唱する専門家たちは、原告団から厳しく追求されはしないのだろうか。
次の政権であろうが、裁判で一部その責任を国が認めたとしても、その膨大な補償の負担は、最終的に原告でもある国民の増税や、関東の電気料金の値上げという形で賄われるのかもしれない。悲しいことだ。
東京電力は、現場で起こっていることをすべて発表したら、実は人が入ることなどできない汚染エリアで、復旧作業が継続できないと考えて、今まで公表を控えていたのだろうか。関東全域を大汚染させない為に本爆発を防ぐことは、すべてにおいて優先されると思う。そういう理由ならば、いくぶん理解できないこともない・・・・。
でも、それなら、最初から事実をしっかり発表して、逃がせる人を少しでも逃がして被曝する住人を減らすべきだろうし、関東全域の汚染の進行を防ぐ為に、現場の作業員については、国家としても基準値を越えた環境でも作業できるように緊急避難措置として、装備面において作業者の被曝を少しでも減らせるように全力を尽くした上で、どうどうとこれを許容すべきだ。
ロボットを含め、装備を持つ外国に頼ることも必要だろう。作業員やその家族への保障を手厚くし、少しでも安心して作業できるように、決死の英雄たちを、国を挙げてバックアップするべきなのではなかろうか。
海外からも英雄と言われている現場の方々は、国の為に死ぬ覚悟があるかもしれないが、実際は線量の高さも知らされず、劣悪な環境で昼夜問わず働かされているとの報道がされている。大臣が命を掛けている消防士を恫喝したり、むちゃくちゃなことを言ったので、都知事が激怒してクレームしていたが、なにかとてつもなく、おかしなことがおこっているように感じる。
事実とニュースの推移を見守っていても、いろいろなニーズがあって悪い情報を積極的に開示したくない、させないという力学がいろいろな方向から働いているように感じた。
まずは、国民は、関東が汚染される可能性について当然ながら受け入れたくない。自分らが実は被曝し、被害者になる可能性など受け入れられるわけがないという気持ちが、原発推進派の専門家たちの言う安全、たいしたことはないという風評防止?パニック防止?原発推進?を目的とする解説に説得されてしまう。これは、もちろん原発周辺の農業・漁業従事者も汚染で生活ができなくなるので、このような事態は理解できないし、受け入れがたいと思うのは当然であり、考え方は似たようなものとなるだろう。
想定しうるリスクについて説明すれば(いまのところ現実となっているが)風評として切り捨てられる。
一方、東電や政府にしても、最初の爆発で汚染の真実を知らせれば、国の定めた基準に照らせば、現場で復旧作業ができなくなる。すなわち危険だから作業員が現場を放棄すれば、更なる爆発や危機的状況が続く、現在進行形の話であるが。きっと見なかったことにして、損傷の度合いは分からないが、復旧作業に従事させたかったのではないかと想像してしまう。
数年後?10年後に、結果的に逃げ遅れて万が一癌になった関東在住の被害者は、福島原発被曝訴訟を起こすのだろうか。そうなれば、電力会社、政府、専門家も含めて被告になるのだろう。汚染が長期にわたって続くことが確定しつつある。もう下手に安全だとか、問題ないとか言えなくなるように思う。
現実問題として、今後関東の放射能汚染が長期的なものとなるのなら最近触れられなくなったが、大気汚染による内部被曝の蓄積を抑える必要があろう。マスクの徹底、エアコン停止等である。
でもこれから夏場に向けて計画停電も続き、また放射能の大気汚染が続くことになれば、空調を使えなくなる。とてもじゃないがオフォス、家庭問わず猛暑にでもなったら暮らしていけるのだろうか?被曝は、問題先送りで、だましだましいけるとしても、関東で生活することに、電力不足であることは、すぐにでも、いろいろなところで破綻がくるような気がしてならない。
もちろん、現時点で判明している農業、漁業従事者への補償、立ち入り禁止区域の住民への補償、数年後の被曝訴訟への補償、そして何よりも恐れるべき、冷却失敗や想定外?の事象による再臨海や再爆発による更なる汚染の拡大による上記の追加補償(関東全域になれば、もう負担しきれない?!)すべての費用について、税負担や関東の電力料金の値上げに跳ね返ってくるとするならば、関東で暮らすことのリスクと費用が尋常なものでなくなることにならないか。
企業としても、原発問題が政府の宣言どおりに数ヶ月で収束しないのであれば、経済性や社員の安全という観点からも、今後について、いろいろ考えていかなくてはならないのだろう。企業や工場が、いくらかでも西へ引っ越せば電力消費も減って、夏場の計画停電を減らせていいのかも・・・・!?
農家もノウハウや技術があるのなら政府の補償を原資に、思い切って西日本の耕作放棄地へ大移動させるのはどうだろうか?若くないとだめだろうけど










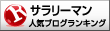











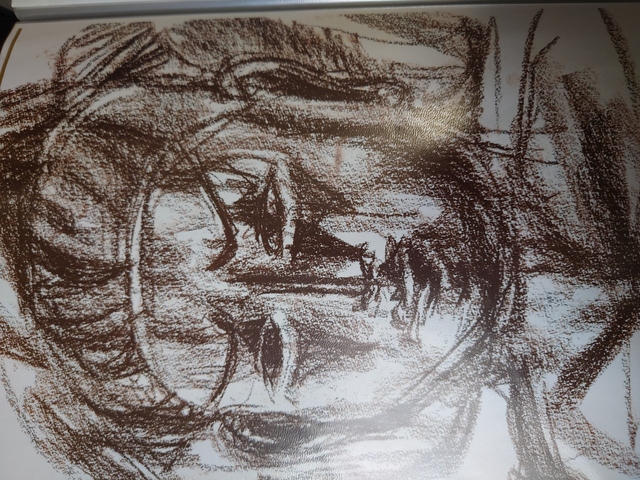





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます