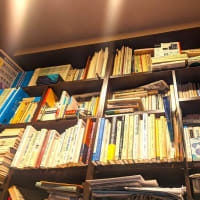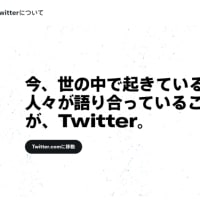2014年9月1日に投稿した記事をリメイクして、2022年1月に再投稿します。
今のこの時代に、是非お伝えしたい曲の話です。
(気軽に安易に「ヒトラー」や「ナチス」という言葉を使うことに、そして、その使ったことに対して感情的に反論することに、誰もが少し反省的になってほしい、という願いを込めて。)
1945年の今日、アウシュヴィッツ絶滅強制収容所が解放されました。
***
まずは、この曲を聴いていただけたら、と思います。
Mein Vater wird gesucht - (Rundfunk-Kinderchor Berlin)
この曲は、ナチス突撃隊に捕らえらて殺された父親を想う歌です。
歌詞を見ていきましょう。
Mein Vater wird gesucht,
er kommt nicht mehr nach Haus.
Sie hetzen ihn mit Hunden,
vielleicht ist er gefunden –
und kommt nicht mehr nach Haus
私の父が捜査されている。
父はもう家には戻ってこない。
彼らは犬を使って追いかける。
きっともう捕まってる。
だからもう家には戻ってこないんだ。
Oft kam zu uns SA
und fragte, wo er sei.
Wir konnten es nicht sagen,
sie haben uns geschlagen,
wir schrien nicht dabei.
ナチス突撃隊が度々家に来る。
そして、「奴はどこにいる?」と訊いてくる。
言うことなんてできなかった。
彼らは私たちを殴った。
私たちは叫び声を上げなかった。
Die Mutter aber weint,
wir lasen im Bericht,
der Vater sei gefangen
und hätt‘ sich aufgehangen –
das glaub‘ ich aber nicht.
でも、母は泣いた。
父は捕まって、首を吊ったという報告書を読んだ。
けど、そんなこと、私は信じない。
Er hat uns doch gesagt,
so etwas tät‘ er nicht.
Es sagten die Genossen,
SA hätt‘ ihn erschossen –
ganz ohne ein Gericht.
父はそんなことはしないって
私たちに言ってくれていたから。
仲間たちは言った。
ナチス突撃隊が彼を撃ち殺したんだと、
裁判所を通すことなく。
Heut‘ weiß ich ganz genau,
warum sie das getan.
Wir werden doch vollenden,
was er nicht konnt‘ beenden –
und Vater geht voran!
今、私ははっきりとよく分かっている、
どうして彼らがそんなことをしたのかを。
だから、私たちはやり抜く、
父がやり遂げられなかったことを。
父が導いてくれるんだ!
【2014年の僕のコメント】
かつての「戦争」をどう子どもたちに伝えるか。そして、二度と戦争を、そしてアウシュヴィッツを繰り返さないために、どうしたらよいのか。どう教育すればよいのか。このことをずっと探究してきたのが、ユルゲン・モイズィッヒだった。
彼の「幼稚園」の始まりは、反権威主義を掲げた小さな教育施設だった。幼稚園ではなかった。3歳から12歳までの子どもを預かり、教育する施設だった。民間の幼稚園+小学校を一元化した少し変わった「学校」だった。
そこで行われていた「アウシュヴィッツ以後の教育」の具体的な実践の中で、彼の学校の先生と子どもたちが一緒に歌っていたのが、この曲。ドイツ語を勉強したことがある人なら、わりとさらっと読めると思う。
大好きなお父さんがナチス突撃隊(「SA」:StrumAbteilung)に連れて行かれてしまい、家にもう戻ってこなかった、行ってしまった、という歌。
もともとは大人が歌っていたのだけれど、子どもがこうやって歌うと、本当に差し迫った悲しい歌に聞こえる。こういう歌を子どもたちに伝える。それもまた、二度とアウシュヴィッツを繰り返さないための大切な教育活動なのだろう、と思った。
日本の教育は、本当に「過去」を子どもたちに向き合わせているのだろうか。「頭」で、「知識」として「過去」を記憶するのが、教育ではない。
モイズィッヒが凄いと心から思うのは、幼稚園や小学校の子どもたちに、ドイツの最も闇となっている「ナチス政権」のことを、極めて自然な形で教え、伝えている、ということ。そして、子どもたちが、そこから、「支配と服従」に対する批判的な態度を学んでいる、ということ。
「支配と服従」に屈することが、アウシュヴィッツへの第一歩だと彼は考える。彼のこの「支配と服従」への抵抗はとてつもなく大きいものだった。
子どもたちに教えるべきは、「自分の意見を自由に言えること」、「先生を批判できること」、「不正に対して立ち向うこと」、「平等に、公正に皆が扱われること」、「無条件で服従しないこと」などが挙げられている。
どれも80年代の匂いがするものだけれど、今もなお、この価値は消え失せてはいないと僕は思う。「ゆとり教育」以後、うやむやにされた感はあるけれど、僕は、こうした抵抗する力を、子どもたちにまずもって与えるべき、と思う。
上に挙げた「自分の意見を自由に言えること」、「先生を批判できること」、「不正に対して立ち向うこと」、「平等に、公正に皆が扱われること」、「無条件で服従しないこと」は、どれも、本当に心から僕も大事だと思う。
広い意味で、「権威」に屈しない力、それこそが、やはり僕的には、生きる上で一番大切なことだと思う。日本は、今僕がいるオーストリアと同様、権威に弱い国民性をもっている。「学歴」だとか、「収入」だとか、「地位」だとか、「認知度」だとか、そういうものに屈してしまう国民性をもっている。特に、「金持ち」に対する抵抗感覚は、これまで戦後の日本ではほとんど育まれてこなかったと思う。つまりは、「資本主義批判」の感覚。
今や、「金持ち」(あるいは高学歴の著名人)は、「羨望の的」になっている。そういう人間に出会うと、僕らはたちまち弱くなる。ペコペコするようになる。同じ人間なのに…
権威主義は、資本主義と重なることで、「弱者」を完全に封じ込めることができるようになる。「殺さないであげるから、黙ってろ」、と。そういう「空気」こそが、今、世界中を包み込んでいるように思えてならない。
とするなら、今、世界で起こっている数々の紛争は、ある意味では、「抵抗運動」なのかもしれない。当然、許されるものではないけれど、戦っている彼らは決して裕福な人々ではない。そういう人たちが、「NO!」を突き付けているとしたら、、、
いずれにしても、戦争や紛争が生み出すのは、上の歌のような「途方もない悲しみ」だけである。そして、「憎しみ」と、「恨み」である。それ以外に生み出されるとするならば、「屈辱」、「敗北感」、「劣等感」、そういった類のものだけだろう。
これから、僕はもっと、この問題を、これまでやってきた研究と重ねて、広い意味での「教育」につなげていけたら、と思っている。
アドルノの言う「同調しない力」を、どうやって、日本の子どもたちに与えていけばよいのか。「暴力」で抵抗するのではなく、「言語」で抵抗し、そして、言語において同調しないことを表明する力をどうやって作っていけばよいのか。
僕の関心から言えば、最も弱き存在である人々に、この力をどうやって与えていけばよいのか、ということになる。社会的・実存的に弱い人にこそ、「自分の意見を自由に言えること」、「先生を批判できること」、「不正に対して立ち向うこと」、「平等に、公正に皆が扱われること」、「無条件で服従しないこと」、という「武器」を与えなければいけない。
「強い人間」は、こうした力を既に獲得している。
強き人間は、僕の関心事ではない。そうではなく、弱き人間(つまりは子どもや女性や障害者や高齢者やその他マイノリティーの人々)に、こうした力を与えることが、僕の最大の関心事なんだろう、と思う。
やっぱり、僕は小さい頃から変わってないや…
【2022年の僕より】
2014年の頃よりも、世界的にどんどん不安定になってきている気がします。
第三次世界大戦がいつ、どこで起こってもおかしくない状況になってきています。
日本の近隣国を見ても、ロシア、中国、アメリカ、北朝鮮、韓国、台湾、そして日本のどの国も、緊張状態に入っているようにも思います。
国民レベルで見ても、どんどんナショナリズムが強くなっていって、「自国防衛」への意識が強くなってきています。2年前の香港の事情も、僕らは目の当たりにしました。
2014年頃、あるドイツ人に言われたことを思い出します。「第三次世界大戦が起こるとしたら、きっと東アジアからだね」、と。ブラックなジョークだとその時は笑いましたが、もう、今は笑えません。
日本人の中国や韓国への嫌悪は、戦後最大級に高まっていますし、また、中国や韓国での日本への嫌悪も相当強まっていると聞きます。ややこしいのは、そこに北朝鮮も入ってくるので、どこがどことどう関わるべきなのか、誰も分からなくなっているんです。
ただ、一つ絶対に言えることは、「なんとしても、戦争だけは回避せねばならない」ということです。そのためには、一度すべてを止めてもいいくらいに。アジアの知恵でいけば、一度、みんな「鎖国しましょう」でいい。でも、それだと、経済的なダメージが大きいので、とりあえず各国の首脳が、しっかり話し合う場を設けてほしい。
領土問題も大事だし、人権問題も大事だし、政治レジーム問題も大事だけど、それ以上に、僕ら一人一人の「いのち」が最重要です。
戦争になるということは、誰かが殺し、誰かが殺されるということが果てなく繰り返されることです。誰かのパパが誰かを殺し、誰かのパパが誰かに殺され、そして、誰かのママが泣き、そして、誰かの子どもが絶望の淵に突き落とされるんです。
先日、ある若い(普通の)男性(21歳くらい)が熱く僕に語ってくれました。
「俺は、中国も韓国も嫌いっす。攻めてきたら、すぐに志願して、戦争に行きますよ。靖国も毎年行ってます。この国を守るためなら、死んでもかまわない。攻めてきたら、敵国の人間を殺すだけです。そういう若者、増えてますよ。逃げたら、ダサいっす。俺は絶対に逃げません。敵国をつぶすか、さもなくば、死ぬだけっす。三島(由紀夫)を尊敬してます(本は読んだことないけど…)。絶対、つぶします。」
って。(ほぼ誇張しないで書いています)
これが、(第一次)安倍政権による教育基本法改正後の「愛国心を教える教育」の成果なんだ…、と愕然としました。
この10年、ネットやメディアを通じて、反中・反韓を煽る動画や文章が次々に若者たちに届けられました。彼曰く、その情報のほとんどがYouTubeだと言っていました。
でも、彼や彼のような若者と話すと、第一次世界大戦のことも、第二次世界大戦のことも、(一部の誇張されたところをのぞいて)本当に何も知らないんです。どことどこが戦争をしていたのかも知らない。いつ頃の話だったかも分からない。ヒトラーが何をしたのかも、「我が闘争」で何を叫んでいたのかも、知らないんです。もちろんヴァイツゼッカーのあの名言も知らないんです。(その代わり、いかに日本がかつての戦争で勇敢に戦ったかについては詳しいんです)
僕も戦争を知らない世代の人間です。戦争の悲惨さや悲痛さを体験的に語ることはできません。もう、戦争の恐ろしさをリアルに語れる人はほとんど残っていないんです。
じゃ、何ができるのか。
例えば、今回ここで紹介した上の歌を伝えることはできます。
ドイツ語の歌詞を翻訳し、それに解説を加えることはできます。
こういうことを今後もっともっとやっていかないといけないなって思いました。
fin.
1945年の今日、アウシュヴィッツ収容所が解放されました。私たちはこの残虐な国家的犯罪を次代に語り継いでいかねばなりません。☞ https://t.co/q4TcwRnOi7
— 岩波書店 (@Iwanamishoten) January 27, 2022
リリアナ・セグレ『アウシュヴィッツ生還者からあなたへ』
高橋秀寿『ホロコーストと戦後ドイツ』
中谷剛『ホロコーストを次世代に伝える』 pic.twitter.com/6e7P97zUTn
【子ども・青年向けの本のご紹介】
これはおススメです。
こちらも読んでほしい一冊です。
この本も若者に届けたい一冊です。
テレジン強制収容所の先に、アウシュヴィッツがありました。