
『レオニー』をDVDで観る。2時間を越える長い作品で、彫刻家イサム・ノグチの母親であったレオニー・ギルモアという女性の半生を描いた伝記映画だった。最初の20分ほどで退屈して、途中で何度もやめようと思ったが、最後まで見た。
この映画は2010年秋に公開された時、出演者の中村獅童さんの事務所から試写会の招待状をいただいたのに、仕事の都合で見に行けなかった。今頃になって見ようと思ったのは、この映画のプロデューサーの永井正夫さんと最近知り合いになって、製作の苦労話を聞いて興味を覚えたからである。
この映画は評判があまりかんばしくなく、話題にもならずに終ってしまったようだが、映画興行というのは水物で、作品の良し悪しと観客の動員数は一致しないことも多い。いい映画がヒットするとは限らないし、話題性のある映画、動員力のある映画というのは、作品の完成度とは別で、何か観客を引きつける大きな魅力があるかないかにかかっている。映画の全盛期ならば主演スターの魅力や監督の知名度で客が入ったが、今の時代は大スターも大監督も不在。もちろん今でも出演者や監督の人気が動員力の一因になるのだろうが、昔に比べれば雲泥の差である。現代にマッチするような映画自体の内容的魅力や話題性がなければ、客はわざわざ映画館まで足を運ばないにちがいない。
『レオニー』という映画は、出演者と監督の知名度はともかく、こういう映画を今さら作って話題にする人がいるのだろうかと感じる映画であった。が、それでも、観客が映画を見て感動すれば良いと思うのだが、はたしてこの映画を見て感動した人がいたのであろうか。私は感動するどころか、うんざりしてしまった。主人公の女性は色気もなく地味だし、相手役の中村獅童は役に合わず(詩人で文学者の役はどうかと思う)、波瀾万丈の女性の人生は、ただ伝記の流れをたどっているだけで、事件の羅列的な説明にすぎず、ドラマもなければ、主人公の苦悩も何も描けていない。映像的な見てくればかりに頼って、中身の稀薄な作品だった。監督・脚本とも松井久子という人で、いわば「女の一生」といった大作に挑むだけの力量がないまま、独りよがりの映画を作ってしまったとしか私には思えなかった。原作はドウス昌代が書いたイサム・ノグチの伝記とのことで、松井さんという人はこの伝記を読んで感動し、イサム・ノグチの母親の生涯をどうしても映画化したいという情熱に取りつかれてしまったのだろう。聞くところによると、7年か8年かけて映画化を実現したそうで、彼女のすごい情熱は賞賛に値すると思うが、映画は出来たもので評価される。ヒットしなくても映画の出来が素晴らしければ満足できるだろうが、いかんせん『レオニー』は作品的に佳作のレベルにも達していなかった。
脚本、キャスティング、演出、すべてに問題があったと思う。人が情熱を傾け一生懸命作った作品を酷評するのは、できるだけ控えたいと思うが、もうすでに酷評してしまったかもしれない。最近、私自身が映画を作ってみようと思っているので、失敗作を見ても腹が立たず、真面目に作っている映画は最後まで見て何が悪かったのか冷静に分析するように心がけている。
脚本について言えば、多くのことを描きすぎて、メリハリがなかったと思う。あれもこれもと欲張りすぎて、結局何も描けないまま終ってしまった。主眼は、レオニーの野口米次郎に対する愛情の変転なのだろうから、そこを中心に描くべきだった。まずレオニーがなぜ野口を愛したのかがよく分からない(逆も同じ)。レオニーが野口の詩を読んで、才能を感じ、それで日本人の野口を愛するようになったといった程度では、納得がいかないのだ。レオニーは娼婦でもないし、インテリにコロッとだまされるような軽薄な女でもないのだから、野口という男の個性に惹かれて彼を愛するようになったはずである。あの時代、アメリカ人の女性が日本人の男を愛し、子供まで作るというのは大変なことだったと思う。だから、二人が愛し合う出発点をしっかり描くべきだった。ここを描かずして、その後の愛情の変転も何もあったものではない。また、相手役の野口米次郎の人物像はまったくつかめないままだった。脚本に人間が描けていないが最大の欠陥であるが、この役をなぜ中村獅童が引き受けたのかも不可解。最初からこの人物は魅力がなく、彼は何度も登場するが、言葉も行動も矛盾が多かった。監督がこの人物をつかんでいないのだから、見る方が首をかしげるのは当然だと言えよう。















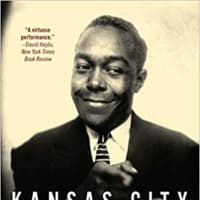

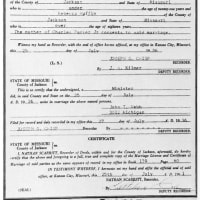








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます