蔦屋重三郎は、吉原大門そばの小さな本屋を、江戸で一、二を争う大出版社に発展させた。
その成功の原因として、まず、重三郎が吉原で生まれ育ったという来歴と、養子に入った家が妓楼ないし引き手茶屋の経営主であったという社会的経済的背景が上げられるだろう。
吉原内部の人間であるという特殊性、そしてそこから生まれる独特な発想が重三郎の強みであった。出来合いの吉原ガイドブック(吉原細見)を単に売っていたのでは詰まらなく感じ、吉原を江戸中さらに地方へも宣伝するために自分で新しい本の企画を考え始めたのが、本屋を版元(出版社)へ変えていく出発点となった。
重三郎とって吉原はいわば身内であり、その裏も表も知った上で特別な愛着を持っていたのは当然であろうし、自分ならこういう吉原本を作るといった具体的なアイディアが湧き上がったにちがいない。重三郎は、蔦屋以外の妓楼の経営主や関係者たち、そしてもちろん、多くの遊女たちのために、商売繁盛を願い、自分ひとりの金儲けではなく、利他的で、ある意味博愛的な立場から本の制作をした。吉原内部から大きな支援を受けたのは重三郎の企画編集への賛同があってのことだった。重三郎は、まさにホームグラウンド吉原をバックグラウンドにして出版界に乗り出し、重三郎でしか企画制作できない出版物によって、事業を拡大発展させていったわけである。
蔦屋の処女出版は安永3年7月発行の遊女評判記『一目千本 花すまひ』で、上下2巻70頁ほどの冊子である。私は見たことがないのだが、「吉原遊女を生花見立てに描いて、あたかも角力を競う風情の、すこぶる雅趣のあのもの」だそうだ。(榎本雄斎氏『写楽――まぼろしの天才』より)
蔦屋版「吉原細見」ではレイアウトを変え、内容も充実させた。そして、重三郎は、序文を有名なベストセラー作家(朋誠堂喜三二、のちに山東京伝)に依頼した。天明3年、吉原細見の版権を完全に押さえてから初春に発行した新吉原細見(「五葉の松」シリーズ)は、序文を朋誠堂喜三二、跋文を四方赤良(大田南畝)、祝言を朱楽菅江(あけらかんこう 天明狂歌四天王の一人)が書くといった著名人三人の揃い踏みであった。
吉原細見は公式ガイドブックであるが、ほかに、遊女評判記、遊女たちの源氏名と自筆サイン入りポートレート集、吉原風俗小説(洒落本)、さらには美しい遊女をモデルにした一枚摺りの浮世絵も、蔦屋重三郎は精力的に出版した。
遊女ポートレート集というのは、各妓楼の遊女たちの多色摺り画集で、彼女たち自作の俳諧や狂歌を自筆で掲載したものである。重三郎は出版社を立ち上げた翌年に、本屋をやりながら夢に描いていたにちがいない画集『青楼美人合姿鏡』(北尾重政と勝川春章の画)3冊を企画編集し、安永5年正月に出版している。この画集については前にも書いたが、大ヒットして、収益も上がったはずである。しかし、5年も経てば遊女たちも様変わりし、新しいポートレート集を出す必要に迫られたのだろう。7年後に企画を練り直し、今度は新進画家の北尾政演(山東京伝)に依頼した。「青楼遊君之容貌」と題し、大判錦絵百枚続きと銘打って、大々的に宣伝し、天明3年正月に何枚か発売するのだが、すぐに大手地本問屋(宿怨のライバル西村屋与八だと言われている)から横槍が入り、発売中止になったようだ。蔦屋が錦絵発行の権利を正式に株仲間から得ていなかったことが理由らしい。結局、これは画帳形式に作り変え、翌天明4年正月に『吉原傾城 新美人合自筆鏡』と改題して発売し、ヒット商品にしたのだった。

政演画「新美人合自筆鏡」より 花魁二人、新造、禿の衣裳も細かいが、調度品から置物、蕎麦屋の丼に至るまで、描写の精密さには驚く。
天明3年から蔦屋重三郎は、各種の狂歌本を続々と出版し始めるが、著名な狂歌師の歌に交えて、遊女の歌も載せるといった配慮も払っている。百人一首のかるたを模した肖像画入りの狂歌本では、北尾政演のウイットに富んだ珍品揃いの変人男たちの絵にはさまり、遊女らしき美女の肖像と歌が彩りを添えている。士農工商の封建的身分も男女の差別も貴賎の区別もなく、狂歌を詠んで興じる人間たちの楽しい雰囲気があふれ、見ていて微笑ましく感じないわけにはいかない。『天明新撰五十人一首 吾妻曲狂歌文庫』(天明6年正月)と続編『天明新撰百人一首 古今狂歌袋』(天明8年正月)(ともに宿屋飯盛撰、北尾政演画)は、傑作(笑える)である。「絵双紙屋」というホームページにどちらも全ページ、狂歌の解説つきで掲載されているのでご覧になることをお勧めする。

玉子香久女(たまごのかくじょ)未詳 政演画『吾妻曲狂歌文庫』より
「卵の四角と女郎の誠」は、あるはずのないものの喩えで、それから狂名を付けているので、遊女であろう。猫(?)に紐を付けている。
歌は、「染るやら ちるやら木々は らちもない いかに葉守の 神無月とて」
私の解釈:女の気(木)心というのは、らちもなく、色に染まったり散ったりで、いくら木の神様がお留守の十月でも、どうしたものでしょう。
もう一つ、現存する資料が少なく、見逃されがちなのが、重三郎と芸能界とのつながりである。歌舞伎とその音曲である富本節(江戸で始まった常磐津の一派で当時全盛を極めた)、そして謡曲(江戸庶民に謡が流行し始めていた)といった分野での出版物も重三郎は手がけている。とくに富本正本(しょうほん)は、かなり早い時期(安永5年ごろ)に版権を買い、蔦屋から刊行している。これは、富本節が使われる歌舞伎の舞台の役者姿を表紙に描き、その歌詞を載せたリーフレットである。表紙絵は、最初北尾政演が描き、のちに歌麿が描いていたという。
吉原大門そばの蔦屋の店では、吉原本に加え、富本正本も売って、定番商品にしていた。この辺の研究は榎本雄斎の『写楽――まぼろしの天才』に詳しいが、あいにく彼のあとを継ぐ研究者がいないのは残念である。榎本氏は、名優中村仲蔵(初代)と重三郎の縁戚関係を強調し、重三郎が仲蔵を通じて歌舞伎役者や関係者たちとコネを持ち、出版に生かしたと述べているが、資料の乏しさもあって、説得力の点では今一歩の感が拭えない。
重三郎が、写楽の役者絵を大々的に売り出すのは、もはや事業が傾いた晩年、寛政6年5月からである。一枚摺りの役者絵を刊行し出すのも、比較的遅く(寛永期に入ってからかもしれない)、富本正本を除いては、歌舞伎関係の出版物は、どうやら二の次だったようだ。やはり、吉原関係の本や画集がまず第一で、その後、黄表紙、洒落本、狂歌本の発行に出版社としての主力を注いでいったと言える。
観世流謡曲本の刊行は天明2年からである。謡曲本も売上げが確実に上がりロングセラーを見込める手堅い本だったと思われるが、出版目録が不完全で、詳しいことは今のところ分らない。
蔦屋重三郎が出版社を発展させた基盤については以上に述べた通りだが、飛躍的に発展させた最大の要因は、時代の流行に自らも従い、その中に飛込んで、時代の寵児たちと親しく交わったことである。重三郎が安永期から流行し始めた狂歌の世界に関心を抱き、蔦唐丸という名前で自らも狂歌を詠み始めたのは、本屋から出版社へ転向をはかった安永半ば以降だったと思われる。狂歌の歌会サークル(「連」という)があちこちで作られ、重三郎も吉原連というサークルに入って、その後、歌会の幹事のようなこともやり出す。サークル同士の合同歌会もあったように推測されるが、狂歌仲間の横のつながりや同好のよしみで互いに仲良くなったりすることはあったはずである。重三郎が狂歌界の旗頭の四方赤良(大田南畝)や朱楽菅江と出会ったのは、安永8年前後のようだが、親しくなったのは天明元年以降であろう。黄表紙『虚言八百万八伝』の作者四方屋本太郎正直が四方赤良だとすれば、この本は安永9年正月発行であるから、前年に重三郎は赤良と原稿の依頼や編集段階で何度か会い、親しくなっていたことも考えられる。
天明2年12月17日に、吉原大門そばの蔦屋重三郎宅に錚々たる面々が集まり、夜、吉原の妓楼大文字屋(主人の狂名・加保茶元成)へ繰り出して遊んだことが記録に残っている。四方赤良、恋川春町、元杢網(もとのもくあみ)、唐来参和(とうらいさんな)、北尾重政、北尾政演、北尾政美らであった。重政は吉原に行かずに家に帰ったという。(恋川春町『年の市の記』)

唐来参和 政演画『吾妻曲狂歌文庫』より
彼は蔦屋重三郎と義兄弟の契りを結んだほど仲が良かったという。北尾政演の絵が面白い。
歌は、「ない袖の ふられぬ身には ゆるせかし 七夕づめの 物きぼしでも」
私の解釈:爪に白い斑点が出来たから、新しい着物でも買ってもらえる幸運があるみたいねって姫様が言うんだけど、ない袖はふれない身の上の僕としては、心の中で許してくれってつぶやくだけなんです、情けないけど。
朋誠堂喜三二や恋川春町とは安永6年までには親交を結び、本を蔦屋から出版している。狂歌師ではないが、絵師の北尾重政は、ごく初期の、出版社設立時に、おそらく版元の鱗形屋孫兵衛の紹介で知り合い、重政を通じて弟子の北尾政演(山東京伝)を知ったことは間違いない。重政は狂歌より俳諧を好んでいたらしく、絵師の鳥山石燕と親しく、その関係で重三郎は石燕やその弟子の志水燕十や北川豊章(喜多川歌麿)と知り合ったようだ。浮世絵師の勝川春章や鳥居派の清満、清経、清長とも同時期に知り合い、作画も頼み本も出しているが、その後、疎遠になっている。
重三郎の人脈作りは、狂歌という共通の趣味と吉原門前に店があるという地の利を生かして進められ、天明期の初めには、のちに蔦屋から作品を出す作家や絵師たちのほぼ八割方の人々と知り合いになっていたと思われる。重三郎がいつどこで知り合ったのかが全く分からない大物は、後年の東洲斎写楽だけである。
その成功の原因として、まず、重三郎が吉原で生まれ育ったという来歴と、養子に入った家が妓楼ないし引き手茶屋の経営主であったという社会的経済的背景が上げられるだろう。
吉原内部の人間であるという特殊性、そしてそこから生まれる独特な発想が重三郎の強みであった。出来合いの吉原ガイドブック(吉原細見)を単に売っていたのでは詰まらなく感じ、吉原を江戸中さらに地方へも宣伝するために自分で新しい本の企画を考え始めたのが、本屋を版元(出版社)へ変えていく出発点となった。
重三郎とって吉原はいわば身内であり、その裏も表も知った上で特別な愛着を持っていたのは当然であろうし、自分ならこういう吉原本を作るといった具体的なアイディアが湧き上がったにちがいない。重三郎は、蔦屋以外の妓楼の経営主や関係者たち、そしてもちろん、多くの遊女たちのために、商売繁盛を願い、自分ひとりの金儲けではなく、利他的で、ある意味博愛的な立場から本の制作をした。吉原内部から大きな支援を受けたのは重三郎の企画編集への賛同があってのことだった。重三郎は、まさにホームグラウンド吉原をバックグラウンドにして出版界に乗り出し、重三郎でしか企画制作できない出版物によって、事業を拡大発展させていったわけである。
蔦屋の処女出版は安永3年7月発行の遊女評判記『一目千本 花すまひ』で、上下2巻70頁ほどの冊子である。私は見たことがないのだが、「吉原遊女を生花見立てに描いて、あたかも角力を競う風情の、すこぶる雅趣のあのもの」だそうだ。(榎本雄斎氏『写楽――まぼろしの天才』より)
蔦屋版「吉原細見」ではレイアウトを変え、内容も充実させた。そして、重三郎は、序文を有名なベストセラー作家(朋誠堂喜三二、のちに山東京伝)に依頼した。天明3年、吉原細見の版権を完全に押さえてから初春に発行した新吉原細見(「五葉の松」シリーズ)は、序文を朋誠堂喜三二、跋文を四方赤良(大田南畝)、祝言を朱楽菅江(あけらかんこう 天明狂歌四天王の一人)が書くといった著名人三人の揃い踏みであった。
吉原細見は公式ガイドブックであるが、ほかに、遊女評判記、遊女たちの源氏名と自筆サイン入りポートレート集、吉原風俗小説(洒落本)、さらには美しい遊女をモデルにした一枚摺りの浮世絵も、蔦屋重三郎は精力的に出版した。
遊女ポートレート集というのは、各妓楼の遊女たちの多色摺り画集で、彼女たち自作の俳諧や狂歌を自筆で掲載したものである。重三郎は出版社を立ち上げた翌年に、本屋をやりながら夢に描いていたにちがいない画集『青楼美人合姿鏡』(北尾重政と勝川春章の画)3冊を企画編集し、安永5年正月に出版している。この画集については前にも書いたが、大ヒットして、収益も上がったはずである。しかし、5年も経てば遊女たちも様変わりし、新しいポートレート集を出す必要に迫られたのだろう。7年後に企画を練り直し、今度は新進画家の北尾政演(山東京伝)に依頼した。「青楼遊君之容貌」と題し、大判錦絵百枚続きと銘打って、大々的に宣伝し、天明3年正月に何枚か発売するのだが、すぐに大手地本問屋(宿怨のライバル西村屋与八だと言われている)から横槍が入り、発売中止になったようだ。蔦屋が錦絵発行の権利を正式に株仲間から得ていなかったことが理由らしい。結局、これは画帳形式に作り変え、翌天明4年正月に『吉原傾城 新美人合自筆鏡』と改題して発売し、ヒット商品にしたのだった。

政演画「新美人合自筆鏡」より 花魁二人、新造、禿の衣裳も細かいが、調度品から置物、蕎麦屋の丼に至るまで、描写の精密さには驚く。
天明3年から蔦屋重三郎は、各種の狂歌本を続々と出版し始めるが、著名な狂歌師の歌に交えて、遊女の歌も載せるといった配慮も払っている。百人一首のかるたを模した肖像画入りの狂歌本では、北尾政演のウイットに富んだ珍品揃いの変人男たちの絵にはさまり、遊女らしき美女の肖像と歌が彩りを添えている。士農工商の封建的身分も男女の差別も貴賎の区別もなく、狂歌を詠んで興じる人間たちの楽しい雰囲気があふれ、見ていて微笑ましく感じないわけにはいかない。『天明新撰五十人一首 吾妻曲狂歌文庫』(天明6年正月)と続編『天明新撰百人一首 古今狂歌袋』(天明8年正月)(ともに宿屋飯盛撰、北尾政演画)は、傑作(笑える)である。「絵双紙屋」というホームページにどちらも全ページ、狂歌の解説つきで掲載されているのでご覧になることをお勧めする。

玉子香久女(たまごのかくじょ)未詳 政演画『吾妻曲狂歌文庫』より
「卵の四角と女郎の誠」は、あるはずのないものの喩えで、それから狂名を付けているので、遊女であろう。猫(?)に紐を付けている。
歌は、「染るやら ちるやら木々は らちもない いかに葉守の 神無月とて」
私の解釈:女の気(木)心というのは、らちもなく、色に染まったり散ったりで、いくら木の神様がお留守の十月でも、どうしたものでしょう。
もう一つ、現存する資料が少なく、見逃されがちなのが、重三郎と芸能界とのつながりである。歌舞伎とその音曲である富本節(江戸で始まった常磐津の一派で当時全盛を極めた)、そして謡曲(江戸庶民に謡が流行し始めていた)といった分野での出版物も重三郎は手がけている。とくに富本正本(しょうほん)は、かなり早い時期(安永5年ごろ)に版権を買い、蔦屋から刊行している。これは、富本節が使われる歌舞伎の舞台の役者姿を表紙に描き、その歌詞を載せたリーフレットである。表紙絵は、最初北尾政演が描き、のちに歌麿が描いていたという。
吉原大門そばの蔦屋の店では、吉原本に加え、富本正本も売って、定番商品にしていた。この辺の研究は榎本雄斎の『写楽――まぼろしの天才』に詳しいが、あいにく彼のあとを継ぐ研究者がいないのは残念である。榎本氏は、名優中村仲蔵(初代)と重三郎の縁戚関係を強調し、重三郎が仲蔵を通じて歌舞伎役者や関係者たちとコネを持ち、出版に生かしたと述べているが、資料の乏しさもあって、説得力の点では今一歩の感が拭えない。
重三郎が、写楽の役者絵を大々的に売り出すのは、もはや事業が傾いた晩年、寛政6年5月からである。一枚摺りの役者絵を刊行し出すのも、比較的遅く(寛永期に入ってからかもしれない)、富本正本を除いては、歌舞伎関係の出版物は、どうやら二の次だったようだ。やはり、吉原関係の本や画集がまず第一で、その後、黄表紙、洒落本、狂歌本の発行に出版社としての主力を注いでいったと言える。
観世流謡曲本の刊行は天明2年からである。謡曲本も売上げが確実に上がりロングセラーを見込める手堅い本だったと思われるが、出版目録が不完全で、詳しいことは今のところ分らない。
蔦屋重三郎が出版社を発展させた基盤については以上に述べた通りだが、飛躍的に発展させた最大の要因は、時代の流行に自らも従い、その中に飛込んで、時代の寵児たちと親しく交わったことである。重三郎が安永期から流行し始めた狂歌の世界に関心を抱き、蔦唐丸という名前で自らも狂歌を詠み始めたのは、本屋から出版社へ転向をはかった安永半ば以降だったと思われる。狂歌の歌会サークル(「連」という)があちこちで作られ、重三郎も吉原連というサークルに入って、その後、歌会の幹事のようなこともやり出す。サークル同士の合同歌会もあったように推測されるが、狂歌仲間の横のつながりや同好のよしみで互いに仲良くなったりすることはあったはずである。重三郎が狂歌界の旗頭の四方赤良(大田南畝)や朱楽菅江と出会ったのは、安永8年前後のようだが、親しくなったのは天明元年以降であろう。黄表紙『虚言八百万八伝』の作者四方屋本太郎正直が四方赤良だとすれば、この本は安永9年正月発行であるから、前年に重三郎は赤良と原稿の依頼や編集段階で何度か会い、親しくなっていたことも考えられる。
天明2年12月17日に、吉原大門そばの蔦屋重三郎宅に錚々たる面々が集まり、夜、吉原の妓楼大文字屋(主人の狂名・加保茶元成)へ繰り出して遊んだことが記録に残っている。四方赤良、恋川春町、元杢網(もとのもくあみ)、唐来参和(とうらいさんな)、北尾重政、北尾政演、北尾政美らであった。重政は吉原に行かずに家に帰ったという。(恋川春町『年の市の記』)

唐来参和 政演画『吾妻曲狂歌文庫』より
彼は蔦屋重三郎と義兄弟の契りを結んだほど仲が良かったという。北尾政演の絵が面白い。
歌は、「ない袖の ふられぬ身には ゆるせかし 七夕づめの 物きぼしでも」
私の解釈:爪に白い斑点が出来たから、新しい着物でも買ってもらえる幸運があるみたいねって姫様が言うんだけど、ない袖はふれない身の上の僕としては、心の中で許してくれってつぶやくだけなんです、情けないけど。
朋誠堂喜三二や恋川春町とは安永6年までには親交を結び、本を蔦屋から出版している。狂歌師ではないが、絵師の北尾重政は、ごく初期の、出版社設立時に、おそらく版元の鱗形屋孫兵衛の紹介で知り合い、重政を通じて弟子の北尾政演(山東京伝)を知ったことは間違いない。重政は狂歌より俳諧を好んでいたらしく、絵師の鳥山石燕と親しく、その関係で重三郎は石燕やその弟子の志水燕十や北川豊章(喜多川歌麿)と知り合ったようだ。浮世絵師の勝川春章や鳥居派の清満、清経、清長とも同時期に知り合い、作画も頼み本も出しているが、その後、疎遠になっている。
重三郎の人脈作りは、狂歌という共通の趣味と吉原門前に店があるという地の利を生かして進められ、天明期の初めには、のちに蔦屋から作品を出す作家や絵師たちのほぼ八割方の人々と知り合いになっていたと思われる。重三郎がいつどこで知り合ったのかが全く分からない大物は、後年の東洲斎写楽だけである。















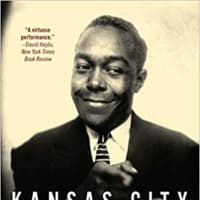

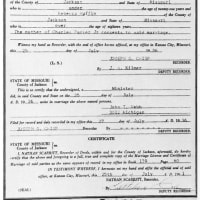



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます