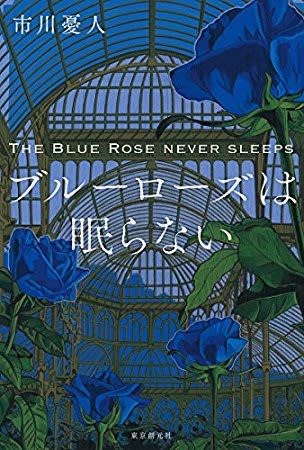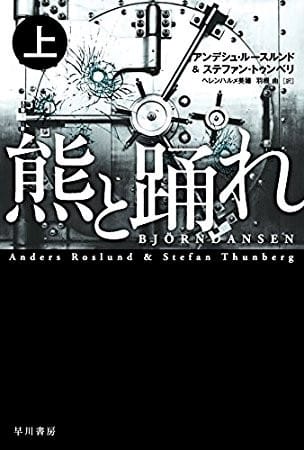1958年に清水俊二氏の翻訳で「ハヤカワ・ポケット・ミステリ」として刊行された「長いお別れ」
チャンドラーがフィリップ・マーロウを主人公にした長編小説を書きあげたのは七冊で
「ロング・グッドバイ(長いお別れ)」は1953年に六冊目として書かれた
ここに上げた本は村上春樹による翻訳で2007年早川書房より刊行された単行本の軽装版です
訳者あとがき、として凖古典小説としての「ロング・グッドバイ」の評論がありますが、このレイモンド・チャンドラーに関しての
アレコレはとても興味深い一文ですから一読をお勧めします
ある意味では彼のお説のとおりだった。テリー・レノックスは私にたっぷりと迷惑をかけてくれた。しかし、
考えてみれば面倒を引き受けるのが私の飯のたねではないか。
「最後に彼に会ったのはいつで、場所はどこだ」私はエンドテーブルの上のパイプを手に取り、煙草を詰めた。
グリーンは身を乗り出してじっと私を見ていた。背の高い若者はずっと後ろの方に腰掛け、赤い縁のついたメモ帳にボールペンを向けていた。
「そこで私が『いったい何があったんだ?』と尋ね、君たちは『質問するのは我々だ』と言うんだろうね」
「分かってもらえると話が早い」
「彼が警察を動かしている訳じゃないぜ」とグリーンが言った。
「本人もそう言っていたよ。市警本部長や地方検事を買収してもいないそうだ。きっと彼が居眠りしている時に、相手の方から膝に上がり込むんだろうな」
「ほざいてろ」とグリーンは言って、私の耳の中でがちゃんと電話を切った。
何をするでもなく、ただ静かに待っていた。バニー・オールズから電話がかかって来たのは九時だった。
すぐこちらに来てくれと彼は言った。途中で寄り道して花を摘んだりするなよ、と念を押された。
「私はロマンティックなんだよ、バーニー。夜中に誰かが泣く声が聞こえると、いったい何だろうと足を運んでみる。そんなことをしたって一文にもならない。
常識を備えた人間なら、窓を閉めてテレビの音量をあげる。あるいはアクセルを踏み込んで、さっさとどこか遠くに行ってしまう。
他人のトラブルには関わり合わないようにつとめる。関わりなんか持ったら、つまらないとばっちりを食うだけだからね。
最後にテリー・レノックスにあったとき、我々は私が作ったコーヒーをうちで一緒に飲み、煙草を吸った。そして彼が死んだことを知ったとき、
私はキッチンに行ってコーヒーを作り、彼のためにカップに注いでやった。そして彼のために煙草を一本つけてやった。コーヒーが冷めて、
煙草が燃え尽きたとき、私は彼におやすみを言った。そんなことをやっても一文にもならない。君ならそんなことはしないだろう。
だから君は優秀な警官であり、私はしがない私立探偵なんだ。
「名前を言えよ。どこの誰だ?」
「マーロウというものだ」
「どのマーロウだ?」
「君はチック・アゴスティーノか?」
「いや、チックじゃない。合言葉を言ってみろ」
「顔を火で焙ってきやがれ」
相手はくすくす笑った。「このまま待ってろ」
フランス人はこのような場にふさわしいひと言を持っている。フランス人というのはいかなる時も場にふさわしいひと言を持っており、
どれもがうまくつぼにはまる。
さよならを言うのは、少しだけ死ぬことだ。

t>