故吉田秀和氏が、この楽章の後半で穿つ連打音やトリルが神がかっている、という様な事を何かで述べられていた。
また僕の学生時代、フランスでフーガのレッスンを受けた際、声部が離れ過ぎると「ベートーヴェンのようだ」と先生から皮肉られたが、それはこの楽章の事だろう。
…ベートーヴェンの最後のピアノソナタ、第32番の終楽章を暗譜した。C dur! 単純な一音一音が重い、深い。
「ハンマークラヴィーア・ソナタ」の終楽章が対位法の極限をさらに破壊し、難解な不協和音、複雑な構成の大暴れするフーガだったのに比べ、こちらは第1楽章にコンパクトなフガートがあるものの、終楽章ではフーガの様な模倣対位法を封印し、浄化された音響、瞑想といった別次元の高みを作る。
冒頭、右手が奏でる優しいアリエッタ(第1楽章の序のリズムが丸くなったもの)を左手が葬送の様な鬱屈した響きで伴奏する。この乖離は直前の第1楽章の終結を受け継いだもので、スムーズに劇的な転換が成され、この楽章全体の響きを決定する。
このソナタは二楽章構成だが、終楽章は変奏曲で、第2, 3変奏は誰もが「ジャズのスイング」の先取りと指摘するリズム(主題のリズムの倍速と4倍速)の無窮動であり、これがスケルツォに相当するとも考えられる。続く第4変奏以降は突如低音のドローンと化し、主題が幻の様に透かし彫りになる。やがて光の粒が立ち昇り、再び低音のドローン、光の粒と交錯するが、この細かい光の粒はパターン化された音型では無く、メロディーとしても成立する自律した動きで円周率のように果てしない。しかしそれも反復音型に収まるとソナタ第30番の冒頭にある様な壮麗なアルペジオを回想し、一転遠隔調Es durの靄に包まれ最も希薄な音響、最高音域と最低音域の2声による巨大な空洞に静止する(第1楽章c mollの第2主題がEs durでは無くAs durだった事の伏線回収)。
底なし沼から脱するようにドローンと共に主題が再現し、瞑想がぐいぐい力強く、濁った響きも辞さず、頂点に達すると天上のオルゴール。
クラシックの名曲の殆どに見られると言っても良い特徴の一つは「永劫回帰」だ。
随分遠くまで来た。地の果てとも思えるほど…そこでふと振り返ると元の場所だった。











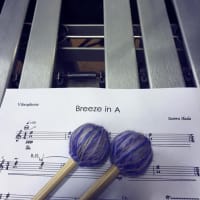

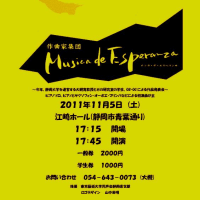

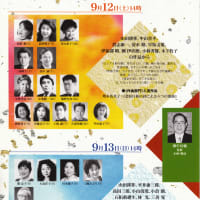
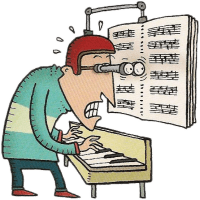

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます