11月8日(火)
脚の具合(変形性関節症)が随分よくなった。いわゆる「始動時痛」といわれる症状は解消していないが、歩くことにほとんど支障を感じなくなった。
これなら思い切って歩行数をのばしても差支えがなさそうである。
歩く距離を勘案してこれまでは比較的距離の短い「神祇大社」にお参りしていたが、今回は距離を伸ばし古くからある八幡野の郷社「来宮神社」まで相当に遠いがMr.TBと連れだって出掛けた。
距離はあっても往きはすべて下り坂だから四囲に広がる秋の風情を楽しみながら気楽に歩いていく。


神社の参道に入るとすぐ「高見の椎の木」と呼ばれる伊東市指定天然記念物の大樹がある。これまで何回かその傍を通ったが、今回は時間をかけてゆっくりと眺めてみた。
なるほど、よくみると、この木はただ大きいというだけでなくなかなかの迫力のある巨大樹だ。瘤に覆われた太い幹の偉容は一見の価値がある。
その奥、八幡野の深い樹叢に囲まれたところに神社が鎮座している。道もそこが行き止まりだ。
社前にある表示板で初めて知ったことだが、この神社を私はこれまで漠然と「来宮神社」と呼んでいたが、正しくは「八幡宮来宮神社」というらしい。
二社併祀の神社とのことで、二間社流造の本殿右に「八幡宮」、左に「来宮」が合祀されているという。多くの神々を一社に祀るのは我が国では普通だが、二社を一つの殿社に合祀しているとは珍しい。
八幡宮の歴史は古く、神護景雲3年(768)一国一八幡制により伊豆国に創建された由緒ある神社とのこと。(来宮はもと八幡野の海辺の窟に祀られていたのを後に遷祀したとある)
1200年の歴史の持つといえば伊豆半島では代表的な最古の社ではないか!(熱海の「来宮神社」は710年と少し早いが)

鳥居の次に神社には珍しい朱色の冠木門があるのも珍しい。ここにも二つの紋所。
鬱蒼とした樹木に覆われ境内はやや暗いがかえって神々しさを増す。鄙びた素朴な石の階段だが、その幅広さはあまり例をみないのではないか。


境内には伊豆半島を北限自生地とする大型の常緑性羊歯「リュウビンタイ」(竜鱗タイ)があちらこちらに見受けられた。
帰りの坂はかなりきつかった。帰ってから歩数計をみたら15257歩。すこし歩き過ぎた。明日どうもなければいいが……。





















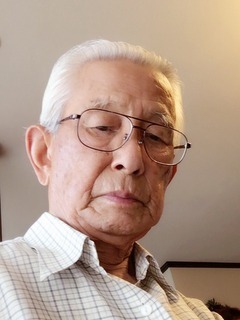





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます