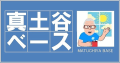PASMOに申請した「マイナポイント5000円分」
さっそく「セブン銀行のATM」で二人分1万円分受取りました。
コロナ禍のあと、交通系ICに入れて、都内散歩に使いましょ。
時をさかのぼること1970年代。
「生録(なまろく)」を趣味として楽しんでいました。
「なまろく」と言っても聞きなれないと思いますが
1970年代当時、“ 生録ブーム ” というものがありました。
愛用の機材は、「SONY 力セットデンスケ TC-2860SD」
※デンスケとは、取材用可搬型テープレコーダーの商標です。


ソニーの “ 力セットデンスケ ” の録音機材を肩にかけ
マイク片手に野鳥の鳴き声を録音したり
当時10万円もしたカセットデッキだけではなく
「高音質のマイク」や「パラボラ集音器」を求め
「ミキサー」でマイク音量を調整したりと
新聞配達・拡張・集金のバイト料から捻出していました。

「生録ブーム」を盛り上げた立役者と言えば、「SL(蒸気機関車)」
国鉄(日本国有鉄道・現在のJRグループ)が
1975年にSLの旅客・貨物の営業運転を終了。
それをきっかけに、鉄道ファンやにわかファンを含め
「生録ブーム」が巻き起こりました。
SLと言えば生録、生録と言えばSL
今もSLが現役で運行している静岡県の「大井川鐵道」 に向かいます。
役目を終えたSLなら見たことはありますが
蒸気を上げ て疾走するSLを見るのは久しぶりです。
果たしてSLの汽笛や蒸気を上げる音などを、うまく録ることはできるのでしょうか。

「なまろく」は結構むずかしく!
「大井川鐵道」のSL運行は、ほとんど1日1往復のみ。
生録に出かけた日は、往路は11時47分に金谷駅を出て、13時8分に千頭駅に到着。
復路 は15時15分千頭駅発、16時34分金谷駅着というダイ ヤであったか。
往路と復路では違う地点で、録音するということも不可能ではないのですが
スケジユール的にはかなり大変になります。
「BE-PAL(1981年・昭和56年創刊)」の特集「大井川鐵道」で
撮影ポイントの解説やドラフト音、ブラスト音、汽笛、勾配の詳細が
地図とともに詳しく掲載されていたことを記憶します。
【ドラフト音とは】汽笛や煙突から吐き出る「ボッ ボッ ボッ」
【ブラスト音とは】蒸気を排出する「シュ シ ュ シュ」
「炭水車(蒸気機関車が使用する燃料や水を積載した車両)」の後ろのデッキに
「ステレオマイク」をデッキバーに固定して
「走行音、ドラフト、ブラスト、汽笛、踏切音」を録音します。
「SONY ECM-99A ワンポイントステレオマイク」

「SONY コンデンサーマイク ECM-2270 ステレオセット(コンデンサー型)」

「ナマ録」というのは、多くの方が理解できない趣味だと思います。
なにせ18万も出した結果が、「音がリアルに録れるだけ」なのですから。
魅力は、この音が現実に聞こえる音よりもリアルで驚きます。
クリアーな音を求めて、1秒の音が19㎝のテープの長さに録音されます。
昭和52年に求めた「SONY オープンデンスケ TC-5550-2」


当時憧れだった【ツートラサンパチ(2トラック38cm)】
1秒の音が38㎝のテープの長さに録音されます、音が鮮明に録音されます。
■プロ用のマスターテープはこの仕様です、これ以上の規格はなく、「究極の録音」です。
■録音ファンなら当時誰でも一度は手にしたいと思った「ツートラ・サンパチ」、70年代に普及し、民生用機は38cmと19cmにスピード切替ができました。
客車の中では、録音マニア意外の人も多く
雑音が入りますが、すべてを録音し、家に持ち帰り編集します。
オーディオ用テープは、音源の頭出しが分かりやすいため
ヘッドフォンで聞きながら、テープを直接切ってつなぎ編集します。
完成した音物語のテープは、オーディオ雑誌の出版会社に投稿した記憶があります。
ヘッドフォンから聞こえる「扉の開く音」
現実よりも鮮明でリアルな音
ビックリして‼️ 「扉に振り向く 私」、驚きと感動した思い出が始まりです。