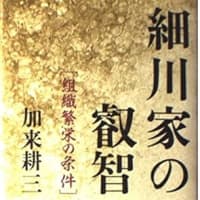いろいろな方が実名で登場してくるところが本当らしくかつ若干いやらしい。京都の町中にある杉本家、下京で300年以上続いている旧家で、今は見学料を取って内部を公開している。公開前に筆者が杉本家の見学に大学生として訪れた際、当主の杉本秀太郎さんに言われたのが、「君は嵯峨の子なんか。昔はあのあたりにいるお百姓さんが、うちへよう肥えをくみにきてくれたんや」。感謝しているような文脈の中に、洛中で暮らしている名家の当主が京都の中では田舎に属する嵯峨の百姓を下に見ている意識がいけずとしてもろに表れている。こういう言い方は実は京都に暮らしている人間ならだれでも一度や二度は耳にするものである。上京に生まれた私も、中京や下京の友人から、祇園祭の鉾町こそが京都であるとか、室町沿いの下京が京都の真ん中だ、などと言われたこともあり、宇治に引っ越してからは、洛外扱い、昔の別荘地扱いで、「わが庵(いほ)は 都のたつみ しかぞすむ 世をうぢ山と 人はいふなり」の通りの感覚で、都の東南の憂し山里で鹿なんかが住んでいる場所である。関東人から見ればそんな、どちらも観光地京都でしょ、という違いでしかないが、現代でも東京でいえば港区と川口、志木くらいの違いはある。
1980年代、京都で結婚適齢後期の中京に住む女性の一言、「とうとう山科の男から結婚話があったんや、もうかんにんしてほしいわ」「山科のどこが問題ですか?」「そやかて、山科なんかに行ったら東山が西に見えてしまうやんか」。京都の東の大津との中間点に山科はあり、桜の時期には山科疎水や毘沙門堂などはたいそう美しく、山科駅からその道すがらなどは立派なお屋敷が並んでいるのだが、そんなことなどこの女性には関係なかったのだろう。こういう人には自分が実は宇治に住んでいることなど言えるはずもない。おまけに、結婚話があったことも同時に自慢しているようでもあり、できればこれ以上のかかわりは持ちたくないと考えるのが洛外ものの考え方としては適切なのだろう。
筆者は考える。これは差別的発言なのかと。差別とは自分が優位に立ち劣位の他者を見下そうとする感覚であり、身体的不具合や人種、民族などを理由にする差別的発言や行為は許されるものではない。しかし、デブ、ハゲ、チビ、などは不具合とまでは考えられないので軽い揶揄の表現などとしてからかいの対象になることがある。洛中から見た洛外へのこうした発言はハゲ、デブ、チビに相当する軽い揶揄的発言なのであろう。言われる側の気分がいい訳はない。ヘイトスピーチや蔑視が許されない時代に、ちょうど手ごろなうっぷん解消相手を見つけたという程度なのかもしれないと。
この後、京都での僧侶たちの祇園での遊び具合を紹介し、百人一首の坊主めくりになぞらえて、京都のキャバクラに僧侶が大勢押しかけているさまを「姫坊主姫坊主姫坊主・・・」と揶揄する。また寺社への古都税問題で京都の有力観光寺院が一斉に拝観停止のストライキを10か月ほど実施した時のことに触れ、その後京都市側が折れて古都税が廃止になり、市民に寺社の力の強さを再度思い出させたと紹介している。寺は戦国時代当時から武士層への食い込みを図るため、寺に侍たちを宿泊させていたという。「本能寺の変」もこうした文脈で理解できる。庭の美しさを競ったのもそのころからで、南北朝以降の寺社の庭の発展はこうした慰安施設としての寺社の位置づけが関係しているはずというのが筆者の主張である。和食の味付けに寺がふるまう精進料理の貢献も大きいという。肉なしで客に満足を与えるためには、寺の歴史、庭の蘊蓄、そして禅の思想などを総動員してもてなした。それが現代の和食文化、ブームの礎になっているというのである。
筆者はさらに、靖国神社、日の丸、君が代も1000年の都の視点から評価して見せる。靖国神社の前身は招魂社、明治政府に盾突いた勢力は排除されていた靖国神社、京都から見れば明治政府が定めた以降のたかだか150年の歴史しか感じられない君が代と日の丸にも反発を感じている。明治維新以前にいくつもあたはずの日本各地の、そして都であった京都の象徴にこそ長い歴史と伝統が宿っているのではないかという主張である。
最後に、筆者はこの本の出版社にも反旗を翻している。「ひち」つまり七のこと。京都では七条は「ひちじょう」、上七軒は「かみひちけん」であるのは当たり前なのだが、明治以来の東京政府は「ひち」を「しち」と書き直してきた。京都を走る京阪電車の駅に「七条」があるが、この読み仮名は「しちじょう」とわざわざ書いてある。京都人なら「ひちじょう」、七五三は「ひちごさん」であり、七面鳥は「ひちめんちょう」、七福神だって「ひちふくじん」でしょう、と。本書の発行元朝日新聞社書籍も索引を作る際に、七条をサ行に入れようとして、筆者と小競り合いになったという。鎌倉の七里ガ浜を「しちりがはま」とするのは勝手だが、七条は「ひちじょう」としておいてほしい、というのが筆者の願いである。
京都のことが本当は大好きな筆者、そのことが端々に表れるので、京都の洛中人もにこにこしながらこの本を読むことだろう。