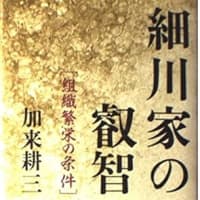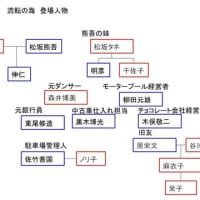コロナ禍が長期化し、労働と通勤に関する考え方に変化が生じている。日本における太平洋戦争後の都市への人口集中は仕事を得るための地方から都市への人口移動が原因だった。リモートワークがきっかけになり、職選び、住まい選びの判断基準に変化が見える。東京都心にある職場には週に一度通えばいい、という仕事なら、都心よりも環境が自分の生活に適合した場所を選べる。海辺、山、田舎、島、実際アメリカではコロナ以前よりそういう職住の分離が進んでいるという。人がどのような判断基準で住む街を選ぶのか、それがこれから発展できる町と衰退の一途をたどる町の評価を分けてくる。
「ニュータウン」三田、鳩山、仙台市泉区、多摩、印西、あすみが丘、ユーカリが丘など、その多くは1970年代から90年代に開発された大規模集積住宅地であり、一定の年齢層の家族ばかりが一気に住まいを構えたため、高齢化も同時に訪れる。30歳代で住み始めた世代が開発後50年ほどが経過して相続の時代を迎える。ニュータウンの中には管理、修理などが十分に行われている物件もあり、交通の便も良ければ子供世代も相続してでも住み続ける可能性もある。しかし、交通の便が悪く管理や修理が十分でなければ、相続しても住まない、管理費も滞納する、相続が放棄されるなどしてスラム化が進む。印西では災害対応をウリにして職住近接の環境を整備、ユーカリが丘では成長管理を継続的に行うことで住民世代の平準化を長期的に行っている。
「タワマン」豊洲、武蔵小杉、晴海、神戸、西宮北口などでは、都心に近くて憧れの住まいとして人気を集めたが、五輪の延期や無観客開催、武蔵小杉では集中豪雨でのマンション機能停止が報道され、一気に熱が冷めた。大規模なビル管理という観点ではニュータウンと同様の問題が指摘される。
「大都市の中の街」池袋、新橋、銀座、渋谷、天王寺、ミナミでは、インバウンド需要から急成長した時期があり、その弊害も指摘された。池袋では外国人街が形成され街の雰囲気が大きく変わっている地区もある。街の再開発が行われ、大きな変化を迎えている渋谷やアベノハルカスの完成後の大変貌を今後どのように活かせるのかという天王寺地区など、課題は多い。
「大都市郊外」逗子、船橋、川口、三浦などでは郊外都市として発展してきたが曲がり角を迎えている。街の機能老朽化にどのように対応していくのか。
「新陳代謝を仕掛ける街」人口が入れ替わり活発な川崎、アジアへのゲートウェイ都市として人が集まる福岡、ホテルやオフィスニーズも高い大宮、古くからの飲み屋街に若者が集まる野毛、自力で人口5万人を達成し市に昇格した野々市、人口増加率日本一の長久手などでは新陳代謝が適切に行われ、人口が入れ替わっている。
「町おこしに挑む街」世界ブランド確立に成功した燕三条、観光業を極める小さな町小布施、学、岳、楽の「三ガク都」の魅力を海外にもアピールする松本、プロ野球誘致に成功した北広島、小江戸ブランド確立に成功した川越、京都へのアクセスの良さで宿場町の繁栄を取り戻そうとする大津。
「盛衰の分岐点に立つ街」脱ベッドタウンが課題の横須賀、東京以外からの人を呼べるか柏、通過される街からの脱却が課題の下関、近隣有名観光地との連携が課題の松江、自然を活かしてチャレンジする国東。
「注目の成長の街」大学誘致に成功した北千住、防災拠点を備えた安心安全の街立川、老若男女が楽しめる中野、新たな下町清澄白河、利便性と自然の両立海老名、子育て世代にアピールする流山。
「奮闘する地方都市」空き家対策先進の鶴岡、魚介類と野菜が魅力の新潟、人口減に苦慮する松阪、歴史と文化の盛岡、大都市へのアクセスの良さがウリの和歌山、情報発信とアピールが課題の佐賀。
「コンパクトシティを目指す街」挫折も味わう青森、市民誘導には成功、これからの富山、生活者視点から商店街を再構築した高松市丸亀町。
「島の将来」新空港整備で観光客増に期待する石垣島、高齢化を街の活性化につなげようとしている周防大島、自然の魅力があるが交通の利便性がネックの隠岐の島、世界遺産に依存しすぎない観光客誘致が課題の新上五島町、農業、漁業、畜産が魅力の南あわじ。
「リゾート誘致に賭ける街」世界に向けたアピール中の別府、空き家問題が深刻な熱海、かつての有名リゾート蓼科、空前の不動産ブームの宮古島、映画ブームで湧いた草津、万博誘致とIR誘致の夢洲。
「空港と港を活かす」農産物が鍵となる成田、茨城空港を活用できるのか小美玉、セントレアとの連携が課題の常滑、国際貿易を発展に繋げられるのか小樽、空港との共存が課題の伊丹。
「インバウンドが集まる」パウダースノーで外国人が集まるニセコ、白馬、SNS発信がキッカケの下吉田、住民参加型の河口湖、30年戦略がある高山、雪こそがおもてなしの旭川。本書内容は以上。
大都市の郊外に両親が建てた実家の周辺ではここ数年空き家が目立っている。ニュータウンでの空き家は、目立たないが確実にその数を増やしている。近年増加している集中豪雨や洪水、盛土や乱伐が原因の山崩れ、地震後の津波、原発による心理的不安、噴火のリスクなど、誰でもが自分が住んでいる場所に関して感じる不安がある。本書は考えてみるいいきっかけになる。