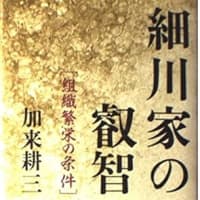上田秋成は二作の浮世草子を明和三年(1766年)に書き、明和五年から八年をかけて「雨月物語」を著したという。本書ではその中から、菊花の約(ちぎり)、浅茅が宿、吉備津の釜、青頭巾の四話を紹介。
菊花の約では、播磨国の学者丈(はせ)部左門は知人宅で病魔に臥す病人に出会い看病の結果、赤穴宗右衛門というその旅人は命拾いをする。意気投合した二人は義兄弟の契りを結ぶ。宗右衛門は生国の出雲で城主が討たれたとして、動静をうかがいたいと言い、重陽の節句には必ず戻ると約束して出雲に出立するが、魂だけが現れ、新城主尼子経久に命じられた赤穴の従兄弟に逆に討ち取られたという。左門は義兄弟赤穴の仇を取るべく出雲に向かい、仇である赤穴の従兄弟を見事に打ち取る。
浅茅が宿。下総の富農を零落させてしまった勝四郎は、京で絹商人になり一旗揚げて秋には帰ると妻の宮木に約束したが、帰ったのは7年後。夕方帰宅した勝四郎はやつれ果てた宮木と再会するが、翌朝目覚めると家は荒れ果てており、勝四郎は宮木の遺筆を見つけその死を悟る。近隣に住まう翁に宮木の最期を聞いた勝四郎は宮木の塚の前で翁と念仏を唱えた。
吉備津の釜。吉備の国の富農の息子正太郎は酒や女に溺れていたが、両親は縁談を持ちかけて酒色が収まることを期待した。相手は磯良、その両親は吉備津神社に縁談の吉凶を占うが、お釜祓いの神事の結果は凶。しかし婚儀は行われ、磯良は大変良く夫の正太郎に仕えた。しかし正太郎は入れあげた遊女袖とともに逃げ、磯良は病気になる。正太郎と袖は従兄弟の家にたどり着くが、袖は数日後に死んでしまう。墓参した正太郎は磯良の怨霊に出会い、陰陽師に占ってもらい、42日間の家籠りを進められる。42日目の明け方、夜明けと勘違いして外に出てしまった正太郎は大量の血を吐き姿を消してしまった。
青頭巾。下野国に山寺があり、その住職は寵愛していた童児が死んでしまい、それがきっかけで人食いの鬼となる。諸国行脚の快庵禅師は、下野国でその鬼を改心させてほしいと地元民に頼まれ、住職に禅宗の証道歌二句を授けて去った。1年後、この山寺を再訪した改庵は住職が授けていた二句を細々と唱えるのを見て一喝。住職の姿は消えて青頭巾と骨だけが残っていた。
近松門左衛門は1653年生、24作の世話物を執筆したが「冥途の飛脚」は14作目。近松の世話物の特徴としては、男の側に欠点や落ち度があり、女性は遊女、妻、恋人と様々だが、男に対してきわめて献身的。「曽根崎心中」では悪辣な男を友人と信じて疑わなかった徳兵衛に対して、おはつはそれを支える。「冥途の飛脚」では短気なあまり公金に手を付けてしまう忠兵衛を支えるのが梅川。「心中天網島」では妻子がありながら遊女小春と深い中になり、家も妻も子も捨てて心中してしまう紙屋治兵衛を、健気に支えるのが妻おさん。状況としては、少々情けない男性を女性の側が支えていかなければ持ちこたえられそうもない、という状況を描く、という近松の状況設定である。
近松の心中物では、心中する死に場所を求める二人の道行きを、三味線の伴奏に乗せた太夫の語りが盛り上げることで、一層の情緒を掻き立てるため、一般の散文とは性質が異なる。韻、リズム、掛け言葉、古典参照などの工夫が凝らされるなかで、近松の技巧的文才が発揮される。浄瑠璃で操られる人形が、参照された源氏物語の描写が乗り移ったようにも見える演出である。雨月物語は書物としての評価が高く、メッセージ性、普遍性、芸術性故に、近代の作家たち、佐藤春夫、芥川竜之介、谷崎潤一郎、太宰治などにより再編されている。本書内容は以上。