病院勤務医のための漢方医学セミナー(ツムラ主催)。
「科学的視点からみた漢方医学」「急性期と療養型で役に立つ漢方の使い方」
に同僚と共に参加してみました。
講師は静内病院の井齋偉矢先生、大学の大先輩でした。

レクチャーをTsudaったものをもとにまとめてみます。
漢方を科学という共通言語で
西洋医学と漢方医学は相対するもの、違う体系の医学ではない。
「漢方科」や「和漢診療科」などと独立して外来や病棟をもうけて分けるのは望ましくない。
すべての科で漢方は使える。
どの科でも漢方を使える所から使っていくというスタンスがいいだろう。
漢方医学独特の言語を使わないと理解出来ない医学は科学ではない。
今の時代は科学という共通言語で理解すべきである。
科学の言葉だけで説明できて初めて漢方医学は科学の土俵に乗ることができる。
科学がない時代の東洋医学の理屈を科学という視点から見ると意外とシンプルに解ける。
「炎症」
傷寒論には急性熱性疾患を中心に発病から経過をおって症候の変化に対応する処置が記されている。
気・血・水以外に、新たに包括的概念としての「炎症」という視点をいれると色々と読み解ける。
漢方薬は炎症反応のカスケードの上流に作用し自然免疫系の感度をアップさせ初期免疫系に作用して炎症を迅速に立ち上げる。また過剰な炎症が遷延したら炎症を抑制し、障害された組織の修復を促進する。
西洋医学の炎症のメカニズムに関する知識と、個々の炎症に関する治療法の実践ノウハウがつながれば科に関わらずこれからの医学に多大な貢献するだろう。
漢方薬は生薬の集合であるが作用機序を生薬単位で説明するのは説明した気になっているだけで本当はおかしい。
それぞれの方剤は試行錯誤で作ってしまったものであり、多数の化学物質がシステムとして作用している。
生薬の中のさまざまな生理活性物質がプロドラッグとなり薬効を示す。
生理活性物質の多くは糖により抱合されており配糖体となっており吸収されにくい。
配糖体の糖分が資化菌で切断されて吸収されて薬効を示す。
腸内細菌叢はそれぞれの人で異なり、この資化菌の個人差が効果の個人差の理由の一つである。
漢方の古典の困ったところは全て文字情報なところでイメージしづらいことである。
使用目標が多すぎて、どれが必須かわからない。
これをビジュアル化して分かりやすくすることが大事。(階層構造にするとわかりやすい)
常に方剤名で思考し直感で処方する。
方剤ごとに2つくらいのキーワードで覚えるとよい。
患者さんのイメージと薬のイメージを確してパターン認識する。
レスポンダーかノンレスポンダーかを判断する期間は方剤や病態によって異なることに注意が必要。
最初の一服で効果があるものもあれば2週間程度は飲んでいないとわからないものもある。
「気」
漢方で言う「気」は形のないものだろうか?
そうなってくると気剤の作用点はどこなのだろうか?
運動連鎖を起こすAnatomy trainと経絡は面白い事にほとんど一致する。
全身の筋骨格系は筋膜で繋がり(筋筋膜経線)、システムとして運動連鎖を形成し、生命体の基本たる動作が成立する。
体は考えれば考えるほどうまく動けなくなるが、意識を集中ししっかり見れば一連の動作がスムーズに流れる。
ということで気剤は「脳」と「筋骨格系」に作用するといえるのではないか。
「気虚(ききょ)」は筋肉や脳の原料であるブドウ糖が十分吸収できないので活発な動作や精神活動が出来なくなる。補気剤の代表である補中益気湯は消化管の機能を高めエネルギーを筋肉や脳に供給する。
「気鬱(きうつ)」は筋肉を使わず閉じこもり動かないから、精神活動も沈滞し抑鬱傾向となるといえる。
「気逆(きぎゃく)」はある部分の筋肉にこわばりや凝りが生じると筋筋膜系の運動連鎖がその部分で滞る。
「血」
動脈系は西洋医学が得意であり、インターベンションや血栓予防などの方法論が確立されてきている。
一方で微小循環系と静脈系は漢方医学が得意。
「瘀血(おけつ)」すなわち微小循障害はストレスなどで内因性ステロイドホルモンが少し多い状態になっておこる。
皮膚疾患はステロイドより駆瘀血薬が有効なことがある。
「水」
「水毒」の病態、利水剤の水分調整作用はアクアポリンで説明できる。
様々なサブタイプのアクアポリンが全身に分布している。
利水薬はそれぞれのアクアポリンに特異的に作用して細胞レベルで水分を調整する。
五苓散などは脳浮腫対策として脳外科でも大ブームである。
国際東洋医学会日本支部で昨年は五苓散シンポジウムを開催した。
来年は芍薬甘草湯シンポジウムを予定しているそうで、薬理、臨床、様々な立場からストーリーテリングを行うのだという。
いきなり古典から入らずに科学の視点から漢方を見直すと様々なことが見えてくる。
まず西洋医学をきっちりやることをすすめる。
急性期病棟で役に立つ漢方
肺炎などの感染症に関しては抗菌薬などはもちろん使うが、体の内部にアクティブな炎症がおきている時には小柴胡湯ファミリーを使う。
最初の2、3日は2、3倍を使うのがポイント。日本の容量は急性期には少なすぎる。
脳梗塞にも。血栓は溶解できても併発する浮腫と炎症に対して漢方は有用である。
小柴胡湯と五苓散を使うと非常に回復が早くなる。
心不全は西洋薬に併用して木防已湯を使うとよい。
ノロウイルスなどの急性ウイルス性胃腸炎には西洋医学では補液しかないが、漢方では桂枝人参湯がよい。
最初5g、その後2.5gを4時間おきに飲み1日で治してしまう。
すぐに補液が出来ない状況は世界にいくらでもあるし、日本でも災害時などでは起こりうる。
偉い先生方は自由診療でのんびりやっており急患はほとんど見ていない。
例え病院に和漢診療科があってもERからは直接いかない。
そういうこともあって急性期での活用は盛んではないが、漢方はもともと急性期で使われていたものであり本来は大いに活用できる。短期大量投与がポイントである。
療養型病床で役に立つ漢方
一方で慢性期の療養型病棟でも漢方薬は高齢者の様々な症状に有用であり医療費削減に貢献する。
それぞれの方剤が効く症候群(証)として捉える。
かぜ症候群や便秘、COPD、認知症などに有効。(時間がなく多くは割愛された)
痰が多く肺炎を繰り返すCOPDには清肺湯を漫然と使うのが良い。
「怒りが深く蓄積」、「怒り以外で発散」、というものには抑肝散がよい。
環境の変化に弱い認知症の方のBPSDによく術後のせん妄や小児のADHDなどにも応用される。
井齋先生はもともと外科医で肝臓移植などをやっていた先生だが科学的視点から漢方薬の本質を追求してきたそうだ。マニアックな東洋医学会のやり方に疑問をもち、サイエンスの視点で漢方を読み解き、どの科でも誰でも使えるようにということで国際東洋医学会や和漢医薬学会などを拠点に学術的にも活躍されている。
難解で抽象的な中医学の理論ではなく、現代科学の最新の基礎医学の知識、特にSystem bilogoy的手法を応用して漢方を読み解くというのは実にオモシロイと思った。
実際に現場でも漢方もつかった医療をすべく静内病院を拠点にしているという。
静仁会静内病院は地方の199床(療養型89床)の総合病院(徳洲会系)だが井齋偉矢院長先生がきてから漢方を使う病院として有名になり、特色を出すことで研修の医師を集めているという。
研修医(初期・後期)がローテートで来たり中堅の医師が勉強に来たりと活発なようで(まだまだ来て欲しいと言っていたが・・)これまた僻地の病院に医師を確保する上手いやり方だとおもった。
(※講演のDVDはツムラさんに言えばもらえるみたいです。)
「科学的視点からみた漢方医学」「急性期と療養型で役に立つ漢方の使い方」
に同僚と共に参加してみました。
講師は静内病院の井齋偉矢先生、大学の大先輩でした。

レクチャーをTsudaったものをもとにまとめてみます。
漢方を科学という共通言語で
西洋医学と漢方医学は相対するもの、違う体系の医学ではない。
「漢方科」や「和漢診療科」などと独立して外来や病棟をもうけて分けるのは望ましくない。
すべての科で漢方は使える。
どの科でも漢方を使える所から使っていくというスタンスがいいだろう。
漢方医学独特の言語を使わないと理解出来ない医学は科学ではない。
今の時代は科学という共通言語で理解すべきである。
科学の言葉だけで説明できて初めて漢方医学は科学の土俵に乗ることができる。
科学がない時代の東洋医学の理屈を科学という視点から見ると意外とシンプルに解ける。
「炎症」
傷寒論には急性熱性疾患を中心に発病から経過をおって症候の変化に対応する処置が記されている。
気・血・水以外に、新たに包括的概念としての「炎症」という視点をいれると色々と読み解ける。
漢方薬は炎症反応のカスケードの上流に作用し自然免疫系の感度をアップさせ初期免疫系に作用して炎症を迅速に立ち上げる。また過剰な炎症が遷延したら炎症を抑制し、障害された組織の修復を促進する。
西洋医学の炎症のメカニズムに関する知識と、個々の炎症に関する治療法の実践ノウハウがつながれば科に関わらずこれからの医学に多大な貢献するだろう。
漢方薬は生薬の集合であるが作用機序を生薬単位で説明するのは説明した気になっているだけで本当はおかしい。
それぞれの方剤は試行錯誤で作ってしまったものであり、多数の化学物質がシステムとして作用している。
生薬の中のさまざまな生理活性物質がプロドラッグとなり薬効を示す。
生理活性物質の多くは糖により抱合されており配糖体となっており吸収されにくい。
配糖体の糖分が資化菌で切断されて吸収されて薬効を示す。
腸内細菌叢はそれぞれの人で異なり、この資化菌の個人差が効果の個人差の理由の一つである。
漢方の古典の困ったところは全て文字情報なところでイメージしづらいことである。
使用目標が多すぎて、どれが必須かわからない。
これをビジュアル化して分かりやすくすることが大事。(階層構造にするとわかりやすい)
常に方剤名で思考し直感で処方する。
方剤ごとに2つくらいのキーワードで覚えるとよい。
患者さんのイメージと薬のイメージを確してパターン認識する。
レスポンダーかノンレスポンダーかを判断する期間は方剤や病態によって異なることに注意が必要。
最初の一服で効果があるものもあれば2週間程度は飲んでいないとわからないものもある。
「気」
漢方で言う「気」は形のないものだろうか?
そうなってくると気剤の作用点はどこなのだろうか?
運動連鎖を起こすAnatomy trainと経絡は面白い事にほとんど一致する。
全身の筋骨格系は筋膜で繋がり(筋筋膜経線)、システムとして運動連鎖を形成し、生命体の基本たる動作が成立する。
体は考えれば考えるほどうまく動けなくなるが、意識を集中ししっかり見れば一連の動作がスムーズに流れる。
ということで気剤は「脳」と「筋骨格系」に作用するといえるのではないか。
「気虚(ききょ)」は筋肉や脳の原料であるブドウ糖が十分吸収できないので活発な動作や精神活動が出来なくなる。補気剤の代表である補中益気湯は消化管の機能を高めエネルギーを筋肉や脳に供給する。
「気鬱(きうつ)」は筋肉を使わず閉じこもり動かないから、精神活動も沈滞し抑鬱傾向となるといえる。
「気逆(きぎゃく)」はある部分の筋肉にこわばりや凝りが生じると筋筋膜系の運動連鎖がその部分で滞る。
「血」
動脈系は西洋医学が得意であり、インターベンションや血栓予防などの方法論が確立されてきている。
一方で微小循環系と静脈系は漢方医学が得意。
「瘀血(おけつ)」すなわち微小循障害はストレスなどで内因性ステロイドホルモンが少し多い状態になっておこる。
皮膚疾患はステロイドより駆瘀血薬が有効なことがある。
「水」
「水毒」の病態、利水剤の水分調整作用はアクアポリンで説明できる。
様々なサブタイプのアクアポリンが全身に分布している。
利水薬はそれぞれのアクアポリンに特異的に作用して細胞レベルで水分を調整する。
五苓散などは脳浮腫対策として脳外科でも大ブームである。
国際東洋医学会日本支部で昨年は五苓散シンポジウムを開催した。
来年は芍薬甘草湯シンポジウムを予定しているそうで、薬理、臨床、様々な立場からストーリーテリングを行うのだという。
いきなり古典から入らずに科学の視点から漢方を見直すと様々なことが見えてくる。
まず西洋医学をきっちりやることをすすめる。
急性期病棟で役に立つ漢方
肺炎などの感染症に関しては抗菌薬などはもちろん使うが、体の内部にアクティブな炎症がおきている時には小柴胡湯ファミリーを使う。
最初の2、3日は2、3倍を使うのがポイント。日本の容量は急性期には少なすぎる。
脳梗塞にも。血栓は溶解できても併発する浮腫と炎症に対して漢方は有用である。
小柴胡湯と五苓散を使うと非常に回復が早くなる。
心不全は西洋薬に併用して木防已湯を使うとよい。
ノロウイルスなどの急性ウイルス性胃腸炎には西洋医学では補液しかないが、漢方では桂枝人参湯がよい。
最初5g、その後2.5gを4時間おきに飲み1日で治してしまう。
すぐに補液が出来ない状況は世界にいくらでもあるし、日本でも災害時などでは起こりうる。
偉い先生方は自由診療でのんびりやっており急患はほとんど見ていない。
例え病院に和漢診療科があってもERからは直接いかない。
そういうこともあって急性期での活用は盛んではないが、漢方はもともと急性期で使われていたものであり本来は大いに活用できる。短期大量投与がポイントである。
療養型病床で役に立つ漢方
一方で慢性期の療養型病棟でも漢方薬は高齢者の様々な症状に有用であり医療費削減に貢献する。
それぞれの方剤が効く症候群(証)として捉える。
かぜ症候群や便秘、COPD、認知症などに有効。(時間がなく多くは割愛された)
痰が多く肺炎を繰り返すCOPDには清肺湯を漫然と使うのが良い。
「怒りが深く蓄積」、「怒り以外で発散」、というものには抑肝散がよい。
環境の変化に弱い認知症の方のBPSDによく術後のせん妄や小児のADHDなどにも応用される。
井齋先生はもともと外科医で肝臓移植などをやっていた先生だが科学的視点から漢方薬の本質を追求してきたそうだ。マニアックな東洋医学会のやり方に疑問をもち、サイエンスの視点で漢方を読み解き、どの科でも誰でも使えるようにということで国際東洋医学会や和漢医薬学会などを拠点に学術的にも活躍されている。
難解で抽象的な中医学の理論ではなく、現代科学の最新の基礎医学の知識、特にSystem bilogoy的手法を応用して漢方を読み解くというのは実にオモシロイと思った。
実際に現場でも漢方もつかった医療をすべく静内病院を拠点にしているという。
静仁会静内病院は地方の199床(療養型89床)の総合病院(徳洲会系)だが井齋偉矢院長先生がきてから漢方を使う病院として有名になり、特色を出すことで研修の医師を集めているという。
研修医(初期・後期)がローテートで来たり中堅の医師が勉強に来たりと活発なようで(まだまだ来て欲しいと言っていたが・・)これまた僻地の病院に医師を確保する上手いやり方だとおもった。
(※講演のDVDはツムラさんに言えばもらえるみたいです。)










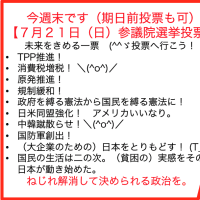
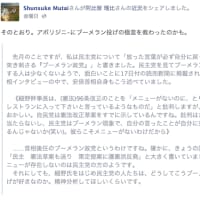








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます