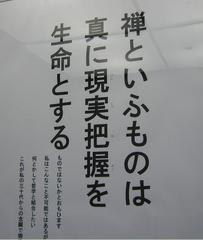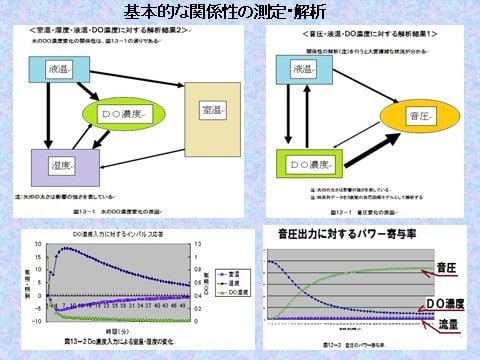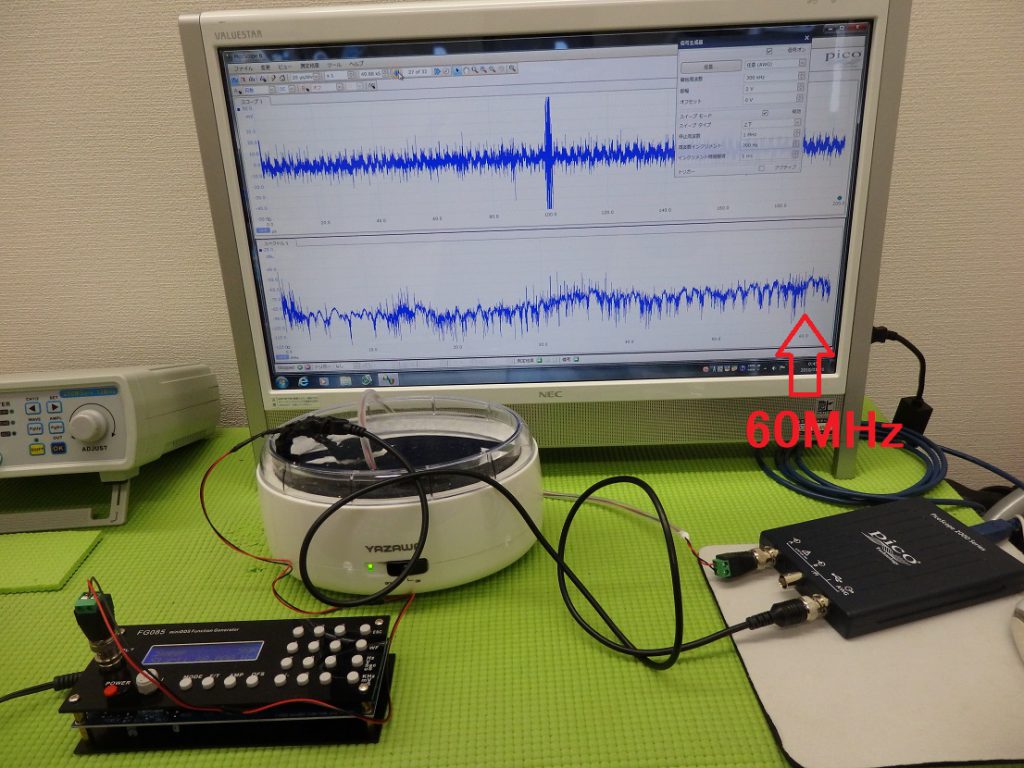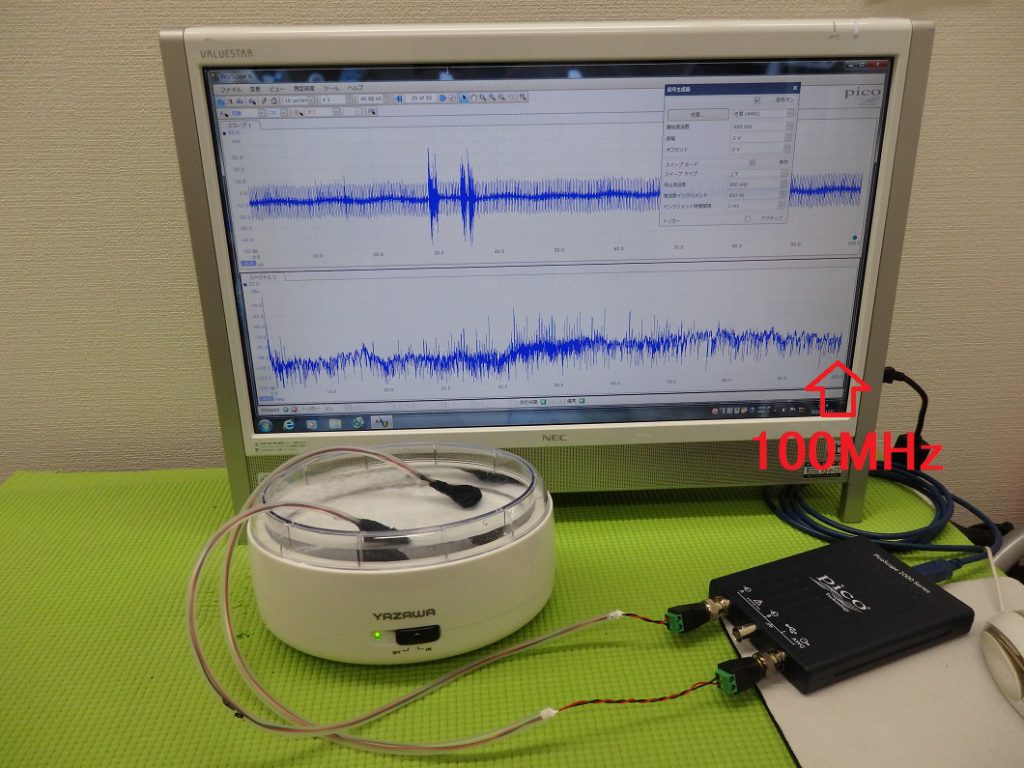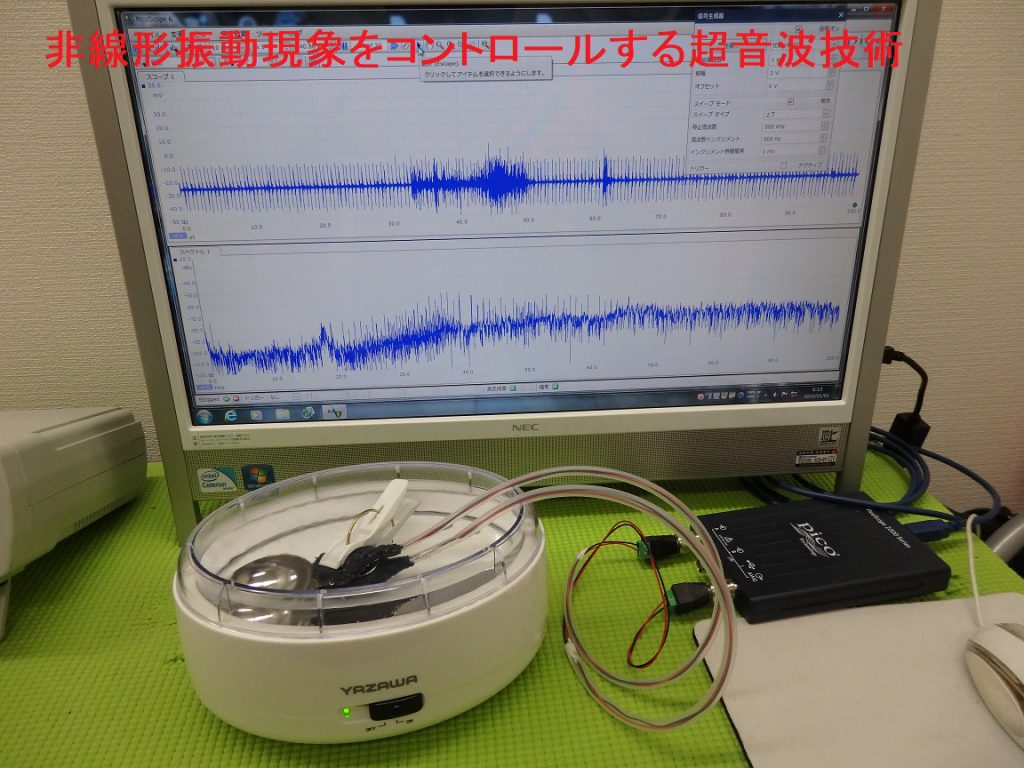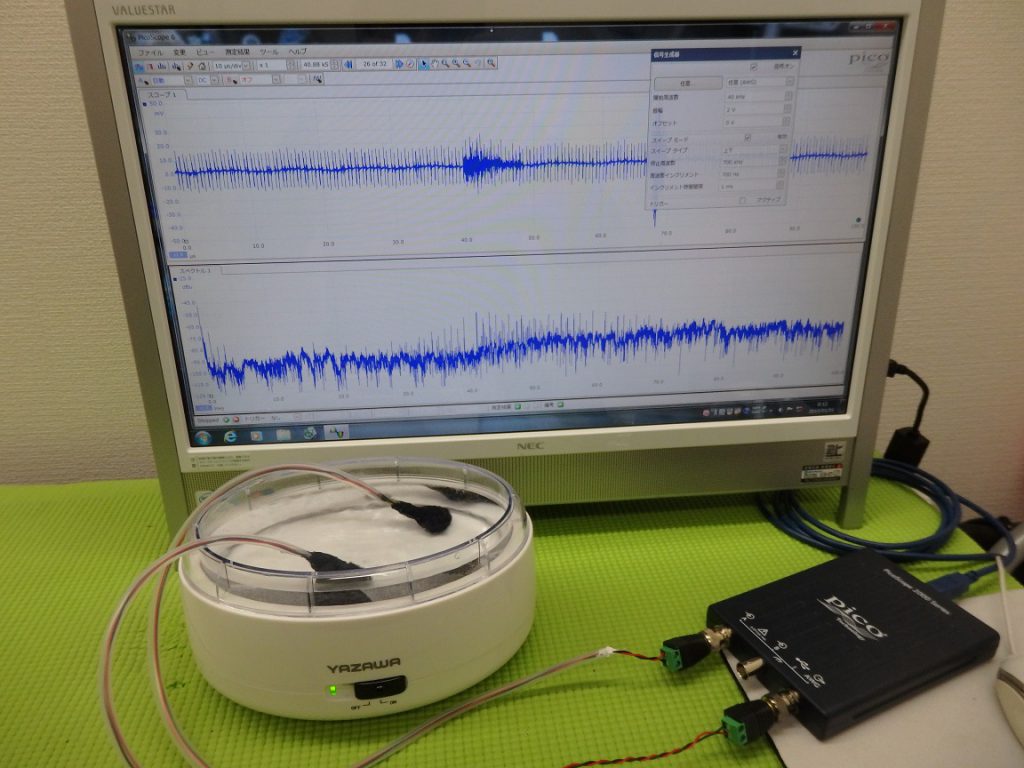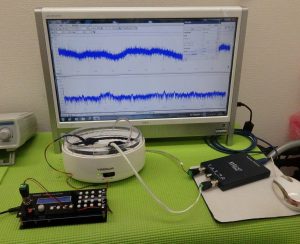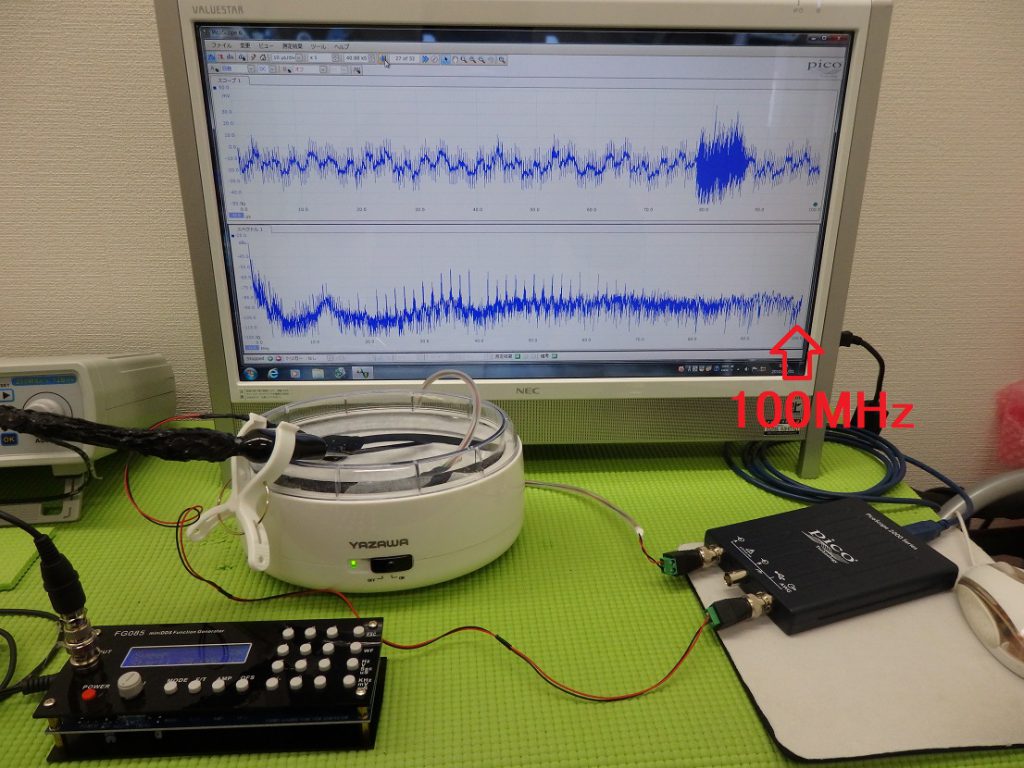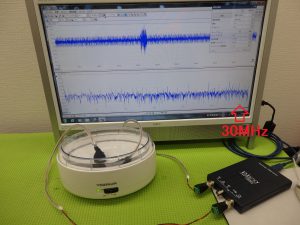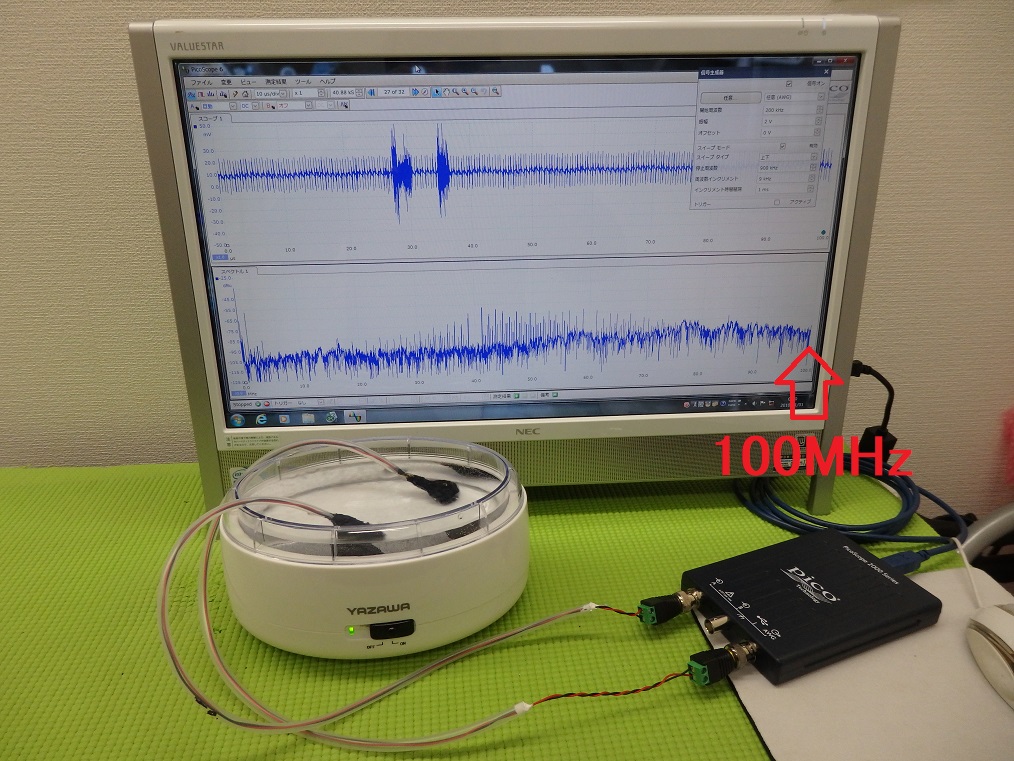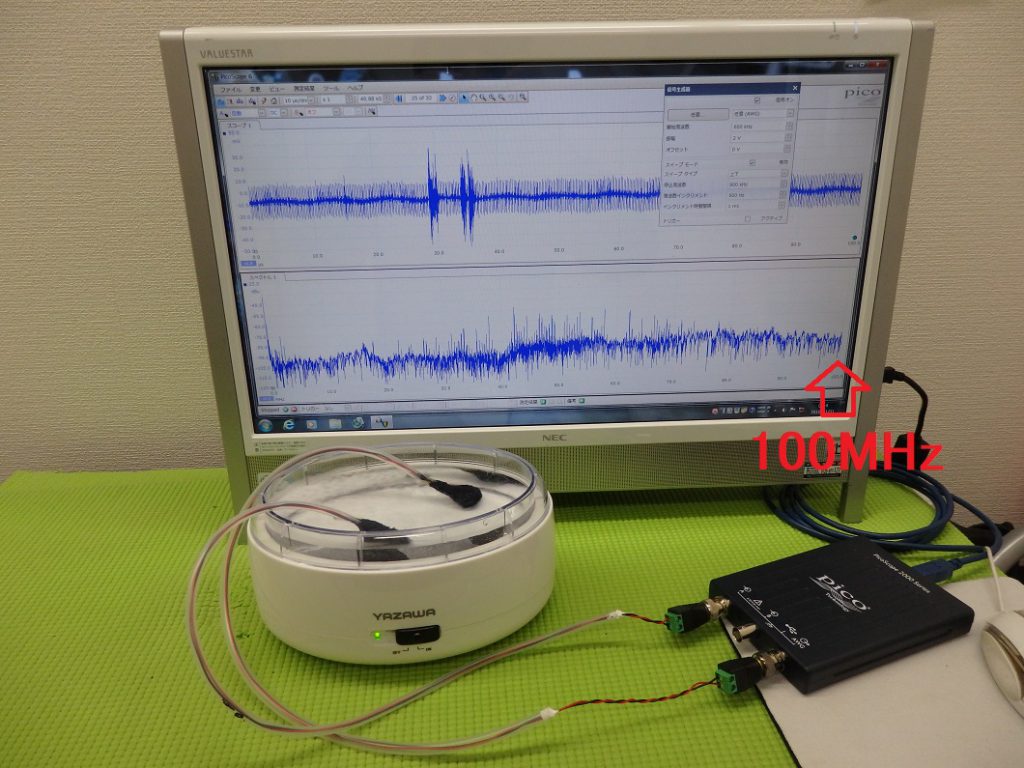長岡先生の休学
湯川秀樹 「創造への飛躍」
長岡先生の休学(昭和四十二年二月)より
人間の一生の中のある時期に自分の生きてゆく道がきまる。
少なくとも一度は、どの道をえらぶかについての決定がなされねばならぬ。
といっても、もちろん自分で決断する機会があたえられるとは限らない。
親のいうとおりにしたとか、自分で考える能力のない小さい時に道がきまってしまっていたとか、
あるいは経済的な事情によって、自分の希望する道が到達不可能だったとかいう場合が、
過去においては非常に多かったであろうし、今日でも少なくないであろう。
私などは仕合わせな人間で、大学教育を受けうる家庭的環境の中で、
高等学校在学中に、自分の意思で物理学者として一生をすごすという決断をすることができた。
それは大正の末期であった。それは私にとって、そんなにむつかしい決断ではなかった。
それにくらべると、私よりずっと前の年代、
特に明治二十年ごろ以前に青年期を迎えた人たちが、
科学者となる決断をするのは、容易なことではなかったはずである。
なぜかといえば、私たちの時代には、すでに多くの先輩の日本人科学者が実在していたのに反して、
明治二十年ごろ以前には、科学に関しては、外国の学者から教えてもらって習い覚えるとか、
外国の研究を追試するとかいう以上のことが、まだほとんど何もなされていなかったからである。
そういう時代に科学者となる決断をするに至った青年たちの心境は、どんなものだったのか。
人によって、また選んだ専門によって、いろいろな違いもあったろうが、
しかし、それらの間の違いよりも、それらと私たちの場合との違いの方がずっと大きいのではないか。
そんなことをかねがね私は漠然と考えていた。
ところが、つい先ごろ私はこの点に関する非常に興味ある文献が残っているのを知った。
それは長岡半太郎先生が八十五歳でこの世を去られる数年前に書かれた
「中学卒業後の指針」と題する開成中学での講演の原稿である。その中に次のような文章がある。
「私の時代には大学に入る予備校すなはち今の高等学校には、文理の区別はなく、
今日より選択には幾分の余裕が存しましたが、私は一時相当に苦しみました。
(…中略…)大学に入りて一年経過いたしましたとき、
多少欧米で研究された事項を了解いたしましたが、自分は他人のなした後を追うて、
外国から学問を輸入し、これを日本人間に宣伝普及する宿志ではありませんでした。
必ずや研究者の群れに入りて、学問の一端を啓発せねば、男子に生まれた甲斐がない」
ここまでは、私が物理学の研究者になろうと志したのと、大して変わりはない。
大正末期と明治二十年ごろとの大きな違いは、その次の文章に、はっきりと現れてくる。
「東洋人は研究に堪能でないか否やを明白にして、
しかる後おもむろに将来の方針を一定するが得策であると考へました。
まだ春秋に富んでいるから、一年を棒に振ったところで損をすることは僅かである。
もしあやまてば取り返しのつかぬ事態に遭遇するから、決然一年休学を願い出て、
支那における科学に関する事項を調べてみました」
はじめて、この文章に接した時の私は、驚愕の念を禁じえなかった。
二十歳になるやならずの青年が、自分の前途を決定するために、
決然として大学生としての一年間を棒に振る。
常人の考えることではない。考えても容易に決行できることではない。
さて大学生、長岡半太郎氏の休学一年間の調査の結果は、次の文章で示されている。
「支那における渾天儀(天文観測機)、暦法、指南軍(黄帝)、
北光の観測(山海経)、有史以前に属します。
○戦国時代恒星表(石氏、甘氏)、太陽黒点(?)、天の蒼々たる、これ本色か(荘子)、
微分の観念(恵施)、共鳴の実例(荘子)、雷電の説明(荘子)、
エネルギーの概念(荘子)(二千三百年前)、金属の研究、
○銅錫の合金(礼記、周公、二千九百年前時代)、鉄製刀剣(二千二百年前)。
大砲と解釈される霹靂車、すなはち火薬の利用(千七百五十年前)。
ことごとく支那独創的のもの。ギリシャ、ローマより渡来せるにあらず。」
かくして得られた結論は、
「これほどの研究があるからには東洋人でもこれに専念すれば終に
欧米に遜色なきに至らんと確信を得るに至りました。
これが私をして物理学に執着するに至らしめた根源であります」
長岡先生の出発点が、このようであったればこそ、
果たして明治三十七年(一九〇四年)には
世界の物理学者に先駆けて原子模型に関する論文を発表するに至ったのである。
今にして思えば、このような大先輩を日本人の中に見出していたことが、
大正末期の高校生であった私をして、迷うことなく、
物理学研究の道を選ばしめる要因の一つとして大きく作用していたのではなかろうか。
最近の中国古代の科学史の研究の成果が、長岡先生の調査結果を、
どこまで裏書しているかについて、私はまだ詳しく検討していないが
、少なくとも「当たらずといえども遠からず」といってよいであろう。
先生は特に「荘子」が好きであったらしいが、私自身も「荘子」の愛読者である。
そこには偶然の一致以上の理由があるに違いない。
この講演の原稿の最後は、もしも調査結果が思わしくなかったと仮定した場合、
どの道を択んだであろうかと問われたなら、 「恐らく東洋史を攻究したらうと思ひます」
という文章で終わっている。
この数年来、日本や東洋や、さらには人類全体の歴史に対する関心が、
とみに強まってくるのを感じている私は、この最後の文章にも「なるほど」と相槌を打ちたくなるのである。湯川秀樹 「創造への飛躍」長岡先生の休学(昭和四十二年二月)より