



 お題『なんじゃこりゃ~』
お題『なんじゃこりゃ~』
 ダチョウ倶楽部のかつてのギャグ 「ヤー!!」
ダチョウ倶楽部のかつてのギャグ 「ヤー!!」
オモロイこの壁画~
ご存知の御方も~そうでない御方も~
お付き合いください
![]()
人気ブログランキングへ
 ≪うー散歩≫上野3153(サイゴーサン)界隈編
≪うー散歩≫上野3153(サイゴーサン)界隈編
~第 2 話~ 



誠にお忙しい中 申し訳ございませんが
ご一緒していただける御方
どうかボチッとお願いします
















↓ 昨日ご紹介した~ 『UENO3153』屋上にて
『UENO3153』屋上にて

↓ 小さな庭園になっていまして
青空が気持ちいいです…
画面中央に

 『東京スカイツリー』が見える御方
『東京スカイツリー』が見える御方
ラッキーです
画面左側の外壁に接近します




↓ このピカピカのガラスの中には~
貴重な 『歌川 広重』の浮世絵があるんですよ。。
『歌川 広重』の浮世絵があるんですよ。。
※反射して何がなにやらわかりません…ゴメンチャイ


↓その浮世絵は~
 『東都名所 上野東叡山全図』
『東都名所 上野東叡山全図』

↓ 西郷さんからは
スカイツリーの更に左手後方にあるため
この浮世絵は見えません

↓ だーーれも上野の山に ひと気がなくなった頃
ひと気がなくなった頃
ご覧になっていらっしゃるかも

↓ 上野の山 を下りてみましょう
を下りてみましょう
ワタクシも歩き方がカッコよくないのですが
階段を下りていく際~がにまた歩きはいけませんね。。



『一本の線を歩く』ように…スマートに歩いていきたいものです


↓上野駅方向へ…更に階段を下りていきましょう




↓ズーム…おおおぅ
台東区界隈の循環バス『東西めぐりん』が通過していきます




↓ 突然ですが~
 《京成上野駅(東京都台東区)》にて無料で見ることができるコレ
《京成上野駅(東京都台東区)》にて無料で見ることができるコレ
なにやら…魚の尾ひれ
素材は…瓦

↓ 冒頭の 陶板壁画が~こんなところにあります
陶板壁画が~こんなところにあります
 鯉のぼりと風車をイメージしていたそうです!!
鯉のぼりと風車をイメージしていたそうです!!
「屋根よ~り高い 鯉の~ぼり~」
見た目は気持ち悪いけど、
日本人の心に訴えかけるものがある素敵な藝術作品

↓左端にあった 『風車』をズーム
『風車』をズーム

↓この陶板壁画を制作したのは、 『ルイス・ニシザワ』
『ルイス・ニシザワ』
彼の祖国は~メキシコ
メキシコを代表する国民的画家。
また、ニシザワという名前からも想像がつくように、
日系二世の御方

↓作品のタイトルは 『風月延年』
『風月延年』

↓ 本日の〆はコチラ…
魚に食われた子供に見えた御方…
ご安心くださいワタクシもです


人気ブログランキングへ
 ≪うー散歩≫上野3153(サイゴーサン)界隈編
≪うー散歩≫上野3153(サイゴーサン)界隈編
~第 2 話~ 



本日は 17 枚 にて、綴らせていただきました。
少しでも…オモロイと感じていただけた 御方
どうかボチッとお願いします




































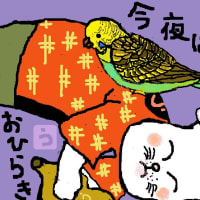
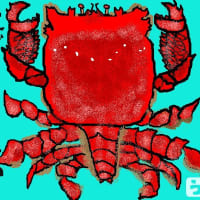


何これですね~
そして最後まで来て鯉のぼりと風車だったのですね。
ふ~ん、なるほどでした。
そして上野3153界隈素敵に楽しませていただきました。
ごめんなさい、作者の方。見えません。笑
これって最近ですよね。見たことがありませんよ。
よかった~教えていただいて。感謝です。
12時を過ぎました。ので、こんにちわ~。
銅版画 最後まで見ないと解りませんね。
子供がお魚に飲まれている~~~では
なくて、「鯉のぼり」でしたか!
手?鯉幟にも手があるんだ~傑作です。
スカイツリー見えますよ。
本物も見たいです。
いつのことやら・・・
珍しいものは、(うーたま)さんに見せて
いただきましよう~
疲れなくていいわ
広重さんの絵に雲がかぶって見えるのも素敵ですね^^
ぽち☆
面白いですね
なにこれ?って思いました
鯉のぼりだなんて
うーーーーん、何処を見ても
そう見えない・・・(汗)
ポチ
鯉のぼりと風車を イメージした作品ですか?
何ともユニークですねぇ~
鯉にお手手が出て へっぇ~傑作なんだぁ~
こういう風なのが 芸術品なのですね?
頭を切り替えなきゃです。
京成上野駅を利用したことが無いので初見~@@!
早速見て来ますね。
余談ですが上野のお山を下りる階段、悲しいイメージにつながるのですヨ。
終戦直後、疎開先から降立った上野駅、
あの階段には焼け出された浮浪者で埋め尽くされていました。
子供心に足が震え、父親の手を握り締めた思い出があります。
今はのどかで幸せですね。
アッ、あの階段下りるおばさん、ワタシでした~(爆)))
撮られちゃったのね!!!
私の我儘に答えていただいて
ありがとうございました。
力強い子供を表現というより
やっぱりのみ込まれているように見えます。
でも色づかいは好きです。
上野からではスカイツリーはちょっと遠いですね。
うーたまさんが、東京ガイドさんに思える
このごろ。
東京スカイツリー、東京名所になっているんですね。
上野とスカイツリーの距離、
さっぱり見当がつかず、へぇ~っと眺めるばかりです。
面白いものを見させていただきました。
こうしたものが街中のあちこちに見ら
れるから都会は面白い。
こうした芸術と企業経営やイベント企画
他諸々のことにこうした個性と独走が、
あいや独創性が必要でしょう。日々
仕事をしていまして、やはりこうした感覚
は大切だとつくづく感じています。