そして製作開始。
小さなオルガン工房で親方と先輩ひとり、研修期間もなく比較的容易な仕事から始めました。
電動工具程度は扱ったことはあっても木工機械は初体験で実戦です。
いきなり実戦はガンダムの基本よ。
マホガニーの塊を自分達で製材して乾燥、そして加工。
僕はこまごまとした部品や第2鍵盤の風箱、木管4フィートの製作と整音などを。
初心者でこれほどやらせてもらえるというのは、およそあり得ないほどラッキーなことなのですが、当時は気付きませんでした。
さて、最終局面、オルガンの装飾部分で問題発生。
これはモダンデザインの楽器では格子状の幾何学パターンであることが多いのですが、歴史的オルガンを目指す工房としてはそれはありません。透かし彫りの彫刻になります。
彫刻は大きな仏像を作っているグループ(仏師ではなかったようです)に依頼したのですが、仕上がって来たのを見てびっくり、水煙とも伽流羅炎ともつかない「くねくね」だったのです。
オルガンに取り付けて見たら安い仏壇のようになってしまいました。
親方の気に入るはずもなく使用中止となりました。
そこで、あのデザインはどうのこうのと調子に乗って語っていたワタクシに白羽の矢がプスッ。
「資料とダメは出すが指導はしない」という暖かい親方のお言葉のもと、装飾のデザインと彫刻をやることになっちまいました。
それからの日々はそりゃもう大変でした。
あくまでヨーロッパの伝統に立脚したデザインで、しかも自分の技量で何とかなること。
ギリシャからの装飾デザインの変遷、キリスト教美術史を日夜圧縮で自分に叩き込みました。
初めからどこかの楽器のデザインをコピーするということは考えていませんでした。
当時職歴数か月の23歳かそこらの若者のささやかな意地ってものでしょうか。
眠れず半覚醒状態の夜、天井からアカンサスやグロテスクが降ってくる幻影なんかが現れたものです。
良いデザインを思いついても自分の技能不足で実現困難ゆえ廃棄というのも悔しかった。
そんな風に必死に仕上げたのです。
今見ても技術的には拙いけれど何か迫力のようなものは感じますね。
次回は写真入です。
小さなオルガン工房で親方と先輩ひとり、研修期間もなく比較的容易な仕事から始めました。
電動工具程度は扱ったことはあっても木工機械は初体験で実戦です。
いきなり実戦はガンダムの基本よ。
マホガニーの塊を自分達で製材して乾燥、そして加工。
僕はこまごまとした部品や第2鍵盤の風箱、木管4フィートの製作と整音などを。
初心者でこれほどやらせてもらえるというのは、およそあり得ないほどラッキーなことなのですが、当時は気付きませんでした。
さて、最終局面、オルガンの装飾部分で問題発生。
これはモダンデザインの楽器では格子状の幾何学パターンであることが多いのですが、歴史的オルガンを目指す工房としてはそれはありません。透かし彫りの彫刻になります。
彫刻は大きな仏像を作っているグループ(仏師ではなかったようです)に依頼したのですが、仕上がって来たのを見てびっくり、水煙とも伽流羅炎ともつかない「くねくね」だったのです。
オルガンに取り付けて見たら安い仏壇のようになってしまいました。
親方の気に入るはずもなく使用中止となりました。
そこで、あのデザインはどうのこうのと調子に乗って語っていたワタクシに白羽の矢がプスッ。
「資料とダメは出すが指導はしない」という暖かい親方のお言葉のもと、装飾のデザインと彫刻をやることになっちまいました。
それからの日々はそりゃもう大変でした。
あくまでヨーロッパの伝統に立脚したデザインで、しかも自分の技量で何とかなること。
ギリシャからの装飾デザインの変遷、キリスト教美術史を日夜圧縮で自分に叩き込みました。
初めからどこかの楽器のデザインをコピーするということは考えていませんでした。
当時職歴数か月の23歳かそこらの若者のささやかな意地ってものでしょうか。
眠れず半覚醒状態の夜、天井からアカンサスやグロテスクが降ってくる幻影なんかが現れたものです。
良いデザインを思いついても自分の技能不足で実現困難ゆえ廃棄というのも悔しかった。
そんな風に必死に仕上げたのです。
今見ても技術的には拙いけれど何か迫力のようなものは感じますね。
次回は写真入です。















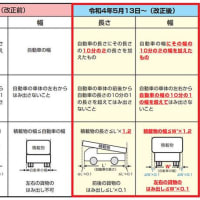




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます