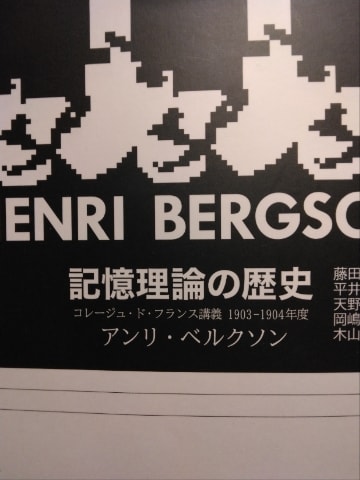柄谷行人がいうように、マルクスの「資本論」は、カントール、あるいはゲーデルの「数学基礎論」、フロイトの「心理学批判」、ソシュールの「言語学批判」と通底する基礎論的な問いの書であり、マルクスの『資本論』は経済学の書というよりは、そのサブタイトルが示すように、あくまでも「経済学批判」の書であるように、私には、思われる。
柄谷行人は、様々な分野の思想家が、その学問的、思想的な探求の頂点で、基礎論的な問いのなかに在る、同じひとつの問題、にぶつかることを、『隠喩としての建築』のなかで、
「それ(→原理論的な思考)は、ゲーデルの定理を他の領域に翻訳することであるよりも、逆にゲーデルの定理こそ、本来数学とは無縁な問題、すなわち、『言語は言語についての言語である』という自己言及性の問題が数字のレベルであらわれたのである。
ゲーデルの定理が形先体系一般に当てはまるとすれば、それは『形式化』が数学そのものとはべつのところからきているからだ。
そして、19世紀後半にはじまる数学基礎論(カントール)は、経済学(マルクス)、心理学(フロイト)、言語学(ソシュール)などの領域における基礎論的な問いと通底するのである」
と表現している。
原理論的な思考を押し進めていくと、最終的には、その思想や学問の基礎的な部分に辿り着くのだが、その基礎的部分は、実は、その思想や学問独自の基礎であることは出来ず、あらゆる人間の思考一般が依拠している基礎である他はないようである。
その基礎論の場所はもはや、数学、経済学、心理学、言語学といった学問的枠組みが通用しない場所であり、数学も経済学も心理学も言語学も、また文学や文芸評論も、柄谷行人のいう「基礎の不在」という現実に直面するのであろう。
もはやそこでは、「科学的」とか「論理的」とか、あるいは「数学的」とかいったことばは、いかなる説得力も持たず、そこでは、文学も数学も科学も等価で、同じように基礎の不在に直面しているのだろう。
たとえば、マルクスが、『資本論』のなかで、
「価値形態、その完成した姿である貨幣形態は、はなはだ無内容かつ単純である。
にもかかわらず人間の頭脳は、二千年以上も前からこれを解明しようとつとめてきてはたさず、しかも他方、これよりはるかに内容ゆたかで複雑な形態の分析には、少なくともほぼ成功している。
なぜだろう?
成体は、体細胞よりも研究しやすいからである。
しかも、経済的形態の分析においては、顕微鏡も、化学試薬も、役に立たない。
抽象力が両者に変わらなければならない」
と述べるとき、価値形態の分析が、あらゆる学問的、思想的、芸術的思考が直面する基礎論的な問いのなかで、「基礎の不在」に直面するため、価値形態の分析には、顕微鏡も化学試薬も役に立たない、と表現しているのではないだろうか。
「商品」の分析から始まるマルクスの『資本論』は単に経済学の書では在りえず、経済学という入口から入りながらも、経済学を超えた基礎論的な問いを問うた書であるように、私には、思われる。
柄谷行人は、マルクスをマルクスたらしめているのは、この「価値形態論」の部分であり、しかも、この「価値形態論」の部分を除いたら、マルクスは、古典経済学や、ヘーゲルの、単なるいち亜流に過ぎないという。
柄谷行人によれば、マルクス主義者やマルクス研究者たちは、ほとんど、この「価値形態論」を問題にすらしてこなかったのだが、それは「マルクス主義」という形而上学にとって必要不可欠なものどころか、不要だったからだとも、いう。
しかし、柄谷行人は、ここにこそマルクスが、ヘーゲルや古典経済学と異なる根拠を見出し、この「価値形態論」のなかに、現代的なあらゆる思考が直面している、もっとも原理的な、基礎論的な問題を見出したのであろう。
マルクスの価値形態論とは、単なる価値の問題ではなく、人間の思考の本質そのものとして重要なのではないだろうか。
たとえば、マルクスが批判した古典経済学では、使用価値と交換価値を区別する。
つまり、商品にはそれぞれ内在的な価値があり、それが貨幣によって交換されるのだが、そこに交換価値が発生するため、商品は、使用価値と交換価値の二重性によって存在しており、貨幣が共通の普遍的な尺度として機能する。
言い換えれば、貨幣は単なる手段にすぎず、それは商品の価値の表示であるに過ぎないのである。
古典経済学は、商品の価値は、その商品に費やされた労働時間である、という労働時間説によって、貨幣を二次的なものとみなした。
つまり、ここには、交換に先立って、商品の価値が存在するという、いわゆる実体論的な思考が前提とされているようである。
これに対して、マルクスが価値形態論で明らかにするのは、交換に先立って価値が存在するという考え方ではなく、交換されることにより、その結果として価値が生み出されるという考え方である。
ここには、超越論的な価値(意味)の否定があり、実体論的な思考が否定されているのだが、マルクスは、それを明確に、体系的に語っているわけではない。
マルクスの思考にも、様々な試行錯誤があり、混乱があるようである。
マルクスは、『資本論』のなかでも、しばしば古典経済学的な思考にとらわれているようであり、たとえば、剰余価値を論じるときに、マルクスは、古典経済学的な労働時間説を採っているし、またふたつの相異なる商品が等価であるためには、なにか「共通の本質」がなければならないし、そしてそれは、商品に対象化された人間的労働だと言っているのだが、これは、価値や意味を実体化した考え方であろう。
しかし、マルクスはここにとどまっているのではないようである。
柄谷行人は、このことについて、『マルクスその可能性の中心』のなかで、
「彼は、等価の秘密を諸商品の『同一性』に還元する。
しかし、そのような同一性は貨幣によって出現するのだ。
貨幣形態こそ、価値形態をおおいかくす。
したがって、貨幣形態の起源を問うとき、マルクスは、もはや『等価』や『共通の本質』という考えを切りすてている。
それらこそ、価値形態の隠蔽においてあらわれるのだからである」
と述べているが、ここに柄谷行人のマルクス論の核心が、あるように、私には、思われるのである。
やはり、柄谷行人がいうように、マルクスの「資本論」は、カントール、あるいはゲーデルの「数学基礎論」、フロイトの「心理学批判」、ソシュールの「言語学批判」と通底する基礎論的な問いの書であり、マルクスの『資本論』は経済学の書というよりは、そのサブタイトルが示すように、あくまでも「経済学批判」の書であるように、私には、思われるのだが、柄谷行人が『マルクスその可能性の中心』以降、絶えずマルクスを引用し、マルクスを問うのは、マルクスのなかに、原理論的な思考を見出しているからであり、また、マルクスのテクストが基礎論的な問いを内包しているからであろう。
柄谷行人は、マルクスを問うことによって、経済学や哲学の問題を問うているのではなく、あるひとつの基礎論的な問いを問うているのだといえるのかもしれない。
柄谷行人にとって、価値形態論の解釈の他に、マルクスの文体についても問題にしており、これは、いわゆるマルクス主義者やマルクス研究者たちとの分岐点となり、柄谷行人のマルクス論が、小林秀雄のそれに急接近する点ともなっているようである。
柄谷行人は、『マルクスその可能性の中心』のなかで、マルクスの文体について、
「マルクスの文体が著しく変わるのは、『ドイツ・イデオロギー』以後である。
そして、思想家が変わるとは文体が変わるということにほかならない。
理論的内容が変わっても文体が変わらなければ、彼は少しも変わっていない。
ヘーゲルから切れることは、さしあたりヘーゲル的ターミノロジーから切れることである」
と述べている。
文体は、理論や思想と切り離すことは出来ず、文体は文体だけで存在できず、理論や思想もそれだけでは存在することはできないだろう。
マルクス自身も『ドイツ・イデオロギー』において、ドイツの古典哲学の文体を問題にし、それ以降、ドイツ哲学の文体から離れたようである。
それは、ドイツ哲学、主にヘーゲル哲学から離れることでもあるのだが、それは単に、理論的な内容のレベルにおいて達成できることではなく、別の困難を含んでいるのだろう。
そこで、マルクスは、ドイツ哲学の内容を問題にするのではなく、ドイツの哲学者たちを問題にした。
このことについて、柄谷行人は、『マルクスその可能性の中心』のなかで、
「しかし、『ドイツ・イデオロギー』におけるマルクスは、むしろ『真理への意志』そのものを解釈しようとしている。
彼が問題にするのは、哲学というよりも哲学者という存在だ。
『真理への意志』は、哲学者という存在(階級)と切りはなすことが出来ないからである。
ニーチェが言ったように、ある言説で『何が語られているか』ではなく、『誰が語っているか』が問題なのだ。
いうまでもなく哲学者が語っている。
しかし、これまで『哲学者』という存在は誰も問題にしなかった。
真理や本質のなかに、哲学者は身をくらましてきたのである」
と述べている。
柄谷行人は、ニーチェに続いてマルクスも、哲学ではなく、哲学者を問題にしたという、重要な指摘をしている。
マルクスが価値形態論で明らかにしたことは、古典物理学がそうであったように「観測するもの」が「観測されるもの」から切り離され、メタ・レベルに特権化されていたということと、「逆のこと」なのではないだろうか。
価値は交換に先立って実在するものではなく、交換という実践のなかで、事後的に発生するものであろう。
古典経済学において自明の物とみなされている価値、つまり、相異なる商品に内在する超越論的な価値は、貨幣形態によって与えられるものにすぎない。
貨幣は価値を代弁するのではなく、貨幣が価値を産み出すのである。
いわば、古典経済学が理想とする等価交換は、何の実在的根拠をも持っていないといえるのかもしれない。
貨幣による交換により、相異なる商品の差異が消去され、価値=概念=意味として同一化され、その結果として、人々は、交換は、同一の価値を有する商品と商品とが交換されると錯覚するようになるのだろう。
マルクスが『資本論』の価値形態論で明らかにしようとしたのは、この錯覚であったが、この錯覚は単に経済学の問題にとどまるものではないのだろう。
この問題は、言語学、物理学、数学といった、あらゆる学問領域に通底する問題ではないだろうか。
柄谷行人は、それを「基礎の不在」とか、「自己言及のパラドックス」あるいは「外部」といったことばで表現し、その根底にある問題を明確化しようとしているのであろう。
しかし、それは、理論や思想として語れるものではなく、それが理論や思想として流通したとき、問題の本質は、見失われてしまうのではないだろうか。
ここまで、読んで下さり、ありがとうございます。
見出し画像は、最近読み始めた本です😊
興味深い本で、私は、かつて落ちこぼれながら😅商学部にいたことを、なんだか思い出しました😊
今日も、頑張り過ぎず、頑張りたいですね。
では、また、次回。