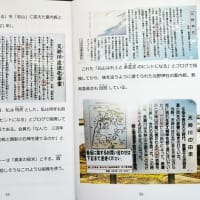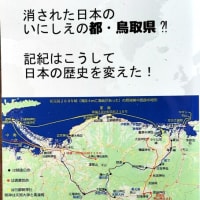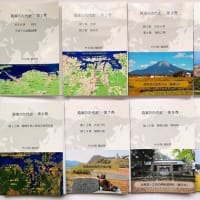1 第23代、第24代、第25代、第26代天皇は百済王家の王であり事績も百済であった出来事である。
弘計や億計の話は百済国であった出来事である。億計の名前は亡命百済人の医師憶仁や山上憶良を連想させる。神楽歌における囃し言葉を「おけおけ」という。祭りの中でも神楽のようなにぎやかな祭りは百済発祥である。逆に盆正月のような静かな祭りは新羅発祥である。弘計や億計の話は列島の地名をちりばめて、列島を舞台にした。その父を殺した雄略天皇を残虐な天皇にする必要があった。
雄略の旧辞は証明できる部分があるので、原古事記にあった旧辞を使っている。ただし、一言主は事代主と書いてあったのを改ざんしている。雄略は実在の倭国天皇(倭王武)である。雄略も倭国の天皇なので、無駄な殺生はしない天皇であった。わずかなことで人を殺すような天皇に仕立て上げたのは、藤原氏である。
藤原氏は無道な百済王(末多王)の事績を日本書紀の武烈天皇の旧辞に持ってきている。武烈天皇(末多王)のような事績を無道と言うのである。百済の国人は末多王を捨てて、武寧王を立てた。継体天皇のモデルは武寧王である。
23代天皇~26代天皇の旧辞と名は百済王の旧辞と名である。第23代と第24代は倭国では1人の天皇であった。石上広高宮(倉吉市大原)に皇居があった1人の天皇の在位期間を2人に分けた。
弘計や億計の話は百済国であった出来事である。億計の名前は亡命百済人の医師憶仁や山上憶良を連想させる。神楽歌における囃し言葉を「おけおけ」という。祭りの中でも神楽のようなにぎやかな祭りは百済発祥である。逆に盆正月のような静かな祭りは新羅発祥である。弘計や億計の話は列島の地名をちりばめて、列島を舞台にした。その父を殺した雄略天皇を残虐な天皇にする必要があった。
雄略の旧辞は証明できる部分があるので、原古事記にあった旧辞を使っている。ただし、一言主は事代主と書いてあったのを改ざんしている。雄略は実在の倭国天皇(倭王武)である。雄略も倭国の天皇なので、無駄な殺生はしない天皇であった。わずかなことで人を殺すような天皇に仕立て上げたのは、藤原氏である。
藤原氏は無道な百済王(末多王)の事績を日本書紀の武烈天皇の旧辞に持ってきている。武烈天皇(末多王)のような事績を無道と言うのである。百済の国人は末多王を捨てて、武寧王を立てた。継体天皇のモデルは武寧王である。
23代天皇~26代天皇の旧辞と名は百済王の旧辞と名である。第23代と第24代は倭国では1人の天皇であった。石上広高宮(倉吉市大原)に皇居があった1人の天皇の在位期間を2人に分けた。
2 第13代、第14代、第15代、第16代
日本書紀は百済王が倭国大王を下僕として(大臣として)使うという構成をとる。たとえば、蘇我氏である。蘇我氏は大王であったのに、日本書紀では大臣として書かれている。武内宿禰もその例であり、倭国大王であったが、大臣として百済王や百済の皇后に仕えたように書いた。神功皇后は新羅を敵対視しているから倭国の皇后ではなく百済の皇后として書かれている。ただしそのモデルは倭国女王の豊鋤入姫(台与)である。日本書紀には百済の皇后として神功皇后の段を設けた。神功皇后と第14代仲哀は百済の皇后と百済王である。史実と原古事記は仁徳天皇が第14代天皇であったが百済王の仲哀を第14代にしたので仁徳天皇を第16代にした。武内宿禰は実在の倭国の第13代の大王であるが、叔母の豊鋤入姫(台与)と行動を共にしていた。
日本書紀は百済王が倭国大王を下僕として(大臣として)使うという構成をとる。たとえば、蘇我氏である。蘇我氏は大王であったのに、日本書紀では大臣として書かれている。武内宿禰もその例であり、倭国大王であったが、大臣として百済王や百済の皇后に仕えたように書いた。神功皇后は新羅を敵対視しているから倭国の皇后ではなく百済の皇后として書かれている。ただしそのモデルは倭国女王の豊鋤入姫(台与)である。日本書紀には百済の皇后として神功皇后の段を設けた。神功皇后と第14代仲哀は百済の皇后と百済王である。史実と原古事記は仁徳天皇が第14代天皇であったが百済王の仲哀を第14代にしたので仁徳天皇を第16代にした。武内宿禰は実在の倭国の第13代の大王であるが、叔母の豊鋤入姫(台与)と行動を共にしていた。
3 武内宿禰と平群木菟宿禰と葛城襲津彦は倭国の大王であった。亡命百済人たちは蘇我氏と同じく倭国大王を百済王に仕える下僕として描いた。日本書紀は百済王家の歴史を記録したものという体裁である。
第13代は武内宿禰大王である。日本書紀には「成務は、同日の生まれであることから武内宿禰を特に可愛がられた。」とある。在位は280年~320年頃である。
第14代仁徳天皇(仲哀は架空天皇)は武内宿禰の四男・平群都久宿禰 (平群木菟宿禰)である。日本書紀には「仁徳天皇と同日に生まれ、飛び込んできた鳥の名を交換して各々の子に名づけた。」とある。在位は320年~354年頃である。
第15代応神天皇は葛城襲津彦(葛城長江曾都毘古)であった。武内宿禰(成務天皇)の六男であり事績が多く書いてある。在位は354年~394年頃である。
藤原氏は崇りを鎮めるために、神功皇后(台与)を稚日女命(卑弥呼)を祀る神社の由緒に登場させて持ち上げている。
第13代は武内宿禰大王である。日本書紀には「成務は、同日の生まれであることから武内宿禰を特に可愛がられた。」とある。在位は280年~320年頃である。
第14代仁徳天皇(仲哀は架空天皇)は武内宿禰の四男・平群都久宿禰 (平群木菟宿禰)である。日本書紀には「仁徳天皇と同日に生まれ、飛び込んできた鳥の名を交換して各々の子に名づけた。」とある。在位は320年~354年頃である。
第15代応神天皇は葛城襲津彦(葛城長江曾都毘古)であった。武内宿禰(成務天皇)の六男であり事績が多く書いてある。在位は354年~394年頃である。
藤原氏は崇りを鎮めるために、神功皇后(台与)を稚日女命(卑弥呼)を祀る神社の由緒に登場させて持ち上げている。
4 倭の五王の讃の在位期間は正しいと思われるので、仁徳と履中の期間は1人の天皇であった。これを履中天皇(讃天皇)とすると、第16代仁徳天皇(平群木菟宿禰)は別の時代の天皇であったことになる。
仁徳天皇は原古事記では13代武内宿禰天皇の皇子として第14代天皇であったが、仲哀を創作し、仲哀を第14代に持ってきたため日本書紀では第16代に移動させた。史実と原古事記は仁徳天皇(竹内宿禰の第4子・平群都久宿禰)は第14代天皇であった。履中(讃)は応神の第1子であり、反正(珍)は応神の第3子であり、允恭(済)は応神の第4子である。
仁徳天皇は原古事記では13代武内宿禰天皇の皇子として第14代天皇であったが、仲哀を創作し、仲哀を第14代に持ってきたため日本書紀では第16代に移動させた。史実と原古事記は仁徳天皇(竹内宿禰の第4子・平群都久宿禰)は第14代天皇であった。履中(讃)は応神の第1子であり、反正(珍)は応神の第3子であり、允恭(済)は応神の第4子である。
5 武内宿禰を祀っている宇部神社
宇部神社が武内宿禰を祀っている理由は、鳥取市国府町が宿禰の終焉の地であるから、とする。武内宿禰の生誕地は木国(岡山県津山市)であり本拠地は鳥取県北栄町原であった。
宇部神社が武内宿禰を祀っている理由は、鳥取市国府町が宿禰の終焉の地であるから、とする。武内宿禰の生誕地は木国(岡山県津山市)であり本拠地は鳥取県北栄町原であった。


宇部神社本殿。一角獣の麒麟獅子舞が4月21日の例祭に奉納される。
この本殿は、明治時代の武内宿禰の一円札・五円札の図柄になっている。
この本殿は、明治時代の武内宿禰の一円札・五円札の図柄になっている。

この亀金の地に双履を残して昇天した、享年360歳とある。上述のように武内宿禰は第13代天皇であり少し長寿の普通の天皇であったと思われる。藤原氏は仁徳天皇(平群木菟)を第16代にし、武内宿禰は仁徳天皇に仕えた、と書いたためこのような結果となった。仁徳天皇は史実と原古事記では第14代であった。

子供は、葛城襲津彦に見える。
6 鳥取県神社誌における武内宿禰(第十三代天皇)
武内宿禰を祭神とする宇倍神社のある因幡国と伯耆国の神社数の差に注目すべし(鳥取県神社誌)
因幡国六社
1宇倍神社 岩美郡宇倍野村 2高良神社 八頭郡八東村 3八幡宮 岩美郡倉田村 4湊神社 岩美郡面影村 5神前神社 6山名神社
伯耆国二十二社
1三朝神社 2賀茂神社 旭村 3八幡神社 倉吉町 4天の神奈斐神社 5犬田神社 6宇田川神社 7国信神社 8高田神社 9真子神社 10逢坂八幡神宮 11大港神社 12阿陀萱神社 13長田神社 14高良神社 15実久神社 16堀神社 17福田神社 18根雨神社 19神奈川神社 20江尾神社 21佐川神社 22国英神社
この因幡国と伯耆国との武内宿禰を祭神とする神社数の差は八幡神社に祭られている神社数では説明できない。単独の場合が多い。因幡国と伯耆国の武内宿禰を祭神とする神社は第13代天皇として祀られていたと思われる。武内宿禰は伯耆国、その中で鳥取県中部(北栄町原集落の元野神社)に皇居があったと思われる。