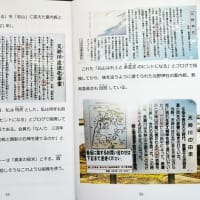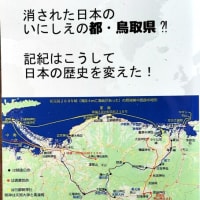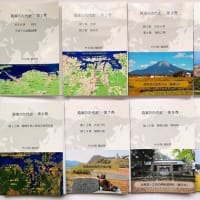ガイドブックによれば、伊射波神社に祀られているのは、稚日女尊、伊佐波登美命、玉柱屋姫命、狭依姫命という4柱の神様で、伊佐波登美命以外は女神とある。
1 狭依姫命(女神)
宗像三女神の一柱である市杵島比売命の別名である。加布良古崎の前海にあたる長藻瀬という島嶼の神乎多乃御子神社のご祭神として祀られていたが、戦国時代の地震によって、その社地は海底1.8mに水没してしまった。幸いご神体は村人らによって見つけ出され、伊射波神社に合祀された。海の守護神として卑弥呼のころに祀ったのかもしれない。もともと伊射波神社の祭神ではなかった。
2 玉柱屋姫命(女神)
伊雑宮の御師・西岡家に伝わる文書には、中世以降に伊雑宮の祭神とされた「玉柱屋姫命」について、玉柱屋姫と瀬織津姫は鎮座顕現する場による呼称のちがいにすぎず、両神は異称同体という認識が記されているそうである。
瀬織津姫は天照大御神の妻であり、天照大御神を女神だとするようになってから、藤原氏が消していったものである。もともと伊射波神社の祭神ではなかった。
3 伊佐波登美命(男神)
伊佐波登美命以外は女神だから伊佐波登美命は男神である。伊佐波登美尊は、倭姫命が天照大神の御魂を鎮座させた折、これを奉迎して鎮座に尽力し、また志摩国の新田開発にも大きな功績を残したと伝えられている。安楽島町には、加布良古崎の伊射波神社以外に安楽島町字二地の贄に伊射波神社本宮がありそこに伊佐波登美命が祀られていたそうである。
安楽島町字二地の贄の遺跡からは、縄文中期から平安中期に至るまでの時代の連続した、おびただしい数の遺物・遺跡が発掘され、皇族、貴族が往来した痕跡が見つかっている。伊射波神社本宮の社殿は贄遺跡の近くの一番高いところにあったそうである。
後、伊射波神社本宮の衰退と共に、伊佐波登美命は加布良古崎の伊射波神社に遷座された。「倭姫命」に仕えた伊佐波登美命はもともと伊射波神社本宮に祀られており、現在の伊射波神社の祭神ではなかった。「倭姫命」と「稚日女尊」は違う神だとすれば、おかしなことをするとなるが、同神だとすれば違和感がない。また安楽島町字二地の贄にあった伊射波神社本宮と加布良古崎の伊射波神社は近いところにある。伊佐波登美命は生前、加布良古崎の伊射波神社の「稚日女尊」のところに行き来していたと思われる。魏志倭人伝には「ただ男子一人あり、飲食を給し、辞を伝え居処に出入す」とある。この男子は伊佐波登美命のことと思われる。
4 稚日女尊(女神)
海部氏系図によると11世孫の日女命は9世孫の日女命と同神であり、11世孫の稚日女命は9世孫の日女尊又の名を倭迹迹日百襲媛命となり、第八代孝元天皇の妹であり、魏志倭人伝にいう卑弥呼である。霊験あらたかな神様として知られる稚日女命は、加布良古太明神とも称され、朝廷に捧げる贄物の一部を太明神にも奉納するという別格の扱いを受けていました。
古代、安楽島の前の海では、朝廷に捧げるアワビを採る神事が行なわれていました。加布良古太明神ともいわれた女神、稚日女尊を姫小松に見立て、「この松は千年の後も栄えるでしょう。加布良古の沖の汐がひいたら、神事で採れた貝を納めに都へ行きます。加布良古の太明神に分け前を奉納してから」と歌にも詠まれています。
稚日女尊は天照大神の妹君、分身とも云われ、第十五代応神天皇の母君である神功皇后の崇敬厚く、皇后が筑紫国から倭国に凱旋した折にも、常に御許においてお祭りされていました。
5 私見
海部氏勘注系図によると11世孫の日女命は9世孫の日女命と同神であることを暗示している。豊鋤入姫命と倭姫命との順番を入れ替えるためにこのような細工をした。本来13世孫の妹であった豊鋤入姫命を10世孫の妹に持ってきた。本来9世孫の妹であった倭迹迹日百襲媛命である日女命を11世孫の妹の日女命に持ってきた。これによって順番は逆になる。11世孫(崇神天皇)の妹の日女命とされる稚日女命・倭姫命は本来9世孫(孝元天皇)の妹の日女命亦の名は倭迹迹日百襲媛命である。
鳥羽市国崎町字鎧崎にある海士潜女神社の由緒には、「倭姫命にアワビを献上したと伝えられている伝説の海女(お弁)は海女の元祖ともいわれ、年初めの漁が始まる前に海女たちは必ずここを訪れ、一年の無事と大漁を祈願する」とある。
志摩国でアワビを献上された姫は一人と思われるから倭姫命(倭姫命世紀)と稚日女尊(全国の神社の祭神)は同一人物だということが判る。
加布良古崎の伊射波神社の祭神は最初は稚日女尊一神だけであった。稚日女尊は加布良古崎の伊射波神社の地に一人で居り、伊佐波登美命が飲食を給し、辞を伝え居処に出入していた。王となりしより、見たことのある者は少なかった(魏志倭人伝)。