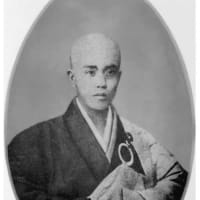このシリアスなテーマを語る上で、いくつかのコラムを参考に載せたかったのですが、うっかりスマホを盗まれてしまい、なんとか新しいスマホ(中古6千円)でログイン出来たのですが、PC版で上手く操作できません。
なので残念ながら当分は文章だけになりますが、その分気合いを入れて書きますので、お付き合いのほど宜しくお願いします。
まず前回のおさらいをしますと、「なぜ世界の半分が飢えるのか」の主因としては、投機(ため込み)によって金待ちが貧乏人から食糧を巻き上げて、その値段を釣り上げているからだとしました。
こうした投機は食糧を商品化し、貧しい農民に商品作物を作るコトを強いて、彼等はそれに抗えずに搾取され続けています。
それ故に、食糧を生産している農民が飢えるという矛盾した社会になっており、この不正から逃れるには昔ながらの自給自足の農業に立ち返り、お金に依存した生活スタイルから抜け出すべきなのですが、それは現代社会ではほぼ不可能と言えます。
何故ならば農業そのものが「緑の革命」によってお金頼みになっており、これは土地のミネラルと貧しい農民を搾取するシステムになっています。
この時代遅れな農法によって生産された作物には必須ミネラルが充分に含まれておらず、それ故に酵素活性が弱くて病害虫にやられ易く、農薬の助けを借りてなんとか育ちはしますが、腐り易くて食べる人を栄養飢餓にします。
更に、この化学農法をずっと続けていると農地のミネラルが失われて行き、ますます作物は病気がちになって農民は農薬を沢山撒かなければならなくなり、その経済的、身体的負担からインドでは自殺する農民が大勢出て、それは「緑の革命の暴力」という本によって知れ渡りました。
今回取り上げた「なぜ世界の半分が飢えるのか」という本でも、この遅れた農業システムを変えなければいけないと訴えておりますが、残念ながら著者は新しい微生物農法についてまでは言及していません。
それはこの本が出たのが1976年だから仕方がなく、日本の琉球大学で「EM農法」が確立されたのは、わたしが生まれた1981年頃になります。
この農法は世界の貧しい農民を多く救って来ており、特に沖縄移民が多く農業で活躍している南米では、カソリック協会が「地球を救う大変革」を新しいバイブルと持ち上げて普及に努めてくれています。
しかし一方、化学農法の利権に縛られた日本などでは、微生物農法による新たな農業革命は歓迎されず、土地と農民を搾取する農法に固執する向きが強くあります。
しかしそれでは「世界の半分が飢える」コトから脱却はできず、化学肥料の原料のリン鉱石も今世紀中には枯渇するので、マイケル ムーアが予言する人類の「個体数激減」を回避するタメには、我々のご先祖様である微生物との共生レベルを一段と高まる必要性があるでしょう。