四国八十八ケ所霊場 ご開創1200年記念のバスツアー巡拝 第9回
平成26年8月25日 第五十五番 別宮山 南光坊を参詣しました (坊とつく 霊場は南光坊だけです)
南光坊は703年伊予国主 越智玉澄公が 文武天皇(在位697~707)の勅命で 大山積(おおやまずみ)
明神を今治沖の大三島に勧請し 航海安全の神として大山祗神社を建て 24坊の別当寺を建立したのが
始まりといわれ その後 海を渡らなくても参拝できるようにと 708年行基菩薩が8坊を現在の今治市に
移され 南光坊はその一坊で 行基菩薩が本尊大通智勝如来を安置され 後に弘法大師が南光坊で
法楽(仏の教えを信じ 得る喜び 楽しみ)をあげて修法され霊場に定められたそうです

南光坊境内図
バスは山門から本堂に向かって右横の 道路から
境内の駐車場に入り 通路を挟んで 本堂側 大師堂側に 分かれています

芭蕉句碑 ものいえば唇寒し秋の風
どなたが建立したか定かでない と説明書きがありました。

本堂に向かって左に 手水場

本堂の左に 金剛界(智拳印を結ぶ)大日如来石像
闇の世界から光明の世界へと導いて下さり 人間が生きていくための
全てを助けて下さる仏さまです


本堂 大通智勝如来 (ダウンロード画像)
ご本尊 大通知勝如来 お釈迦さま以前の仏さまで 金剛界の大日如来像に似ていますが
よく見たら 宝冠がなく印の結び方が反対です 八十八カ所の札所でここだけの仏さまです
ご真言 なむ だいつう ちしょうぶつ
伊予の領主 河野氏の先祖にちなんだ仏さまだそうで 河野水軍に崇拝され
五穀豊穣を祈って多くの人々にも信仰されているようです

本堂の 右手前に 薬師堂
薬師如来を祀られ ご真言 おん ころころ せんだり まとうぎ そわか
病気を治し 特に 眼病に霊験があると言われています

慈母観音さま 深く大きい慈愛の心で 見守って下さる菩薩さまです

白衣観音
頭に白い帽子をかぶった観音様は 白は清浄潔白な心を現し
全ての災難を除き 延命を授かる仏さまです

六地蔵
悩み苦しむ人々を救ってくださる 六種類の地蔵菩薩さまです
お地蔵さまは人間界だけでなく 六道と呼ばれる六つの世界
地獄道 餓鬼道 畜生道 修羅道 人間道 天道を 救済する仏さまです

六僧正快道塔
石仏のつづきに 立派な五輪塔があります 「六僧正快道」と書かれています
南光坊 中興の祖 天野快道僧正のお墓だそうです

金比羅堂
讃岐の金比羅宮から勧請している金比羅大権現を祀る堂
1861~1864年の建立で 大師堂とともに 第二次世界大戦の戦火を免れ
海の安全 五穀豊穣 大漁 商売繁盛に信仰されているそうです

山門の外に 弁天堂
弁財天をお祀りし 湖 沼 池などに棲む魔物を 鎮めるとして 水辺にいる神様です
芸事 豊穣 学問 蓄財に ご利益があります

国道沿いの 大きく 立派な山門は 平成10年の建築
山門の 表裏左右に 迫力のある立派な 四天王が立っています



山門表 北方を守る 多聞天 東方を守る 持国天


山門裏 西方を守る 広目天 南方を守る 増長天

山門を入って右に大師堂です

山門を入って左に 使った筆を供養する 筆塚
弘法大師と 橘逸勢 嵯峨天皇の3人が日本の三筆といわれる
平安時代初期の能書家であったと伝わっていまです


南光坊の左隣に 道路を挟んで 大山祗神社 があります
明治初年の神仏分離令で 大山祇神社の本地仏の 大通智勝如来を
南光坊に移され 境内を分割したといいます
つぎ56番札所 泰山寺まで 約4km バスで約10分です
おしまい 















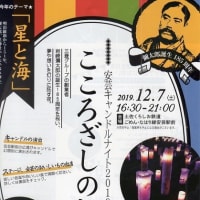




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます