四国八十八ケ所霊場 ご開創1200年記念のバスツアー巡拝
平成26年6月22日 天気雨 第四十三番 源光山 明石寺を参詣しました
明石寺は6世紀の半ば 欽明天皇(在位532〜71)の勅願により
円手院正澄(えんじゅいんせいちょう 行者)が千手観音菩薩像を安置 七堂伽藍を
建立して開創 その後734年に 役行者小角から5代目の寿元という行者が
紀州熊野から12社権現を勧請 十二坊を建立して 修験の道場となっていました
その後822年に弘法大師が この地を訪れ 荒廃した伽藍を整え 嵯峨天皇(在位809〜23)に
申し出 勅命で 金紙金泥の『法華経』を納めて 諸堂を再興し霊場に定めました
その後 鎌倉時代に再び荒れ果て 1194年に 源頼朝が伽藍を修復 恩人の 池禅尼の
菩提を弔って 阿弥陀如来像を奉納 経塚を築いて 山号の「現光山」を「源光山」に改めたそうです

境内図

30段ほどの石段を上がると右手に 納経所 と本坊

左に 手水場

単層の 仁王門


仁王門の天井に大草鞋が掛かっています

仁王門をくぐると右に 地蔵堂

さらに石段を上ると 正面に 赤茶色屋根の 本堂


本堂 お賽銭入れが 床に切りこまれています

仏足跡
お釈迦さまの足跡を印したもので 仏足跡を礼拝した手で
身体の悪い所を撫でると 罪障が消え 願が成就するといわれています
大師堂

苔むし 文字も読めない大きな石碑が
本堂脇から大師堂の前まで10基ほど並んでいます

大師堂の前に鐘楼

大師堂の右に 夫婦杉

本堂左の石仏

本堂に向かって左隣に 権現堂
明治の神仏分離までは 習合の寺であり 熊野権現が祀られています
この権現堂の裏に源頼朝の命の恩人 池の禅尼の 菩提のための
経塚(五輪宝塔)建立されているそうです



昔若い娘が大きな石を一夜のうちに山の上に運ぼうとしたところ 天邪鬼が鶏の
鳴きまねをしたので 娘は夜明けと思って驚き消え去ったという 伝説があり大きな石を
担ぎ上げた 「上げ石」 から 「明石寺」の寺名の由来となったそうです
明石寺を最後に 7回目の巡拝の打ち止めです
おしまい
















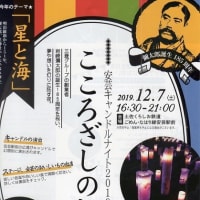




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます