「あんたくの旅行は 何時も しぶい所へ行くねえ」 「なにせ 旅行のボスが 歴史が好きなもんで」
8月13~15日お盆休みに 娘家族4人と 両おばあちゃんの6人で
古都 奈良の 世界遺産 お寺 神社の たくさんの国宝や重要文化財 巡りをしてきました
1日目 13日午前5時出発 高知道 淡路島を通って 神戸 大阪 奈良へ約5時間
最初に 世界遺産 いにしえの奈良の都 平城宮跡へ

藤原京から 710年に 奈良時代の日本の首都 平城京に都を移し(遷都)
南北約5km 東西約6㎞の 都の中央の北端に 政治の中心となる平城宮が造られました
平城宮の遺跡を 特別史跡として保存されています


明治~大正時代に文化財保護運動をされた方で 平城宮跡が放置されていた ため
私財を投じて 保存に力をつくされたそうです 大極殿の方を指しています


平城宮の正門 朱雀門
間口25m 奥行き10m 高さ22m 1998年に復元されたそうです


広場の向こうの大極殿
平城宮跡は東西1.3Km 南北1㎞の広大な地に
大極殿 朝堂院などの宮殿や天皇の住まい 国の役所などが建ち並んでいたそうです
朱雀門から 大極殿まで真っ直ぐで 800mの距離
広場を囲む 歩道は かなりの距離 汗だくで 歩く 歩く


左の建物は 第一次大極殿と呼ばれています 天皇の 即位式などが行われた最も重要な建物で
2010年に 間口44m 高さ27mの復元だそうです
右は 天皇様がお座りになる高御座(たかにくら)です
資料館 歴史館は入館 カット!



次は 奈良公園周辺の 社寺巡り 駐車場は どこも 満車の御礼 やっと見つけて
世界遺産 法相宗 大本山 興福寺へ
興福寺は 平城京遷都がおこなわれた710年 藤原鎌足の子 不比等が創建し 藤原氏の
氏寺として栄え 聖武天皇や 光明皇后(不比等の娘)も堂塔など建立したといわれています


公園の石柱のあった道を 進むと 興福寺の 五重塔 東金堂のある 境内に着く
五重塔(国宝)は高さ50m 国内で京都 東寺の塔に次いで 2番目に高く
5回の焼失 再建を繰り返し 6代目の室町時代の建造だそうです
東金堂(国宝)も 6代目の 室町時代の再建 ご本尊に 薬師如来坐像(重要文化財)
十二神将立像(国宝)四天王立像(国宝)が安置されています

中金堂は再建中

五重塔 東金堂と向き合う位置に 左から 不動堂 南円堂 興善院
南円堂(重要文化財)は江戸時代に 再建され 日本最大の木造八角円堂です
ご本尊 不空羂索(ふくうけんさく)観音像(国宝)四天王立像(国宝)が安置されています

国宝館
全国の 国宝指定仏象の17%が 所蔵されているそうです
盆休みとあって 国宝館内はかなりの人でした


奈良時代の 傑作仏像といわれる 阿修羅立像(国宝)(ダウンロード画像)は
仏教を守る八部衆のひとり 戦いに明け暮れ お釈迦さんに諭され 改心したという
この像は 憂いを秘めた3つの顔と 6本の腕をバランスよく配置したのがいいそうです
大人気 必見中の必見です



次は 朱塗りの華麗な社殿が立ち並ぶ 世界遺産 春日大社へ
春日大社は 全国に3000社ある春日神社の総本社であり 奈良時代に
武甕槌命(たけみかづちのみこと)を茨城県 鹿島神宮から
勧請され平城京の 守り神としたのが 始まりとされています
神が白鹿に乗って来たと伝わり そんなことで 公園一帯は
神の使いの鹿さまが あっちにも こっちにもいっぱい
そして 落し物も・・・

奈良のキュ-トなアイドルと呼ばれている鹿さま

ボスの後について 金魚のフン 春日大社 一の鳥居に着く ここからは表参道


参道の左には 決まった間隔で(歩数で測ってみた)露店商がずら~っと 右側は灯篭がずら~っと
露店商が閉まっているのは?一の鳥居から 本殿までどのくらい? 掃除をしている方に聞いてみたら
午後3じからの開店 2kmはあると・・・長い参道だから つい余分なことを・・・


やっと 2の鳥居をくぐる 鹿さまは公園の 森 参道 境内 何処で でも
観光客から おせんべいを いただくのを 楽しみにしています

手水場にも 鹿さま

一の鳥居から 森の中の参道を ひたすら歩いて1K300m 本社正門の
南門(重要文化財)に辿り着く

幣殿・舞殿
本殿(国宝)は4棟並んで立っていて 祭神には 第一殿に鹿島の神 「武甕槌命」
第二殿に香取の神「経津主命」 第三殿に杈岡の神「天児屋根命」
第四殿に比売神が祀られているそうですが 拝殿はなく
一般の参拝者は幣殿・舞殿の前で参拝をします

中門
本殿のすぐ前に建つ 高さ10mの楼門 と 左右に伸びている建物を御廊(おろう)といい
1613年建立され ともに重要文化財です

本殿などを取り囲む朱塗りの回廊(重要文化財)と ずら~っと並ぶ釣灯篭



総宮神社 風宮神社 一言主神社
春日の森には 本社の神様の他に六十一社の神社があちこちに点在しています



次は 世界最大級の木造建築 世界遺産 東大寺へ
東大寺(以前は金鐘山寺)は奈良の大仏さんで有名 盧舎那仏座像(るしゃなぶつざぞう)を本尊とする
華厳宗大本山の寺で 728年 聖武天皇が 亡くなられた皇太子供養のために 建立されたといいます

参道脇にびっしり つまって並んでいる露店商
人の流れも 切れることがないほどの拝観の人です

東大寺の正門 南大門(国宝)
鎌倉時代に 重源上人が再建 高さ25,5m 日本で最大の山門といわれています


山門の両側に高さ8mの金剛力士像(国宝)が
人間の頭の位置から上で 向かい合って立ち まさに圧巻です
像は運慶 快慶らがわずか69日で完成させたといわれています

山門から右手に 手水場

中門(重要文化財)1716年の再建です
大仏殿の手前にある楼門で 左右に回廊がのび大仏殿に通じています

大仏殿(金堂)1709年に再建の3代目 正面幅を 創建当時の
3分の2に縮小されたそうですが それでも 幅57m 奥行き50m 高さ48mの
世界で最大級の木造建築といわれています

大仏殿の 軒下の びんずるさんも ハンパじゃない
なでて病気を治してくれる 撫仏さんも
こんなに大きく高くては 頭も肩も 撫でれません

いよいよ内陣 金銅仏の大仏さま(国宝)盧舎那仏座像(るしゃなぶつざぞう)を拝顔
高さ15m世界最大級といわれ 大仏さんを造った当時(奈良時代)延べ260万人の
国民の人達が 大仏造りに 関わったそうです

大仏さんの鼻の穴くぐり
大仏殿の柱の1本に 大仏さんの鼻の穴の大きさ 高さ30㎝ 幅37㎝の
穴があり くぐると厄除けに また大仏さんの 左掌の上には10人の子供が
のれるといわれ 人々に慈悲の光を照らし 悟りに導いて下さるといわれています

法華堂(国宝) 三月堂ともいわれ奈良時代前半の建立の 東大寺では最古のお堂
ご本尊 不空羂索観音立像(ふくうけんさくかんのん)(国宝)高さ 3m62㎝ 3つの目をつけ
8本の腕をつけています 他に堂内に安置されている 3~4mの巨像10体も 奈良時代作で 国宝です

三昧堂(重要文化財) 四月堂と呼ばれています

高台に建つ 二月堂は お水取りが 行われる舞台造りのお堂で
西面に 張り出した舞台から奈良市街が一望できます
江戸時代に再建された 国宝です
1日目の拝観は終了 市内の会員制のホテルへチェックイン
おしまい















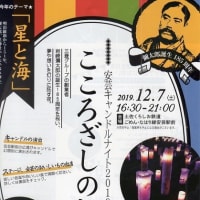




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます