四国八十八ケ所霊場 ご開創1200年記念のバスツアー巡拝
平成26年7月28日 天気雨 四国八十八ケ所霊場のちょうど半分 中礼所
第四十四番 菅生山(すごうざん) 大宝寺 を参詣しました
大宝寺は大和朝廷の時代 百済(朝鮮)から来た僧が この地に質素な小屋を建て
携えてきた十一面観音像を安置 701年 安芸の国(広島)から来た 明神右京・隼人の狩人兄弟が
萱草の中から 十一面観音像を見つけ 小堂を建て安置し 当時の文武天皇(在位697〜707)が
この話を聞き 勅命で寺院を建立し 寺名は当時の年号にちなんで 大宝寺と 名づけられ
その後 822年 この地を訪れた弘法大師が 密教を修法されて
天台宗だった宗派を 真言宗に改め 四国霊場の中札所として定められたそうです

大宝寺境内


陵権現(みささぎごんげん) 勅使橋
後白河天皇は 1156~1159に 病気平癒を祈願したところ 成就したので
勅使をたてて大宝寺の伽藍を再建し妹宮を住職に任じられ 橋もその当時の名残り
妹宮はこの地で亡くなられ 堂宇と五輪塔を建立して 陵権現として祀られていたそうです
現在は堂宇 五輪塔すら見えず その跡と思われるところに 木札が立っています

坂道の途中曲がり角に 地蔵堂

仁王門
明治7年の火災で焼失 昭和31年に再建されたそうです


百年に一度取り替えられるという 健脚を願う大草鞋は
仁王門に入りきれないほどの大きさで 奉納されています
金剛力士像は焼失を免れ 再建されて仁王門に据えられたそうです

仁王門をくぐって進むと 右手に不動明王


坂道を上りきると 水子地蔵 手水場

納経所 があります



本堂へはさらに石段を上る 上り口右に
山頭火句碑 「朝まゐりはわたし一人の銀杏ちりしく」と詠っています


石段を上ると 鐘楼が2つあります 左の鐘楼は平和の鐘と呼ばれ
第2次世界大戦で亡くなった 地元の 英霊を供養するために建てられたそうです
右側は古くからのものです

本堂
ご本尊は十一面間世音菩薩
ご真言 おん まか きゃろにきゃ そわか
四方八方にお顔を向けてすべての人々を救って下さいます


本堂から右に階段を上がったところに 御影堂 (大師堂) 昭和59年に再建されています

本堂と大師堂の間に立つ十一面観音像



平和の鐘の奥に掘出観音堂があるそうです
昭和9年の正月 石田そよさんが 何かが乗り移ったように突然
「我管生山の金の性じゃ、掘り出せ!掘り出せ!」と口走るようになりその年の5月7日に
寺は人夫を雇い そよさんの示すところを掘ると 地中から七体の 金銅仏が掘り出され
昭和31年にも そよさんの養子の山本猛六さんが もう一体を 掘り出し
計八体の(3cmから10cm位)金銅仏がお堂に祀られて
体から病気や悪霊を掘り出し 才能を掘り起こしてくれるといわれ 信仰されているそうです

大師堂右下段に興教大師堂
興教大師覚鎖(こうぎょうだいしかくばん)上人は 1095年 肥後の国に生まれ 早くから聡明で
8歳の時から僧侶になると誓い 真言教学をきわめられ 坐禅観法を修法されて
高野山の復興を志され 真言宗の高僧となられた 覚鑁上人が祀られています


樹齢800年の杉や檜の巨木の立ち並ぶ 参道は昼なお暗く
参道脇には 小さなお堂 石仏がお遍路を迎え見送るかのように佇んでいます



大宝寺は 3度の火事のわざわい
1度目は仁平2年(1152)の失火 1156年後白河天皇の寄進で再建
2度目は天正年間(1572~1592)の長宗我部の兵火1688~1704の雲秀法師が再建
3度目は明治7年(1874)の失火 地元の寄進で再建 されています
つぎ46番札所 浄瑠璃寺まで 約42km バスで約50分です
浄瑠璃寺に着くと お寺の前の旅館 で昼食

おしまい















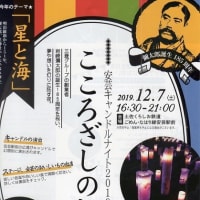




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます