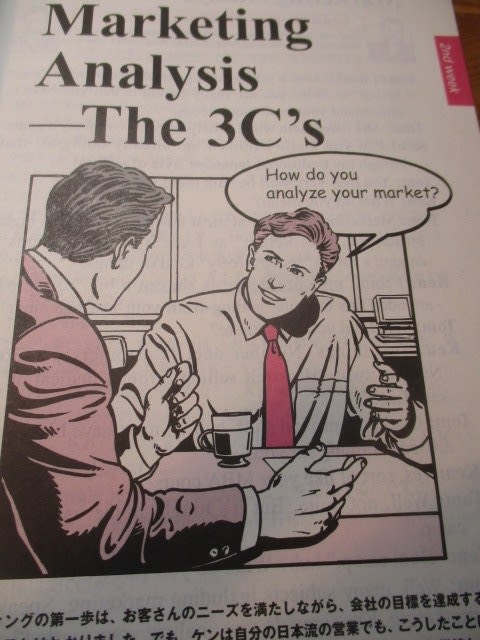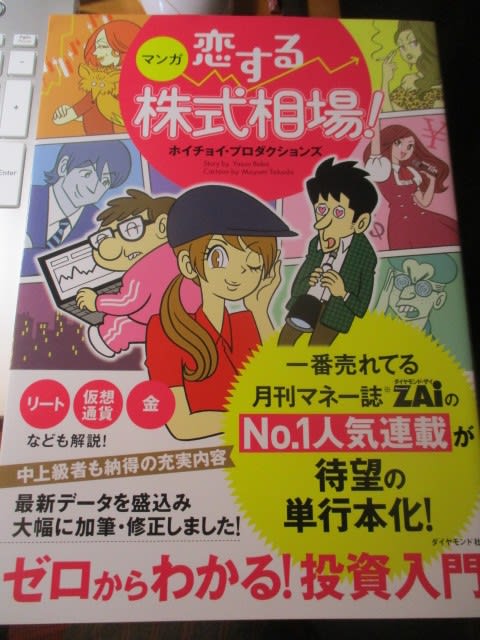380万社あると言われている日本の会社・・・そのうち97%が中小企業、零細企業と言われています。
労働者の7割が中小企業、零細企業で働いています。
日本経済の活力である中小企業・・・国も補助金や各種施策で支援、サポートしています。
が、単にカネを出すことだけだと経営革新、経営改善に繋がらないことが多々あります。
そこで、現在、経済産業省や中小企業庁で推奨、推進している「伴走型支援」。
元中小企業庁長官が自らの現場体験の中から導き出した経営コンサルティング手法に関する書籍を出しました。
役人、官僚とは思えない、現場指向、実務志向の著者に驚かされました。

経営の力と伴走支援 対話と傾聴が組織を変える
角野然生著 光文社新書 860円+税
著者の角野さんは元中小企業庁長官。
福島県の中小企業の再生、復興のため、官民合同チームを作ったりアフターケアしたりした方です。
福島県のプロジェクトも紹介されており、現場の泥臭いリアルなシーンには臨場感があります。
目次
第1章 復興の現場から
第2章 対話と傾聴
第3章 潜在力を引き出すメカニズム
第4章 伴走支援の全国展開
第5章 地域再生と伴走支援
第6章 企業と人の潜在力を引き出す社会へ
著者は「伴走支援」について、「企業経営者と外部の支援者が信頼関係の下で対話を行うことを通じ、経営者が本質的な経営課題に気づき、意欲を高めて会社の自己変革などに取り組むことにより、組織が本来持っている潜在的な力を発揮させていく一連の営みのプロセス」と定義しています。
中心となる手法は、対話と傾聴。
OD(組織開発)の手法も有効であると指摘します。
上から目線ではなく、対等な立場で「気づき」を引き出す努力を継続していくことが重要であるとします。

中小企業の社長は、創業者や現場叩き上げの方が多く、理論や横文字を嫌う方が多いです。
単なる経営診断や経営指導といった上から目線は、まっぴらと言う方も多々います。
そんな中で、対話と傾聴で伴走支援していくという手法は有効だと思います。
経営者は本当に孤独・・・本音で語ることが出来る相手もいないのが現状です。
時間と手間はかかりますが、この手法は、企業組織が変わっていく経緯を体感することが出来ます。
中小企業診断士として、これからも「伴走型支援」に特化した動きを強化していこうと思います。