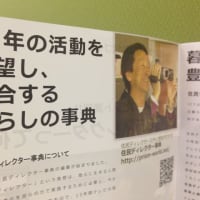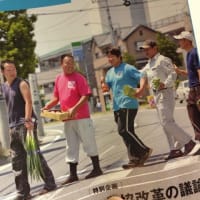花子がラジオで子どもたちのためのニュースを読むことになった顛末を見ていたら「花子さんは住民ディレクターだった」とよくわかりました。
ラジオ局の若きディレクターが白連さんの知り合いで花子さんと出会い、家の庭先で子どもたちに読み聞かせをしているところを見て、子どもニュースの読み手を花子さんに頼みます。ラジオ局に行くといかにもエリートアナウンサーらしき人物が、ニュースは「色を出さずに透明で読むべき」的な話をします。この辺りは住民ディレクターの皆さんがよくプロに言われることと全く同じ状況です。
そしてニュースを読む当日に「飛び込み原稿」を読むことを強要されます。いきなりで頭が痛くなった花子さんの手にはラジオが大好きだった亡くなった子どもの写真があります。子どもがよくラジオの真似をしていたのを思い出し、花子さんは奮起します。そして慌ててスタジオに飛び込んでラジオ局のディレクターに頼んだのが「自分が書き直した原稿を読みたい」という申し出。原稿にはあちこちに赤字で添削されています。当時は逓信省に許可をとらないといけなかったのですがディレクターが原稿を読んで即断します。
そして両親や夫、知人たちがそれぞれの土地でラジオの前に群がり、遠く離れた東京にいる花子さんの第1声を待っています。そして・・・。
住民ディレクターの姿がそのままでした。特に夫が、花子さんがあがり症で不安を隠せない様子に「原稿を読むのではなく、子どもの顔を浮かべて語りかけるといい」というようなアドバイスをします。まさにこれはわたしが18年間言い続けていることです。書いたものを読むのではなく「具体的に人の顔を浮かべてその人に話すんです」。
花子さんのラジオ放送の声を少し前に飯塚市の伊藤伝右衞門邸で聞きましたが、本当に本当にやさしい声でいつまでも聞いていたい語りでした。住民ディレクター花子さんたちの模索があって一時的にはラジオもテレビもプロのものになってしまっていましたが、ICTの発展は花子さんとのつながりを今に創ってくれていることを感じました。
ラジオの前で花子さんの声が聞こえて大喜びしている当時の人達の姿は自分自身の撮った映像が流れて大喜びしている住民ディレクターの皆さんの感動とダイレクトにつながっています。