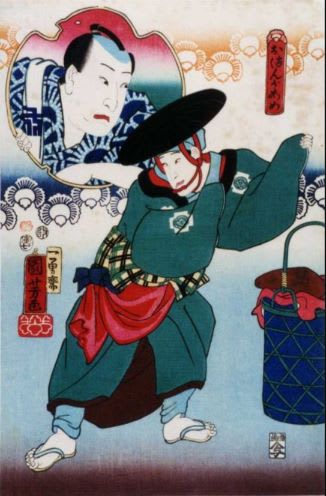昔の写真を見ると顔位の大きさまで膨らませてますね
おそらく
子供たちの要求に応えるためにだんだんと
大きくなっていったんだろうな~と考えられます
飴の大きさにつきましては約300年後の今でも
飴細工の形よりも大きい(飴の量が多い)のをと子供達に要求される事は
しばしば有ります
言い伝えでハサミを使用される前の飴細工を少し作って見ました
単純素朴な物ほど拘ると面白い物で
瓢箪の空気の入れ方には大きく分けて2通りの作り方が御座います
真ん中できっちり区切っているのではなく
空気が通るほど繋がっている作り方と
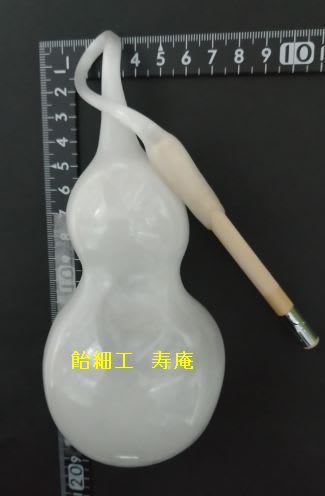
もう1つは真ん中で区切って空気を入れる方法です

飴の歴史を調べる中、度々でてくる飴屋の歌、踊り、口上
色々調べていると沢山あり1日がアッと言う間に過ぎます
ほんの一部しか紹介できませんがリンクさせてもらいました
不思議に思ったのは関東近辺や東北方面では継がれていましたが
関西方面で広がった又は後を継がれた方は、ほぼ見当たりませんでした
もっと探せば、いらっしゃるのかもしれませんが

飴屋の笛 長唄童謡vol.9 杵屋佐喜-Saki Kineya
飴売り口上
第47回東京都民俗芸能大会―道の芸・街角の芸― 飴売り芸
流山加台の飴屋唄」に合わせて「飴屋踊り」千葉県の無形文化財
NHK ほっとタイム音楽アラカルト 日本の民謡より。
ヨカヨカ飴屋の唄 茨城県結城郡石下町(現:常総市) 唄:増山たか
宮田章司・坂野比呂志 飴売りの売り声の比較
第47回東京都民俗芸能大会―道の芸・街角の芸― 飴売り芸
AKT民謡あきたの唄っこ 飴売り節
秋田飴売り節(歌詞入り)冨岡久美子
三味線と遊ぼう・唐人飴屋の唄
菊名の飴屋踊り
横須賀市指定重要無形民俗文化財
「手踊り 飴やさん(飴屋踊り)」”来迎寺白山神社秋季大祭2022