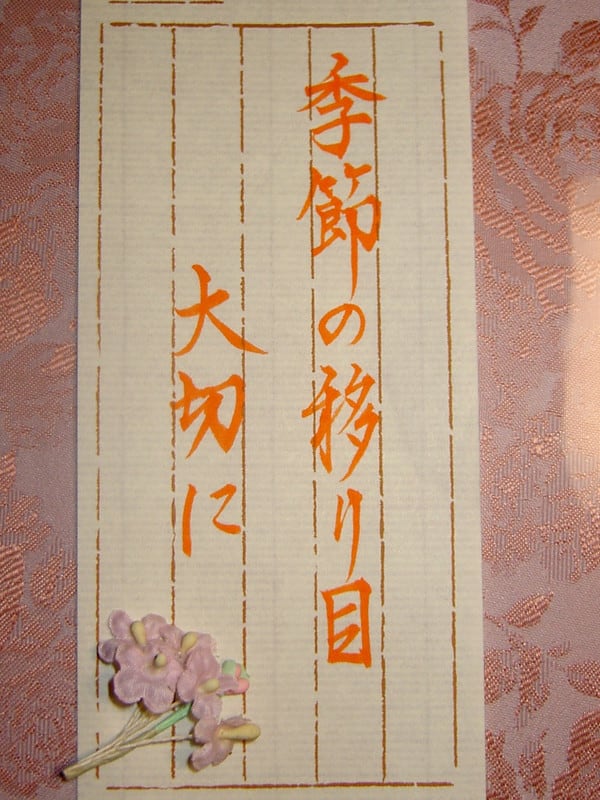二十代の頃に習っていたお茶を、定年退職した今また再開している。お茶のお稽古をしていると、日本人の感性というのは本当に繊細で、日本人に生まれてよかったと、感動する瞬間がよくある。
春一番が吹く彼岸の入りの頃、お茶の世界では、春のしらせと言う透木釜、釣釜がお目見えする。炉から風炉へとかわる前のわずかな時期の気温の変化を絶妙な感覚で、五徳を取り除いた炉で見事に表現する。
透木釜は、暖かくなる季節に客に暑苦しさを感じさせないように、平たい釜の胴の部分に張り出した羽根で炉を覆うように炭の火を隠すしつらえで、火を遠ざける気配りの工夫が感じられる。
釣釜は、天井に打たれた蛭釘から、釜を釣り下げて使用し、日本の懐かしい風情がある。釣釜に使う釜そのものも、通常よりも細長い小さめのものが使用されていて、点前のとき天井から吊り下げた釜が春風のようにゆらめいて気持ちも和む。昔の人はよく考えたものだ。
今日宮崎は20度を越す暖かさで、桜の開花発表があった。稽古の帰り、自動に設定したカーエアコンからはクールな風が吹き出てきて、せっかくわびさびの繊細な気温変化を学んだのに複雑な思いだった。((+_+))