
この記事が役に立つと思われましたら、クリックをお願いします。

ランキングに参加
しています。
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
第四章 JR体制への移行と国労の闘い
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
第四節 国労組織の再編問題
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
二 JR体制下の国労組織と活動
国関労から鉄道関連労へ
国労をはじめ国鉄に関連した企業などで働く労働者の労働組合が国関労(国鉄関連産業労働組合懇談会)を結成したのは1966(昭和41)年12月26日、その後とくに毎年の春闘などを通じて共闘を強めるなかで「協議会」へと発展し、国関労(国鉄関連産業労働組合協議会)が発足したのは1973(昭和48)年9月10日のことであった。この協議会発足時点での加盟組合は、国鉄労組、動力車労組、鉄道弘済会労組、日本食堂労組、全整労協、国鉄共済労組、鉄建公団労組、帝国ホテル労組、鉄荷労連、新生電業労組、ビュッフェとうきょう労組、弘済食堂労組、国際観光会館労組、弘済サービス食堂労組、都ホテル労組、日本電設労組、(オブザーバー加盟・日本交通公社労組)の16組合であった。以来15年近くにわたって、春闘時の賃上げ闘争だけでなく国鉄関連企業労働者の最低賃金制や雇用安定協定などの締結を求めて中央闘争を展開し、国鉄当局や経営者協会などに交渉をせまった。国鉄当局と経営者協会は交渉当事者能力がないとして要求にこたえようとはしなかったが、個別的には1977年(昭和52)年に本四架橋にともなう雇用確保について運輸省・国鉄当局と全交運・国労・国関労との間で確認事項が締結されるなどの成果も生んでいた。
しかし、1980年代に入って展開された国鉄の分割・民営化策の推進は、国鉄関連企業の存続すら危ぶまれる状況をつくりだしていた。国鉄の「余剰人員」に名を借りた関連企業の国鉄直営化拡大、出向・移籍などは、国関労内部の矛盾と対立を引き起こしかねなかった。そうしたなかで国関労は、お互いに本音で話し合い、各企業での雇用創出の努力と首切りを許さない闘いに取り組んでいった。
さて、1987(昭和62)年4月1日の国鉄分割・民営化後の国関労組織のあり方について、国関労各労組の代表者会議、組織検討委員会などが数回にわたって開かれ、最終的には1987年3月5日と6日の代表者会議で、①各鉄道会社との対応を行うために各社に関係する国鉄関連企業の組合ごとに「鉄道関連産業労働組合協議会」を結成する、②現行の中央国関労は、全国的に各鉄道会社、通信・情報会社などの情報収集、宣伝活動、各鉄道会社に対する統一要求統一解決などの全体的な意思統一と闘いの取り組みなどをはかるために存続させる、の2点を決定した。そして、エリアごとの関連労の結成に中央・地方国関労が一致して取り組むことを確認した。しかしこの間、国労へのすさまじい組織攻撃により、国関労組織人員自体も1年間で11万人減員となり、分割・民営化直後の7月末現在で7万人の組織であった。
1987年10月14日に開いた国関労第15回定期評議会においてその名称を「鉄道関連産業労働組合協議会」(鉄道関連労、3万8000人)と改め、骨子次のような運動方針を決定した。
① JR各社の関連企業に対する攻撃は、直営化の拡大、業務量・委託費の削減、企業分割・企業再編などに伴う要員削減など、きびしい攻撃にたいして職場と雇用を守るため団結を固め組織の強化をはかる。
② 関連企業のJR各社への直営化拡大攻撃は、ますます鉄道関連労の内部矛盾と対立を深めかねない状況にあり、関係組合間の話し合いと各企業の雇用確保のための運動を強め、首切りを許さないための運動を進める。
③ エリアごとの「鉄道関連産業労働組合協議会」(鉄道関連労)の組織化と各地方「鉄道関連労」の再建を中央・地方 が一体になって取り組む。
1990年代に入り、鉄道関連労の中心組合たるべき国労がJRのなかで依然として少数派組合であり、国関労時代に比べれば加盟組織も加盟人員も激減している。また国労自体の交渉能力の減退によって全体として活動が停滞していることは否めない。そして、鉄道関連労加盟組合のほとんどが東日本および東京に偏在していることである。1992年7月現在の加盟組合は、国労、鉄産総連(92年5月解散)、鉄建公団労組、全臨海労連、整備関連労、全国旅従労、日本運輸倉庫労組、国際観光会館労組、弘栄堂書店労組の9組合で、会費納入人員は合計3万6080人という状況になっている。
他方、1987年2月に結成された鉄道労連(のちJR総連)は、同年8月に開催した第2回定期全国大会において「全ての関連事業労組の加盟を目指し、鉄道労連をJR関連の一大産別組織として確立する」よう取り組み、将来的には「JR関連一般労働組合」(仮称)の結成を目指すことを決めた。そして国鉄分割・民営化からちょうど1年経った1988年4月1日、鉄道労連準加盟の7組合で「JR関連一般労組連絡会」(4800人)が結成され、鉄道労連としても各鉄道労組が同系列企業労組と連携を強化し、今年度中1万人を目標にJR一般労組への加盟を働きかける方針を決めた(同年11月の第4回定期中央委員会)
続く










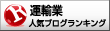
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます