
この記事が役に立つと思われましたら、クリックをお願いします。

ランキングに参加
しています。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
第三章 分割・民営化攻撃の本格化と国労闘争
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
第五節 労使共同宣言と国鉄内労組の再編
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
┌──────────────────────────┐
├○ 三 ダイヤ「改正」に対する闘いと団体交渉の形骸化 │
└──────────────────────────┘
61・3ダイヤ改正は、60・3ダイヤ改正で設定した試行列車の定期列車化をはかるのが目的とされ、地方におけるダイヤ改正を実施するとして、地方ごとに提案された。しかし、その狙いは国鉄の分割・民営化を既定の事実として、駅の無人化、勤務の改悪、出・改札、ホーム要員の削減、運転関係は基地の統廃合や検査体制の改悪などによる要員削減計画の実施であった。この交渉で当局は、提案内容からいかなる譲歩もせず、時期が来れば一方実施を強行した。多くの地方でも、団交日時の一方的指定がなされ、団交形骸化が鮮明となった。しかも合理化事案の提案権は当局にあり、労働組合の要求を当局が判定した上で、労働条件の交渉を行うという態度を露骨に示した。そのうえ組合の要求に対し、管理運営事項として交渉制限や拒否を行うという方向が強まった。第146回中央委員会の61・3ダイヤ「改正」闘争の総括には、地方事案ゆえに、全国統一した闘いに十分展開できなかったとの指摘がなされていた。
61・11ダイヤ「改正」については、86年4月10日に概要提案を事前協議として国鉄当局からなされた。国労は、61・11ダイヤ改正に関する解明要求、61・11ダイヤ改正に対する要求を当局に提起し、事前協議をすすめた。国労が解明要求の一番最初に掲げた「61・11ダイヤ改正と国鉄改革法案との関わりはあるのか」に対して、当局は「法案の成立に伴い62年(1987年)4月に経営形態が変更することになった場合には、今回のダイヤ改正で確立した輸送体系が新しい事業体の商品となることになる」と答えた。ここで明らかなように、このダイヤ改正は分割・民営化にむけた国鉄減量化の総仕上げの意味をもっていた。
このダイヤ改正により、監理委員会答申の示した要員規模、21万5000人、実質19万5300人への人員削減を進め、貨物輸送の縮小、荷物輸送の切り捨て、旅客輸送では大都市圏・主要都市間中心の増発により、採算主導の輸送機関の確立をはかることを目指していた。こうした施策により、ローカル線などでの利便性の放棄や関連労働者も含む国鉄労働者の雇用不安の一層の増大を招くものであった。
国労は、61・11ダイヤ改正の提案は「利用者・国民と国鉄労働者に犠牲を押しつける内容をもった」ものと見なし、取り組みを強化する方針を第147回中央委員会で決定した。この闘いは、国鉄分割・民営化に反対する闘いの一環に位置付けられ、利用者・国民の要望を取り入れた、幅広い要求づくりと運動の拡大の追求していくことにおいた。
国鉄当局は7月31日にダイヤ改正の提案をしたが、「労使共同宣言」締結四組合(動労、鉄労、全施労、真国労)は、直ちに妥結の態度を表明した。こうした動きは最初から交渉に不利に作用し、状況打開に至らず、10月23日に妥結を余儀なくされた。
中央闘争委員会は、①国民生活の混乱と協定未締結のまま11月の勤務予定表が一方的に発表されるなどの混乱を回避する、②地方での団体交渉の経過を今後も追求する、③雇用と生活の不安を解消するため、さらに取り組みを強める等を確認して協定締結したのであった。
続く










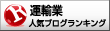
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます