
この記事が役に立つと思われましたら、クリックをお願いします。

ランキングに参加
しています。
実父が9月25日に他界し、更新が遅れたことお詫び申し上げます。
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
第五章 分割・民営体制の矛盾の表面化と国労運動
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
第六節 国労の政策要求
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
分割・民営化後の国労の政策づくり
また、運輸省は同年10月、「国鉄改革5年間の成果と課題」を発表し、いくつかの問題点も指摘した。さらに総務庁も、JR各社および清算事業団の行政監察を行い、その結果を運輸省に指摘した。これらの報告や指摘のなかでは、国労などのかねてから主張していた国鉄分割・民営化後の諸矛盾がいくつも明らかにされていた。
しかし、国鉄「分割・民営化」後もJR各社で事故が多発し( 第3節3参照) 、職場における要員不足と過重労働が蔓延し、そしていぜんとして”国労つぶし”をねらった不当労働行為がつづき、他方に運輸省=国のすすめる21世紀を見すえた今後の鉄道をめぐる施策が展開されようというなかで、国民の生活と権利を守り、事故のない安全でサービスのゆき届いた鉄道輸送の確立?公共交通の再生を目指し、そして鉄道事業に働く労働者の労働条件を改善していくという課題を、いずれも一体のものとして追求していくというのが国労の基本釣考え方であった。そこで国労は、1993年7月25日から開いた第58回定期全国大会( 伊東) において「『分割・民営化』の6年間を具体的に検証し、その矛盾を明らかにして宣伝すると同時に、国民の足としての交通権確立の立場から将来の公共交通のあり方を中心に鉄道輸送を軸とした交通政策づくりを進めていく」ことを決定した。
政府・国鉄当局の「再建計画」と国労の政策要求 国労が「政策要求」を提言するのは、もとより今回が初めてではない。すでに1964年以来国鉄経営が赤字に転落し、とくに1970年代に入ってからは国鉄財政の悪化が深刻さを増してくるなかで、たびたび繰り出された各種「再建計画」案と「合理化」案に対して国労は、それらがたんに国鉄経営の守備範囲で解決できるものでなく、広く地域住民と利用者に支持され、国鉄に働く労働者の労働条件の改善なくして「再建」はありえないとの立場から、「政策要求」も含めた具体的な要求を対躍して闘いをすすめてきた。とくに、石油ショック直後に策定された国鉄当局による「新10ヵ年再建計画」( 1974年3月) は、その翌年には当局もその破綻を表明せざるをえなかったが、国労は1975年6月24日からの第36回定期全国大会( 水戸) において「国鉄を民主化し、国民の国鉄にするたたかい」の新方針を決定した。この年秋のスト権奪還ストライキにのぞんでも政府と国鉄当局に「国鉄再建に関する要求書」を提出し、「民主的な総合交通体系を樹立し、体系的な公共交通機関の整備を行うとともにすべての交通・運輸労働者の労働条件の改善をはかることにを要求した。
政府が閣議決定した「日本国有鉄道再建対策要綱」( 75年12月) は、2年間で国鉄の収支均衡を同役しようというもので、その骨子は①2年連続50% ( 計125% ) の運賃値上げ、②5万人要員「合理化」、であった。国労は、翌76年2月に開かれた全文運の交通問題研究全国集会に「国鉄再建に関する緊急要求」を提起し、その実現のために広範な国民と労働者とともに運動をすすめることを訴えた。この「緊急要求」は先の「要求書」をさらに具体的にしたものであった。さらに、国鉄当局が1976年11月発表した貨物大「合理化」は、①貨物取扱駅とヤードを3割削減し、②要員1万5000人を削減することを柱としたものであったが、79年7月に国鉄当局が運輸大臣に提出した「国鉄再建の基本構想案」は、今後6年間に7万4000人の要員を削減し( 35万人体制) 、赤字ローカル線を切り捨てていくという大規模な〝減量経営〃構想であった。つまり、1970年代後半の政府.国鉄当局の国鉄「再建」策は、相も変わらず運賃値上げと要員削減、貨物「合理化」とローカル線切り捨て、それに若干の公的助成という数字余わせ的な対症療法の域を出ず、抜本的な総合交通政策も提示しないまま国鉄の公共的使命を放棄して、年ごとにその縮小再編の方向をはっきりさせていた。
このような事態のなかで国労は、1977年7月4日から開いた第40回定期全国大会(高知) において、前年度大会からの論議をうけて「『国民の国鉄』をめざす民主化・政策要求闘争」の方針を決定し、79年7月17日からの第41回定期全国大会( 鹿児島)では、それまでの「国民の国鉄」をめざす民主化・政策要求闘争の成果と問題点を整理し、その後の闘いの目標とその組織化方針も明らかにした。その骨子は①国民の生活要求にもとづく国鉄づくり、②国鉄経営の民主化、であった。( 以上、『国鉄労働組合40年史』参照)
続く










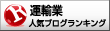
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます