
この記事が役に立つと思われましたら、クリックをお願いします。

ランキングに参加
しています。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
第三章 分割・民営化攻撃の本格化と国労闘争
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
第七節 国労攻撃の本格化と国労の反撃
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
┌───────────────────────────┐
├○ 五 普通課程特設職員研修科の教育・訓練と国労の反撃 │
└───────────────────────────┘
国鉄当局の攻撃は、全国に「人材活用センタ-」という名称の「収容施設」を設置するだけに留まらなかった。企業人教育が、国労組合員を排除するような形で行なれたのに対して、普通課程特設職員研修科は、「人材活用センタ-」に収容された国労所属の活動家を主たる対象にして実施された。
この職員研修は、国鉄の「分割・民営化」を目前とする1986年8月末以降、2回ほど実施されたが、第1回普通課程特設職員研修科に参加した活動家によれば、受講者全員が各地の「人材活用センタ-」から送られてきた人達であり、しかも、国鉄当局に「改悛の情」を示した、あるいは、国鉄当局側に「寝返る」のではないかと推測された、国労所属の活動家だけに対象者が絞られた。このような一部の組合活動家だけが選抜されて、この企業内研修に派遣された。
国鉄当局の考え方は、「人材活用センタ-」に収容された国労所属の活動家であっても、「いささかなりとも、救える目のある職員は救ってやること、しかし、言っても聞かない職員はほっとくしかない。人活=清算事業団ではない、人活から救ってやる人を是非申告してほしい」というものであった。中野人活センタ-から参加した活動家の証言によれば、上司から「研修を受ければ何か良いことがある」という言質が与えられたという。ここで「何か良いこと」という言質が、国鉄の「分割・民営化」後にJRに残れるということを意味していたと想定される。
第1回普通課程特設職員研修科の教育研修カリキュラムによれば、第1に、このカリキュラムでは、「てんびんの詩」「それぞれの岐路」「未知に挑む」「八甲田山」などのビデオ鑑賞時間が設定されており、このビデオを見た後、受講者は小集団に分かれて討論を行うことが求められた。このような小集団活動での討論は、「自主研修」「職員意見発表会」と連動しており、民営化に向けての職員の「意識改革」「思想転換」を狙いとするものであった。
第2に、この教育研修の後半部分は、AIA訓練(Adventure InAtitudes) という名の感受性訓練で占められた。これは「内観トレーニング」と連動するものであり、その狙いは受講者に対する接客態度の改善であった。つまり、人活センア-から派遣された受講者に、「望ましい接客態度とは何か」を反省させ、そのことを通じて将来のJR社員に「望ましい接客態度とは何か」を感じ取らせようというのである。
第3に、入学当日から最後の日まで、毎朝必ず団体行動訓練が行なわれ、「国旗」の掲揚と体操が行なわれた。団体行動訓練とは「国鉄体操、指差確認、喚呼応答、基本姿勢等業務遂行の基本となる動作を中心とする」訓練であるが、その実はまるで軍事教練であるかのように、指導教官から「歩け」「進め」「止まれ」「右へ回れ」などの号令が繰り返され、そのたびに受講者は隊列を組んで号令にしたがって行動するのである。この団体行動訓練、「オープンロード」は、ビデオ「八甲田山」と連動しており、受講者は入学当夜に「八甲田山」を見せられた。この団体行動訓練の総仕上げは、8月の猛暑のさなかに箱根八里を縦歩する「オープンロード」であった。この軍隊の行軍にも似た「地獄の特訓」は、国労組合員のみならずマスコミの注目を集めた。多くのマスコミは、普通課程特設職員研修科の教育・訓練を「国鉄人活センタ-特訓」「企業人教育の一環」として批判的に取り上げた。
結局、箱根八里のオープンロードは、ビラ配布、抗議集会等を組織した国労本部、国鉄闘争を支援する他労組、支援団体などの激しい抗議によって中途で中止に追い込まれた。
なお、第2回の普通課程特設職員研修科の教育・訓練に対しては、国労は組合員への指導を強化した。なぜなら、第1回目の普通過程特設職員研修科への参加者の多くが、国労本部において国労バッジを付けて堂々と参加するように指導されたにも拘らず、三島駅に着いた途端に、国労バッジを付けるかどうかで意見が分かれ、結局、国労バッジを取りさって参加することになったからであり、また、この普通課程特設職員研修科の教育・訓練を受講したものの中から、国労を自ら進んで脱退するものが出たからである。
このような事態を重視して、国労本部は、国労の活動家たちに対して国労バッジを胸に付けて入校するように指導した。国労バッジを着けて入校した国労活動家たちは、即刻、研修所所長から全員が放校処分に付されたが、国鉄当局は、事実上、第2回目の普通課程特設職員研修科の教育・訓練の実施を断念せざるをえないという事態に追い込まれた。
続く










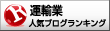
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます