すみません、2週間近くも空けてしまいましたが、本日も国会審議のお話を少しさせていただこうと思います。
今回のお話は、正直殆ど議論が噛みあっていないと言うか敢えて外しているということなのか、のらりくらりと逃げている…そんな風に受け取れます。
実際には、播但線の姫路~飾磨港のように播但線という本来であればくくりから見れば廃止対象にならなかったかもしれませんが、極端に旅客扱いが少なかったことから結局は廃止になりましたし、通称尼崎港線のように貨物線となっていたところなどもその実態に応じて廃止されていったところも多数ありました。
三浦議員の「 現在の国鉄線路名称に基づけば、たとえば本線に入っている、そういうものを政令を制定する段階で本線から外してしまうというようなことは、法律上は可能なのでしょう。どうですか。」という質問であり、実際にはより実態に応じた形で整理が図られたので播但線の飾磨港のように、本来は播但線という位置づけで残せたかもしれませんが、現実的対応として廃止に追い込んでいますよね。

以下は、工藤政府委員と三浦委員の審議の様子です。
明日以降は出来るだけきちんと書けるようにしますので、今回は節にご容赦を

昭和56年4月で旅客営業を廃止した通称尼崎港線(尼崎港~塚口間)の区間列車
*********************以下国会審議の内容*************************
○三浦(久)委員 法制局、来ておりますか。
質問いたしますが、現在の国鉄線路名称に基づけば、たとえば本線に入っている、そういうものを政令を制定する段階で本線から外してしまうというようなことは、法律上は可能なのでしょう。どうですか。
○工藤政府委員 お答え申し上げます。
法律案におきましては、第八条の一項あるいは二項におきまして、「政令で定める基準に該当する営業線」という形で書いてございます。一応政令の委任の範囲内において規定し得るものは規定する、こういうことだと思います。
○三浦(久)委員 質問に答えてくださいよ。もう一回質問いたします。たとえば、いま国鉄線路名称に基づけば本線に入っている、そういうものを本線から外してしまう、また逆にいま本線に入っていない支線、それを政令制定の段階で本線に編入してしまう、そういう決め方をしてもそれは法律に違反をするということにはならないのでしょうというふうに聞いているのです。
○工藤政府委員 お答え申し上げます。政令案の中身につきまして、私ども実はまだ審査をいたしておりませんので、断定的なことは、あるいは結論めいたことは申し上げるのは差し控えさせていただきますが、いまお尋ねの点につきましては、「政令で定める基準に該当する」ということで、一応基準に該当する営業線というものは政令に委任されております。その委任されております範囲内におきましては、これは八条以下のこの制度の趣旨にかんがみまして、妥当な線を妥当な基準で決めていく、こういうことでございます。したがいまして、本線であるか支線であるかという点につきまして、私ども実態を運輸省その他からまだよく伺っておりませんので、その実態的な判断を含めましては保留させていただきます。
○三浦(久)委員 法制局だから法律的な見解を聞いているわけですよ。妥当とか妥当じゃないとか、そんなことは政策の問題なんです。私は違法かどうかということを聞いているのです。ですから、政令で委任された範囲内で可能だというのなら、いま私が言った、たとえば支線を本線に編入したり、また本線に編入されているものを取り除いたりというような作業は、政令で委任されている範囲というふうにあなたたちは考えているのですかどうですかと言っている。
○工藤政府委員 お答え申し上げます。
基準の考え方自身をまだ私ども実は伺っておりません。そういうことで線路をそれぞれ決めるということ自身は、政令で該当するということで可能でございますが、どのように決めるかということについては、実は私どもまだ伺っていないということでございます。
○三浦(久)委員 ですから、結局この法律には、線路の終点、起点、それをどういうふうに定めるかというような定め方についての基準を何も書いていない。ですから、それはまず政令で自由にてきるというふうに考えなければならない。そうすると、結局いままで廃止されないと思っていたものが廃止されてみたり、または廃止される対象線区が廃止されなかったりというふうに、自由自在に政令で操ることができるということになるのですよ。ですから、この法律というのは全く切り捨て御免の法律だと言わなければいけないのです。
それで私は聞きますけれども、それでは営業線の区分が法律によって政令に委任されていますか。こんなことがどこに書いていますか。ちょっとお尋ねしたい。
○工藤政府委員 お答え申し上げます。
第八条第一項におきまして「運営の改善のための適切な措置を講じたとしてもなお収支の均衡を確保することが困難であるものとして政令で定める基準に該当する営業線を選定し、」云々というふうにございますが、昨年の十二月の閣議了解を基礎にしまして私どもこれを審査いたしましたときに、輸送密度というものを考えてくれという話は運輸省の方から伺っているところでございます。
ところで、輸送密度につきましては、区間とそこにおきます輸送量、この輸送量を区間で割らなければ輸送密度が出てまいりません。そういう意味で、区間というものがそこに並行して出てくるということは当然であろうかと思っております。
○三浦(久)委員 それは区分をされていなければ、乗車密度が何ぼだといってそれを当てはめて選定することはできない。そんなことはあたりまえです。しかし、それが必要だということと、それが合法性を持つということとは全く違うことですよ。あなたたちが必要だからといって、それが合法性を帯びるということにはならない。そうすると、法制局は、この八条の一項にしぼりますが、一番最初の「日本国有鉄道は、鉄道の営業線のうち、」云々と書いてあって、「政令で定める基準に該当する」とありますが、この基準というものの中には、そうすると四千人とか八千人とかという乗車密度、これは本当の基準、それと同時に線路区分も入っているというふうにお考えになっているのですか。
○工藤政府委員 お答え申し上げましたように、四千人、八千人という数字が出てくる前提がまず問題でございまして、輸送量と区間、営業キロ、この二つがもとになりまして、四千人、八千人という数字も出てまいります。したがいまして、それを決めます場合に、この区間における輸送量が幾ら、こういうことで政令に定める基準に該当するかどうかという判定もまたできるのではないか、かように思います。
○三浦(久)委員 全然もう法律家の議論じゃないよ。そんなものはアプリオリに決まっておるというわけですか。この法律制定の前に決まっておるというわけですか。それだったら国有鉄道線路名称でやらなければならぬということになるじゃありませんか。
そうすると、私はあなたに、逃げの答弁をしておるから言っておきますけれども、八千人とか四千人というのは一つの基準、しかし線路区分というのはこれは基準じゃありませんよ。これはある基準によって区分されたその結果なんですよ。日本語であればそうです。基準というのは、多くのものの中からあるものを選ぶ、そういう場合のもとになる標準を言うのです。だから、この区分というのはこの基準には該当しないと私は思う。しかし、あなたに何ぼ言ってもそういうことをうんと言わないから、私はもう時間もないから私の見解を述べるけれども、たとえば私の考え方では、この基準に該当しないのです。これは委任していない。たとえば、道路法をあなた見てごらんなさい。道路法の第五条に一般国道の定義というのがありますね。この中で「一般国道とは、高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号の一に該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。」その第二項で「前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。」こういうように、道路法でははっきり法律によってその路線名と起点と終点というものが決められているのです。委任されている。これに基づいて決めているのです。ところが、この再建法はそんなことは一つも書いていない。結局どういうことかというと、あなたたちはまずこの法律をつくったときに、国有鉄道線路名称、これがあるからこれでやればいいのだ、そういうように思っておったということです。ところが、この国有鉄道線路名称によればいろいろな矛盾が出てくるということを指摘されて、それでやるというわけにいかなくなってしまって、それで結局いまのような答弁になっている。だから、もともとあなたたちはこの国有鉄道線路名称をもとに考えておったということなんです。ということは、結局明確な法律に基づく政令委任というものがないわけですから、この法律に基づいてはそういうことを決めることができないのですよ。ということは、私はこの法律の致命的な欠陥だというふうに思いますけれども、いかがですか。法制局どうですか。
○工藤政府委員 お答え申し上げます。
ただいまの道路法の規定は、先生御指摘のとおりの規定がございます。
ただ、今回のこの再建法と道路法とは、その趣旨においても異なりますし、したがいまして規定のしばりもまた異なって当然かと思います。
○三浦(久)委員 もう終わりますけれども、しかし営業線についての区分を決めるのは、何の縛りもないのですよ。法律による区分というものは、性格上適用にならないのですよ。結局これは政令委任のないことを勝手に政令でやろうとしているということにほかならないし、また自由に政令でもって線区を決めることによって、切り捨て御免というような結果をもたらしているというまさに欠陥法案だと私は思うのです。こういう法律が制定されて、そしてまた線区別運賃でも設定された場合に、住民の皆さんから、その線区別運賃は不当であるから不当利得の返還請求訴訟というものが起きるかもしれない。そういう訴訟にもたえられないような致命的な欠陥を持った法律なんだということを私は最後に一言申し上げて、時間が来ましたので、質問を終わらしていただきたいと思います。
○小此木委員長 この際、午後三時二十五分まで休憩いたします。
午後三時一分休憩
――――◇―――――
今回のお話は、正直殆ど議論が噛みあっていないと言うか敢えて外しているということなのか、のらりくらりと逃げている…そんな風に受け取れます。
実際には、播但線の姫路~飾磨港のように播但線という本来であればくくりから見れば廃止対象にならなかったかもしれませんが、極端に旅客扱いが少なかったことから結局は廃止になりましたし、通称尼崎港線のように貨物線となっていたところなどもその実態に応じて廃止されていったところも多数ありました。
三浦議員の「 現在の国鉄線路名称に基づけば、たとえば本線に入っている、そういうものを政令を制定する段階で本線から外してしまうというようなことは、法律上は可能なのでしょう。どうですか。」という質問であり、実際にはより実態に応じた形で整理が図られたので播但線の飾磨港のように、本来は播但線という位置づけで残せたかもしれませんが、現実的対応として廃止に追い込んでいますよね。

以下は、工藤政府委員と三浦委員の審議の様子です。
明日以降は出来るだけきちんと書けるようにしますので、今回は節にご容赦を

昭和56年4月で旅客営業を廃止した通称尼崎港線(尼崎港~塚口間)の区間列車
*********************以下国会審議の内容*************************
○三浦(久)委員 法制局、来ておりますか。
質問いたしますが、現在の国鉄線路名称に基づけば、たとえば本線に入っている、そういうものを政令を制定する段階で本線から外してしまうというようなことは、法律上は可能なのでしょう。どうですか。
○工藤政府委員 お答え申し上げます。
法律案におきましては、第八条の一項あるいは二項におきまして、「政令で定める基準に該当する営業線」という形で書いてございます。一応政令の委任の範囲内において規定し得るものは規定する、こういうことだと思います。
○三浦(久)委員 質問に答えてくださいよ。もう一回質問いたします。たとえば、いま国鉄線路名称に基づけば本線に入っている、そういうものを本線から外してしまう、また逆にいま本線に入っていない支線、それを政令制定の段階で本線に編入してしまう、そういう決め方をしてもそれは法律に違反をするということにはならないのでしょうというふうに聞いているのです。
○工藤政府委員 お答え申し上げます。政令案の中身につきまして、私ども実はまだ審査をいたしておりませんので、断定的なことは、あるいは結論めいたことは申し上げるのは差し控えさせていただきますが、いまお尋ねの点につきましては、「政令で定める基準に該当する」ということで、一応基準に該当する営業線というものは政令に委任されております。その委任されております範囲内におきましては、これは八条以下のこの制度の趣旨にかんがみまして、妥当な線を妥当な基準で決めていく、こういうことでございます。したがいまして、本線であるか支線であるかという点につきまして、私ども実態を運輸省その他からまだよく伺っておりませんので、その実態的な判断を含めましては保留させていただきます。
○三浦(久)委員 法制局だから法律的な見解を聞いているわけですよ。妥当とか妥当じゃないとか、そんなことは政策の問題なんです。私は違法かどうかということを聞いているのです。ですから、政令で委任された範囲内で可能だというのなら、いま私が言った、たとえば支線を本線に編入したり、また本線に編入されているものを取り除いたりというような作業は、政令で委任されている範囲というふうにあなたたちは考えているのですかどうですかと言っている。
○工藤政府委員 お答え申し上げます。
基準の考え方自身をまだ私ども実は伺っておりません。そういうことで線路をそれぞれ決めるということ自身は、政令で該当するということで可能でございますが、どのように決めるかということについては、実は私どもまだ伺っていないということでございます。
○三浦(久)委員 ですから、結局この法律には、線路の終点、起点、それをどういうふうに定めるかというような定め方についての基準を何も書いていない。ですから、それはまず政令で自由にてきるというふうに考えなければならない。そうすると、結局いままで廃止されないと思っていたものが廃止されてみたり、または廃止される対象線区が廃止されなかったりというふうに、自由自在に政令で操ることができるということになるのですよ。ですから、この法律というのは全く切り捨て御免の法律だと言わなければいけないのです。
それで私は聞きますけれども、それでは営業線の区分が法律によって政令に委任されていますか。こんなことがどこに書いていますか。ちょっとお尋ねしたい。
○工藤政府委員 お答え申し上げます。
第八条第一項におきまして「運営の改善のための適切な措置を講じたとしてもなお収支の均衡を確保することが困難であるものとして政令で定める基準に該当する営業線を選定し、」云々というふうにございますが、昨年の十二月の閣議了解を基礎にしまして私どもこれを審査いたしましたときに、輸送密度というものを考えてくれという話は運輸省の方から伺っているところでございます。
ところで、輸送密度につきましては、区間とそこにおきます輸送量、この輸送量を区間で割らなければ輸送密度が出てまいりません。そういう意味で、区間というものがそこに並行して出てくるということは当然であろうかと思っております。
○三浦(久)委員 それは区分をされていなければ、乗車密度が何ぼだといってそれを当てはめて選定することはできない。そんなことはあたりまえです。しかし、それが必要だということと、それが合法性を持つということとは全く違うことですよ。あなたたちが必要だからといって、それが合法性を帯びるということにはならない。そうすると、法制局は、この八条の一項にしぼりますが、一番最初の「日本国有鉄道は、鉄道の営業線のうち、」云々と書いてあって、「政令で定める基準に該当する」とありますが、この基準というものの中には、そうすると四千人とか八千人とかという乗車密度、これは本当の基準、それと同時に線路区分も入っているというふうにお考えになっているのですか。
○工藤政府委員 お答え申し上げましたように、四千人、八千人という数字が出てくる前提がまず問題でございまして、輸送量と区間、営業キロ、この二つがもとになりまして、四千人、八千人という数字も出てまいります。したがいまして、それを決めます場合に、この区間における輸送量が幾ら、こういうことで政令に定める基準に該当するかどうかという判定もまたできるのではないか、かように思います。
○三浦(久)委員 全然もう法律家の議論じゃないよ。そんなものはアプリオリに決まっておるというわけですか。この法律制定の前に決まっておるというわけですか。それだったら国有鉄道線路名称でやらなければならぬということになるじゃありませんか。
そうすると、私はあなたに、逃げの答弁をしておるから言っておきますけれども、八千人とか四千人というのは一つの基準、しかし線路区分というのはこれは基準じゃありませんよ。これはある基準によって区分されたその結果なんですよ。日本語であればそうです。基準というのは、多くのものの中からあるものを選ぶ、そういう場合のもとになる標準を言うのです。だから、この区分というのはこの基準には該当しないと私は思う。しかし、あなたに何ぼ言ってもそういうことをうんと言わないから、私はもう時間もないから私の見解を述べるけれども、たとえば私の考え方では、この基準に該当しないのです。これは委任していない。たとえば、道路法をあなた見てごらんなさい。道路法の第五条に一般国道の定義というのがありますね。この中で「一般国道とは、高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号の一に該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。」その第二項で「前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。」こういうように、道路法でははっきり法律によってその路線名と起点と終点というものが決められているのです。委任されている。これに基づいて決めているのです。ところが、この再建法はそんなことは一つも書いていない。結局どういうことかというと、あなたたちはまずこの法律をつくったときに、国有鉄道線路名称、これがあるからこれでやればいいのだ、そういうように思っておったということです。ところが、この国有鉄道線路名称によればいろいろな矛盾が出てくるということを指摘されて、それでやるというわけにいかなくなってしまって、それで結局いまのような答弁になっている。だから、もともとあなたたちはこの国有鉄道線路名称をもとに考えておったということなんです。ということは、結局明確な法律に基づく政令委任というものがないわけですから、この法律に基づいてはそういうことを決めることができないのですよ。ということは、私はこの法律の致命的な欠陥だというふうに思いますけれども、いかがですか。法制局どうですか。
○工藤政府委員 お答え申し上げます。
ただいまの道路法の規定は、先生御指摘のとおりの規定がございます。
ただ、今回のこの再建法と道路法とは、その趣旨においても異なりますし、したがいまして規定のしばりもまた異なって当然かと思います。
○三浦(久)委員 もう終わりますけれども、しかし営業線についての区分を決めるのは、何の縛りもないのですよ。法律による区分というものは、性格上適用にならないのですよ。結局これは政令委任のないことを勝手に政令でやろうとしているということにほかならないし、また自由に政令でもって線区を決めることによって、切り捨て御免というような結果をもたらしているというまさに欠陥法案だと私は思うのです。こういう法律が制定されて、そしてまた線区別運賃でも設定された場合に、住民の皆さんから、その線区別運賃は不当であるから不当利得の返還請求訴訟というものが起きるかもしれない。そういう訴訟にもたえられないような致命的な欠陥を持った法律なんだということを私は最後に一言申し上げて、時間が来ましたので、質問を終わらしていただきたいと思います。
○小此木委員長 この際、午後三時二十五分まで休憩いたします。
午後三時一分休憩
――――◇―――――










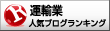
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます