
飯坂温泉みちのく荘にて、國分功一朗『中動態の世界』を読む会が開催されました。
こんな難解な本なのに、遠くはいわき市や郡山市から、なんと14名もの参加者に恵まれました。

今回のカフェマスターは、10年来の國分功一郎ファン(弟子⁈)を自称する島貫さん。
第一部は島貫さんによる明快な「中動態」の解説に目が開かれる思いでした。
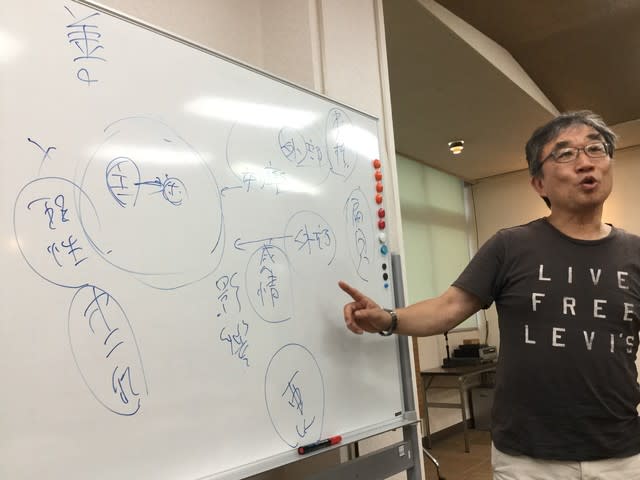
そのまとめは島貫さんがまとめて下さると思うので、ここでは第2部で渡部が報告した内容をまとめてみます。
國分功一郎『中動態の世界』におけるアーレント批判をどう読むか?(渡部 純)
はじめに―『中動態の世界』への違和感から
今村雅弘復興相の「自主避難は本人の責任」問題(2017.4.4)をめぐり、國分はツイッターにこう呟いています。
「いま原発問題を経済学的に研究している極めて優秀な元教え子から、『中動態の世界』を読みながらずっと自分は「自主避難者」のことを考えていたと聞き、眼が覚めるような思い。選択の事実が自発性・能動性へと自動的に連絡されてしまう思考回路の問題」〔2018.2.6〕
わたしは、この発言が切り捨てのための自己責任論批判として自主避難を中動態として捉える見方に賛同しますが、一方で彼・彼女らが「移住者」ではなく、あえて「自主避難者」と名乗ることの意味をどのように考えているのか。
彼らの中には「避難者」の公的認定を外されてもなお、「移住者」ではなく「避難者」を名乗っているのは、果たして中動態的な枠組みで論じるべきなのでしょうか。
また、本書で國分はアーレントの意志論を徹底して否定していますが、しかし國分はアーレントの意志論の核心をあえて無視しています。
それはなぜなのか?両者の折り合いの悪さはどこにあるのか?果たして結びつかないのだろうか?
そんな関心から本書を突っ込んで読んでみようと思った次第です。
1.『中動態の世界』が目指すもの―「尋問する言語」(能動態/受動態)の支配を批判する
國分は中動態について、次のように説明しています。
「「能動/中動」の対立では行為を「自分の外側で終わるか/自分の中で完結するか」で分類します。例えば「惚れる」というのは中動態です。誰かを“好きになろう”と意識して惚れるのではなく,好きという感情が“自分の中に立ち現れてくる”というイメージですよね。一方,中動態と対立する意味での能動態は,例えば誰かを「殴る」というような“他人に働き掛ける”行為のことです。このように中動態の世界では,能動態のほうも現在のイメージとは異なっていたのです」「中動態の世界」と医療 第16回小林秀雄賞 受賞記念インタビュー)
能動でも受動でもなく内に立ち現れるもの。それが中動態なるものだといいます。
「重要なのは、謝罪が求められているとき、実際に求められているのは何かということである。/たしかに私は「謝ります」という。しかし、実際には、私が謝るのではない。わたしのなかに、私の心のなかに、謝る気持ちが現れることこそが本質的なのである」(『中動態の世界』)
しかし、その中動態は歴史的には意志の出現とともに消え去ります。
國分はアーレントとともに、古代ギリシアに「意志」概念がなかったことを指摘しますが、アーレントによれば、これは古代ギリシアの時間観念が円環的時間であることと関係し、意志はパウロによって発見されたというように、キリスト教の直線的な時間観念の登場と関係します。
円環的な時間観念の世界では、常にある行為は先行する過去の要素(可能態)に影響を受けたものになります。
これは「選択」と呼ばれるプロアイレシスと呼ばれ、ランチを蕎麦にするかラーメンにするか選択をする際の判断力に近い能力として、アリストテレスが発見します。
しかし、アーレントはこの行為の原動力となるプロアイレシスは「意志」ではないといいます。
意志は、過去から未来へ向かうという直線的な時間観念において「未来」に対応する能力でであり、過去の要素に規定されるのではなく、いまだない「未来」に投企する「新しく始める」能力なのです。
2.なぜ、國分はアーレントの「意志」論を批判するのか?
國分はアーレントの功績はアリストテレスのプロアイレシスを発見したことだといいながら、精神において過去から切り離された純粋な「自発性」などは存在しないと、その考え方をばっさり否定します。
少なくとも、それは哲学的には基礎づけられない。その証拠にアーレントはキリスト教神学に答えを求めようとするではないか。
なるほど、アーレントは意志の存在をパウロやアウグスティヌス、ドゥンス・スコトゥスなどキリスト教神学・哲学者を参照します。
そして、それこそがアーレントの意志論の核心であるにもかかわらず、國分は神学的であって哲学的ではないとばっさり切り捨てるのです。
そこから國分は「アーレントの意志論はカツアゲ問題を解決できない」という批判を展開します。
アーレントであれば、「暴力によって脅されてはいるものの、物理的には強制されずに行った行為」であり、アリストテレス的には「自発的行為」と見なせるだろう。しかし、脅されて金を差し出す行為は「させられている」とも「している」とも言えない奇妙な状態であり、自発的か非自発的行為か区別するのは困難であり、むしろ、アリストテレスは同じ行為でも状況や視点によって自発的とも非自発的ともいわれる両義性に着目していた。
さらに、國分はフーコーが「権力は押さえつけるものではなく行為させるもの」という論に注目しながら、便所掃除をやらせるためには、進んで便所掃除をすると同時に便所掃除を嫌々させられているという事態をクリアに解明します。
それゆえ、カツアゲは「嫌々ながらも同意している」(非自発的同意)のではないか?
アーレントは、この「非自発的な同意」を「同意」と認めなかったがゆえに、つまり彼女が自発か非自発か(能動か受動か)という図式で考えていたがゆえに、「カツアゲ」問題を説明できないのだというわけです。
強制はないが自発的でもなく同意している。そうした事態は日常にあふれている。
もし、非自発的同意を行為の一類型として認めないならば、セクハラのように、ある同意に対して「同意したから自発的であったのだ」と見なされる可能性が出てくるわけです。

3.なぜ、アーレントは「責任」を問うたのか?―尋問するアーレント
以上の國分の分析は、「仕方なく選んだ行為」を意志による自発的行為では説明できない中動態的なものを見事に描き出します。そこには「尋問する言語」が責任を追及することに終始し、うまく非自発的同意という事態を説明できない問題を解明しています。
それによって主に医療やケアの領域で中動態の世界観が注目され始めていることは島貫さんの報告の通りです。
しかし、その一方で、國分はなぜアーレントが「責任」や「意志」を論じようとしたのか、その背景をまったく無視してることが気になります。
果たして、そこを無視したまま、アーレントの意志論は幻想だ、哲学的にはありえないと切り捨ててもよいのか?
むしろ、なぜアーレントと國分の議論がかみ合わないのか、その部分に着目してみなければいけないと思います。
なぜ、アーレントは「責任」や「意志」を論じようとしたのか。
それは全体主義が席巻し始める中、「私たちを困惑させたのは、敵の行動ではなく、こうした状況をもたらすために何もしなかった友人たちのふるまいだったのです」(「暗い時代の人々」)というアーレントの絶望に端的に示されていると思います。
しばしば、アーレントの戦争責任をめぐる議論は厳しいと指摘されます。
たとえば、メアリ・マッカーシーの「誰かがあなたに銃を向けて〈お前の友人を殺せ、さもなくばお前を殺すぞ〉といったとすると、その人はあなたを誘っているのです。それだけです」ということばを用いながら、「誘惑」は法的には言い訳になるが道徳的に正当化する理由にはならないといいます(「独裁体制のもとでの個人の責任」)。
「誘惑」は断ることもできたはず。実際に、そのような選択をした人々もいる。
ユダヤ人絶滅計画になにがしか加担した人々に対し、アーレントはまさに「尋問的な言葉」を突きつけるわけです。
さらに、いわゆる「歯車問題」において、戦後の戦犯裁判でしばしば主張された被告の「私ではなく、私がその単なる歯車に過ぎなかったシステムが実行したのです」という発言に対して、「それではあなたは、そのような状況においてなぜ歯車になったのですか、なぜ歯車であり続けたのですか」という問いを投げかけながら、「高官から末端の役にまで公的問題を処理したすべての人々は歯車に過ぎなかった。だからといって、だれも個人の責任を負わないということになるでしょうか」と徹底した尋問を繰り出します。
アーレントはこう問う一方で、全体主義政策に対して協力しなかった人々が存在した事実を引き合いに出しながら、それがどういう人々だったのかを論じます。
すなわち、彼・彼女らは「殺人者である自分とともに生きていることができないと考えた人々」であり、自分が悪だと判断したものに加担することで自分自身と矛盾することを拒否した人々だった問うのです。
「たとえ世界の大多数の人びとと不調和であったとしても、自分自身と調和しないわけにはいかない」
これはアーレントのほとんど唯一の道徳命題ですが、「善く生きる」という意味での自己への配慮をなせた人々だけが巨悪に加担せずにいられたというのです。
もちろん、アーレントは「世界への責任を負えなくなる極端な状況は起こりうる」とも言います。
猛烈な全体主義の台頭の勢いを個人一人の力で止めることはできない状況は起こりうるでしょう。
アーレントはこれを「自分が無能力であることは公的な事柄に関与しない言い訳としては妥当なもの」とします。
そして、「どんな絶望的な状況においても、強さと力をわずかながらも残すことができるのは、まさに自分の無能力を自ら認めることによってなのです」というのです。
これは、パウロが「わたしは善をなそうと意志するが、できない」という無能力の経験のうちに「意志」を発見したというアーレントの分析と重なります。
そうであるにもかかわらず、アーレントは「合意するのは成人であり、服従するのは子どもである」と言い切ります。
「独裁体制下の下で公共生活に参加しなかった人々は、服従という名のもとに『責任』ある立場に登場しないことで、その独裁体制を支持することを拒んだのです。十分な数の人々が「無責任に」行動して、支持を拒んだならば、積極的な抵抗や叛乱なしでも、こうした統治形態にどれほどこの武器が効果的であるかわかるはずだ」。
ふつう、戦時中に徴用などに協力しない人々は社会の側から「無責任」だというレッテルを張られます。しかし、ここでアーレントはむしろ社会的に無責任であったことが全体主義という巨悪を止める可能性があったという逆説を提示します。
「自発的にいかなる犯罪にも手を染めなかった人々も、自ら行ったことに対して責任を問うことができるのは、政治的問題と道徳的問題に関して服従などは存在しないからです」という結論に至ります。
したがって、「公的な生活に参加し、命令に服従した人々に提起すべき問いは、「なぜ服従したのか」ではなく「なぜ支持したのか」という問いです」。
なぜ、支持したのか?
中動態的には、このような尋問は人々の行為を暴力的に裁く言語になっており、多様な行為のバックグラウンドをなきものにしてしまいかねない暴力的なものに響くでしょう。
では、中動態はナチス政権当時に「仕方なく協力した」ふつうのドイツ人の行動を肯定するということになるのでしょうか。
さらにいえば、アイヒマンが裁判の最終場面で語った次の言葉を中動態的にはどのように解釈すればよいのでしょうか?
(※これについては島貫さんから応答がありました。)
「…私はぜひともこう断言したい。私はこの殺人、ユダヤ人の絶滅を、人類の歴史上、最も重大な犯罪の一つであると考えている、と。最後にこう明言しておきたい。私は当時からすでに、個人的に、この暴力的な解決は正当化されるものではない、と思っていた、と。恐るべき行為だと考えていた。しかし、とても悔やまれることに、忠誠の誓いに縛られていたので、私は自分のもとで輸送の組織の問題に携わらなければならなかった。その誓いから解放されていなかったのです…ですから、私は心の底では責任があるとは思っていません。あらゆる責任から免除されていると感じていました…私は…命令に従って義務を果たした。そして、義務を果たさなかったと非難されたことは一度もない。今日でもなお、私はそれを言っておかねばなりません」(ブローマン、シヴァン『不服従を讃えて』)。
5.國分とアーレントの何がかみ合わないのか?
そもそも、スピノジアンの國分とアーレントがかみ合うはずはない、と思っています。
國分がスピノザよろしく自由とは必然性を認識することだというならば、アーレントは人間の自由は偶然性にあるのだという思想です。
それでも、以上のことから両者のかみ合わなさがどこにあるのか、的外れかもしれませんが私なりに考えてみたいと思います。
まず一つは、日常の意志行為を問う國分に対して、アーレントは非常事態における意志行為を問うている点を見逃すべきではないのではないでしょうか。
アーレントは『精神の生活 下巻 意志』において、「実際にわれわれが新たな一連のことを始めることはめったにない」や「我々は自由だが、意志していることはめったにない」と述べています。
日常における行為については國分が指摘するように、アリストテレスのプロアイレシス(選択)によって説明することは十分可能でしょう。
しかし、非常事態において、自分自身が無力であるという状況において、あらゆる因果性からでは説明できない行為というものを求めずにはいられなかった、あるいは事実、そのような「異常な行為」というものが出来した。
アーレントは歴史の出来事を過去からのプロセスの過程の上に連鎖するものではなく、その時間を中断する「新しい始まり」だとみなします。
ここは難しい問題で、起こった出来事は後から認識で捉えようとすると、あらゆる出来事が因果関係で説明できてしまいます。
そこに偶然性を見出すことは、國分流に言えば「あり得ない」ということになるでしょう。
しかし、歴史の出来事を必然とみるか偶然とみるかは、決定的な要素です。
もちろん、歴史的な出来事は人々の行為によって引き起こされるものですが、アーレントはその原動力となる意志は意志自らが原因であり、それは偶然性という事実によって因果性によって説明されないというのです。
アーレントは、「何かが偶然的であることを否定するものは、自らが拷問されないこともありうることを認めるまでは、拷問をかければよい」というドゥンス・スコトゥスの言葉を引きながら偶然性を擁護しますが、これはまさに逃れられない「拷問」状況にある人々が奇跡的な出来事が起こることをの求めずにはいられないことを肯定するために、意志を擁護する必要があったのだと思うのです。
重要なのは、アーレントが神の恩寵にではなく、人間の意志という能力に求めたという点なのです。
もう一つは、事態(現象)の次元を問う國分に対して、アーレントは倫理の次元を問う点です。
冒頭で自主避難者をめぐる國分の発言に注目しましたが、たしかに今村のように自主避難者の行動を自己責任と責める言説がある一方で、あの「正解がない状況」においては「誰もその選択を責められない」という言説が、被災地にはあることを無視すべきではありません。
むしろ、福島に生活していれば前者の考え方が少数派であるように感じます。
そして、まさにそれこそが中動態的な見方であり、複雑な状況の中で選ばざるを得なかった避難/残留という行動を肯定してくれる論理だと思うのです。
しかし、そうであるにもかかわらず、それぞれの選択において「負い目」を抱く人々が少なくないこともまた事実です。
自分の家族を守るために職場である病院を離れて患者を見捨てた罪悪感に苛む看護師、放射線量の高い時期に福島県産の食材を用いた給食を食べさせることに葛藤を覚える小学校教員…
その状況において「仕方なく同意した」、「それ以外の選択肢は考えられなかった」にもかかわらず、「負い目」が生じてしまう問題に中動態はどう応えてくれるのか?
〈わたしは意志するが実行できない〉という無能力のうちに意志が発見されるのだとすれば、まさに原発事故被災者のほとんどが「意志」を発見していたのかもしれません。
そして、その意志とは、常に〈わたしは意志する〉と〈わたしは否と意志する〉の抗争が生じているというのがアーレントの分析です。
この「闘争の結果は行為によってのみわかる」のですが、どちらが勝利するのかを決定するのは、理性でも欲望でもなく意志自身だというのです。
つまり、それこそ、どちらが勝利するかはほとんど偶然にゆだねられているということなのかもしれません。
「誰かがあなたに銃を向けて〈お前の友人を殺せ、さもなくばお前を殺すぞ〉といった」とき、それにYESと答えるか、NOと答えるかは道徳意識でも実践理性でもなく、偶然性を本質とする意志自身なのです。
相手を殺さなければ自分が殺される「にもかかわらず」、殺すことにNOという。
この「にもかかわらず」という逆説において、意志の自由は見出される可能性があるのではないでしょうか。
アーレントは、「自由な行為の試金石は、常に我々が実際に行ったことを行わないままにしておくことができたはずだということを我々が知っていることにある」といいます。
ということは、意志の存在は事後的に判明するものであり、そして為しえなかった無能力においてこそ見いだされるものだということになるのでしょう。
したがって、原発事故のさなか、被ばくの不安を抱きながら沈黙する学校の職員室の光景を思い浮かべながら、「もし、あのとき、みんなで声を上げていたとして、それがいったい何になったのでしょうか?」と問いかけるある教員の言葉は、意志の発見の端緒に立っているというべきかもしれません。
この問いかけに、私はいまだ答えをもっていないのですが、あえてアーレント流にいえば、「わからない。けれど、声を上げることで別の何かが起きていたかもしれない。それが時間を中断する新しい始まりなのかもしれない」と、さしあたり応えるしかないように思われます。
6.國分とアーレントの議論は結びつかないのか?
さて、國分とアーレントのかみ合わなさについて述べました。
では、両者の議論が絶対的に結びつかないのかといえば、私はそんなことはないと思っています。
むしろ、中動態の議論はまさにアーレントの思想を十全なものにするために必要なものだとさえ考えています。
既に述べたように、アーレントが責任を論じる背景には、全体主義に協力していった「友人」たち、「ふつうのドイツ人」たちへの絶望がありましたが、それは言いかえれば、そのこと対する応答―責任を求める点にありました。
そして、その問題はアーレントが『人間の条件』で論じた「裁き」や「赦し」の問題において、その結びつきが重要なのだと思います。
アーレントは、人々の「行為action」は予言不可能な偶然性を本質としているといいます。
それが意志の偶然性と関係することあ言うまでもありませんが、そうであるがゆえに人間の行為はとんでもない事態を引き起こすこともあるわけです。
とんでもないこととは、つまり大きな被害をもたらしたり、大悪事を引き起こしたりしてしまうということです。
しかも、しでかしてしまったことは元に戻すことができない不可逆性も、行為の自由の本質に含まれています。
そうなると人間の行為とは困ったものになってしまうわけですが、アーレントはそれに対応する人間の活動能力が「裁き」と「赦しだというわけです。
テロという行為は復讐の連鎖を生み出します。
その連鎖を断ち切るための能力が、とりわけ「赦し」なのです。
しかし、自分の愛する家族を殺した相手を「赦す」などということは、果たしてできるのでしょうか?
「汝、敵を愛すべし」というキリスト教の道徳律は、まさにその不可能性を命題として提示します。
その逆説にこそ、意志の自由、偶然性が問われると思うのですが、しかしそれは形式的に「赦す」というだけで可能になるものではないでしょう。
そして、「赦し」が実現するために相手の「謝罪」が条件の一つであることはいうまでもありません。
しかし、「尋問する言語」によってでは、心からの反省や謝罪の言葉を生まないのではないか。
そのことを考えさせられるのは、いわゆる「撫順戦犯法廷の奇跡」です。
これは日中戦争期に中国国内で戦争犯罪を犯した容疑で、戦犯容疑者が撫順戦犯管理所と太原戦犯管理所に収容された際、中国共産党政府の設置した戦犯管理所で、シベリア抑留時代とは異なり栄養豊富な食事、病人や怪我人への手厚い看護、衛生的・文化的生活が戦犯容疑者たちに保障されながら、戦争中「日本による数多くの非人道的な犯罪行為を目にし、加担し、実行した」自分たちの行為を「反省」し、罪を「自主的に」告白する「認罪運動」が行われたものです。「認罪」とは、心からの反省と謝罪を自分で認め告白することですが、それが認められれば放免されるという制度でした。
まさに、「認罪」とは、「わたしのなかに、私の心のなかに、謝る気持ちが現れることこそが本質的なのである」という國分お言葉と重なるでしょう。
しかし、それの言葉や語りは、「尋問する言語」から解放されていることにおいて可能になることを、この撫順の奇跡は示してはいないでしょうか。
まさに、その意味において責任に応える謝罪は中動態的なものにならざるを得ないわけです。
他方、「赦し」を行う側もまた「赦す」気持ちが心のなかに現れなければ可能にはならないはずです。
今日、内戦による国内分断を克服する方法として真実和解委員会という制度が国際的に実践されています。
そこでは、復讐の連鎖を断ち切るために「罰」ではなく、を自分が犯した人種差別的な暴力や虐殺行為を洗いざらい告白すれば罪を問わないという「赦し」が制度化されています。
修復的司法など、和解を目的とした紛争解決方法の模索は今日、各国で模索されていますが、制度化されればその目的が達成されるわけではありません。
そこにおいて謝罪と赦しのプロセスの中で絶えず中動態的な行為が努力されていくということになるのでしょう。
最後に、原発事故での経験を聞き取りしていると、意志的ではなく、ふと到来するような言葉や語りに出会うということがたまにあります。
そのたびごとに、私はアレクシエーヴィチの次の文章を想い起します。
「どれだけ時間がかかるか分からないのだが、突然、ふっと、待ちかねていた瞬間が訪れる。判で押したような、わが国の鉄筋コンクリートでできた記念碑のような常識を離れて、自分に返っていくときが。自分の奥に入っていく。戦争をではなく、自分の青春を思い起こす。自分にしかない人生の一部を。その瞬間をとらえなければならない。いろいろなおしゃべりや事実を羅列した長い一日をすごしたあげくに残るのは、たった一つの文章だったりする(でもそれがすごい!)」(アレクシエーヴィチ,『戦争は女の顔をしていない』)
くり返すと、このような「到来する言葉」は「尋問する言葉」から解放されていることで可能になるのではないか。
すると、アーレントが「尋問」する責任は、「尋問する言語」から解放されるという中動態的な条件が必要なのかもしれません。
しかし、それはまた、「仕方なく同意した」という無責任体制を肯定するような論理に絡めとられかねない緊張を要するものではないでしょうか。
その境界の緊張を維持することで、〈赦し〉の条件としての中動態的な「謝罪」は可能になるのではないでしょうか。
さて、質疑応答の時間には、さまざまな質問やご意見をいただきながら、3時間半にわたるアツい議論が交わされました。
そして、夜も夜で、政治談議からアート談義、新しいカフェロゴ企画案など、午前様を過ぎてもなお暑苦しいトークは止まらないのでした。

(文・渡部純)










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます