古生物学者のスティーヴン・ジェイ・グールド(Stephen Jay Gould)は、生物進化学の啓蒙書でのベストセラーのひとつと言える『ワンダフル・ライフ』(1989)[Ref-1]の中で「進化の歴史をもう一度巻き直したら全く違った世界になる」と述べています。『ワンダフル・ライフ』の内容の基となっているのはカナダのヨーホー地区に広がるバージェス頁岩(Burgess Shale)に含まれる化石群の研究ですが、それを実際に調査研究した古生物学者であるサイモン・コンウェイ・モリス(Simon Conway Morris)はその著書『カンブリア紀の怪物たち(Journey to the Cambrian: the Burgess_Shale and the explosion of animal life)』[Ref-2]の中で真っ向から反論を述べています。後者は前者ほど有名ではありませんが、真理を判断しようとするなら両者の見解を共に知ることが必要でしょう。なおモリスの業績については『ワンダフル・ライフ』の中でもたびたび紹介されています。
では両者の論点を紹介しましょう。まずモリスの主張は割と明確です。
生物進化には収斂進化という現象があります。これは、祖先が異なる生物種が同じような生態的地位(ニッチ)を得た場合、同じような形態になるという現象です。例えば水中を高速で移動するという生き方をする生物は流線形の体になるのが一例です。空を飛ぶニッチなら翼を持つのもそうですね。
そして系統が違っても同じような形態に収斂するということは、偶然でどの系統が生き残ったとしても同じような生物が現れるというこであり、どの系統が生き残るかは偶然で構わないとも言えます。そのよい例が白亜紀末の巨大隕石落下による恐竜絶滅です。恐竜が絶滅したために、恐竜が占めていた陸上大型動物のニッチに空席ができ、生き残った哺乳類から進化した動物たちがそのニッチを埋めた結果、似たような動物が登場しました。しかし、もしも巨大隕石落下という偶然がなければ哺乳類たちが進化できなかったのは、今や明らかです。
『カンブリア紀の怪物達』7章の次の文章にはモリスの主張がよくまとめられています。
--------引用開始(下線は私の強調) -------
進化の最終産物として人間を捉えてはいけないという一連の議論は、あるポイントをはずしている。この議論は、ある生物の系統--ある家柄の血統であれ、ある一つの門の系統であれ--の運命と、ある生物や生物学的特徴が、進化過程において自ずと現われてくる公算があることとを混同しているのだ。系統の運命は、例えば鯨が進化することは、カンブリア紀の爆発の時点では、他の何百もの動物の運命と同様、予測することはできない。けれども海中をすばやく泳ぎ、海水を濾過して食物を得るある種の動物が進化することは、たぶんかなりあり得る話であり、恐らくそれは事実上避けられないことだ、というところがポイントなのだ。カンブリア紀の爆発に続く進化には一〇億もの可能な道筋があるだろうが、実際の可能性の幅は、すなわち予想される最終産物の種類は、だいぶ限定されるように思われる。もしこれが正しい判断であるなら、進化は拘束されない無制限の実験の連続であるとは言うことができない。生物のデザインには限りがある。
--------引用終り ---------------
すなわち、同じような環境で進化し得る生物のデザインには限りがあり、歴史をもう一度巻き直してもそれほど違った世界にはならない、というのがモリスの反論です。対するグールドは、カンブリア紀に出現し繁栄した多様な生物の門の一部だけが生き残ったのは偶然であり、歴史をもう一度巻き直したら別の門が生き残り、代わりに現在反映している門世界は実際に生じた世界とは非常に異なったものになっただろう、と述べています。
さてここでグールドの主張には複数の要素があるように見えて、ややわかりにくい面があります。モリスもどの系統が生き残るかは偶然に左右された可能性は否定していないので、この点では両者は一致しますし、収斂進化の存在はグールドも否定しないはずです。するとグールドの主張には2つの可能性があります。
1.異なる系統が生き残った世界は(たとえ収斂進化していても)異なる世界である。
2.異なる系統では、基本的デザインが異なるために収斂進化の可能性に限界がある。
ゆえに、ある系統が偶然に絶滅した場合は絶対に実現しないデザインがある。
ゆえに、異なる系統が生き残った世界では、それぞれ異なるデザインが優勢になる。
1であるなら単なる見方の違いにすぎません。しかし2であるなら、実際に観測事実で検証可能な論争です[*1]。実のところはどうなのか? グールドが挙げている実例に沿って考えてみるのがよいでしょう。それがまとまっているのは『ワンダフル・ライフ』5章「実現しえた世界」の「考えうる7通りの世界」の部分です。
この7通りの世界の前に、注意したいことがあります。
ひとつは、全体として「歴史を巻き直しても人類のような知的生物(文明を作れる生物)は登場するか?」という命題が大きなテーマとなっていることです。私見ではこれは現在のところは難問です。特殊過ぎて生物進化全体に通じる理論の実例としては不適切に思えます。
もうひとつはグールドの論法のいくつかについてです。それは1番目のシナリオ「真核生物の進化」に出てくる文章です。
--------引用開始(下線は私の強調) -------
着実な進歩という古い信念に照らしてみると、初期の生命の進化ほど奇妙なものはありえないだろ
う。じつに長いあいだ、ほとんど何も起こらなかったのだ。
(中略)
二〇億年以上にわたってストロマトライトとそれをつくった原核生物の化石ぼかりが世界中から見つかる。最初の真核生物(核とさまざまな細胞小器官をそなえた複雑な細胞からなる生物)が登場したのは一四億年ほど前のことである。
(中略)
したがって生命の歴史の優に半分以上は、原核生物しか登場しない物語であり、地球上に生命が誕生してからこれまでの時間のうちの後半六分の一だけにしか多細胞動物は登場しないのである。
そんなにも遅れたこと、そんなにも長い時間を要したことが、偶発性の介在と可能性が実現しなかった膨大な領域の存在を強く物語っている。原核生物が真核生物になるべく向上しなければならなかったのだとしたら、そうなるにあたってはまちがいなくそれだけの時間がかかった。
--------引用終り ---------------
ここで「着実な進歩という古い信念」と呼ばれているのは、人類が進化の頂点であり頂点の登場は必然だという信念のことで、第1章で「人類が登場したのは必然であり他に優越している」「直線的な向上という思考の拘束着」「進化とはすなわち"進歩"と理解されている」と書かれている考え方です。これは『ワンダフル・ライフ』の著作当時であっても進化生物学者の間ではとっくに廃れていたはずの考え方であり、未だにこのような誤解をしているであろう専門外の人達に対する啓蒙として書かれているようにも見えます。が、実のところは、この古い考え方をしている主要な仮想論敵は、バージェス頁岩の発見者である古生物学者チャールズ・ウォルコット(Charles Doolittle Walcott)のようです[*2]。
さて上記の引用で注意したいもうひとつの点は、「登場に長い時間を要したから真核生物や多細胞動物の登場は偶然だった」という論法は正しくないということです。ここには「それだけの長い時間の間は、真核生物や多細胞動物が登場するような環境ではなかった」という可能性があるからです。実際に多細胞動物の登場は全球凍結という大きな環境変化の直後だったと判明しています。もちろんここで全球凍結のような生物圏の外の現象を偶然と考えれば、多細胞動物の登場は偶然となりますが、全球凍結が偶然か必然かは惑星の進化についてのさらなる研究によるしかないでしょう。
また人類の様々な文化、例えば農業の発展や土器制作なども氷河期のような環境変化に対する適応として理解しようとする試みもなされています。では氷河期は偶然か必然かという話になるでしょうが、その前に環境変化と進化との関係を具体的に明らかにすることは必要でしょう。しかし『ワンダフル・ライフ』では、このような議論はあまりなされてはいません。むしろ「地球環境の生物圏外の変化は同じだったとしても」という条件での歴史の巻き直しを想定しているように思えます。
続く
-------------
Ref-1)
a) 渡辺政隆(訳)『ワンダフルライフ:バージェス頁岩と生物進化の物語』早川書房(1993/04/15) ISBN10: 4-15-203556-0
b) 渡辺政隆(訳)『ワンダフルライフ:バージェス頁岩と生物進化の物語』早川書房(2000/03/01) ISBN10: 4-15-050236-6
Ref-2) 松井孝典(訳)『カンブリア紀の怪物たち』講談社(1997/03) ISBN-10: 4-06-149343-4
モリスが現代新書のために書き下ろしたもので英語版の本はないらしい。本書の「後記」を参照。
-------------
*1) 実は「異なるデザイン」の分類が人により異なることが大いにありうる。2つの生物が同じデザインなのか異なるデザインなのかで見方が食い違いうるということだ。
*2) ウィキペディアの記事によれば、グールドによる批判は「バージェス動物群の特異性を強調するためのレトリック的な面もある」。
では両者の論点を紹介しましょう。まずモリスの主張は割と明確です。
生物進化には収斂進化という現象があります。これは、祖先が異なる生物種が同じような生態的地位(ニッチ)を得た場合、同じような形態になるという現象です。例えば水中を高速で移動するという生き方をする生物は流線形の体になるのが一例です。空を飛ぶニッチなら翼を持つのもそうですね。
そして系統が違っても同じような形態に収斂するということは、偶然でどの系統が生き残ったとしても同じような生物が現れるというこであり、どの系統が生き残るかは偶然で構わないとも言えます。そのよい例が白亜紀末の巨大隕石落下による恐竜絶滅です。恐竜が絶滅したために、恐竜が占めていた陸上大型動物のニッチに空席ができ、生き残った哺乳類から進化した動物たちがそのニッチを埋めた結果、似たような動物が登場しました。しかし、もしも巨大隕石落下という偶然がなければ哺乳類たちが進化できなかったのは、今や明らかです。
『カンブリア紀の怪物達』7章の次の文章にはモリスの主張がよくまとめられています。
--------引用開始(下線は私の強調) -------
進化の最終産物として人間を捉えてはいけないという一連の議論は、あるポイントをはずしている。この議論は、ある生物の系統--ある家柄の血統であれ、ある一つの門の系統であれ--の運命と、ある生物や生物学的特徴が、進化過程において自ずと現われてくる公算があることとを混同しているのだ。系統の運命は、例えば鯨が進化することは、カンブリア紀の爆発の時点では、他の何百もの動物の運命と同様、予測することはできない。けれども海中をすばやく泳ぎ、海水を濾過して食物を得るある種の動物が進化することは、たぶんかなりあり得る話であり、恐らくそれは事実上避けられないことだ、というところがポイントなのだ。カンブリア紀の爆発に続く進化には一〇億もの可能な道筋があるだろうが、実際の可能性の幅は、すなわち予想される最終産物の種類は、だいぶ限定されるように思われる。もしこれが正しい判断であるなら、進化は拘束されない無制限の実験の連続であるとは言うことができない。生物のデザインには限りがある。
--------引用終り ---------------
すなわち、同じような環境で進化し得る生物のデザインには限りがあり、歴史をもう一度巻き直してもそれほど違った世界にはならない、というのがモリスの反論です。対するグールドは、カンブリア紀に出現し繁栄した多様な生物の門の一部だけが生き残ったのは偶然であり、歴史をもう一度巻き直したら別の門が生き残り、代わりに現在反映している門世界は実際に生じた世界とは非常に異なったものになっただろう、と述べています。
さてここでグールドの主張には複数の要素があるように見えて、ややわかりにくい面があります。モリスもどの系統が生き残るかは偶然に左右された可能性は否定していないので、この点では両者は一致しますし、収斂進化の存在はグールドも否定しないはずです。するとグールドの主張には2つの可能性があります。
1.異なる系統が生き残った世界は(たとえ収斂進化していても)異なる世界である。
2.異なる系統では、基本的デザインが異なるために収斂進化の可能性に限界がある。
ゆえに、ある系統が偶然に絶滅した場合は絶対に実現しないデザインがある。
ゆえに、異なる系統が生き残った世界では、それぞれ異なるデザインが優勢になる。
1であるなら単なる見方の違いにすぎません。しかし2であるなら、実際に観測事実で検証可能な論争です[*1]。実のところはどうなのか? グールドが挙げている実例に沿って考えてみるのがよいでしょう。それがまとまっているのは『ワンダフル・ライフ』5章「実現しえた世界」の「考えうる7通りの世界」の部分です。
この7通りの世界の前に、注意したいことがあります。
ひとつは、全体として「歴史を巻き直しても人類のような知的生物(文明を作れる生物)は登場するか?」という命題が大きなテーマとなっていることです。私見ではこれは現在のところは難問です。特殊過ぎて生物進化全体に通じる理論の実例としては不適切に思えます。
もうひとつはグールドの論法のいくつかについてです。それは1番目のシナリオ「真核生物の進化」に出てくる文章です。
--------引用開始(下線は私の強調) -------
着実な進歩という古い信念に照らしてみると、初期の生命の進化ほど奇妙なものはありえないだろ
う。じつに長いあいだ、ほとんど何も起こらなかったのだ。
(中略)
二〇億年以上にわたってストロマトライトとそれをつくった原核生物の化石ぼかりが世界中から見つかる。最初の真核生物(核とさまざまな細胞小器官をそなえた複雑な細胞からなる生物)が登場したのは一四億年ほど前のことである。
(中略)
したがって生命の歴史の優に半分以上は、原核生物しか登場しない物語であり、地球上に生命が誕生してからこれまでの時間のうちの後半六分の一だけにしか多細胞動物は登場しないのである。
そんなにも遅れたこと、そんなにも長い時間を要したことが、偶発性の介在と可能性が実現しなかった膨大な領域の存在を強く物語っている。原核生物が真核生物になるべく向上しなければならなかったのだとしたら、そうなるにあたってはまちがいなくそれだけの時間がかかった。
--------引用終り ---------------
ここで「着実な進歩という古い信念」と呼ばれているのは、人類が進化の頂点であり頂点の登場は必然だという信念のことで、第1章で「人類が登場したのは必然であり他に優越している」「直線的な向上という思考の拘束着」「進化とはすなわち"進歩"と理解されている」と書かれている考え方です。これは『ワンダフル・ライフ』の著作当時であっても進化生物学者の間ではとっくに廃れていたはずの考え方であり、未だにこのような誤解をしているであろう専門外の人達に対する啓蒙として書かれているようにも見えます。が、実のところは、この古い考え方をしている主要な仮想論敵は、バージェス頁岩の発見者である古生物学者チャールズ・ウォルコット(Charles Doolittle Walcott)のようです[*2]。
さて上記の引用で注意したいもうひとつの点は、「登場に長い時間を要したから真核生物や多細胞動物の登場は偶然だった」という論法は正しくないということです。ここには「それだけの長い時間の間は、真核生物や多細胞動物が登場するような環境ではなかった」という可能性があるからです。実際に多細胞動物の登場は全球凍結という大きな環境変化の直後だったと判明しています。もちろんここで全球凍結のような生物圏の外の現象を偶然と考えれば、多細胞動物の登場は偶然となりますが、全球凍結が偶然か必然かは惑星の進化についてのさらなる研究によるしかないでしょう。
また人類の様々な文化、例えば農業の発展や土器制作なども氷河期のような環境変化に対する適応として理解しようとする試みもなされています。では氷河期は偶然か必然かという話になるでしょうが、その前に環境変化と進化との関係を具体的に明らかにすることは必要でしょう。しかし『ワンダフル・ライフ』では、このような議論はあまりなされてはいません。むしろ「地球環境の生物圏外の変化は同じだったとしても」という条件での歴史の巻き直しを想定しているように思えます。
続く
-------------
Ref-1)
a) 渡辺政隆(訳)『ワンダフルライフ:バージェス頁岩と生物進化の物語』早川書房(1993/04/15) ISBN10: 4-15-203556-0
b) 渡辺政隆(訳)『ワンダフルライフ:バージェス頁岩と生物進化の物語』早川書房(2000/03/01) ISBN10: 4-15-050236-6
Ref-2) 松井孝典(訳)『カンブリア紀の怪物たち』講談社(1997/03) ISBN-10: 4-06-149343-4
モリスが現代新書のために書き下ろしたもので英語版の本はないらしい。本書の「後記」を参照。
-------------
*1) 実は「異なるデザイン」の分類が人により異なることが大いにありうる。2つの生物が同じデザインなのか異なるデザインなのかで見方が食い違いうるということだ。
*2) ウィキペディアの記事によれば、グールドによる批判は「バージェス動物群の特異性を強調するためのレトリック的な面もある」。










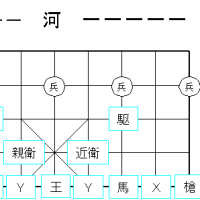
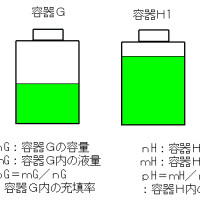
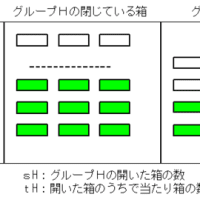
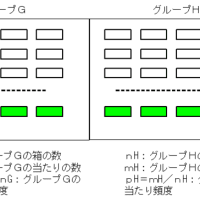
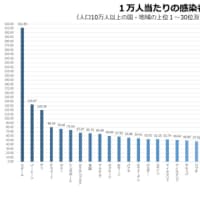
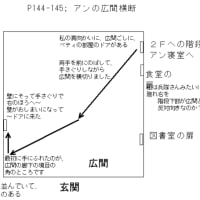
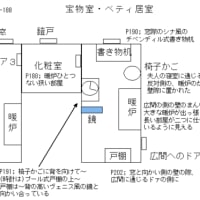

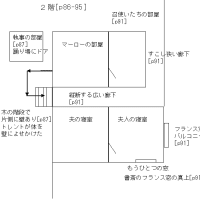
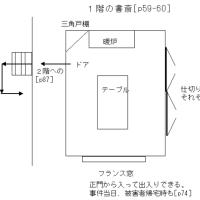






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます