04/06の記事の続きです。
グールドの示した7つの世界は以下の通りです。
1)真核生物が登場しなかった可能性
原核生物のみで複雑な多細胞生物も登場しない。
2)最初の多細胞生物群
エディアカラの平板状生命が生き残り、後生動物は排除された。
3)カンブリア紀の爆発後最初の動物群
多数の門の中で現代につながるグループが絶滅したかも知れない。
4)カンブリア紀におけるその後の現生動物群の起源
多数の門の中で現代につながるグループが絶滅したかも知れない。
5)陸生脊椎動物の起源
主流からはずれたごく一部の魚類グループである扇鰭類が絶滅していたら、陸上は昆虫と顕花植物の天下になる。
6)希望の光を哺乳類に託す
もし地球外の原因による天変地異が恐竜類を犠牲者に指名しなかったとしたら、地球上に意識が進化することはなかっただろう。
7)ホモ・サピエンスの起源
ホモ・エレクトスのすべての系統が絶滅したかも知れない。
さて、この7つの世界を示して論破しようとしている仮想的な論敵は「人間の登場、意識の出現は必然である」と考えています。そして上記の各段階で現在のホモ・サピエンスにつながる系統が消滅する可能性をいやいやながら受け入れながらも、「しかし、その系統が生き残りさえすれば、その後は必然的に人間の登場に至る」と反論するのです。しかし、グールドは「人間の登場には至らない歴史の分岐点」が7回も考えられることを示し、その考えを粉砕します。
この仮想的な論敵の思想というのは代表的にはバージェス頁岩の発見者である古生物学者チャールズ・ウォルコット(Charles Doolittle Walcott)の考え方としています。さらにこの仮想的な論敵の思想には「生物の多様性は進化が進むほどに増加する」というものがあるとしています。それに対してグールドは「最初に多様性が最大になり、その後に多くの系統が刈り取られる、すなわち絶滅する」というパターンが一般的なのだとして、論敵の思想を否定します。それがまさにバージェス頁岩を始めとするカンブリア紀の化石群からわかった事実だからというのが理由です。
これに対してコンウェイ・モリスは、この論敵のような考えは持っていません。前回も述べたように収斂進化ということを考えればグールドの考えは極端すぎるという見解だと思います。私も基本的にはモリスの考えに近くて、問題は、どのような形質なら歴史を巻き直しても再登場しやすいのだろうかということの解明だろうと考えます。
まずはクールドの7つの世界の中で、比較的わかりやすそうな6)を考えてみます。
恐竜類が繁栄したままで哺乳類がねずみ並のままだったら意識は登場しなかった、というのは暴論と言ってもよいでしょう。意識という観測しにくいものはともかく、ホモ・サピエンス並の技術文明の登場ということなら、確かに登場しなかった可能性は大きそうです。なんといっても長い生命の歴史の中で、ただ1回しか起きなかった事象なのは事実ですから。しかしある程度の知能、例えば集団で頭脳的な狩りをする、群れの中で社会生活を営む、といったことのできる知能、ということであれば、何度も収斂進化しています。哺乳類の中でも様々な系統で独立に登場しているのはむろんのこと、恐竜類の一部も集団で狩りをしたことを示す化石が見つかっています。そして、ある程度の知能を持った恐竜類の中の一部が偶然にも、というか、人類がたどったのと似たような環境変化に促されて、文明化に至るという可能性は決して否定できないと思います。
魚類であるマグロなども小魚を集団で海面へ追い込んで狩る、という行動はとれるようです。もっともこれだけなら例えば高度なコミニュケーションをする知能がなくてもできるようにも思えます。また軟体動物門であるタコやイカもかなり知能的である考える研究者もいます。
ここで指摘しておきたいのは、もしもタコやイカの系統が文明化できると判明したとして、2つの見方ができるということです。
1.どの系統が生き残ったとしても文明化できる生物の登場は必然である
2.ある時点の多数の系統のうち、どの系統が文明化してチャンピオンになれるかは偶然である。
同じ事実から、必然を強調することもできるし、偶然を強調することもできるのです。
長くなりましたので続きは次回にします。
グールドの示した7つの世界は以下の通りです。
1)真核生物が登場しなかった可能性
原核生物のみで複雑な多細胞生物も登場しない。
2)最初の多細胞生物群
エディアカラの平板状生命が生き残り、後生動物は排除された。
3)カンブリア紀の爆発後最初の動物群
多数の門の中で現代につながるグループが絶滅したかも知れない。
4)カンブリア紀におけるその後の現生動物群の起源
多数の門の中で現代につながるグループが絶滅したかも知れない。
5)陸生脊椎動物の起源
主流からはずれたごく一部の魚類グループである扇鰭類が絶滅していたら、陸上は昆虫と顕花植物の天下になる。
6)希望の光を哺乳類に託す
もし地球外の原因による天変地異が恐竜類を犠牲者に指名しなかったとしたら、地球上に意識が進化することはなかっただろう。
7)ホモ・サピエンスの起源
ホモ・エレクトスのすべての系統が絶滅したかも知れない。
さて、この7つの世界を示して論破しようとしている仮想的な論敵は「人間の登場、意識の出現は必然である」と考えています。そして上記の各段階で現在のホモ・サピエンスにつながる系統が消滅する可能性をいやいやながら受け入れながらも、「しかし、その系統が生き残りさえすれば、その後は必然的に人間の登場に至る」と反論するのです。しかし、グールドは「人間の登場には至らない歴史の分岐点」が7回も考えられることを示し、その考えを粉砕します。
この仮想的な論敵の思想というのは代表的にはバージェス頁岩の発見者である古生物学者チャールズ・ウォルコット(Charles Doolittle Walcott)の考え方としています。さらにこの仮想的な論敵の思想には「生物の多様性は進化が進むほどに増加する」というものがあるとしています。それに対してグールドは「最初に多様性が最大になり、その後に多くの系統が刈り取られる、すなわち絶滅する」というパターンが一般的なのだとして、論敵の思想を否定します。それがまさにバージェス頁岩を始めとするカンブリア紀の化石群からわかった事実だからというのが理由です。
これに対してコンウェイ・モリスは、この論敵のような考えは持っていません。前回も述べたように収斂進化ということを考えればグールドの考えは極端すぎるという見解だと思います。私も基本的にはモリスの考えに近くて、問題は、どのような形質なら歴史を巻き直しても再登場しやすいのだろうかということの解明だろうと考えます。
まずはクールドの7つの世界の中で、比較的わかりやすそうな6)を考えてみます。
恐竜類が繁栄したままで哺乳類がねずみ並のままだったら意識は登場しなかった、というのは暴論と言ってもよいでしょう。意識という観測しにくいものはともかく、ホモ・サピエンス並の技術文明の登場ということなら、確かに登場しなかった可能性は大きそうです。なんといっても長い生命の歴史の中で、ただ1回しか起きなかった事象なのは事実ですから。しかしある程度の知能、例えば集団で頭脳的な狩りをする、群れの中で社会生活を営む、といったことのできる知能、ということであれば、何度も収斂進化しています。哺乳類の中でも様々な系統で独立に登場しているのはむろんのこと、恐竜類の一部も集団で狩りをしたことを示す化石が見つかっています。そして、ある程度の知能を持った恐竜類の中の一部が偶然にも、というか、人類がたどったのと似たような環境変化に促されて、文明化に至るという可能性は決して否定できないと思います。
魚類であるマグロなども小魚を集団で海面へ追い込んで狩る、という行動はとれるようです。もっともこれだけなら例えば高度なコミニュケーションをする知能がなくてもできるようにも思えます。また軟体動物門であるタコやイカもかなり知能的である考える研究者もいます。
ここで指摘しておきたいのは、もしもタコやイカの系統が文明化できると判明したとして、2つの見方ができるということです。
1.どの系統が生き残ったとしても文明化できる生物の登場は必然である
2.ある時点の多数の系統のうち、どの系統が文明化してチャンピオンになれるかは偶然である。
同じ事実から、必然を強調することもできるし、偶然を強調することもできるのです。
長くなりましたので続きは次回にします。










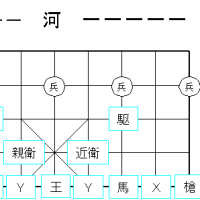
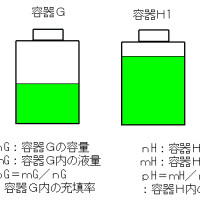
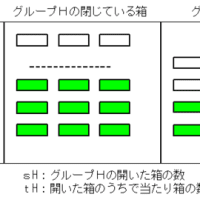
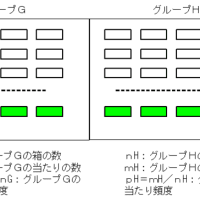
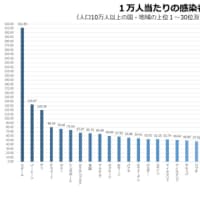
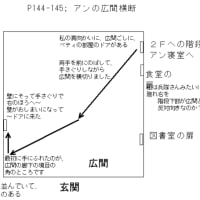
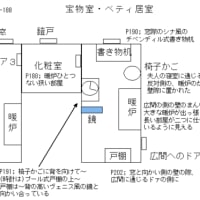
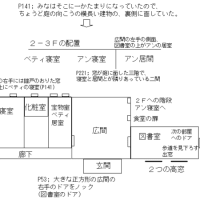
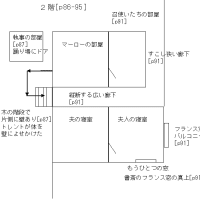
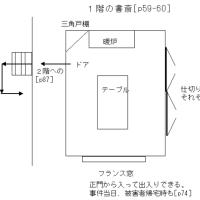






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます