前回の続きです。
著者は自然科学分野での歴史のiFの例としてスティーヴン・ジェイ・グールド(Stephen Jay Gould)『ワンダフル・ライフ』(1989)[Ref-4]を挙げています。『ワンダフル・ライフ』では「進化の歴史をもう一度巻き直したら全く違った世界になる」と述べていますが、サイモン・コンウェイ・モリス(Simon Conway Morris)『カンブリア紀の怪物たち』[Ref-5]は真っ向から反論を述べています。
生物進化には収斂進化という現象があります。これは、祖先が異なる生物種が同じような生態的地位(ニッチ)を得た場合、同じような形態になるという現象です。例えば水中を高速で移動するという生き方をする生物は流線形の体になるのが一例です。空を飛ぶニッチなら翼を持つのもそうですね。したがって、同じような環境で進化し得る生物のデザインには限りがあり、歴史をもう一度巻き直してもそれほど違った世界にはならない、というのがモリスの反論です。
しかしここで重要なことは、モリスはグールドの考えを普通に科学的な議論と捉えて生物学の土俵上での論争として反論をしているということです。言い換えると、進化の歴史を巻き戻すという歴史のiFの予測を反証可能な議論と捉えているのであり、科学の土俵にも載らないものとは考えてはいないのです。これは多くの?歴史学者が反実仮想の歴史を「歴史学の対象ではない」として否定している態度とはまったく異なります。一見反証不可能に見える歴史のiFを想定しているにもかかわらず、グールドやモリスの議論はなぜ科学的議論とみなせるのでしょうか?
それを考える前に、自然科学分野での歴史のiFの例をもうひとつ挙げます。ニール・F. カミンズ(Neil F. Comins)『もしも月がなかったら(What if the Moon Didn’t Exist)』[Ref-6]では、次のような様々な場合の地球のiFを想定して、その結果を予測しています。
1章 もしも月がなかったら?―惑星ソロン
2章 もしも月が地球にもっと近かったら?―惑星ルンホルム
3章 もしも地球の質量がもっと小さかったら?―惑星ペティエル
4章 もしも地軸が天王星のように傾いていたら?―惑星ウラニア
5章 もしも太陽の質量がもっと大きかったら?―惑星グランスター
6章 もしも地球の近くで恒星が爆発したら?―恒星アンタール
7章 もしも恒星が太陽系のそばを通過したら?―恒星ケルベロン
8章 もしもブラックホールが地球を通り抜けたら?―ブラックホールディアブロ
9章 もしも可視光線以外の電滋波が見えたら?―地球
10章 もしもオゾン層が破壊されたら?―「もしも…」の世界から、現実の地球へ
個別の予測については、その予測は間違いだという反論もあるかも知れませんが、これらの想定と予測を全くの絵空事という天文学者はいないでしょう。それに、予測が間違いだと言えること自体が、これらの予測に関して科学的議論ができるということを意味しています。しかし実際に地球のiFを再現して実証することは極めて困難に見えるのに、科学的議論などできるのでしょうか?
カミンズの議論が科学的議論だと考えてよい理由はいくつかあります。
1.宇宙には多くの惑星が存在することは確実であり、カミンズが想定したものに近い惑星が実在して観測できる可能性はゼロではない。
現実に21世紀に入って既に数千もの惑星が発見されており、地球型の惑星も複数見つかっていて、その多くは地球のような大きな月を持ちません。
2.予測される事象は自然法則の範疇内であり、使った自然法則が妥当ならば、妥当な科学的命題と考えられる。
予測自体の検証をするのではないのですが、使った自然法則は反証可能なものです。そしてそこからの予測の妥当性は、推論過程の妥当性にかかっており、それは正しさを確認できるものです。
2が問題なのですが、例えば月と地球の初期条件を設定したとして、ある時点の地球と月の距離や自転速度などはニュートン力学のみで正確に予測ができ、結果を疑う余地はほとんどありません。もしあるとすれば、予期せぬ擾乱があった場合だけです。
地上がどのような環境になるかという予測はこれよりは複雑ですが、基本的には質量や物質組成、公転軌道と速度、自転の軸と速度、などを初期条件として定めれば決まると考えられます。具体的にどんなパラメータを入れ、どんな予測ができるか、どこまで正確に予測できるかは様々な見解があるとしても、原理的には予測可能であることを否定する自然科学者はいないでしょう。
では、そのような環境ではどのような生物が進化し、どんな進化の歴史を展開するかという予測となると、はるかに難しくなります。それでも例えば、どんな環境ではどのような性質を持つ生物が生きやすいかという予測はある程度はわかってきていて予測することができます。ただ、ニュートン力学のように完璧な予測ができるほどにはわかっていないだけです。また、集団生物学や集団遺伝学では生物相互間の影響による個体数変動についての法則性がわかってきています。これは上記のグールドvsモリスの論争でモリスが強調している点です。
しかしながら、生物のひとつの個体に注目してその運命を予測する、ということになるとこれはほぼお手上げでしょう。そこには、たまたま木の枝を踏み抜いて細菌に感染したといったような多くの偶然が作用するはずであり、法則性など見出せないと多くの人は考えるでしょう。生物学が予測ですることは、「落ちた木の枝の多い環境では、踏み抜かないように注意深い性質の個体が多く生き残る」「足の底の皮が厚くて踏んでもケガをしない個体が多く生き残る」といったような統計的現象だけです。そして生物学が関心を持つのも統計的性質だけであり、生物個体の運命は生物学の興味の対象ではありません。出土した化石ひとつひとつについては、その個体がどのように生きて死んだのかを知ることができます。しかしそれは、同じ種の代表的標本として扱われるのであり、歴史上の人物のように、同一種のなかの特別な個体として扱われることはありません。その化石から知り得たことは、同一種の他の個体にも当てはまるという仮定の基に生物学の研究は行われます。
一個体から得た知識が他の個体にも当てはまるということは、未観測の他の個体に関しても予測ができるということであり、一種の再現性があるということです。これは、研究者が生物の歴史にも反証可能性があると考えるひとつの理由にはなるでしょう。
これが歴史学となるとがぜん状況は一変し、特定の個人に注目が集まります。そうなると、たまたま伝染病に感染したとか、足を滑らせたとかいった偶然が歴史を変える要因になってきます。同じように過去の人類を調べる学問でありながら、歴史学と古人類学とではこの点のスタンスが大きく異なります。例えば氷河期に死んだアイスマンと呼ばれる死体があります。この人はなかなか政治的に波乱の人生を歩んだ人のようですが、それがどのような状況だったのかという歴史物語のような点には学問的興味は集まっていません、たぶん。今のところはアイスマンは当時の人類の一代表として扱われているだけです。このように調べられる対象はあくまでも集団の代表サンプルと考えるか固有のものと考えるかは、自然科学と歴史学とのおおきな違いのひとつだと言えるでしょう。
『「もしもあの時」の社会学』にも書いてありますが、歴史学でも集団の統計的性質に着目した研究はありますが、それはむしろ近代の数量的思考法が取り入れられてからの、比較的新しい研究方法なのです。
続く
-------------
Ref-1) 赤上裕幸『「もしもあの時」の社会学:歴史にifがあったなら』筑摩書房 (2018/11/12)
Ref-2) 三浦 俊彦『可能世界の哲学―「存在」と「自己」を考える(NHKブックス)』日本放送出版協会 (1997/02),ISBN-13: 978-4140017906
Ref-3) E.H.カー;清水幾太郎(訳)『歴史とは何か(岩波新書)』岩波書店(1962/03/20), ASIN: B000JAL794
Ref-4)
a) 渡辺政隆(訳)『ワンダフルライフ:バージェス頁岩と生物進化の物語』早川書房(1993/04/15) ISBN10: 4-15-203556-0
b) 渡辺政隆(訳)『ワンダフルライフ:バージェス頁岩と生物進化の物語』早川書房(2000/03/01) ISBN10: 4-15-050236-6
Ref-5) 松井孝典(訳)『カンブリア紀の怪物たち』講談社(1997/03) ISBN-10: 4-06-149343-4
Ref-6) ニール・F. カミンズ『もしも月がなかったら』東京書籍 (1999/07)
著者は自然科学分野での歴史のiFの例としてスティーヴン・ジェイ・グールド(Stephen Jay Gould)『ワンダフル・ライフ』(1989)[Ref-4]を挙げています。『ワンダフル・ライフ』では「進化の歴史をもう一度巻き直したら全く違った世界になる」と述べていますが、サイモン・コンウェイ・モリス(Simon Conway Morris)『カンブリア紀の怪物たち』[Ref-5]は真っ向から反論を述べています。
生物進化には収斂進化という現象があります。これは、祖先が異なる生物種が同じような生態的地位(ニッチ)を得た場合、同じような形態になるという現象です。例えば水中を高速で移動するという生き方をする生物は流線形の体になるのが一例です。空を飛ぶニッチなら翼を持つのもそうですね。したがって、同じような環境で進化し得る生物のデザインには限りがあり、歴史をもう一度巻き直してもそれほど違った世界にはならない、というのがモリスの反論です。
しかしここで重要なことは、モリスはグールドの考えを普通に科学的な議論と捉えて生物学の土俵上での論争として反論をしているということです。言い換えると、進化の歴史を巻き戻すという歴史のiFの予測を反証可能な議論と捉えているのであり、科学の土俵にも載らないものとは考えてはいないのです。これは多くの?歴史学者が反実仮想の歴史を「歴史学の対象ではない」として否定している態度とはまったく異なります。一見反証不可能に見える歴史のiFを想定しているにもかかわらず、グールドやモリスの議論はなぜ科学的議論とみなせるのでしょうか?
それを考える前に、自然科学分野での歴史のiFの例をもうひとつ挙げます。ニール・F. カミンズ(Neil F. Comins)『もしも月がなかったら(What if the Moon Didn’t Exist)』[Ref-6]では、次のような様々な場合の地球のiFを想定して、その結果を予測しています。
1章 もしも月がなかったら?―惑星ソロン
2章 もしも月が地球にもっと近かったら?―惑星ルンホルム
3章 もしも地球の質量がもっと小さかったら?―惑星ペティエル
4章 もしも地軸が天王星のように傾いていたら?―惑星ウラニア
5章 もしも太陽の質量がもっと大きかったら?―惑星グランスター
6章 もしも地球の近くで恒星が爆発したら?―恒星アンタール
7章 もしも恒星が太陽系のそばを通過したら?―恒星ケルベロン
8章 もしもブラックホールが地球を通り抜けたら?―ブラックホールディアブロ
9章 もしも可視光線以外の電滋波が見えたら?―地球
10章 もしもオゾン層が破壊されたら?―「もしも…」の世界から、現実の地球へ
個別の予測については、その予測は間違いだという反論もあるかも知れませんが、これらの想定と予測を全くの絵空事という天文学者はいないでしょう。それに、予測が間違いだと言えること自体が、これらの予測に関して科学的議論ができるということを意味しています。しかし実際に地球のiFを再現して実証することは極めて困難に見えるのに、科学的議論などできるのでしょうか?
カミンズの議論が科学的議論だと考えてよい理由はいくつかあります。
1.宇宙には多くの惑星が存在することは確実であり、カミンズが想定したものに近い惑星が実在して観測できる可能性はゼロではない。
現実に21世紀に入って既に数千もの惑星が発見されており、地球型の惑星も複数見つかっていて、その多くは地球のような大きな月を持ちません。
2.予測される事象は自然法則の範疇内であり、使った自然法則が妥当ならば、妥当な科学的命題と考えられる。
予測自体の検証をするのではないのですが、使った自然法則は反証可能なものです。そしてそこからの予測の妥当性は、推論過程の妥当性にかかっており、それは正しさを確認できるものです。
2が問題なのですが、例えば月と地球の初期条件を設定したとして、ある時点の地球と月の距離や自転速度などはニュートン力学のみで正確に予測ができ、結果を疑う余地はほとんどありません。もしあるとすれば、予期せぬ擾乱があった場合だけです。
地上がどのような環境になるかという予測はこれよりは複雑ですが、基本的には質量や物質組成、公転軌道と速度、自転の軸と速度、などを初期条件として定めれば決まると考えられます。具体的にどんなパラメータを入れ、どんな予測ができるか、どこまで正確に予測できるかは様々な見解があるとしても、原理的には予測可能であることを否定する自然科学者はいないでしょう。
では、そのような環境ではどのような生物が進化し、どんな進化の歴史を展開するかという予測となると、はるかに難しくなります。それでも例えば、どんな環境ではどのような性質を持つ生物が生きやすいかという予測はある程度はわかってきていて予測することができます。ただ、ニュートン力学のように完璧な予測ができるほどにはわかっていないだけです。また、集団生物学や集団遺伝学では生物相互間の影響による個体数変動についての法則性がわかってきています。これは上記のグールドvsモリスの論争でモリスが強調している点です。
しかしながら、生物のひとつの個体に注目してその運命を予測する、ということになるとこれはほぼお手上げでしょう。そこには、たまたま木の枝を踏み抜いて細菌に感染したといったような多くの偶然が作用するはずであり、法則性など見出せないと多くの人は考えるでしょう。生物学が予測ですることは、「落ちた木の枝の多い環境では、踏み抜かないように注意深い性質の個体が多く生き残る」「足の底の皮が厚くて踏んでもケガをしない個体が多く生き残る」といったような統計的現象だけです。そして生物学が関心を持つのも統計的性質だけであり、生物個体の運命は生物学の興味の対象ではありません。出土した化石ひとつひとつについては、その個体がどのように生きて死んだのかを知ることができます。しかしそれは、同じ種の代表的標本として扱われるのであり、歴史上の人物のように、同一種のなかの特別な個体として扱われることはありません。その化石から知り得たことは、同一種の他の個体にも当てはまるという仮定の基に生物学の研究は行われます。
一個体から得た知識が他の個体にも当てはまるということは、未観測の他の個体に関しても予測ができるということであり、一種の再現性があるということです。これは、研究者が生物の歴史にも反証可能性があると考えるひとつの理由にはなるでしょう。
これが歴史学となるとがぜん状況は一変し、特定の個人に注目が集まります。そうなると、たまたま伝染病に感染したとか、足を滑らせたとかいった偶然が歴史を変える要因になってきます。同じように過去の人類を調べる学問でありながら、歴史学と古人類学とではこの点のスタンスが大きく異なります。例えば氷河期に死んだアイスマンと呼ばれる死体があります。この人はなかなか政治的に波乱の人生を歩んだ人のようですが、それがどのような状況だったのかという歴史物語のような点には学問的興味は集まっていません、たぶん。今のところはアイスマンは当時の人類の一代表として扱われているだけです。このように調べられる対象はあくまでも集団の代表サンプルと考えるか固有のものと考えるかは、自然科学と歴史学とのおおきな違いのひとつだと言えるでしょう。
『「もしもあの時」の社会学』にも書いてありますが、歴史学でも集団の統計的性質に着目した研究はありますが、それはむしろ近代の数量的思考法が取り入れられてからの、比較的新しい研究方法なのです。
続く
-------------
Ref-1) 赤上裕幸『「もしもあの時」の社会学:歴史にifがあったなら』筑摩書房 (2018/11/12)
Ref-2) 三浦 俊彦『可能世界の哲学―「存在」と「自己」を考える(NHKブックス)』日本放送出版協会 (1997/02),ISBN-13: 978-4140017906
Ref-3) E.H.カー;清水幾太郎(訳)『歴史とは何か(岩波新書)』岩波書店(1962/03/20), ASIN: B000JAL794
Ref-4)
a) 渡辺政隆(訳)『ワンダフルライフ:バージェス頁岩と生物進化の物語』早川書房(1993/04/15) ISBN10: 4-15-203556-0
b) 渡辺政隆(訳)『ワンダフルライフ:バージェス頁岩と生物進化の物語』早川書房(2000/03/01) ISBN10: 4-15-050236-6
Ref-5) 松井孝典(訳)『カンブリア紀の怪物たち』講談社(1997/03) ISBN-10: 4-06-149343-4
Ref-6) ニール・F. カミンズ『もしも月がなかったら』東京書籍 (1999/07)










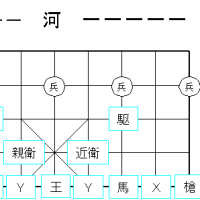
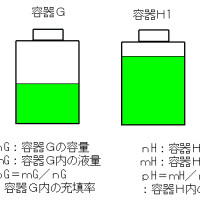
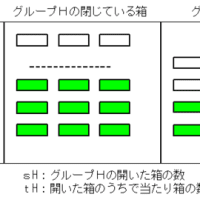
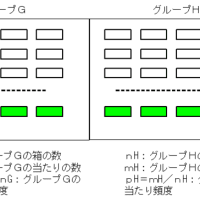
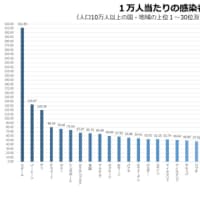
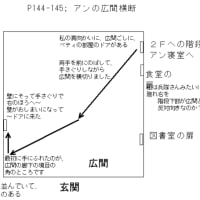
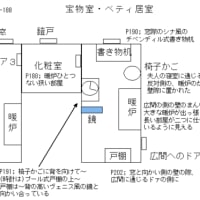

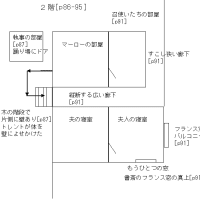
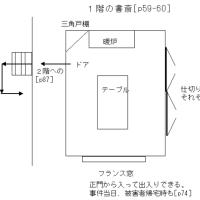






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます