映画やアニメならいざ知らず、書物形態の推理小説では探偵が犯人に向かっていわゆる決め台詞を吐くという場面はあまりないようです。確かにポワロにしてもクイーンにしても最後に真犯人に向かって真相を指摘するという場面は多いのですが、「犯人はお前だ」みたいな定型的セリフは使っていないように思います。意味としては「犯人はあなたしかいないのです。」などに該当するセリフはでてきますが。
推理小説の始祖エドガー・アラン・ポー(Edgar Allan Poe)の『お前が犯人だ("Thou Art the Man")』[*1]ではタイトル通りの決めぜりふが真犯人に向けられて、驚いた犯人は自白してしまいます。このセリフもポーが始祖だったのですね。
なお 江戸川コナンの「真実はいつもひとつ!」や金田一一の「ジッチャンの名にかけて! 」も決め台詞とする人もいますが、これらは犯人に向かって吐くわけではないし、それどころか厳密には作品中ではなく前置き部分や宣伝部分でのセリフであって、私の感覚では仕事に取り掛かる時の心構えというか自戒の言葉のように感じられます[*2]。これを決め台詞に含めるならホームズには「すべての可能性を排除して最後に残ったものは云々」他多数の名言がありますし、他の名探偵達にも色々な名言はあります。
古典本格推理の中でも、私がこれは決め台詞と確信できるのが次のセリフです。
「これからあなたの話すことは全て証拠として使われる可能性があります。あなたには、あなたが罪に問われる恐れのあることについて黙っている権利があります。また、あなたは弁護士を呼ぶことができます。」
実にかっこいいセリフです。「さあ公平に武器を渡してやるから十分に準備してかかってこい。こちらはいつでも受けてたってやる。」・・いやまあ本来の趣旨はそうじゃありませんが(^_^)。
この決めぜりふは私立探偵は使わないものなので、てっきりフリーマン・ウィルス・クロフツ(Freeman Wills Crofts)の作品の探偵役フレンチ警部(後に警視)が多用していると思い込んでいたのですが、改めて読み直してみるとそうでもありません。上記3つの要件がはっきり述べられていたのは『フレンチ警視最初の事件』の一場面です[*3]。しかも真犯人に対するものとは言えません。
==========引用開始==================
そのうちダルシーの耳にフレンチが何か言っているのが聞こえてきた。「……質問に答える必要はありませんし、弁護士の同席を希望されるのであれば、それからでもかまいません。断っておきますが、あなたの発言はすべて記録され、証拠として採用される場合があります」
==========引用終り==================
クロフツと言えば、犯人の立場から犯罪を描き、逮捕されるようなへまをどこで犯したのかを推理する、いわゆる「倒叙形式」の短編を多数書いていますが、その作品のいくつかでは「これから君の話すことはすべて証拠として採用され・・」という声を真犯人が聞くという描写がありますが、多用というほどには描かれてはいませんでした[*4]。もちろんスコットランド・ヤードの模範的な捜査官たるフレンチは毎回使っているはずですが。
実はこの決め台詞はシャーロック・ホームズ物にも登場します。ホームズ自身は警察官ではないので使いませんが、ホームズが助ける警部たちが使っています。『シャーロック・ホームズの復活(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM75-3)』(1981/10/31)から引用しましょう。
(p48;ノーウッドの建築業者)では犯人と疑われそうになった人物がホームズに「こうなれば何もかも話した方がいいでしょう。」と前置きしたときに、同席していたレストレイド警部が、「また、本人の供述は、すべて証拠として採用されることを警告する義務があります。」と述べています。
(p113;踊る人形)ではノーフォーク警察のマーチン警部が使っています。
-----引用開始-----------------
「私の義務として一言注意しておくが、その申し立ては、きみにとって不利な材料として用いられるかも知れないぞ。」と、マーチン警部は大きな声で英国刑法の崇高な公正ぶりを示した。
-----引用終わり----------------
p113の文章からはコナン・ドイルの法治国家たる祖国への誇りが感じられていい感じですね。ここでノーフォークという、いわば田舎警察の警部でさえも英国刑法の崇高な公正精神を義務として心得ているということになります。
黙秘権、発言が証拠とされる可能性の通告、弁護士を呼ぶ権利、の3点セットはアメリカではミランダ警告("Miranda warning")と呼ばれているようです。リンク先のwikipediaの記事でわかる通り、この呼び名は1966年以降のものですが、むろんルール自体はそれ以前から存在していたのであり、1966年の出来事を契機にアメリカにおけるルール適用が厳格になったというだけのことです。そして、英米での法的ルールとしては上記の通りホームズ登場の時代(1890年~)にはすでに定着していたと考えられます。むろん実際にはどこまでルールが守られていたのかは私は知りません。
ひるがえって日本ではと言えば残念ながらルール化すらされていないのか、ルールがあっても有名無実なのか、日本を舞台とするミステリーではこのかっこいい決めぜりふが登場できません。
さて英国でのこのようなルールの起源はwikipedia英語版によれば17世紀(1600年代)にさかのぼるようですが、「そんな古くから被告の人権が保障されていたのか」と誤解してはいけません。「The defendant was considered "incompetent" to give evidence」つまり「被告人には証拠を示す能力がない」と見なされるから、「そんな者の自白は証拠として採用できない」という論理なのですが、裏を返せば、「被告は自分の無罪を示す能力もない」つまり「無罪だと抗弁することも許されない」となるのです。
このあたりの歴史はグランヴィル・ウィリアムズ(Glanville Williams)『有罪の証明-英国刑事裁判の研究』第3版(1963)の庭山英雄(中京大学教授)による翻訳が日本語資料では一番詳しいようです[*5]。特に第1章の「2節 19世紀以前の陪審裁判」と「3節 19世紀の変化」に、その歴史が書かれています。3節の終わりの部分には「18世紀の間、なにが起きたかについての被告人の陳述は一切聴いてもらえなかった」と書かれています。1898年に至り、ようやく刑事証拠法("Criminal Evidence Act")[*6]が被告人に宣誓供述を認めました。
それまでの被告の権利確立までの長い歴史は以下のとおり。
・12世紀: 陪審裁判の始まり。それ以前はいわゆる神判が行われていたらしい。神ならぬ人間たる陪審(語義としては裁判官と言うべきか)が被告から真実を聞き出すことになり、やむなく拷問が始まったとの意味の記載がある。
・1352年: 起訴陪審と公判陪審が同一人のとき、被告は異議申し立てができるようになった。
・1640年: 重罪で問責された者も実際に証人召喚を許されるようになった。が、許可は稀だった。
・1760年: 被告側弁護人に証人の反対尋問が許された。が、陪審に直接語りかけることは許されなかった
・1836年: 完全な弁護人依頼権が与えられた。当時の裁判官15人中12人が強硬に反対した。
・1898年: 被告人の宣誓供述が認められた。
ときに「重罪で」と断りがあるところを見ると、軽犯罪ではもっと早期に改革がなされていたようです。現在の感覚では重犯罪ほど被告側の反論も十分に聴かないと間違いが起きやすいと思えるので、逆の感覚に感じられます。それにしても完全な弁護人依頼権が与えられたのが名探偵デュパンと同時代だとは、意外に新しいのですね。しかも被告人の宣誓供述が認められたのは、シャーロック・ホームズのデビュー以後のことです。それでも発言が証拠とされる可能性の通告が捜査官の義務だということは、少なくともコナン・ドイルは常識とみなしていたと考えられるのです。
著者のグランヴィル・ウィリアムズは1章5節の最後に「一般の印象とは逆に、現在のイギリス刑事司法の美点は、今日の自由なイギリス人にとってほとんど理解しがたい--何世紀にもわたる--法的抑圧と映るできごとに堪えぬいて、比較的最近の輸入にかかるものである。」と述べています。
とはいうものの、日本人から見ると上記のような法的欠陥を欠陥と認識できたという点だけでも英国人は素晴らしいと思えます。そして実際に欠陥を正してきたのですから。そのおかげで他の国も英国を手本として欠陥を正すことができたのですから。他の国ではフランスが真っ先に手本としたようですが。
-----------------------------
*1) 探偵小説を探せ(2017/05/06)で書いたように、私としてはc)をまず読むことを推奨したい。
a) 丸谷才一(訳)『ポオ小説全集 4 (創元推理文庫 522-4)』東京創元社(1974/09/27)
b) 谷崎精二(訳)『ポオ小説全集〈1〉推理小説 』春秋社(1998/09)初版(1962)
c) 桜庭一樹(翻案)『E・A・ポー ポケットマスターピース09 (集英社文庫 ヘリテージシリーズ)』(2016/06/23)
*2) 『7人の女弁護士』釈由美子版には、「真実はいつもひとつ!」に似ている「残された答えはひとつです」というセリフがあり、これは最後に法廷で真犯人に突きつける言葉であり、確かに決め台詞と言える。
*3) 『フレンチ警部最大の事件(創元推理文庫)(Inspector French's Greatest Case)』東京創元社(1960/12),ASIN=B000JASFE4,p330
*4)
a) F.W.クロフツ; 井上勇(訳)『殺人者はへまをする』東京創元社(1960/12)
a1) ISBN10 = 4-488-10617-X a2) ASIN = B000JANYY0
b) F.W.クロフツ; 向後英一(訳)『クロフツ短編集1』
b1) ISBN10 = 4-488-10619-6 b2) ASIN = B000JAI3WS
c) F.W.クロフツ; 井上勇(訳)『クロフツ短編集2』
c1) ISBN10 = 4-488-10620-X c2) ASIN = B000JAI3WI
*5) 原著は"The Proof of Guilt; A Study of the English Criminal Trial"で、第2版が1958年で、初版(1955)のレビューがある。翻訳へのリンクは現在(2020/05)はリンク切れ。
*6) イングランドとウェールズでの最新のものは"Police_and_Criminal_Evidence_Act_1984"と呼ばれるものらしい。米国では"Findlaw"の"Law of Criminal Evidence"の一般的解説記事からリンクされている"Federal Rules of Evidence (FRE)"(証拠に関する連邦政府規則)がそれに当たるようだ。
推理小説の始祖エドガー・アラン・ポー(Edgar Allan Poe)の『お前が犯人だ("Thou Art the Man")』[*1]ではタイトル通りの決めぜりふが真犯人に向けられて、驚いた犯人は自白してしまいます。このセリフもポーが始祖だったのですね。
なお 江戸川コナンの「真実はいつもひとつ!」や金田一一の「ジッチャンの名にかけて! 」も決め台詞とする人もいますが、これらは犯人に向かって吐くわけではないし、それどころか厳密には作品中ではなく前置き部分や宣伝部分でのセリフであって、私の感覚では仕事に取り掛かる時の心構えというか自戒の言葉のように感じられます[*2]。これを決め台詞に含めるならホームズには「すべての可能性を排除して最後に残ったものは云々」他多数の名言がありますし、他の名探偵達にも色々な名言はあります。
古典本格推理の中でも、私がこれは決め台詞と確信できるのが次のセリフです。
「これからあなたの話すことは全て証拠として使われる可能性があります。あなたには、あなたが罪に問われる恐れのあることについて黙っている権利があります。また、あなたは弁護士を呼ぶことができます。」
実にかっこいいセリフです。「さあ公平に武器を渡してやるから十分に準備してかかってこい。こちらはいつでも受けてたってやる。」・・いやまあ本来の趣旨はそうじゃありませんが(^_^)。
この決めぜりふは私立探偵は使わないものなので、てっきりフリーマン・ウィルス・クロフツ(Freeman Wills Crofts)の作品の探偵役フレンチ警部(後に警視)が多用していると思い込んでいたのですが、改めて読み直してみるとそうでもありません。上記3つの要件がはっきり述べられていたのは『フレンチ警視最初の事件』の一場面です[*3]。しかも真犯人に対するものとは言えません。
==========引用開始==================
そのうちダルシーの耳にフレンチが何か言っているのが聞こえてきた。「……質問に答える必要はありませんし、弁護士の同席を希望されるのであれば、それからでもかまいません。断っておきますが、あなたの発言はすべて記録され、証拠として採用される場合があります」
==========引用終り==================
クロフツと言えば、犯人の立場から犯罪を描き、逮捕されるようなへまをどこで犯したのかを推理する、いわゆる「倒叙形式」の短編を多数書いていますが、その作品のいくつかでは「これから君の話すことはすべて証拠として採用され・・」という声を真犯人が聞くという描写がありますが、多用というほどには描かれてはいませんでした[*4]。もちろんスコットランド・ヤードの模範的な捜査官たるフレンチは毎回使っているはずですが。
実はこの決め台詞はシャーロック・ホームズ物にも登場します。ホームズ自身は警察官ではないので使いませんが、ホームズが助ける警部たちが使っています。『シャーロック・ホームズの復活(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM75-3)』(1981/10/31)から引用しましょう。
(p48;ノーウッドの建築業者)では犯人と疑われそうになった人物がホームズに「こうなれば何もかも話した方がいいでしょう。」と前置きしたときに、同席していたレストレイド警部が、「また、本人の供述は、すべて証拠として採用されることを警告する義務があります。」と述べています。
(p113;踊る人形)ではノーフォーク警察のマーチン警部が使っています。
-----引用開始-----------------
「私の義務として一言注意しておくが、その申し立ては、きみにとって不利な材料として用いられるかも知れないぞ。」と、マーチン警部は大きな声で英国刑法の崇高な公正ぶりを示した。
-----引用終わり----------------
p113の文章からはコナン・ドイルの法治国家たる祖国への誇りが感じられていい感じですね。ここでノーフォークという、いわば田舎警察の警部でさえも英国刑法の崇高な公正精神を義務として心得ているということになります。
黙秘権、発言が証拠とされる可能性の通告、弁護士を呼ぶ権利、の3点セットはアメリカではミランダ警告("Miranda warning")と呼ばれているようです。リンク先のwikipediaの記事でわかる通り、この呼び名は1966年以降のものですが、むろんルール自体はそれ以前から存在していたのであり、1966年の出来事を契機にアメリカにおけるルール適用が厳格になったというだけのことです。そして、英米での法的ルールとしては上記の通りホームズ登場の時代(1890年~)にはすでに定着していたと考えられます。むろん実際にはどこまでルールが守られていたのかは私は知りません。
ひるがえって日本ではと言えば残念ながらルール化すらされていないのか、ルールがあっても有名無実なのか、日本を舞台とするミステリーではこのかっこいい決めぜりふが登場できません。
さて英国でのこのようなルールの起源はwikipedia英語版によれば17世紀(1600年代)にさかのぼるようですが、「そんな古くから被告の人権が保障されていたのか」と誤解してはいけません。「The defendant was considered "incompetent" to give evidence」つまり「被告人には証拠を示す能力がない」と見なされるから、「そんな者の自白は証拠として採用できない」という論理なのですが、裏を返せば、「被告は自分の無罪を示す能力もない」つまり「無罪だと抗弁することも許されない」となるのです。
このあたりの歴史はグランヴィル・ウィリアムズ(Glanville Williams)『有罪の証明-英国刑事裁判の研究』第3版(1963)の庭山英雄(中京大学教授)による翻訳が日本語資料では一番詳しいようです[*5]。特に第1章の「2節 19世紀以前の陪審裁判」と「3節 19世紀の変化」に、その歴史が書かれています。3節の終わりの部分には「18世紀の間、なにが起きたかについての被告人の陳述は一切聴いてもらえなかった」と書かれています。1898年に至り、ようやく刑事証拠法("Criminal Evidence Act")[*6]が被告人に宣誓供述を認めました。
それまでの被告の権利確立までの長い歴史は以下のとおり。
・12世紀: 陪審裁判の始まり。それ以前はいわゆる神判が行われていたらしい。神ならぬ人間たる陪審(語義としては裁判官と言うべきか)が被告から真実を聞き出すことになり、やむなく拷問が始まったとの意味の記載がある。
・1352年: 起訴陪審と公判陪審が同一人のとき、被告は異議申し立てができるようになった。
・1640年: 重罪で問責された者も実際に証人召喚を許されるようになった。が、許可は稀だった。
・1760年: 被告側弁護人に証人の反対尋問が許された。が、陪審に直接語りかけることは許されなかった
・1836年: 完全な弁護人依頼権が与えられた。当時の裁判官15人中12人が強硬に反対した。
・1898年: 被告人の宣誓供述が認められた。
ときに「重罪で」と断りがあるところを見ると、軽犯罪ではもっと早期に改革がなされていたようです。現在の感覚では重犯罪ほど被告側の反論も十分に聴かないと間違いが起きやすいと思えるので、逆の感覚に感じられます。それにしても完全な弁護人依頼権が与えられたのが名探偵デュパンと同時代だとは、意外に新しいのですね。しかも被告人の宣誓供述が認められたのは、シャーロック・ホームズのデビュー以後のことです。それでも発言が証拠とされる可能性の通告が捜査官の義務だということは、少なくともコナン・ドイルは常識とみなしていたと考えられるのです。
著者のグランヴィル・ウィリアムズは1章5節の最後に「一般の印象とは逆に、現在のイギリス刑事司法の美点は、今日の自由なイギリス人にとってほとんど理解しがたい--何世紀にもわたる--法的抑圧と映るできごとに堪えぬいて、比較的最近の輸入にかかるものである。」と述べています。
とはいうものの、日本人から見ると上記のような法的欠陥を欠陥と認識できたという点だけでも英国人は素晴らしいと思えます。そして実際に欠陥を正してきたのですから。そのおかげで他の国も英国を手本として欠陥を正すことができたのですから。他の国ではフランスが真っ先に手本としたようですが。
-----------------------------
*1) 探偵小説を探せ(2017/05/06)で書いたように、私としてはc)をまず読むことを推奨したい。
a) 丸谷才一(訳)『ポオ小説全集 4 (創元推理文庫 522-4)』東京創元社(1974/09/27)
b) 谷崎精二(訳)『ポオ小説全集〈1〉推理小説 』春秋社(1998/09)初版(1962)
c) 桜庭一樹(翻案)『E・A・ポー ポケットマスターピース09 (集英社文庫 ヘリテージシリーズ)』(2016/06/23)
*2) 『7人の女弁護士』釈由美子版には、「真実はいつもひとつ!」に似ている「残された答えはひとつです」というセリフがあり、これは最後に法廷で真犯人に突きつける言葉であり、確かに決め台詞と言える。
*3) 『フレンチ警部最大の事件(創元推理文庫)(Inspector French's Greatest Case)』東京創元社(1960/12),ASIN=B000JASFE4,p330
*4)
a) F.W.クロフツ; 井上勇(訳)『殺人者はへまをする』東京創元社(1960/12)
a1) ISBN10 = 4-488-10617-X a2) ASIN = B000JANYY0
b) F.W.クロフツ; 向後英一(訳)『クロフツ短編集1』
b1) ISBN10 = 4-488-10619-6 b2) ASIN = B000JAI3WS
c) F.W.クロフツ; 井上勇(訳)『クロフツ短編集2』
c1) ISBN10 = 4-488-10620-X c2) ASIN = B000JAI3WI
*5) 原著は"The Proof of Guilt; A Study of the English Criminal Trial"で、第2版が1958年で、初版(1955)のレビューがある。翻訳へのリンクは現在(2020/05)はリンク切れ。
*6) イングランドとウェールズでの最新のものは"Police_and_Criminal_Evidence_Act_1984"と呼ばれるものらしい。米国では"Findlaw"の"Law of Criminal Evidence"の一般的解説記事からリンクされている"Federal Rules of Evidence (FRE)"(証拠に関する連邦政府規則)がそれに当たるようだ。










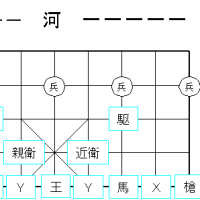
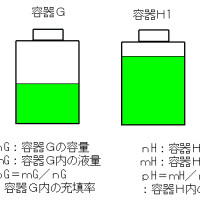
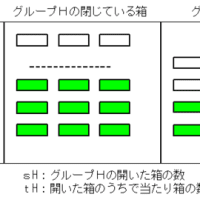
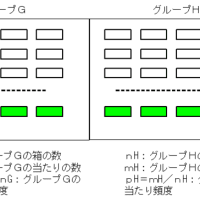
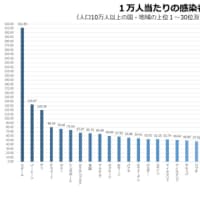
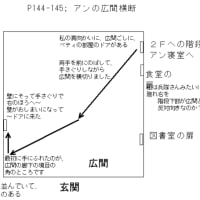
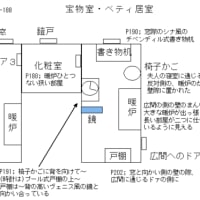

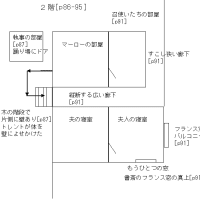
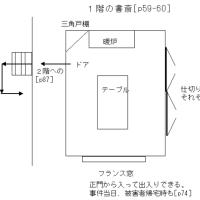






どうやら問題はフィクション作家の方々の怠慢(は言い過ぎか?)にありそうですね。それと捜査当局(警察および検察)の公報不足? もっとも公報しすぎて任意同行を拒否され過ぎたら困るという動機は疑われても仕方ないとは思いますが。
いかりや長介主演の「取調室」というTVドラマの再放送が最近ありましたが、弁護士は出てこないは、48時間以上拘留しているように思われるは(しっかり見ていないので私の誤解かも知れませんが)、「もう帰してくださいよ」「それを決めるのはお前じゃない」なんてやりとりがあるはで、あまり気分の良くない作品でした。被疑者の自由では帰れないという以上は任意ではないはずで、長介さんは検察官でもありません。
[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E8%AA%BF%E5%AE%A4_(%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E)]
まあ48時間というのも捜査側には厳しいとは思いますし、それゆえ逮捕のタイミングを熟慮するという場面もフィクョンには出てきますね。もしかして被疑者側とすれば、「弁護士が来るまで何も話さない」と宣言すればいくばくかの時間を稼げるでしょうか?
まあ何も知らない無垢な時代なら「取調室」も純粋に心理戦のおもしろさを楽しめたのでしょうが、今では主人公側が不当に有利過ぎるように見えて困ります。
日本国憲法にも被疑者の権利が明記されているのは忘れていました。38条が「自己に不利益な供述を強要されない」権利、37条が「刑事被告人」の「弁護資格を有する弁護人を依頼することができる」権利ですね。厳密には「被疑者」の弁護人依頼権は規定されてはいませんね(^_^) こちらは刑法での規定でしょうか?
もっとも私なぞは、「有利でも不利でも、黙ってしまったら無理矢理話させることは不可能だろう。拷問したとしても真実が出るかどうかは不確実だろう。」などと考えるので、自己負罪拒否特権と供述拒否権との違いがピンときません。黙秘という事実の解釈に制限があるかどうかは(真実を明らかにすることとは別に)裁判結果には重要でしょうが。そもそも様々な理由で嘘や勘違いの入りうる「証言」などというものを得るのに必死になる感覚がよくわかりません。まあ得られる物証に限界があるのだから仕方ないと言えばそれまでですが。
>それを捜査官が聞いたからというだけでは、裁判上有力な供述証拠にはなり得ません
なるほど納得です。まったくの想像ですが、英米では捜査官のメモと証言が裁判では有力な証拠とされるのかも知れません。特にフレンチ警部以前の時代ならば。被告が言ってないと証言すれば、どちらを信じるかは陪審員の心証、でしょうか? 現在なら「録音しますがいいですか?」とすれば「物証」が取れますね。
なるべく噛み砕いている都合上、厳密には若干不正確な記述もあります。
>第一項の内容を通告するという場面はみたことがない
ドラマ等では単に省略しているものと思われます汗。
>署に引っ張り込んでから黙秘権のある旨を通告すればルールには反しないことになりますね
「署に引っ張る」はあくまで「任意できてもらう」というニュアンスです笑。取調べに入ってから、供述拒否権を告げることになります。なお、自己負罪拒否特権(自己に不利益なことは話さなくてもよい(英米法系))の規定は憲法にもありますが、供述拒否権(≒黙秘権(不利だろうと何だろうと供述しなくてよい(大陸法系)))を告知するかどうかは立法政策の問題であるというのが最高裁のスタンスです。
>条文を厳密に読む限り……ことだけ
そのとおりです。退去が自由であることを告知することは義務ではありません。一方、被疑者が「帰りたい」などと申し出た場合には、捜査官側は当然これを拒否できないことになります(拒否し続けることは逮捕類似状態になるため、違法捜査の疑いがあります。)。
逮捕されているわけでもなく「任意」で来ているだけなので、帰りたければ帰れるのは当たり前(わざわざ告知しなくても分かるでしょ)、というニュアンスが分かりやすいでしょうか。無論、同意があれば何でもアリではなく、社会的相当性を超えたりすれば違法な取調べになります。
>百九十八条第二項による通告の場面もほとんど見たことがない
フィクションでは省略しているだけと思われます汗。現実では逮捕等に当たり「弁解録取書」を作成するため、弁護人の選任及び犯罪事実の要旨の告知、弁解の聴取が行われます。とにかく、地味な笑、しかし粛々と確実に行われる手続きです。
>任意同行時どころか警察署の外で被疑者が自主的に話し始めるときでさえ…
当時の英国の刑事手続きがどうであったか詳細に存じあげず、また、「不利な証拠とされる」の意味合いが解釈しがたいところですが、既述のとおり、日本では取調べという正式な手続きで適法になされた供述のみが裁判で証拠となり得ますから、取調べ外で被疑者がボソッと漏らした発言については、それをきっかけに何か別の証拠を見つけ出すことはあり得ても、それを捜査官が聞いたからというだけでは、裁判上有力な供述証拠にはなり得ません(供述調書に書き込もうとしても、被疑者側は「そんなことは言ってない」と署名指印を拒否できますし、それ以外の報告書に書き記しても、警察の独りよがりの伝聞証拠を、裁判所が有力と認めるかは疑問です。)。
ですので、被疑者のそのような発言は、それが供述証拠としてはそもそも証拠になり得ないため、「不利な証拠とされるかも」と告げる必要が無いのです。
なにせ職質を受けた経験もないもので、日本の捜査に関する知識はほぼ本やドラマのフィクションと若干のノンフィクションからのものしかありません。よろしければもう少し御教示ください。
百九十八条はいわゆる任意同行の場合ですね。ドラマ等を見る限り任意同行を求めた捜査官が第一項の内容を通告するという場面はみたことがないのですが、これは実際にそうなのですよね? 最近ではようやく被疑者の方から「これは任意だから拒否できますよね?」などと確認する場面も登場するようになり、国民への啓蒙が始まってるようですが(^_^)。確かに通告の義務は第二項にだけしかありませんから、任意同行を求める時には通告せず、署に引っ張り込んでから黙秘権のある旨を通告すればルールには反しないことになりますね。それどころか条文を厳密に読む限り、第一項の内容は全く通告しなくても違反にはなりません!! 通告の義務があるのは「自己の意思に反して供述をする必要がない」ことだけ。わざとなのか見落としなのか、巧妙な抜け道に見えてしまいます(^_^)。
ただ百九十八条第二項による通告の場面もほとんど見たことがないのですが、これは作者が省略しているだけなのでしょうか? それとも実態を反映した描写だからなのでしょうか?
ドイルらの描写によればヤードの捜査官は、任意同行時どころか警察署の外で被疑者が自主的に話し始めるときでさえ、事前に「その発言は不利な証拠とされるかも知れない」ことを通告する義務があるようです。
◇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
〇第百九十八条第一項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
〇第百九十八条第二項
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
〇第二百三条
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え……なければならない。
上記のとおり、現代日本に「ミランダ警告」類似の制度が無いわけではないので、付言申し上げます。ただ、海外ドラマや小説のように逮捕する際に言うのではなく、基本的には正式に取調べの場所に移ってから、冒頭で説明されます(個人的にも、逮捕の動揺した現場で言われるよりも、場所を移して落ち着いてからゆっくり説明してもらったほうが、被疑者の権利としても効用があるように思います。文学的には逮捕の現場でスパッと言い渡すのがかっこいいのかもしれませんが笑)。
蛇足ですが、日本の刑事司法制度(ことに刑事手続きの面)は江戸時代~明治・戦前~戦後とかなり大きな転換を行っているため、ブログ主様が示されている「権利の歴史」みたく、判例を基礎に直線的に一貫した法体系を保つ英米法とはその様相がかなり異なります(もともと日本の近代刑事司法は大陸法の継受に始まるわけですが…)。
仮に物語が逮捕までを描くものであれば、いわゆる「ミランダ警告」のようなものは日本のミステリには登場しないでしょうね。
また、上記の条文にもあるとおり、このような仕組みが制度化されたとき(戦後~の憲法・刑訴法)から、捜査官としては当たり前に行うべき義務化的事務のひとつになってしまっていますので、これをあえてドラマチックなセリフとして活用することが、そもそも日本の物語にはなじまないのかもしれませんね。もちろん、多分に私見でしかありません笑。