本日は『宝くじの日』だそうです。
く(9)じ(2)の語呂合わせにちなんで、昭和42年に宝くじの運営管理業務を行っているみずほ銀行(当時は第一勧業銀行)が制定しました。
宝くじって銀行が運営してたのか...!
手元の宝くじが当せんしていないか、当せん金の引き換えを忘れていないかを再確認するよう呼び掛けを行う日でもあります。
日本の宝くじ=富くじの歴史は、江戸時代初期に始まったと言われています。
現在の大阪府にあたる摂津国の箕面山瀧安寺で、お正月に参拝した人の中から三人の当せん者を選び出し、福運のお守りを授けたことが最初だそうです。
この時はお守りを授けるだけでしたが、次第に金銭と結びついて町中に溢れかえるようになりました。
そのため江戸幕府は、寺社の修復費用調達以外の富くじを全面的に禁止しました。
これにより富くじは、天下御免の富くじ「御免富(ごめんとみ)」と呼ばれるようになりました。
ですがそれも天保13(1842)年の改革により禁止されてしまったので、以来103年にわたって日本で富くじが発売されることはありませんでした。
戦後の復興資金調達のために「宝くじ」が発売され、以降オリンピックや万博などの国家的行事への協力や、災害の復興に役立てるための特別な宝くじが発売されるなどしてきました。
ちなみにこの記事を書きながら、「どのホームページを見ても宝くじの”当せん”って書いてあるけど、これって”当選”じゃないの?」と思いました。
どうやら、籤(くじ)で選んだのが宝くじの当せん者なので、漢字を使うなら”当籤”が正しいということのようです(こちらのHP)。
し、知らんかった...!
























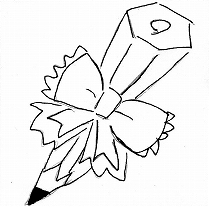

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます