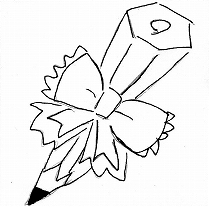1日1枚画像を作成して投稿するつもりのブログ、改め、一日一つの雑学を報告するつもりのブログ。
本日は私も大好きな『アロエヨーグルトの日』です!
1994(平成6)年12月10日に、日本で初めてアロエ葉肉入りのヨーグルトが発売されたことを記念して、製造・販売元の森永乳業株式会社が制定しました。

参照:アロエヨーグルト公式ホームページ
当時の森永乳業では、次世代の健康的なデザートとしてナタデココに次ぐ新素材を探していました。
つまりアロエよりナタデココの方が古いってこと!?
と思って調べてみましたが、1970年ごろに日本にやってきたナタデココのブームは、なんと1993(平成5)年。
たったの一年前やん!
ナタデココの方が先だったということにも驚きましたが、アロエの登場がナタデココブームの一年後という早さにも驚きました。
さて、「食感に特徴がある健康によい食材」という条件で探していた森永乳業が出会ったのが、アロエベラという南国タイが原産地のアロエの一種でした。
それまで日本ではキダチアロエという別のアロエが栽培され、火傷に塗ったり解熱剤や胃腸薬として活用されていました。
なのでアロエ自体には馴染みがあったものの、このキダチアロエには苦くて食べづらいという印象が根付いており、アロエヨーグルトの開発には社内から慎重論も出ていたそうです。
ですが、皮を取り除いたアロエベラのゼリーのような葉肉は無色の無味無臭。
ここに南国フルーツのようなフレッシュ感を加えることで、酸味が少なくコクがあるヨーグルトとうまくマッチさせることに成功しました。
こうして、「素肌とカラダのために」をキャッチコピーに売り出されたアロエヨーグルトは、翌年には全国展開して日平均10万個を記録するほどのヒット商品となりました。
さらに、時流に合わせて変化しながら今でも販売を続けるロングセラー商品にもなったのです。
アロエヨーグルトの思い出といえば、入院した幼稚園の頃にばあちゃんが買ってきてくれたものですかね。
...あれ、りんごヨーグルトだったっけ(笑)???
* * * *
私、霧ヶ原悠の作品は下記のサイトにあるので、気になった方は覗きにきてください!
○唄うビブリオドール(小説家になろう様)(カクヨム様)
○「こうして英雄は魔女を討った」(カクヨム様)
○影絵童話集Ⅰ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
○影絵童話集Ⅱ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
本日は『しそ焼酎「鍛高譚」の日』だそうです。
1992(平成4)年12月9日に、しそ焼酎「鍛高譚」が発売されたことを記念して、25周年の節目に製造・販売元のオエノンホールディングス株式会社が制定しました。
しそ焼酎「鍛高譚」は、北海道白糠町産の厳選された香り高い赤シソと、大雪山系を望む旭川の清冽な水を使用した、爽やかな風味の焼酎です。

参照:オエノン公式ホームページ
シソといえば緑色のものをよくスーパーなどで見かけますが、赤シソとはその名の通り、鮮やかな紫色のシソです。
だから鍛高譚も赤っぽいものが通常だと思ってたんですが、あくまで赤シソは香りと味わいで使用するだけで、色は別みたいですね。
焼酎は麹を原材料に混ぜて発酵させ、蒸留と熟成を経て完成しますから、基本は無色の液体です。
赤いものは「赤鍛高譚」といって、こちらの分類はリキュールとなっていました。

しそ焼酎「鍛高譚」に使用する赤シソの5倍の量を使って作られているそうです。
元々赤い色がついているので「サンライズ」や「ヨーグルト」など、公式ホームページでは非常に見栄えが美しい飲み方が紹介されています。
ところで、「鍛高譚(たんたかたん)」ってすごくリズミカルな名前ですよね。
どんな由来があるのかと思っていたら、なんと鍛高(タンタカ)はアイヌ語でカレイ科の魚を意味するそうです。
しかも高級魚( ゚д゚)
このタンタカの物語=譚ということで、「鍛高譚」と名付けられたそうです。
この物語はオエノン公式ホームページから見ることができます。
* * * *
私、霧ヶ原悠の作品は下記のサイトにあるので、気になった方は覗きにきてください!
○唄うビブリオドール(小説家になろう様)(カクヨム様)
○「こうして英雄は魔女を討った」(カクヨム様)
○影絵童話集Ⅰ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
○影絵童話集Ⅱ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
本日は『針供養』の日です。
折れたり曲がったりして使えなくなった針を労い、裁縫の上達を願う風習です。
今では取れたボタンをつけ直すときにしか針を使わないという人もいますが、昔は針仕事は当たり前の家事のひとつでした。
針も生活必需品のひとつだったわけで、その針が使えなくなったなら感謝を込めて供養しました。
これが『針供養』で、大事な民間行事として江戸時代ぐらいから始まったとされています。
実は12月8日が『針供養』の日なのは西日本で、東日本では2月8日が『針供養』の日なんです。
現在ではその地域差がなくなったり、あるいは逆に両方やるというところも多いそうですが。
そもそも日本には、12月8日と2月8日を「事八日」といって、事を始めたり納めたりする日という風習がありました。
針供養はその代表的な行事です。
この「事八日」には考え方が二つあります。
○年神様を迎える準備を始めるのが12月8日の「事始め」、それを終えるのが2月8日の「事納め」で、ここから人の一年が始まります。
○田の神様を迎えて人の一年が始まるのが2月8日の「事始め」、それを終えるのは12月8日の「事納め」です。
このどちらかの考えに則り、各地・各神社や寺は事納めの日に針供養を行っているようです。
針供養のやり方として一番知られているのは、豆腐やこんにゃくなどの柔らかいものに刺す方法です。
最初知ったときは「なんで?」と思いましたが、実は「これまで硬い生地などを刺してきた針に対し、最後は柔らかいところで休んで成仏してほしい」という人間からの心遣いでした。
な、なるほど〜!
* * * *
私、霧ヶ原悠の作品は下記のサイトにあるので、気になった方は覗きにきてください!
○唄うビブリオドール(小説家になろう様)(カクヨム様)
○「こうして英雄は魔女を討った」(カクヨム様)
○影絵童話集Ⅰ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
○影絵童話集Ⅱ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
本日は『大雪』です。
「おおゆき」ではなく、二十四節気のひとつ「たいせつ」です(笑)
雪が降り始めて本格的に冬が到来することを指します。
例年、大雪が過ぎたあたりから気温が下がり始め、スキー場がオープンしたりブリなどの冬の魚の漁が盛んになったりします。
ただし、今年2020年12月の頭に発表された一ヶ月予報では、11日までは平年より高い気温になるようです。
朝晩はストーブをつけるほど寒くなりましたが、昼間は晴れが続いてあったかいどころか、歩いてると汗ばむぐらいですからねえ。
平安時代に活躍した清少納言は、随筆「枕草子」の中でこう言っています。
冬は、つとめて。
雪の降りたるは、言ふべきにもあらず、霜のいと白きも、またさらでも、いと寒きに、火など急ぎおこして、炭持てわたるも、いとつきづきし。
昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、火桶の火も白き灰がちになりて、わろし。
超意訳すれば、
冬は早朝が一番よ!
雪が降っているのも霜が白いのも良いし、寒いから急いで火をおこして炭を持って廊下を歩いているのも良いわね。
昼になって暖かくなっていくと、火鉢の炭が白くなってダサい。
こんな感じでしょうか。
現在の私たちからすると、(仕事などを除いて)冬の早朝に外に出ようものなら物好きと言われそうなものですがねえ...。
そもそも高温多湿の日本では、「家の作りやうは、夏をむねとすべし。冬は、いかなる所にも住まる。(徒然草)」と言われているように、風通しの良さを重視していました。
平安時代の貴族が暮らした寝殿造の屋敷なんか壁がほとんどなく、戸や障子などで間仕切りして生活していたと言います。
絶対寒いやろ。
地球規模で見れば、温暖期と寒冷期とを繰り返していて平安時代は温暖期にあったという説もあるそうですが、それにしたって寒いやろ。
雪は、上空1500m付近の温度が-6℃以下で地上付近の温度が3℃以下の場合に降ることが多いとされています。
つまり雪が降ってたってことは、いくら温暖期とはいえ外気温は3度ぐらいだったはず!
吹きっさらしの部屋で火鉢抱いて重ね着してても、寒いもんは寒いやろ!!!
昔の日本人頑丈かよぉ...😭(暑いのより寒い方がダメなタイプ)。
* * * *
私、霧ヶ原悠の作品は下記のサイトにあるので、気になった方は覗きにきてください!
○唄うビブリオドール(小説家になろう様)(カクヨム様)
○「こうして英雄は魔女を討った」(カクヨム様)
○影絵童話集Ⅰ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
○影絵童話集Ⅱ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
本日は『聖ニコラウスの日』または『サンタクロース・デー』だそうです。
ドイツやオランダなどの中欧諸国では、クリスマスの12月25日よりも盛り上がる行事なんだそうです。
前日にブーツを磨いて置いておくと、一年いい子にしていた子はお菓子がもらえるらしいので、日本人が想像するクリスマスとだいたい同じでしょうかね。
サンタクロースのモデルには諸説あるそうですが、女性や子供を守護する4世紀ごろに実在した聖ニコラウスもその一人。
「その昔、聖ニコラウスは娘が身売りをして生計を立てている貧しい家庭に胸を痛めた。
そこで、真夜中に煙突から金貨を投げ入れると、たまたま干されていた靴下の中に入った。
このお金のおかげで娘は身売りをやめて結婚できるようになった」
と言われています。
聖ニコラウスと一緒にやってくるのは、サンタクロースでおなじみのトナカイではありません。
オランダでは黒人の少年を、ドイツでは黒い服のサンタクロースを、オーストリアでは悪い子を連れて行く悪魔を、チェコでは天使と悪魔を連れています。
国によってまちまちなのも面白いですが、だいたいは「聖ニコラウスがいい子を褒めてお菓子をあげるのに対して、お付きは悪い子にお仕置きをする」と役割分担されているみたいですね。
中には、袋に詰めてさらっていってしまうお付きもいるとか。
ちなみに12月6日が『聖ニコラウスの日』なのは、彼が死んだと言われているのが12月6日だからだそうです。
* * * *
私、霧ヶ原悠の作品は下記のサイトにあるので、気になった方は覗きにきてください!
○唄うビブリオドール(小説家になろう様)(カクヨム様)
○「こうして英雄は魔女を討った」(カクヨム様)
○影絵童話集Ⅰ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
○影絵童話集Ⅱ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。