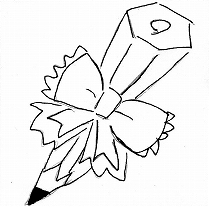1日1枚画像を作成して投稿するつもりのブログ、改め、一日一つの雑学を報告するつもりのブログ。
本日は『観光バス記念日』です。
1925(大正14)年12月15日、東京乗合自動車によって日本初の定期観光バス「ユーランバス」が運行され始めたことにちなんで制定されました。
ユーランバスは、皇居前~銀座~上野を走る定期観光バスでした。
途中下車、乗車も可能で、実際は近距離観光地間を運行する路線バスのようなものだったそうです。
庶民の間で好評だったユーランバスですが、戦争の影響で1940年には運行が終了してしまいました。
ちなみに戦後、東京の観光バス事業は黄色いバスが目印の「はとバス」として復興しました。
日本のバスの始まりには諸説ありますが、1903(明治36)年に二井商会が京都市内で始めたのが最初と言われています。
大正12(1923)年に関東大震災が起こり、壊滅的な被害を受けた路面電車に代わって、バスは庶民の足として急速に普及していきました。
ちなみに最初は大学卒の知識豊富な男性が添乗員として同乗していたそうですが、やがて流暢で優しい口調の女性バスガイドが採用されるようになっていったそうです。
現在、バスを使い方で分類すると以下のようなものになるそうです。
○乗合バス:いわゆる「路線バス」で、通勤・通学に利用されています。
○貸切(観光)バス:修学旅行や社員旅行などで貸し切って利用されるバスです。
○高速バス:片道50km以上の長距離を走り、高速道路を運行しているバスです。
ちなみに、夜中走って翌朝目的地に着くバスを一般的に「夜行バス」と言いますが、法律上そういう用語はないそうです。
○空港アクセスバス:空港とターミナル駅間などで運行するバスです。
○定期観光バス:観光地・路線・運行時間などが決められたバスです。
意外とあったなあ。
* * * *
私、霧ヶ原悠の作品は下記のサイトにあるので、気になった方は覗きにきてください!
○唄うビブリオドール(小説家になろう様)(カクヨム様)
○「こうして英雄は魔女を討った」(カクヨム様)
○影絵童話集Ⅰ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
○影絵童話集Ⅱ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
今日は『箱根西麓・三島大吊橋が開業した日』なんだそうです。
どこにあるかというと、静岡県は三島市↓

2015(平成27)年12月14日、全長400mという日本最長の歩行者専用吊り橋として開業しました。
ただし、これは観光的な吊り橋としてであり、生活橋としては奈良県十津川村の谷瀬橋が日本一(全長297m)だそうです。
「三島スカイウォーク」という愛称で親しまれているこの橋は、一大観光施設でもあるので、営業時間と入場料が必要です。
橋って、日本にあるもの全部道の延長みたいなものだと思っていたので、営業時間と入場料がいるってことに驚きました。
○営業時間:9:00-17:00(年中無休) ただし、イベントや天候によって異なる
○入場料:大人1100円 中高生500円 小学生200円
レストランの他、アスレチックパークや展望デッキなどがあります。
しかも、ジップラインやセグウェイなどのアクティビティも充実しているそうです。
「日本一の富士山を眺める、日本一の大吊り橋を造ろう!」というコンセプトで造られた橋だそうなので、そりゃ眺めは文句なしの一番でしょう!
いいな〜行ってみた〜い!!
たとえば土曜日に新大阪からだと...
10:00新大阪駅(新幹線のぞみ)→名古屋駅(新幹線こだま)→12:49三島駅 13:15三島駅(東海バスN65)→13:41三島スカイウォーク
合計3時間44分、片道13080円!
わぁお(O_O)
参照:三島スカイウォーク公式ホームページ
* * * *
私、霧ヶ原悠の作品は下記のサイトにあるので、気になった方は覗きにきてください!
○唄うビブリオドール(小説家になろう様)(カクヨム様)
○「こうして英雄は魔女を討った」(カクヨム様)
○影絵童話集Ⅰ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
○影絵童話集Ⅱ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
本日は『正月事始めの日』です。
江戸時代中頃まで使用されていた宣明暦において、12月13日は「鬼宿日」と言って、婚礼以外の全てのことが吉とされていました。
そのため、この日から1月1日の元旦を迎えるために準備を始める風習がありました。
鬼宿日というのは二十七宿のひとつで、インドで生まれた天文学であり占星術です。
月の運行が約27.3日であることをもとに天球を27分割して、月が1日ごとに宿を移っていくことに基づいています。
1日ごとに宿が割り当てられ、それぞれに吉凶禍福の意味が込められています。
唐の時代に中国へもたらされ、日本にも伝わりました。
ちなみに中国では、東西南北にそれぞれ7つずつ星宿を配する二十八宿も考え出され、これもやがて日本に伝わりました。
この二十八宿を元ネタにした作品が、渡瀬悠宇氏による「ふしぎ遊戯」シリーズです!
思えばこれが初めてキャラソンをTSUTAYAでレンタルした作品だし、小説版を図書館で探して読んだ初めての作品だわ...。
絵もきれいでストーリーも凝っているので、ぜひ読んでみてください! → Renta! ふしぎ遊戯
さて、宣明暦の後も何度か改暦が行われましたが、正月事始めの習慣は残りました。
○煤払い:家の中に一年の間に積もった煤や埃を掃除し、一年間の厄をはらい落として家の中を清めること。
なお、このことからハウスクリーニング事業などを展開している株式会社東和総合サービスは今日を『大掃除の日』に制定していたりします。
○松迎え:年神様を迎えるための門松やおせち料理を作るための薪など、正月に必要なさまざまな木を山から伐ってくること。
こちらは逆に、現代ではあまり馴染みのなくなってしまった習慣ですね。
* * * *
私、霧ヶ原悠の作品は下記のサイトにあるので、気になった方は覗きにきてください!
○唄うビブリオドール(小説家になろう様)(カクヨム様)
○「こうして英雄は魔女を討った」(カクヨム様)
○影絵童話集Ⅰ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
○影絵童話集Ⅱ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
本日は『ダズンローズデー』です。
ヨーロッパには「愛する人に12本のバラを送ると幸せになれる」という言い伝えがあり、ダズンローズ=12本のバラの花束を贈る習慣があるそうです。
この文化を広めようと、ブライダルファッション業界の第一人者である桂由美氏と内田和子氏が制定しました。
日付の由来は、一年の中で12が重なる日だからです。
ダズンでは聞き馴染みがありませんが、要するに12でひとつの「ダース」のことです。
ダズンローズは、19世紀ごろのヨーロッパで始まった習慣だと言われています。
ある男性が恋人のところへプロポーズに行く途中、12本の野薔薇を摘んだ。
男性は12本それぞれに異なる誓いを立てて、恋人にその花束を差し出した。
恋人の女性は「お願いします」という返事の代わりに、1本を選んで男性の胸に飾った。
ロマンチックで素敵な言い伝えですよね〜😍
12本の誓いは、「感謝・誠実・幸福・信頼・希望・情熱・真実・尊敬・栄光・努力・永遠」と言われています。
ダズンローズの日は恋人や奥さんに日頃の感謝と愛を伝える日でもありますが、ダズンローズ自体は結婚式の演出としても人気があるそうです。
たとえば式の参列者12人に薔薇を持ってもらって、新郎はバージンロードを歩いている間にそれを受け取って花束にし、後から来る新婦へ渡すとか。
それはそれでまた美しい...!
ちなみに、薔薇は色と本数で意味が変わることで有名ですが、単純に12本だと「私と付き合って下さい」「日ごとに愛が強まります」という意味があるそうです。
「あなたを愛する」「愛情」「情熱」などの意味がある赤い薔薇で贈るとぴったりかもしれませんが、一口に赤といっても色んな「赤」があるのが薔薇の良いところで、困ったところでもあります(笑)



ちなみに薔薇全体で見ると、4万種以上の品種があるそうですよ。
ひえ〜〜。
* * * *
私、霧ヶ原悠の作品は下記のサイトにあるので、気になった方は覗きにきてください!
○唄うビブリオドール(小説家になろう様)(カクヨム様)
○「こうして英雄は魔女を討った」(カクヨム様)
○影絵童話集Ⅰ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
○影絵童話集Ⅱ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
本日は『百円玉記念日』というそうです。
1957(昭和32)年12月11日、日本で初めて百円硬貨が発行されたことを記念して制定されました。
それまでは板垣退助が肖像となっていた百円紙幣が使われていました。
ですが紙幣は硬貨に比べて寿命が短く、今後使用する頻度が多くなったときに硬貨のほうが丈夫で長持ちするからという理由で変更されました。
また、当時の諸外国の貨幣制度を参考にして百円は硬貨にしたという理由もあるそうです。
百円紙幣は昭和49(1974)年8月1日に発行停止になっていますが、日本銀行のホームページを見てると、有効な銀行券ではあるみたいなんですよね...。
ホントかよ😓
発行された当時の百円硬貨は、銀(正確には銀60%、銅30%、亜鉛10%)で作られていて、図柄は鳳凰でした。
大きさは今と同じ22.6mmで、重さも4.8gで変わらないようです。
2年後の1959年には、素材もサイズも変えず、図柄だけ鳳凰から稲穂に変更して新しい百円硬貨が発行されました。
ですがこの後、世界的に電子工業で銀の需要が増加し、保有銀量も不足したため昭和42(1967)年から現在の百円硬貨が発行されるようになりました。
素材は銅75%、ニッケル25%の白銅が使われています。
図柄は桜の花三輪です。
ちなみに、昭和36年、昭和39年、平成13年、平成14年の百円硬貨は発行数の少なさなどから、運がよければ100円以上の値がつくかもしれないんだとか!
地味ですけど、見つけたらちょっと嬉しくなるやつですね😁
参照:日本銀行 日本のお金
* * * *
私、霧ヶ原悠の作品は下記のサイトにあるので、気になった方は覗きにきてください!
○唄うビブリオドール(小説家になろう様)(カクヨム様)
○「こうして英雄は魔女を討った」(カクヨム様)
○影絵童話集Ⅰ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。
○影絵童話集Ⅱ(ノベリズム様)
※文章のみの公開となっています。