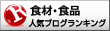・アルミニウムAluminium あるみにうむ
アルミニウムは銀色に近い色をした軽金属です。食品中ではベーキングパウダー、ミョウバンに多く含み食品添加物として膨張剤・色止め剤・形状安定剤・品質安定剤・着色に用いています。
膨脹剤(ベーキングパウダーなど):一部の菓子パン(メロンパンなど)、焼菓子(スポンジケーキなど)、揚げ菓子(ドーナツなど)、蒸し菓子(小麦饅頭・蒸しパン)など
色止め剤:漬物(ナスの漬物・シソの実漬など)
形状安定剤(煮崩れ等の防止):魚介類(たこ、いか、くらげ、うになどの魚介類)など
品質安定剤:野菜等(芋、豆、ごぼう、れんこん、栗など)の煮物
着色料:食品全般
胃薬などの医薬品などにも広く使用しています。
非常に多くの生活用品の調理器具、アルミ箔、医薬品の包装材、 アルミサッシ、一円硬貨などにも用いています。
アルミニウムは、地球の地殻を構成する元素の中で、酸素46%、ケイ素28%の次に多い元素で、地球全体に対しておよそ8%存在していると言われます。また、自然界ではいろいろな化合物になっており、鉱物や土壌、水、空気、植物、動物などに含まれています。
そのため、自然に食べ物や飲み物、水や空気などを通して、毎日、アルミニウムを摂取しています。しかし、このように色々なところに存在していても、単体になりにくい性質から、発見されたのが約200年前と、金属の中ではごく最近で、当時は珍しい金属でもありました。
1782年にフランスの科学者A.L.ラボワジェが、明ばん石(ばん土・アルミナ)は金属の酸化物である可能性が大きいという説を発表し、1807年 イギリスの電気化学者デービーは明ばん石を電気分解してアルミニウムの存在を確認、その後、呼称はアルミーヌAlumine、アルミアムAlumium、アルミナムAluminum、アルミニウムAluminiumと変化しています。米国では現在アルミナムと呼んでいます。
1825年にデンマークの電気物理学者エールステッドが分離し、この金属をミョウバンの古代ギリシャ名AlumenよりアルミアムAlumiumと命名しています。
ボ-キサイトBauxite鉱床(アルミニウムを含む鉱石)の鉄ばん土は熱帯雨林地域、又は過去に熱帯雨林地域であった所に分布します。 産出国は1位オーストラリア 2位中国 3位ブラジル、インド、ギニアなどでボーキサイト生産量上位5カ国で世界全体の年間ボーキサイト生産量の約76%を占めます。
原料となる茶色いボーキサイトBauxite(鉄礬土[てつばんど]ともいい、酸化アルミニウム[Al2O3, アルミナ]を 52%~ 57% 含む)という鉱石から不純物の二酸化ケイ素と酸化鉄(III)を除いて作られます。
反応性が高いため、自然界では遊離の状態では見られず、空気中では酸化物の被膜を生じるので、内部まで錆びることはなく軽くて熱をよく伝える金属です。
水酸化ナトリウム(NaOH)で溶かし、アルミン酸ソーダ液(NaAlO2)を作ります。そこから抽出したアルミナ(Al2O3)を電気分解することで、アルミ地金を製造しています。地金を原料として圧延、押出、鍛造、鋳造などの加工を行い、様々な形の製品素材にしていきます。
軽くて強く、リサイクル性にも優れている素材として世界中で使用する金属です。
単体では強度が低く、他の物質と合わせて作られ「合金」にすると、比重が軟鋼(純鉄に近いもっとも炭素を含む量の少ない鉄)の3分の1と軽い上に、強度が増し亜鉛5.6%、銅1.6%、マグネシウム2.5%、クロム0.3%を持つものを「超々ジュラルミン」と呼んでいます。
軽量化の目的で航空機の外板や電車、自動車の構造材などに広く用い、このことによって、さらに二酸化炭素排出量の削減に貢献しています。
原子番号13、原子量26.98、比重2.70、元素記号はAl、軽銀(けいぎん:アルミニウムのこと)やアルミニウムをアルミと略すことも多く、医薬品では制酸剤(胃薬)に含まれ、その他、抗炎症剤、抗潰瘍剤などにもアルミニウムを成分として含むものがありますが現在では使用の度合いが少なくなる傾向です。
ラットを用いた動物実験で、アルミニウムを多量に投与すると腎臓や膀胱への影響や握力の低下などが認められています。吸収を促進する食品成分としてクエン酸が挙げられアルミニウム含有食品とクエン酸の同時摂取は避けましょう。シュウ酸、ケイ酸、リン酸の共存で低下します。
人体内には35~40mgのアルミニウムが安定した状態で存在しているといわれ、体内の分布は骨、肺に多く、脳、筋肉にもみられます。呼吸等により経口摂取したそのほとんどの約99パーセントが吸収されずにそのまま排泄されることがわかっています。
また、吸収した1%のわずかに残った分の大部分は腸管を通して吸収された後、腎臓を通って尿とともに排泄しています。
アルミニウムの体内の働きについては、はっきりと解明していないのが現状です。
アルミニウムの主用排泄経路は腎臓であり、腎機能に障害がある場合は特に要注意です。透析脳症は、1970年代に腎臓透析に使用される水道水中のアルミニウムにより引き起こされ、言語障害・精神症状・運動障害から意識障害へ移行し、多くは死に至り現在は透析に水道水は使用していません。
WHO基準では、飲料水のアルミ濃度は0.2ppm(0.2mg/L)以下、暫定耐容週間摂取量PTWIは2mg/kg/週、さらに中毒では骨形成に異常をきたしたり貧血を起こしたりすることもあります。
経口摂取で体内に吸収されるアルミニウムは約1%程度で吸収後は主に骨に分布します。 中毒の治療にはアルミニウムキレート剤としてデフェロキサミンDesferrioxamineの投与が有効とし広く使用しています。
厚生労働省では、平成23年度~24年度に加工食品と野菜などの生鮮食品からアルミニウムをどれくらい摂取しているのか調査を行っていました。その結果、アルミニウムの推定摂取量の平均値は、すべての年代層で暫定的な許容量の体重1kg、一週間当たり、2mg(14.3mg/1日/50kg)を下回っていました。
小児(1~6歳)では、許容量に対する摂取量の割合が最も大きく、許容量の約43%です。
アルミニウムを含む食品を多く食べる場合の推計では、小児では摂取量の多い5%の人が許容量を超える可能性があるとしています。
1日当たりのアルミニウムの摂取量は、地域や食生活によって異なりますが、世界的な研究機関であるWHO(世界保健機構)の報告では、1日当たりの摂取量は2.5~13mgとしています。
たとえば、加熱調理をすべてアルミ製の鍋で行うようなケースでも、食物からの摂取を主として4~6mg程度と考えています。
昭和女子大学報告
水道水0.017ppm(0.017mg/L)、炭酸飲料0.22ppm、緑茶1.33ppm、ウーロン茶3.43ppm、缶ビール0.11ppm、葉菜類12ppm、根菜類2.6ppm、白米1.2ppm、肉・魚類2ppm、貝類38ppm、海藻85ppm
アルミニウムの推定摂取量には、穀類加工品や菓子類などの寄与が大きく、膨脹剤として使用する食品添加物(硫酸アルミニウムカリウムや硫酸アルミニウムアンモニウム)によるものと推察しています。
国際的にアルミニウムを含む食品添加物の基準の設定や見直しが進められています。
現在、日本ではアルミニウムを含む食品添加物の使用基準(使用量の上限)を設定していません。
このような状況を踏まえ、厚生労働省では、より高い水準での安全性を確保する観点から、パンと菓子類に膨脹剤として使用される食品添加物(硫酸アルミニウムカリウムと硫酸アルミニウムアンモニウム)について、関係業界に対して、さらなる自主的な低減化の取組みを依頼、現状の使用実態を確認した上で、使用基準を検討するの取組みを行うとしています。
加工食品では膨脹剤:膨張剤、ベーキングパウダー、ふくらし粉
色止め剤、形状安定剤、品質安定剤:硫酸アルミニウムカリウム、ミョウバン、カリミョウバン、硫酸アルミニウムアンモニウム、アンモニウムミョウバン
と食品には以上のように表示しています。
アルミニウム器具からの食物への溶出はわずかです。アルミニウム溶出量について、
1) 加熱調理をすべてアルミニウム製鍋でおこなった場合に調理器具から1.68mg、アルミ箔製品から0.01mg、飲料缶0.02 mg摂取すると推定しています。
2) 酸や食塩が強い食品ではアルミニウム容器からの溶出が比較的大きいですが、全ての食品がアルミニウム容器で調理・保存されていた場合でも、容器由来のアルミニウム摂取量は6mg/日程度といいます。
以上の報告からも分かるように、アルミニウム器具からの溶出に対して過度に心配する必要はありません。
ドイツBfR(Bundesinstitut fur Risikobewertung:ドイツ連邦リスクアセスメント研究所)からの報告で、市販アルミニウム製品からのアルミニウム摂取量は、食品や制酸剤((水酸化アルミニウムやケイ酸アルミニウム)から摂取するアルミニウム量よりも少なく、毒性を示す量よりも明らかに少ないことを示唆しています。
ただし、アルミニウムは酸性条件下で溶解性が高くなるため、酸や塩濃度の高い食品 (リンゴをすりつぶしたものやトマトピューレ、塩漬けニシンなど) にはアルミ製の容器やアルミホイルを使用しないことを勧めています。
一時期、アルツハイマー病とアルミニウムの関係があるといった情報もありましたが、現在は、この因果関係を証明する根拠はないとしています。
過度な偏食に注意し、バランスの良い食生活を心がけることが大切です。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。