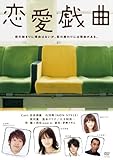2011/1/24
札幌演劇大学の近代戯曲講座で、「わが町」の舞台映像を見せてもらう。
1987年公演。セリフはすべて英語。字幕なし。
英語はほとんどわからない。でも、英会話の勉強してるわけじゃないので、リラックスして見る。あらすじはなんとなくわかってたし。
で、これがまた身震いするほどおもしろい。
そりゃ言葉の意味がわかったほうが良いに決まってるんだけど、ふしぎなもんで言葉がわからないからこそ見えてくるものもある。
その役が何を感じているのかはわかるし、どんなシーンを見せたいのかもわかる。皮膚を取っ払って筋肉の動きをじかに見ている感じ。これが「意識の流れ」というやつなんだろうか。
そして、なぜか戯曲の凄みも感じる。これは構成力だと思うんだけど、よくわからない。
初演は70年以上も前の戯曲なのに、何度見ても斬新だと思ってしまうから困る。
札幌演劇大学の近代戯曲講座で、「わが町」の舞台映像を見せてもらう。
1987年公演。セリフはすべて英語。字幕なし。
英語はほとんどわからない。でも、英会話の勉強してるわけじゃないので、リラックスして見る。あらすじはなんとなくわかってたし。
で、これがまた身震いするほどおもしろい。
そりゃ言葉の意味がわかったほうが良いに決まってるんだけど、ふしぎなもんで言葉がわからないからこそ見えてくるものもある。
その役が何を感じているのかはわかるし、どんなシーンを見せたいのかもわかる。皮膚を取っ払って筋肉の動きをじかに見ている感じ。これが「意識の流れ」というやつなんだろうか。
そして、なぜか戯曲の凄みも感じる。これは構成力だと思うんだけど、よくわからない。
初演は70年以上も前の戯曲なのに、何度見ても斬新だと思ってしまうから困る。