主語Sは青、動詞Vは赤、目的語Oは黄色、補語Cは銀色で色分けすると以下のようになります。(便宜上that節は修飾語句も含めて一色にしました)
①Obama pointed out that before deciding on a new strategy, he sought advice from U.S. military leaders.
②They urged the President to increase the fighting force in Afghanistan.
③They told the President that U.S. security is at stake in the region.
出典TIMEFORKIDS Dec11, 2009 The Plan for Afghanistan 第三段落
①はpointed outという他動詞がthat節を目的語にするSVO構造の第3文型です。
②はthe Presidentという目的語が第二の主語に転換しto increase the fighting force以下の補語と主述関係を構成するSVOC構造の第5文型です。
③はtoldという他動詞がthe Presidentとthat節という二つの目的語を持つSVO’O構造の第4文型です。
五文型分類においては第4文型と第5文型の区別がつけにくいという悩みをよく目にします。肝心なのは第1~第4文型においては文頭の主語が最後まで行為もしくは状態の主体であるのに対して、第5文型は目的語が第二の主語に転換する特異な文型であるということです。②においてto increaseする主体はthe Presidentであって断じて文頭のThey(U.S. military leaders)ではありません。①と③はthat節の内部に五文型構造(①はSVO構造の第3文型、③はSVC構造の第2文型)を持つものの、that節を押さえているのは文頭に置かれた主語です。
目的語が第二の主語に転換する第5文型という発想は日本人に馴染みにくいものの英語では多用されるため、第5文型の原理を英英思考的に理解すると英文の理解度が飛躍的に高まります。そのためにはまず、「第5文型はO=C」という古い定義から脱却して「第5文型はOCの主述」という定義を頭に入れる必要があります。第4文型はSVO’Oであるのに対して第5文型はSVO(S')Cと考えれば、第4文型と第5文型の区別は容易だと思います。
①Obama pointed out that before deciding on a new strategy, he sought advice from U.S. military leaders.
②They urged the President to increase the fighting force in Afghanistan.
③They told the President that U.S. security is at stake in the region.
出典TIMEFORKIDS Dec11, 2009 The Plan for Afghanistan 第三段落
①はpointed outという他動詞がthat節を目的語にするSVO構造の第3文型です。
②はthe Presidentという目的語が第二の主語に転換しto increase the fighting force以下の補語と主述関係を構成するSVOC構造の第5文型です。
③はtoldという他動詞がthe Presidentとthat節という二つの目的語を持つSVO’O構造の第4文型です。
五文型分類においては第4文型と第5文型の区別がつけにくいという悩みをよく目にします。肝心なのは第1~第4文型においては文頭の主語が最後まで行為もしくは状態の主体であるのに対して、第5文型は目的語が第二の主語に転換する特異な文型であるということです。②においてto increaseする主体はthe Presidentであって断じて文頭のThey(U.S. military leaders)ではありません。①と③はthat節の内部に五文型構造(①はSVO構造の第3文型、③はSVC構造の第2文型)を持つものの、that節を押さえているのは文頭に置かれた主語です。
目的語が第二の主語に転換する第5文型という発想は日本人に馴染みにくいものの英語では多用されるため、第5文型の原理を英英思考的に理解すると英文の理解度が飛躍的に高まります。そのためにはまず、「第5文型はO=C」という古い定義から脱却して「第5文型はOCの主述」という定義を頭に入れる必要があります。第4文型はSVO’Oであるのに対して第5文型はSVO(S')Cと考えれば、第4文型と第5文型の区別は容易だと思います。











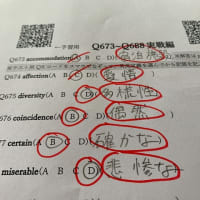


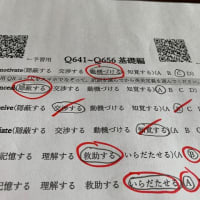

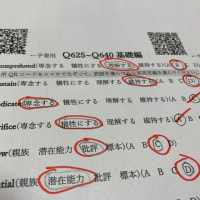





「OとCはイコールではなく主述関係」という説明を見て、(2)番のto以下はthe Presidentがこれから取るだろう行動を表してるから「第5文型かな?」と迷いました。
そこで、ジーニアス英和を見たら「SVO+to do」と書いてあったので「第3文型」とコメントに書いたのですが、ジーニアスの文型分類は、「OCの主従関係のあるもののうちO=C関係なもの」だけを第5文型に分類している・・・言葉を換えれば定義が古いまんま になってます。
もしも「Oと主述関係を成し得る句(to不定詞句とか動名詞句)は、OとCがイコール関係でなくてもC(補語)」の定義が定着したら、かなりの動詞の用法が書き変わるように思います。
ask+(人)+to 不定詞の文とか、tell+(人)+to 不定詞の文とか・・・
ちなみに私は英文読む時「この文第○文型?」というのはあまり気にしませんが・・・(汗)
「英語 5文型 定義」でgoogleをポチっとしてみたら、ウィキペディアで
「<SVOC>:(SV原因)⇒(OC結果)の論理関係が基本であり、「SのせいでOがCになる」(因果関係)や、「OがCだとSが思う」(知覚、思考、発言)の意味を持つことが多い。 」
という記述を見つけました。
これで鈴木様おっしゃる「第5文型はOCの主述」がすぅ~っとなじみました!
ちなみに私手持ちのG4は2006年初版でした。
英文法概念の世界では4年も一昔なのでしょうか??
たとえばALLINONEのp61には、After all, radical reformers tried in vain to persuade the conservative leadership to carry out bold health care reforms.という例文がSVOC(C=to不定詞)として掲載されています。
シグマベスト入試英文法問題特講p25では、I want him to go there alone.という例文がSVOC型として掲載されています。
ただこういった分類はまだ少数派のようで、古典的名著と目される「英文法解説」(江川泰一郎著)改訂三版の331頁には、「『S+V+O+不定詞』の構文を8品詞5文型の学習文法の枠内で処理することは不可能なので,本書の旧版においても各動詞の意味と統語的な特徴に基づく分類を試みたが、さらに検討を加えて分類をしてみた。」という記載がありました。
たしかにO=Cという旧来の日本的発想の五文型分類では「S+V+O+不定詞」の構文は5文型の枠内におさまりません。しかし第5文型のOCを主述とみなせば、「S+V+O+不定詞」の構文はまぎれもない第5文型で、こうすれば第5文型の守備範囲が飛躍的に広がります。
「英文法解説」(江川泰一郎著)改訂三版の193頁には「つまり第5文型の文には第2文型の文が組み込まれており,組み込みにあたっては第2文型のbe動詞が削除されたと考える。」とされています。しかし第5文型のOCを主述とみなせば、第1~第5まですべての文型を組み込めるのが第5文型であるのは2009年12月20日にお示しした通りです。
「英文法概念の世界では4年も一昔」というよりは、辞書や文法書は良くも悪しくも一種の権威で、より合理的な分類法が後から出てきてもなかなか旧来の説明を覆すわけにはいかないのだろうと思います。
けっして五文型を絶対視するわけではありませんけれども、「第5文型はO=C」とするよりは「第5文型はOCの主述」とした方が使い勝手がいいと思います。
PS
私は英語は面白い考えや出来事を知るための道具と考えています。以前はあまり英文法にこだわらず論の流れに頼った読み方をしていましたものの、文法を考えると読む精度が高まることに気づいてからは、かなり五文型や品詞分類にもこだわるようになりました。