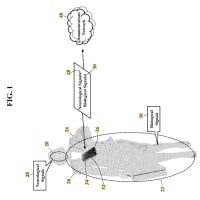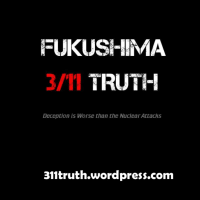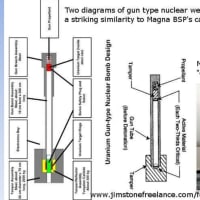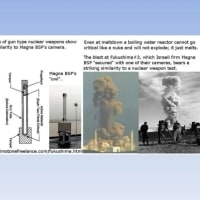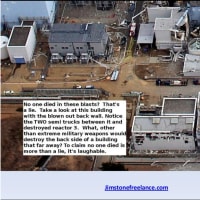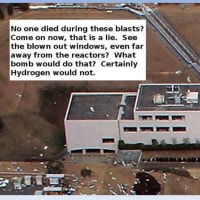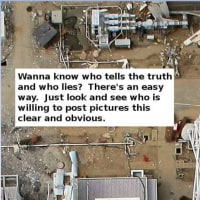2019/2/27(水) 午後 1:30
産業革命後の西欧諸国が次々と近代国家となる中で、アジアの中でいち早く、自力で近代国家に変貌できたのは唯一日本のみであった。この頃の清も李氏朝鮮もそれぞれ「末期的」な様相を呈しており、それ故にこれらの国々はその様々な権益を欧米諸国に売り渡すという「草刈り場」(半植民地状態)になっていった。
李氏朝鮮の「末期的な状況」の中身として、為政者の権力闘争、様々な権益の売却、ロシアによる半植民地化、各地で暴動発生、財政難、進まない改革など、様々な問題を抱えており、そこに日本がまず、李氏朝鮮の宗主国である清との衝突が生じ、その結果として日清戦争が勃発。その後もロシアとの交渉などを通じて朝鮮情勢にどんどん介入していったようなのである。(後には日露戦争にまで発展)
隣国とはいえ、なぜこのように他国の状況に介入していかなければならなかったのであろうか。
日本にとって歴史上の最悪の凶事「日韓併合」に至った経緯として李氏朝鮮時代末期の朝鮮半島の状況をみてみることに。
まず、李氏朝鮮という国家は清の柵封体制のままであったこと、近代国家としての要件である近代法体系の不備、国民の教育水準が低く人材が欠如していたこと、産業基盤が殆どなく、資源に乏しく、財政難であったことなど様々な問題を抱えていたようだ。
19世紀後半に列強の帝国主義政策が東アジアにまで及ぶと、1875年(明治8年)の江華島事件を契機に翌1876年(明治9年)に日本と締結した日朝修好条規を始め、李氏朝鮮は米国や仏国などの欧米諸国と不平等条約を結ぶ。
■李氏朝鮮末期の為政者の権力闘争(閔妃 vs 大院君)、閔妃によるクーデター
世継ぎ問題などで大院君と権力争いをしていた閔妃は、高宗が成人して親政をとるようになると、1873年(同治12年)、ロシア軍の力を借りてクーデターを起こし大院君を追放。大院君とその一派を失脚させた。そして自分の一族(閔氏)を高官に取り立て、政治の実権を握った。大院君はその後京畿道楊州に隠居させられたが、閔妃の存在を国家存続を脅かすものとして政局復帰、閔妃追放の運動を始め、それが朝鮮末期の政局混乱の一因にもなった。
両者の権力闘争は敵対者を暗殺するなど熾烈なもので、1874年11月には閔妃の義兄の閔升鎬が自宅で爆弾によって暗殺された。閔妃は大院君の仕業と信じ、申哲均の食客で張という姓の者を捕えた。更に申哲均は大院君の腹心だったため、簡単には死なないようにする惨い拷問の末に獄死させた。これは大院君の恨みを買い、双方で暗殺が続き国内が乱れた。大院君は自身が国のために貯めておいた国庫を空にする無駄遣いを繰り返す閔妃暗殺のために、閔妃によって親族や親友を殺された者から暗殺者を募り始めたいう。
■開化党(日本より) vs 大党(清より)の対立
朝鮮国内では清国との冊封体制を脱して近代化をすべきだという者(開化党)と、清国との関係を維持すべきだという者(事大党)とが対立。
そうした中で1882年(明治15年)、両派の暗闘から壬午事変(注1)が起こり、日本公使館も暴徒に焼き討ちされて死亡者が発生。公使館保護を名目とする日本と、朝鮮を属国と主張する清の両国は鎮圧を理由としてともに出兵、日清の対立は決定的となった。
(注1)壬午事変 (じんごじへん):
1882年(明治15年)7月23日(旧暦では光緒8年=高宗19年6月9日)、興宣大院君らの煽動を受けて、朝鮮の首府漢城(現、ソウル)で起こった閔氏政権および日本に対する大規模な朝鮮人兵士の反乱(壬午事変 じんごじへん)が起こる。朝鮮国王高宗の王妃閔妃を中心とする閔氏政権は、開国後、日本の支援のもと開化政策を進めたが、財政出費がかさんで旧軍兵士への俸給が滞ったことが反乱のきっかけとなった。
閔氏政権は近代的軍隊として「別技軍」を新設し、日本人教官を招致して教練を開始したが、これに反発をつのらせた旧式軍隊が俸給の遅配・不正支給もあって暴動を起こし、それに民衆も加わって閔氏一族の屋敷や官庁、日本公使館を襲撃し、朝鮮政府高官、日本人軍事顧問、日本公使館員らを殺害。朝鮮王宮にも乱入、閔妃は王宮を脱出。反乱軍は閔氏政権を倒し、興宣大院君を担ぎ出して大院君政権が再び復活。
日本は軍艦4隻と千数百の兵士を派遣し、清国もまた朝鮮の宗主国として属領保護を名目に軍艦3隻と兵3,000人を派遣した。反乱軍鎮圧に成功した清は、漢城府に清国兵を配置し、大院君を拉致して中国の天津に連行、その外交的優位のもとで朝鮮に圧力をかけ、閔氏政権を復活させた。日本は乱後、清の馬建忠の斡旋の下、閔氏政権と交渉して済物浦条約を締結し、賠償金の支払い、公使館護衛のための日本陸軍駐留などを認めさせた。
清国は朝鮮政府に外交顧問を送り、李鴻章を中心とする閣僚は朝鮮に袁世凱を派遣、袁が事実上の朝鮮国王代理として実権を掌握。こののち袁世凱は、3,000名の清国軍をひきつづき漢城に駐留させた。この乱により、朝鮮は清国に対していっそう従属の度を強める一方、朝鮮における親日勢力は大きく後退。
1884年12月4日「甲申政変」
独立党(急進開化派)によるクーデター。親清派勢力(事大党)の一掃を図り、日本の援助で王宮を占領し新政権を樹立したが、清国軍の介入によって3日で失敗。
当時の朝鮮半島は、共に自らの勢力圏におさめようとする日本と清朝の対立の場でもあり、日本は権益を確立するため朝鮮に対する清朝の影響を排除する必要があった。
■東学農民運動
1894年1月上旬、重税に苦しむ朝鮮民衆が宗教結社の東学党の下で蜂起し農民反乱が勃発。東学党によって首都ソウルを脅かされた李氏朝鮮政府は、5月下旬に宗主国である清国の来援を仰ぐ。清国側の派兵の動きを見た日本政府も天津条約に基づいて居留民保護を目的にした兵力派遣を決定。6月5日に大本営を設置。
続々と押し寄せる日清双方の部隊群に驚いた朝鮮政府は慌てて東学党と和睦し、6月11日までに農民反乱を終結させると日清両軍の速やかな撤兵を求めたが、日本政府は両軍が派兵する場合は事前に通達する条約に清が従わなかった為、この事態を機に朝鮮への介入強化を恐れ政情が完全に安定するまでの撤兵を拒否。朝鮮政府に日本の助言を入れた国内改革を要求。日本に対抗する清国側もそのまま部隊駐留を継続。こうしてソウル周辺で日清双方の駐留部隊が睨み合う事になった
そして、1894年(明治27年)に日清戦争が勃発。
■日清戦争(1894年7月25日~1895年4月17日)後の「下関条約」(1895年4月17日調印、5月8日発効)
日清戦争には「日英同盟」「桂・タフト会談」の当事者で、首相在任日数最長(2886日)の桂太郎が名古屋の第3師団長として出征している。桂は日清戦争出征の後、台湾総督を経て、第3次伊藤内閣で陸軍大臣になり、続く第1次大隈内閣に次ぎ、第2次山縣内閣でも陸相とともに山縣の参謀格を務め、1900年に発生した義和団の乱では中国に軍を出動させた人物でもあるが、日韓併合の重要なキーパーソンなのである。
日本が勝利し、伊藤博文全権が起草・調印した「下関条約」により、大日本帝国は清国に朝鮮が自主独立国であることを認めさせ、李氏朝鮮から清国に対する貢献・臣下の典礼等を廃止させ、清の冊封体制から朝鮮を離脱させた。これによって第26代の高宗が中国皇帝の臣下を意味する「国王」の称号を廃して、はじめて「皇帝」と称することとなった。
「下関条約」は500年間中国(明、清)の属国であった李氏朝鮮を独立させた条約なのである。
■1895年10月8日閔妃暗殺事件(乙未事件)
ロシアと通じていた閔妃を日本軍が殺害したという見方もあり、これに関わった容疑で三浦梧楼以下48名、広島地方裁判所にて予審開始、1896年1月20日 三浦梧楼以下48名、証拠不十分で免訴となった。
1896年高宗勅令で閔妃殺害事件の犯人として特赦された趙羲淵、禹範善、 李斗璜、李軫鎬 李範来 権濚鎮の首を持ってロシア公館に持参せよと命令(当時高宗は露館播遷で、約1年間ロシア公館内に居住) 閔妃殺害事件についての再調査も実施され、漢城で発行されていた英文雑誌に調査結果が掲載された。
■太宗の「露館播遷都」(96年2月11日~97年2月20日)
1896年
2月5日 李範晋はロシアの指示で春川、忠清道で暴動を起こし、日本の電信線を切断し日本との連絡手段を遮断。
2月10日ロシア軍が王宮突入(107名の水兵 20名の食料担当兵 大砲一門を漢城に搬入。ロシア兵150名)
2月11日 宮女金明載より「各大臣等日本兵が密かに国王を廃位しようとしているので甚だ危険なり。速かに露館に播遷し回避されたし」旨の書状を高宗に届けられた高宗と世子(純宗)が宮女用のかごに乗り、ロシア公使館へに逃げ込み翌97年2月20日慶運宮へ戻るまでの約1年間、高宗と世子はロシア公館に移された(露館播遷)。
高宗がロシア公使館で政務を執り行った結果、親露派の政権の李氏朝鮮は財政不足から、不平等条約による治外法権どころか、様々な権益、鉱山の採掘権と森林伐採権、鉄道の施設権が欧米に売却され、李氏朝鮮は欧米の草刈り場状態となる。
こうしてロシアやロシア外も他の欧米列強も同等の利権を獲得することになった。 一国の元首が外国の公館内で1年匿われるなど常識的に異常な事態で、これは国としての自主性を放棄するのに等しく、後に日露戦争時に中立を宣言したが日露両国から無視されるような結果となった。
■ロシアの影響と半植民地化
権益を欧米に売却する国力の乏しい朝鮮を目の当たりにし、日本はロシアの朝鮮半島植民地化を恐れ、ロシアとの間で朝鮮問題について話し合いを開始。
1896年5月14日、日本とロシアは小村・ウェーバー覚書(注)を交わす。
(注)小村・ウェーバー覚書:
1896年5月14日ソウルにおいて日本側小村寿太郎、ロシア側 K.I.ウェーバーの両公使によって調印された朝鮮問題に関する日露間の覚え書。ロシア公使館にいる朝鮮国王の還宮実現の条件として両国軍隊の駐屯定員などを取決めている。
2月18日 仁川に4000余名の暴徒蜂起 官衙官宅を毀壊。
2月21日 各地に起こる暴動のうち 、内部参書官徐相潗と申大均は騷優地方坡州、開城、驪州、利川等に乱民鎮撫に関する勅諭頒示の為に向かう。
2月22日 内閣体制の更新。李範晋は法部大臣兼警務使となり大院君派の粛清を開始。
新内閣の公示
総理大臣に金炳始、内部大臣に朴定陽、軍部大臣兼警務使李允用、法部大臣に趙秉稷、学部大臣に李完用、宮内大臣に李載純を命じる。
3月16日 大院君一派の人々、漢城府観察使金経夏、呂圭亨等従犯等数十名を逮捕、裁判へ
3月27日 アメリカ、雲山の金鉱採掘権、 京仁線敷設権、 漢城の電灯・電話・電車の敷設権取得
4月22日 ロシア、慶源・鍾城両処の鉱山採掘権を取得
5月14日 日本・ロシア間で朝鮮問題に関し、第1次日露議定書調印。
5月22日 流刑10年に処せられた閔泳駿(後に閔泳徽と改名)、赦免となる。
6月9日 日本・ロシア間で朝鮮問題に関し、第2次日露議定書調印。
6月12日 ロシア、月尾島西南地段(44,316m2 年銀貨361元)租借契約を取得。
7月 フランス、京義線敷設権を取得
8月20日 機械厰でのロシア技士雇傭契約(機械士官Remnevに每年銀貨200元)
9月 ロシア、豆満江上流地域・鴨緑江上流地域・鬱陵島・茂山の森林伐採権(注)を取得
(注)森林伐採権:朝鮮王大院君はロシアに豆満・鴨緑両江から鬱陵島までの森林伐採権を20年間与えた。
11月21日 旧臣ら、高宗に還宮請願計画(未遂)
1897年
1月 ロシア人N・ビルコフをロシア語教師として雇用
2月13日 機械厰でのロシア技士雇傭契約(雇傭期間3年、俸給毎月銀貨260元、路費500元、帰路費800元、退職金2,000元)
2月20日 高宗ロシア公館から慶運宮に還宮(露韓播遷が終結)
7月、英国人の税関長ブラウンが財政顧問となる。
10月、ロシア公使シュペイエルが、財政顧問を英国人ブラウンを強制解任し、ロシア人キリル・アレキセーフへと変えようとする事件(度支顧問事件)(注2)が起きた。
(注2)度支顧問事件 (たくしこもんじけん):
1897年、高宗の即位に合わせて、ロシア公使アレクセイ・ニコラビッチ・シュペイエルが、大韓帝国の度支衛門 (日本の大蔵省相当)の顧問を、イギリスの推薦したジョン・マクレヴィ・ブラウンから自国人のキリル・アレキセーフに変えさせ、露韓銀行を設立した事件。これに反発したイギリスは東洋艦隊を仁川に派遣、朝鮮の「独立協会」は救国宣言上疏を行った。
厳密にはここまでが李氏朝鮮時代。
■国号の改元(1897年):李氏朝鮮→大韓帝国
1897年10月12日 大韓帝国へ国号を改める
もはや清の藩属国でなくなった以上、国王号を使用することは望ましくないという儒者の建言に従い以下の改革が実施、国号を「朝鮮」から「大韓」と改め、元号も前年のグレゴリオ暦への改暦にともなって定めた「建陽」から「光武」に改元。
高宗は、圜丘壇を新たに設けて10月12日に祭天の儀式を行い、翌13日に詔を出して皇帝に即位した。その後、清の冊封の象徴であった「迎恩門」や「恥辱碑」といわれる大清皇帝功徳碑を倒して「独立門」を立て独立を記念
10月20日 高宗の第7男子李垠誕生(母は露館播遷で同行した女官厳氏(厳妃))
余談ですが、太宗の次の皇帝となった純宗には子がなく、異母弟の李垠が大韓帝国最後の皇太子となった人物で、梨本宮方子と政略結婚。第二次世界大戦後、帝政復古を疑った李承晩の妨害や日韓の国交正常化に時間を要したことで簡単には日本から祖国韓国へ帰国できず、ようやく帰国を果たしたのは日韓基本条約締結の2年前の1963年11月で、方子夫人と夫婦ともに韓国へ渡るも、病身であったため金浦国際空港からソウルの聖母病院へと直接運ばれ、1970年4月28日、結婚生活50周年の金婚式を病院で開くも、その3日後に病院で死去。李垠は皇帝への即位はなかったが、朴正煕の許可を経て王家の宗廟である永寧殿に「懿愍太子」の諡号で位牌が納められたそうです。
つづく
引用:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%94%E5%A6%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AC%E5%8D%88%E8%BB%8D%E4%B9%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%A2%E6%9D%A1%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%82%E5%A4%AA%E9%83%8E
産業革命後の西欧諸国が次々と近代国家となる中で、アジアの中でいち早く、自力で近代国家に変貌できたのは唯一日本のみであった。この頃の清も李氏朝鮮もそれぞれ「末期的」な様相を呈しており、それ故にこれらの国々はその様々な権益を欧米諸国に売り渡すという「草刈り場」(半植民地状態)になっていった。
李氏朝鮮の「末期的な状況」の中身として、為政者の権力闘争、様々な権益の売却、ロシアによる半植民地化、各地で暴動発生、財政難、進まない改革など、様々な問題を抱えており、そこに日本がまず、李氏朝鮮の宗主国である清との衝突が生じ、その結果として日清戦争が勃発。その後もロシアとの交渉などを通じて朝鮮情勢にどんどん介入していったようなのである。(後には日露戦争にまで発展)
隣国とはいえ、なぜこのように他国の状況に介入していかなければならなかったのであろうか。
日本にとって歴史上の最悪の凶事「日韓併合」に至った経緯として李氏朝鮮時代末期の朝鮮半島の状況をみてみることに。
まず、李氏朝鮮という国家は清の柵封体制のままであったこと、近代国家としての要件である近代法体系の不備、国民の教育水準が低く人材が欠如していたこと、産業基盤が殆どなく、資源に乏しく、財政難であったことなど様々な問題を抱えていたようだ。
19世紀後半に列強の帝国主義政策が東アジアにまで及ぶと、1875年(明治8年)の江華島事件を契機に翌1876年(明治9年)に日本と締結した日朝修好条規を始め、李氏朝鮮は米国や仏国などの欧米諸国と不平等条約を結ぶ。
■李氏朝鮮末期の為政者の権力闘争(閔妃 vs 大院君)、閔妃によるクーデター
世継ぎ問題などで大院君と権力争いをしていた閔妃は、高宗が成人して親政をとるようになると、1873年(同治12年)、ロシア軍の力を借りてクーデターを起こし大院君を追放。大院君とその一派を失脚させた。そして自分の一族(閔氏)を高官に取り立て、政治の実権を握った。大院君はその後京畿道楊州に隠居させられたが、閔妃の存在を国家存続を脅かすものとして政局復帰、閔妃追放の運動を始め、それが朝鮮末期の政局混乱の一因にもなった。
両者の権力闘争は敵対者を暗殺するなど熾烈なもので、1874年11月には閔妃の義兄の閔升鎬が自宅で爆弾によって暗殺された。閔妃は大院君の仕業と信じ、申哲均の食客で張という姓の者を捕えた。更に申哲均は大院君の腹心だったため、簡単には死なないようにする惨い拷問の末に獄死させた。これは大院君の恨みを買い、双方で暗殺が続き国内が乱れた。大院君は自身が国のために貯めておいた国庫を空にする無駄遣いを繰り返す閔妃暗殺のために、閔妃によって親族や親友を殺された者から暗殺者を募り始めたいう。
■開化党(日本より) vs 大党(清より)の対立
朝鮮国内では清国との冊封体制を脱して近代化をすべきだという者(開化党)と、清国との関係を維持すべきだという者(事大党)とが対立。
そうした中で1882年(明治15年)、両派の暗闘から壬午事変(注1)が起こり、日本公使館も暴徒に焼き討ちされて死亡者が発生。公使館保護を名目とする日本と、朝鮮を属国と主張する清の両国は鎮圧を理由としてともに出兵、日清の対立は決定的となった。
(注1)壬午事変 (じんごじへん):
1882年(明治15年)7月23日(旧暦では光緒8年=高宗19年6月9日)、興宣大院君らの煽動を受けて、朝鮮の首府漢城(現、ソウル)で起こった閔氏政権および日本に対する大規模な朝鮮人兵士の反乱(壬午事変 じんごじへん)が起こる。朝鮮国王高宗の王妃閔妃を中心とする閔氏政権は、開国後、日本の支援のもと開化政策を進めたが、財政出費がかさんで旧軍兵士への俸給が滞ったことが反乱のきっかけとなった。
閔氏政権は近代的軍隊として「別技軍」を新設し、日本人教官を招致して教練を開始したが、これに反発をつのらせた旧式軍隊が俸給の遅配・不正支給もあって暴動を起こし、それに民衆も加わって閔氏一族の屋敷や官庁、日本公使館を襲撃し、朝鮮政府高官、日本人軍事顧問、日本公使館員らを殺害。朝鮮王宮にも乱入、閔妃は王宮を脱出。反乱軍は閔氏政権を倒し、興宣大院君を担ぎ出して大院君政権が再び復活。
日本は軍艦4隻と千数百の兵士を派遣し、清国もまた朝鮮の宗主国として属領保護を名目に軍艦3隻と兵3,000人を派遣した。反乱軍鎮圧に成功した清は、漢城府に清国兵を配置し、大院君を拉致して中国の天津に連行、その外交的優位のもとで朝鮮に圧力をかけ、閔氏政権を復活させた。日本は乱後、清の馬建忠の斡旋の下、閔氏政権と交渉して済物浦条約を締結し、賠償金の支払い、公使館護衛のための日本陸軍駐留などを認めさせた。
清国は朝鮮政府に外交顧問を送り、李鴻章を中心とする閣僚は朝鮮に袁世凱を派遣、袁が事実上の朝鮮国王代理として実権を掌握。こののち袁世凱は、3,000名の清国軍をひきつづき漢城に駐留させた。この乱により、朝鮮は清国に対していっそう従属の度を強める一方、朝鮮における親日勢力は大きく後退。
1884年12月4日「甲申政変」
独立党(急進開化派)によるクーデター。親清派勢力(事大党)の一掃を図り、日本の援助で王宮を占領し新政権を樹立したが、清国軍の介入によって3日で失敗。
当時の朝鮮半島は、共に自らの勢力圏におさめようとする日本と清朝の対立の場でもあり、日本は権益を確立するため朝鮮に対する清朝の影響を排除する必要があった。
■東学農民運動
1894年1月上旬、重税に苦しむ朝鮮民衆が宗教結社の東学党の下で蜂起し農民反乱が勃発。東学党によって首都ソウルを脅かされた李氏朝鮮政府は、5月下旬に宗主国である清国の来援を仰ぐ。清国側の派兵の動きを見た日本政府も天津条約に基づいて居留民保護を目的にした兵力派遣を決定。6月5日に大本営を設置。
続々と押し寄せる日清双方の部隊群に驚いた朝鮮政府は慌てて東学党と和睦し、6月11日までに農民反乱を終結させると日清両軍の速やかな撤兵を求めたが、日本政府は両軍が派兵する場合は事前に通達する条約に清が従わなかった為、この事態を機に朝鮮への介入強化を恐れ政情が完全に安定するまでの撤兵を拒否。朝鮮政府に日本の助言を入れた国内改革を要求。日本に対抗する清国側もそのまま部隊駐留を継続。こうしてソウル周辺で日清双方の駐留部隊が睨み合う事になった
そして、1894年(明治27年)に日清戦争が勃発。
■日清戦争(1894年7月25日~1895年4月17日)後の「下関条約」(1895年4月17日調印、5月8日発効)
日清戦争には「日英同盟」「桂・タフト会談」の当事者で、首相在任日数最長(2886日)の桂太郎が名古屋の第3師団長として出征している。桂は日清戦争出征の後、台湾総督を経て、第3次伊藤内閣で陸軍大臣になり、続く第1次大隈内閣に次ぎ、第2次山縣内閣でも陸相とともに山縣の参謀格を務め、1900年に発生した義和団の乱では中国に軍を出動させた人物でもあるが、日韓併合の重要なキーパーソンなのである。
日本が勝利し、伊藤博文全権が起草・調印した「下関条約」により、大日本帝国は清国に朝鮮が自主独立国であることを認めさせ、李氏朝鮮から清国に対する貢献・臣下の典礼等を廃止させ、清の冊封体制から朝鮮を離脱させた。これによって第26代の高宗が中国皇帝の臣下を意味する「国王」の称号を廃して、はじめて「皇帝」と称することとなった。
「下関条約」は500年間中国(明、清)の属国であった李氏朝鮮を独立させた条約なのである。
■1895年10月8日閔妃暗殺事件(乙未事件)
ロシアと通じていた閔妃を日本軍が殺害したという見方もあり、これに関わった容疑で三浦梧楼以下48名、広島地方裁判所にて予審開始、1896年1月20日 三浦梧楼以下48名、証拠不十分で免訴となった。
1896年高宗勅令で閔妃殺害事件の犯人として特赦された趙羲淵、禹範善、 李斗璜、李軫鎬 李範来 権濚鎮の首を持ってロシア公館に持参せよと命令(当時高宗は露館播遷で、約1年間ロシア公館内に居住) 閔妃殺害事件についての再調査も実施され、漢城で発行されていた英文雑誌に調査結果が掲載された。
■太宗の「露館播遷都」(96年2月11日~97年2月20日)
1896年
2月5日 李範晋はロシアの指示で春川、忠清道で暴動を起こし、日本の電信線を切断し日本との連絡手段を遮断。
2月10日ロシア軍が王宮突入(107名の水兵 20名の食料担当兵 大砲一門を漢城に搬入。ロシア兵150名)
2月11日 宮女金明載より「各大臣等日本兵が密かに国王を廃位しようとしているので甚だ危険なり。速かに露館に播遷し回避されたし」旨の書状を高宗に届けられた高宗と世子(純宗)が宮女用のかごに乗り、ロシア公使館へに逃げ込み翌97年2月20日慶運宮へ戻るまでの約1年間、高宗と世子はロシア公館に移された(露館播遷)。
高宗がロシア公使館で政務を執り行った結果、親露派の政権の李氏朝鮮は財政不足から、不平等条約による治外法権どころか、様々な権益、鉱山の採掘権と森林伐採権、鉄道の施設権が欧米に売却され、李氏朝鮮は欧米の草刈り場状態となる。
こうしてロシアやロシア外も他の欧米列強も同等の利権を獲得することになった。 一国の元首が外国の公館内で1年匿われるなど常識的に異常な事態で、これは国としての自主性を放棄するのに等しく、後に日露戦争時に中立を宣言したが日露両国から無視されるような結果となった。
■ロシアの影響と半植民地化
権益を欧米に売却する国力の乏しい朝鮮を目の当たりにし、日本はロシアの朝鮮半島植民地化を恐れ、ロシアとの間で朝鮮問題について話し合いを開始。
1896年5月14日、日本とロシアは小村・ウェーバー覚書(注)を交わす。
(注)小村・ウェーバー覚書:
1896年5月14日ソウルにおいて日本側小村寿太郎、ロシア側 K.I.ウェーバーの両公使によって調印された朝鮮問題に関する日露間の覚え書。ロシア公使館にいる朝鮮国王の還宮実現の条件として両国軍隊の駐屯定員などを取決めている。
2月18日 仁川に4000余名の暴徒蜂起 官衙官宅を毀壊。
2月21日 各地に起こる暴動のうち 、内部参書官徐相潗と申大均は騷優地方坡州、開城、驪州、利川等に乱民鎮撫に関する勅諭頒示の為に向かう。
2月22日 内閣体制の更新。李範晋は法部大臣兼警務使となり大院君派の粛清を開始。
新内閣の公示
総理大臣に金炳始、内部大臣に朴定陽、軍部大臣兼警務使李允用、法部大臣に趙秉稷、学部大臣に李完用、宮内大臣に李載純を命じる。
3月16日 大院君一派の人々、漢城府観察使金経夏、呂圭亨等従犯等数十名を逮捕、裁判へ
3月27日 アメリカ、雲山の金鉱採掘権、 京仁線敷設権、 漢城の電灯・電話・電車の敷設権取得
4月22日 ロシア、慶源・鍾城両処の鉱山採掘権を取得
5月14日 日本・ロシア間で朝鮮問題に関し、第1次日露議定書調印。
5月22日 流刑10年に処せられた閔泳駿(後に閔泳徽と改名)、赦免となる。
6月9日 日本・ロシア間で朝鮮問題に関し、第2次日露議定書調印。
6月12日 ロシア、月尾島西南地段(44,316m2 年銀貨361元)租借契約を取得。
7月 フランス、京義線敷設権を取得
8月20日 機械厰でのロシア技士雇傭契約(機械士官Remnevに每年銀貨200元)
9月 ロシア、豆満江上流地域・鴨緑江上流地域・鬱陵島・茂山の森林伐採権(注)を取得
(注)森林伐採権:朝鮮王大院君はロシアに豆満・鴨緑両江から鬱陵島までの森林伐採権を20年間与えた。
11月21日 旧臣ら、高宗に還宮請願計画(未遂)
1897年
1月 ロシア人N・ビルコフをロシア語教師として雇用
2月13日 機械厰でのロシア技士雇傭契約(雇傭期間3年、俸給毎月銀貨260元、路費500元、帰路費800元、退職金2,000元)
2月20日 高宗ロシア公館から慶運宮に還宮(露韓播遷が終結)
7月、英国人の税関長ブラウンが財政顧問となる。
10月、ロシア公使シュペイエルが、財政顧問を英国人ブラウンを強制解任し、ロシア人キリル・アレキセーフへと変えようとする事件(度支顧問事件)(注2)が起きた。
(注2)度支顧問事件 (たくしこもんじけん):
1897年、高宗の即位に合わせて、ロシア公使アレクセイ・ニコラビッチ・シュペイエルが、大韓帝国の度支衛門 (日本の大蔵省相当)の顧問を、イギリスの推薦したジョン・マクレヴィ・ブラウンから自国人のキリル・アレキセーフに変えさせ、露韓銀行を設立した事件。これに反発したイギリスは東洋艦隊を仁川に派遣、朝鮮の「独立協会」は救国宣言上疏を行った。
厳密にはここまでが李氏朝鮮時代。
■国号の改元(1897年):李氏朝鮮→大韓帝国
1897年10月12日 大韓帝国へ国号を改める
もはや清の藩属国でなくなった以上、国王号を使用することは望ましくないという儒者の建言に従い以下の改革が実施、国号を「朝鮮」から「大韓」と改め、元号も前年のグレゴリオ暦への改暦にともなって定めた「建陽」から「光武」に改元。
高宗は、圜丘壇を新たに設けて10月12日に祭天の儀式を行い、翌13日に詔を出して皇帝に即位した。その後、清の冊封の象徴であった「迎恩門」や「恥辱碑」といわれる大清皇帝功徳碑を倒して「独立門」を立て独立を記念
10月20日 高宗の第7男子李垠誕生(母は露館播遷で同行した女官厳氏(厳妃))
余談ですが、太宗の次の皇帝となった純宗には子がなく、異母弟の李垠が大韓帝国最後の皇太子となった人物で、梨本宮方子と政略結婚。第二次世界大戦後、帝政復古を疑った李承晩の妨害や日韓の国交正常化に時間を要したことで簡単には日本から祖国韓国へ帰国できず、ようやく帰国を果たしたのは日韓基本条約締結の2年前の1963年11月で、方子夫人と夫婦ともに韓国へ渡るも、病身であったため金浦国際空港からソウルの聖母病院へと直接運ばれ、1970年4月28日、結婚生活50周年の金婚式を病院で開くも、その3日後に病院で死去。李垠は皇帝への即位はなかったが、朴正煕の許可を経て王家の宗廟である永寧殿に「懿愍太子」の諡号で位牌が納められたそうです。
つづく
引用:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%94%E5%A6%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AC%E5%8D%88%E8%BB%8D%E4%B9%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%A2%E6%9D%A1%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%82%E5%A4%AA%E9%83%8E