『みんなの椅子 ムサビのデザインⅦ』を観た。その1 よりつづく
2章「トーネットとデザイン運動」です。
2-06 アドルフ・ロースのムゼアムチェア 1899年の初号はヤコブ&ヨーゼフ・コーン製造。
順番通りではないけれど、出展されている曲木椅子のなかではこれが一番気に入ったのでトップ。曲木のしなやかな曲線と籐の座面が軽やかだ。
トーネットの特許が切れた頃に作られたものだそうで、トーネットで一番売れたNo.14の背もたれの上縁を少し窪ませたデザイン。座面の前と後ろも同様に窪ませ 背もたれの材の太さに緩急をつけたことで、量産品っぽいNo.14よりもずいぶん優美に見える。

実家ではNo.209とNo.18を使っていたのでトーネットの曲木椅子にわたしはとても親しみがある。
No.209(ウィーンチェア)は子どもの頃だと思いっきり深く座ると腰から後ろに転げ落ちる代物だった。
No.18は輸出用で海外ではむしろNo.14より有名だそうだが、実家で使っていたのは座面が籐で座面下の補強が輪になっていないタイプだ。画像検索するといくつか別のタイプが出てくるのだが、時期や工場が異なるせいもあるらしいし、特許が切れてから作られたリプロダクト物なのかもしれない。実家で使っていたのは 秋田木工 あたりかな?こんど帰ったら椅子の後ろをよく見ておこう。
No.18はNo.14によく似ているが、背もたれの中2本が座面から伸びている。
今回はNo.14の写真は撮っていないが、下の写真↓に赤いものがチラと写っている。ちなみにNo.14は1859年初号からその後40年間の間に5000万脚売れたらしい。
トーネット といえばミヒャエル・トーネットが1830年にドイツで始めた曲木椅子メインの家具メーカーのことで、1841年にウィーンに拠点を移した。そこでカフェ・ダウムの注文で作ったNo.4↓をはじめ、一般向けの低廉で良質な椅子をどんどん作った。1851年にはクリスタルパレスで有名なロンドン開催の第1回万国博覧会に出品し注目を集めた。
1920年代なかばにはバウハウスのミース・ファン・デル・ローエやマルセル・ブロイヤーのデザインしたスチールパイプを構造に用いた椅子を作り始め、曲木以外のモダンな路線を切り拓いた。トーネットは時代に左右されないデザイン・機能性を持つ家具メーカーの老舗だ。
2-01 ミヒャエル・ト―ネットのカフェ ダウム(NO.4 /V-400P) 1849年の初号はTON[トーネット]製造

19世紀半ばは産業革命を経て都市改造、科学技術の発達など近代化が進み、ブルジョワジーが社会を大きく動かすようになった時代だ。木材を蒸して治具にあわせて曲げるトーネットの曲木の技術は産業革命がなければ実現しなかった。情報伝達も流通も拡大しスピードアップした。椅子も大量生産されたのだ。
浜松市楽器博物館でピアノを見たり、武田尚子『チョコレートの世界史』を読んだが、現在のような身の回りに物がいくらでもあるような生活はブルジョワジーがどんどん出てきたここら辺から始まっているのだなあ、と最近になって世界史で習ったことを実感するようになった。
大量生産するようになるとつきものなのが原材料の枯渇だ。トーネットも曲木椅子の材料のブナを求めて工場をチェコのコリッチャヌイに移し、他にも工場をいくつも建てた。また工場を動かすのに大量のエネルギーが必要になるが、ポーランドのノヴォ・ラスドムスクの工場は炭鉱の近くだ。
2-05 ミヒャエル・ト―ネットのトーネットロッキングチェア(No.825) 1890年頃の初号はゲブリューダ・トーネット製造。 くるくるした脚がたまらない。

ちょいと寄り道をしてイギリスだ。
2-10 フィリップ・ウェブのサセックスチェア。1860年頃の初号はモリス商会製造。 スピンドルで挽いたパーツが印象的だ。丁寧な印象と民芸っぽい味わいがうまく融合していると思う。
ウェブはイギリスのアーツアンドクラフツ運動で重要な役割を果たした。アーツアンドクラフツ運動で一番有名なのはウィリアム・モリスだろうけど。 そしてその流れは巡り巡って日本の民芸運動にも影響を与えるのだ。

モリスのデザインは好きだが、モリス、バーン・ジョーンズ、ロセッティの泥沼の女性関係には辟易する。作品と人格は分けて考えるべきだ、と思ってはいるんだけどね。 ノラの絵画の時間 3分でわかるウィリアム・モリス モリス商会を設立したモダンデザインの父、ウィリアム・モリスの生涯と作品 ←フィリップ・ウェブの名がチラと出てくる。
話はトーネットに戻る。
2-07 アームチェア(No.81) デザイナーは不明だが1900年頃の初号はゲブリューダ・トーネット製造だそうだ。トーネットの割に曲木の曲線が少ないな、と思うも、3本脚をつなぐ2本の曲木は印象的だ。別の角度から写真を撮ればよかった。ぜひリンク先で別角度写真を見てほしい。

2-11 ヨーゼフ・ホフマンのNo.728(No.T760PF) 1905年の初号はゲブリューダ・トーネット製造。
アールデコっぽい。当然だ、ホフマンだもの。

ホフマンはウィーン工房のデザイナー/建築家だ。産業革命の進行で大量のものが生活に浸透してきたが しばしば粗悪で悪趣味なものもあって、生活の質を見直そうという意識が出てきた。アーツアンドクラフツ運動だ。産業革命はイギリスから始まったのでアーツアンドクラフツ運動がイギリスから始まったのも納得する。そしてその考え方を取り入れたホフマンとデザイナー コロマン・モーザーが実業家フリッツ・ヴェルンドルファーの支援を受けて1903年に設立したのがウィーン工房だ。ウィーン工房を画像検索すれば、いかにもアールデコというものをいくつも見ることが出来る。そして、わたしはアールヌーヴォーよりアールデコの方が好きだ。
ええっと、これでイギリスのフィリップ・ウェブの寄り道を回収したことにする。
トーネットってアールデコには見えないよ、って思うけど、なるほどトーネットはホフマンと同じウィーンだし、ホフマンデザインのトーネット製造ではアールデコに見えるね。
2-12 ヨーゼフ・ホフマンのフレダーマウス(No.T760) 1905年の初号はゲブリューダ・トーネット製造。 背もたれが布張りではなく横木の桟になっているものもあるらしい。フレダーマウスというのはコウモリという意味だそうで、キャバレーの名前なんだそうだ。

2-13 ヨーゼフ・ホフマンのジッツマシーネ 1908年頃の初号はヤコブ&ヨーゼフ・コーン製造。 トーネットじゃない、と思うもヤコブ&ヨーゼフ・コーン社は曲木家具も製造し、最終的にはトーネット社に吸収された。一番上のムゼアムチェアも初号はヤコブ&ヨーゼフ・コーン社製造だったね。
クッションがないと痛くて座れないだろうなあ。座面の下からオットマンを引き出すことが出来るようだ(リンク参照)。オットマンの脚はどこに収納されているんだろう?

アップ。キノコのような突起は飾りかと思いきや、機能がある。背もたれの傾きを変えられる。

2-14 オットー・ワーグナーのウィーン郵便貯金局の椅子(No.247P) 1902年の初号はヤコブ&ヨーゼフ・コーン製造だが、展示された椅子は1985年ゲブリューダ・トーネット製造。この椅子 好きだなあ。

オットー・ワーグナーはホフマンの師匠。ワーグナーと弟子たちの団体はクンストラーハウスというが、そこからクリムトらが抜け出てウィーン分離派となった。そしてどちらの団体も現在まで存続しているらしい。
2-16 チャールズ・レ二―・マッキントッシュのウィロー(No.312) 1904年の初号はアレックス・マーチン製造。
チャールズ・レ二―・マッキントッシュといえばヒルハウス1(No.292)2-15 が有名で、この写真の右後ろに写っている。ラダーバック(背中が梯子)という方が有名かな?

ウィローはちょっと特殊な用途なんだそうで(上記2-16リンク参照)それならば座り心地が悪くても仕方がないな。
そしてヒルハウス1もかなり座り心地が悪い。本物には座ったことがないが、模した椅子を川島テキスタイルスクールの寮で使っていたのだ。これが後ろにバッタンと倒れる危険なものだった。そのせいかな?ヒルハウス1は座らせない展示だよ。
『みんなの椅子 ムサビのデザインⅦ』を観た。その3 につづく
2章「トーネットとデザイン運動」です。
2-06 アドルフ・ロースのムゼアムチェア 1899年の初号はヤコブ&ヨーゼフ・コーン製造。
順番通りではないけれど、出展されている曲木椅子のなかではこれが一番気に入ったのでトップ。曲木のしなやかな曲線と籐の座面が軽やかだ。
トーネットの特許が切れた頃に作られたものだそうで、トーネットで一番売れたNo.14の背もたれの上縁を少し窪ませたデザイン。座面の前と後ろも同様に窪ませ 背もたれの材の太さに緩急をつけたことで、量産品っぽいNo.14よりもずいぶん優美に見える。

実家ではNo.209とNo.18を使っていたのでトーネットの曲木椅子にわたしはとても親しみがある。
No.209(ウィーンチェア)は子どもの頃だと思いっきり深く座ると腰から後ろに転げ落ちる代物だった。
No.18は輸出用で海外ではむしろNo.14より有名だそうだが、実家で使っていたのは座面が籐で座面下の補強が輪になっていないタイプだ。画像検索するといくつか別のタイプが出てくるのだが、時期や工場が異なるせいもあるらしいし、特許が切れてから作られたリプロダクト物なのかもしれない。実家で使っていたのは 秋田木工 あたりかな?こんど帰ったら椅子の後ろをよく見ておこう。
No.18はNo.14によく似ているが、背もたれの中2本が座面から伸びている。
今回はNo.14の写真は撮っていないが、下の写真↓に赤いものがチラと写っている。ちなみにNo.14は1859年初号からその後40年間の間に5000万脚売れたらしい。
トーネット といえばミヒャエル・トーネットが1830年にドイツで始めた曲木椅子メインの家具メーカーのことで、1841年にウィーンに拠点を移した。そこでカフェ・ダウムの注文で作ったNo.4↓をはじめ、一般向けの低廉で良質な椅子をどんどん作った。1851年にはクリスタルパレスで有名なロンドン開催の第1回万国博覧会に出品し注目を集めた。
1920年代なかばにはバウハウスのミース・ファン・デル・ローエやマルセル・ブロイヤーのデザインしたスチールパイプを構造に用いた椅子を作り始め、曲木以外のモダンな路線を切り拓いた。トーネットは時代に左右されないデザイン・機能性を持つ家具メーカーの老舗だ。
2-01 ミヒャエル・ト―ネットのカフェ ダウム(NO.4 /V-400P) 1849年の初号はTON[トーネット]製造

19世紀半ばは産業革命を経て都市改造、科学技術の発達など近代化が進み、ブルジョワジーが社会を大きく動かすようになった時代だ。木材を蒸して治具にあわせて曲げるトーネットの曲木の技術は産業革命がなければ実現しなかった。情報伝達も流通も拡大しスピードアップした。椅子も大量生産されたのだ。
浜松市楽器博物館でピアノを見たり、武田尚子『チョコレートの世界史』を読んだが、現在のような身の回りに物がいくらでもあるような生活はブルジョワジーがどんどん出てきたここら辺から始まっているのだなあ、と最近になって世界史で習ったことを実感するようになった。
大量生産するようになるとつきものなのが原材料の枯渇だ。トーネットも曲木椅子の材料のブナを求めて工場をチェコのコリッチャヌイに移し、他にも工場をいくつも建てた。また工場を動かすのに大量のエネルギーが必要になるが、ポーランドのノヴォ・ラスドムスクの工場は炭鉱の近くだ。
2-05 ミヒャエル・ト―ネットのトーネットロッキングチェア(No.825) 1890年頃の初号はゲブリューダ・トーネット製造。 くるくるした脚がたまらない。

ちょいと寄り道をしてイギリスだ。
2-10 フィリップ・ウェブのサセックスチェア。1860年頃の初号はモリス商会製造。 スピンドルで挽いたパーツが印象的だ。丁寧な印象と民芸っぽい味わいがうまく融合していると思う。
ウェブはイギリスのアーツアンドクラフツ運動で重要な役割を果たした。アーツアンドクラフツ運動で一番有名なのはウィリアム・モリスだろうけど。 そしてその流れは巡り巡って日本の民芸運動にも影響を与えるのだ。

モリスのデザインは好きだが、モリス、バーン・ジョーンズ、ロセッティの泥沼の女性関係には辟易する。作品と人格は分けて考えるべきだ、と思ってはいるんだけどね。 ノラの絵画の時間 3分でわかるウィリアム・モリス モリス商会を設立したモダンデザインの父、ウィリアム・モリスの生涯と作品 ←フィリップ・ウェブの名がチラと出てくる。
話はトーネットに戻る。
2-07 アームチェア(No.81) デザイナーは不明だが1900年頃の初号はゲブリューダ・トーネット製造だそうだ。トーネットの割に曲木の曲線が少ないな、と思うも、3本脚をつなぐ2本の曲木は印象的だ。別の角度から写真を撮ればよかった。ぜひリンク先で別角度写真を見てほしい。

2-11 ヨーゼフ・ホフマンのNo.728(No.T760PF) 1905年の初号はゲブリューダ・トーネット製造。
アールデコっぽい。当然だ、ホフマンだもの。

ホフマンはウィーン工房のデザイナー/建築家だ。産業革命の進行で大量のものが生活に浸透してきたが しばしば粗悪で悪趣味なものもあって、生活の質を見直そうという意識が出てきた。アーツアンドクラフツ運動だ。産業革命はイギリスから始まったのでアーツアンドクラフツ運動がイギリスから始まったのも納得する。そしてその考え方を取り入れたホフマンとデザイナー コロマン・モーザーが実業家フリッツ・ヴェルンドルファーの支援を受けて1903年に設立したのがウィーン工房だ。ウィーン工房を画像検索すれば、いかにもアールデコというものをいくつも見ることが出来る。そして、わたしはアールヌーヴォーよりアールデコの方が好きだ。
ええっと、これでイギリスのフィリップ・ウェブの寄り道を回収したことにする。
トーネットってアールデコには見えないよ、って思うけど、なるほどトーネットはホフマンと同じウィーンだし、ホフマンデザインのトーネット製造ではアールデコに見えるね。
2-12 ヨーゼフ・ホフマンのフレダーマウス(No.T760) 1905年の初号はゲブリューダ・トーネット製造。 背もたれが布張りではなく横木の桟になっているものもあるらしい。フレダーマウスというのはコウモリという意味だそうで、キャバレーの名前なんだそうだ。

2-13 ヨーゼフ・ホフマンのジッツマシーネ 1908年頃の初号はヤコブ&ヨーゼフ・コーン製造。 トーネットじゃない、と思うもヤコブ&ヨーゼフ・コーン社は曲木家具も製造し、最終的にはトーネット社に吸収された。一番上のムゼアムチェアも初号はヤコブ&ヨーゼフ・コーン社製造だったね。
クッションがないと痛くて座れないだろうなあ。座面の下からオットマンを引き出すことが出来るようだ(リンク参照)。オットマンの脚はどこに収納されているんだろう?

アップ。キノコのような突起は飾りかと思いきや、機能がある。背もたれの傾きを変えられる。

2-14 オットー・ワーグナーのウィーン郵便貯金局の椅子(No.247P) 1902年の初号はヤコブ&ヨーゼフ・コーン製造だが、展示された椅子は1985年ゲブリューダ・トーネット製造。この椅子 好きだなあ。

オットー・ワーグナーはホフマンの師匠。ワーグナーと弟子たちの団体はクンストラーハウスというが、そこからクリムトらが抜け出てウィーン分離派となった。そしてどちらの団体も現在まで存続しているらしい。
2-16 チャールズ・レ二―・マッキントッシュのウィロー(No.312) 1904年の初号はアレックス・マーチン製造。
チャールズ・レ二―・マッキントッシュといえばヒルハウス1(No.292)2-15 が有名で、この写真の右後ろに写っている。ラダーバック(背中が梯子)という方が有名かな?

ウィローはちょっと特殊な用途なんだそうで(上記2-16リンク参照)それならば座り心地が悪くても仕方がないな。
そしてヒルハウス1もかなり座り心地が悪い。本物には座ったことがないが、模した椅子を川島テキスタイルスクールの寮で使っていたのだ。これが後ろにバッタンと倒れる危険なものだった。そのせいかな?ヒルハウス1は座らせない展示だよ。
『みんなの椅子 ムサビのデザインⅦ』を観た。その3 につづく




















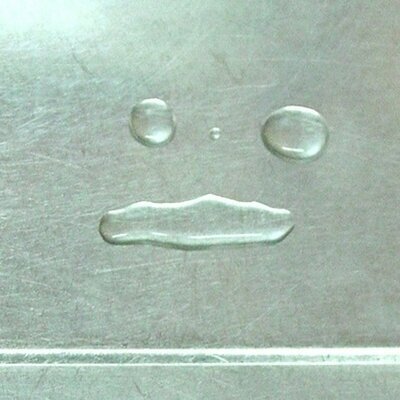






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます