トヨタ産業技術記念館に行った。繊維機械館編その1 よりつづく

お次は機(はた)。
↑この機は

である。
世界史の産業革命で必ず出てくる飛び杼(とびひ)です。分かりにくいが、筬框(おさかまち)の上の竹の小管のついた紐を引っ張ると開口した経糸(たていと)の間を杼が左右に行き来する、という発明。飛び杼/フライイング・シャトルはイギリス人ジョン・ケイの発明だ そうだ。世界史の先生、これ分かっていたかなぁ。
西欧の発明を取り入れた、とはいっても機は高機(たかはた)です。足元に緯糸(よこいと)を巻いた小管を入れた缶箱がなんかいい感じ。
豊田佐吉がバッタン高機を改良したもの。

↑この機は

である。
どこをどのように改良したのか、分かりやすい写真は撮らなかった。しかし、おねいさんの素敵な解説動画があったので貼る。★
杼を飛ばすための紐を引っ張る動作を筬の動きに組み込んだところが発明なんであるが、木と紐で制御するあたり、もう夏休みの工作級。こういうところから発明は始まるんだなあ。
そこからG型織機がずらりと並ぶ工場に至るわけだ。(この写真は2012年に撮ったもの)

工場の動力は天井の梁の上に渡った回転シャフトからベルトで織機に伝えられる。接触したら危なそうだなあ。
かつて紡織機の原動力として使われていたスイス スルザー社製の蒸気機関。1898年製のこれは高圧/低圧の2本のシリンダーと直径4.7mの巨大なフライホイールを備えていて9本のロープ伝動により発電機を回転させたらしい。

G型織機などもそうだが、なんか古い鋳物製の機械って現在のものにない優雅な味わいがあるんだよなあ、
お次はモーター。

その説明。

ロープの継ぎ方。

蛇足だが、高機より古い方式の腰機(こしばた)は伝統的な整経の写真の背景に写っている。経糸のテンションを体のつっぱりで保つタイプ。
再掲

トヨタ産業技術記念館に行った。繊維機械館編その3 へつづく

お次は機(はた)。
↑この機は

である。
世界史の産業革命で必ず出てくる飛び杼(とびひ)です。分かりにくいが、筬框(おさかまち)の上の竹の小管のついた紐を引っ張ると開口した経糸(たていと)の間を杼が左右に行き来する、という発明。飛び杼/フライイング・シャトルはイギリス人ジョン・ケイの発明だ そうだ。世界史の先生、これ分かっていたかなぁ。
西欧の発明を取り入れた、とはいっても機は高機(たかはた)です。足元に緯糸(よこいと)を巻いた小管を入れた缶箱がなんかいい感じ。
豊田佐吉がバッタン高機を改良したもの。

↑この機は

である。
どこをどのように改良したのか、分かりやすい写真は撮らなかった。しかし、おねいさんの素敵な解説動画があったので貼る。★
杼を飛ばすための紐を引っ張る動作を筬の動きに組み込んだところが発明なんであるが、木と紐で制御するあたり、もう夏休みの工作級。こういうところから発明は始まるんだなあ。
そこからG型織機がずらりと並ぶ工場に至るわけだ。(この写真は2012年に撮ったもの)

工場の動力は天井の梁の上に渡った回転シャフトからベルトで織機に伝えられる。接触したら危なそうだなあ。
かつて紡織機の原動力として使われていたスイス スルザー社製の蒸気機関。1898年製のこれは高圧/低圧の2本のシリンダーと直径4.7mの巨大なフライホイールを備えていて9本のロープ伝動により発電機を回転させたらしい。

G型織機などもそうだが、なんか古い鋳物製の機械って現在のものにない優雅な味わいがあるんだよなあ、
お次はモーター。

その説明。

ロープの継ぎ方。

蛇足だが、高機より古い方式の腰機(こしばた)は伝統的な整経の写真の背景に写っている。経糸のテンションを体のつっぱりで保つタイプ。
再掲

トヨタ産業技術記念館に行った。繊維機械館編その3 へつづく




















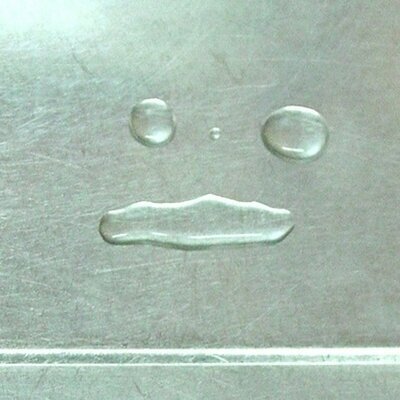





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます