10.後三年前夜
前九年の戦いから20年。
その間に,清原氏は武則-武貞-真衡と,急速に世代交代が進んだ。
武則は鎮守府将軍任官直後に没し,武貞も短命だったと思われる。
武貞長子真衡が家督を継ぎ,やがて後三年の合戦が始まるまでの間,清衡とその母がどのような思いで日々を過ごしたかは想像するしかないが,非業の最期を遂げた父経清のことを忘れることはなく,臥薪嘗胆を誓ったものであったことだろう。
母は清原の人となり,清衡も決して目立たず,波風立てぬように暮らしていたのだろう。
安倍氏の往事を知る人々にとっても,昔日の栄光は次第に過去のものとして,風化していくように思われたかも知れない。
歴史の歯車が動き出したのは,永保3(1083)年のことである。
既に清衡は26歳の青年になっていた。
異父弟の家衡は7つ下の19。
異母兄の当主真衡は30~35ぐらいだろうか。
その真衡には子がいなかったので,海道小太郎成衡という者を養子に迎えていた(つまり,この時点で清衡と家衡の相続権は無くなった)。
海道とは変わった姓だが,現在の福島県浜通地方にあった岩城,楢葉,磐前,菊多各郡を総称して海道四郡と呼んだので,おそらくその地に根を張った平氏の一族と思われる。
また,成衡の妻は源頼義娘にして義家弟であった。
父は,常陸の豪族である多気氏というから,これまた平姓である。
つまり真衡は,常磐地方の豪族から養子と嫁を貰ったことになり,しかも源氏にも平氏にも関係する者との縁組みが成立したことになる。
奥州を固める上で,順当な布石と言えよう。
その成衡の婚礼の場で事件が起こった。
前九年の戦いで功があった清原一族の長老(妻が武則娘なので真衡叔父)である吉彦(きみこ)秀武が祝物として朱塗りの盤に,この地方特産の砂金を堆く盛って地面に跪いていた。ところが,屋敷内の真衡は護持僧の奈良法師との囲碁に夢中で,秀武に気付かない。
或いは,日頃から口うるさい長老をからかうつもりだったのかもしれないが,秀武はキレた。
頭上に捧げ持った朱の盤を砂金ごと投げ出すと,家臣を引き連れて出羽へ帰ってしまった。目出度い婚礼の席が,おそらく真衡の怒号が響く散々なものとなったことだろう。
怒った真衡は,秀武討伐を目論んで兵を起こす。
世に云う後三年の役は,ここに始まった・・・。
(続く)










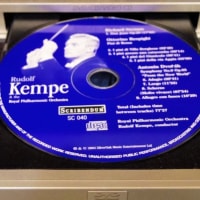
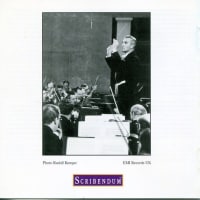
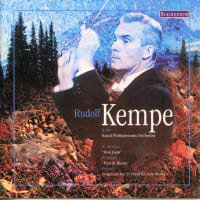







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます