2019.7.25高橋洋一 (元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)
日本の解き方
MMT(現代貨幣理論)の提唱者の1人とされるステファニー・ケルトン教授が来日し、話題となった。
筆者はMMTの「教科書」とされている書物を読んだが、モデルが数式で構成されていないので分かりづらかった。筆者の周りの経済学者にも似たような印象を持っている人は少なくない。
数式モデルを勝手に想像してみると、おそらくリフレ政策と同じだろうという結論だった。そこで、日本でMMTを提唱している人たちに問い合わせると、予想通り、リフレ政策と同じという回答だった。
リフレ政策は、(1)ワルラス式(2)統合政府(3)インフレ目標-が構成要素だ。読者の中には、モデル式なんてどうでもいい、過去の自然科学の歴史の中には式なしの発想も大発見になった例もあるという人もいるかもしれない。数学言語が未発達な昔にはそうした事例もなくはないが、今では科学で数式モデルは必須だ。アインシュタインの相対性理論もリーマン幾何学とテンソル解析で書かれている。
何より、数式モデルがないと学者レベルだと相手に誤解を与えるので、この意味で数式モデルは今や必須だ。
リフレ政策のモデルは統合政府なので、財政政策も金融政策もどちらも協力すれば有用だ。インフレ目標までは、国債買い入れの金融緩和と国債発行の積極財政の合わせ技、政府通貨発行による積極財政など、いくらでも多種多様な政策を考えることができる。その場合、一般的に統合政府のバランスシート(貸借対照表)は改善するので、財政赤字や財政破綻も考えなくてもいい。これは、MMTでも強調されている。
しばしば、リフレ政策は金融政策ばかりで財政政策を考えていないという批判者がいるが、それは間違いだ。筆者が20年ほど前に書いた書物では、上記の数式モデルとともに、財政政策と金融政策の同時発動、さらには政府通貨発行まで書いてある。
米国の正統派経済学者からMMTは批判されるが、感情的なものを除けば、数式モデルが欠如しているわりに政治的な影響力を持っていることが原因なのだろう。
筆者に「MMTの数式モデルはリフレ政策と同じ」と伝えた人についても、政治的意味合いから誰なのか明言できない。邪推するに、リフレ政策と同じだと、政治的に「新しい」と言えなくなる。まして安倍晋三政権と根っこが同じということでは、政治運動に不都合だからだろう。
MMTとリフレが異なる点は、ケルトン氏が「利上げが物価上昇要因」としていることだ。そのロジックは、立憲民主党の枝野幸男代表が述べていた「利上げは経済成長要因」と似ており、利子所得者の購買力が増すからという。
資金を借りて事業を行おうとする者と、資金がありそれで消費する者を比べると、前者のほうが社会に活力を与える。この考えから、ケルトン氏の意見は、枝野氏と同様におかしいといえる。(元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)
髙橋 洋一(たかはし よういち、1955年(昭和30年)9月12日 -65歳 )は、日本の経済学者。学位は博士(政策研究)(千葉商科大学・2007年)。
財務官僚(大蔵官僚)として、理財局資金企画室長[3]、プリンストン大学客員研究員[3]、内閣府参事官(経済財政諮問会議特命)[3][1]、総務大臣補佐官[1]、内閣参事官(内閣総理大臣補佐官付参事官)[3][1]などを務めた。内閣参事官を退官後に金融庁顧問[3]、大阪市特別顧問(橋下市政)を務めた。退官後、東洋大学教授を経て、現在は嘉悦大学教授[4]。
官僚国家日本を変える元官僚の会幹事長[5]。株式会社政策工房代表取締役会長[3]、NPO法人万年野党アドバイザリーボード。内閣官房参与(経済・財政政策担当)










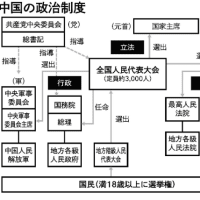


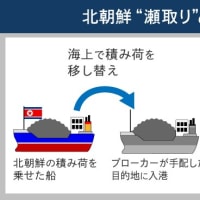

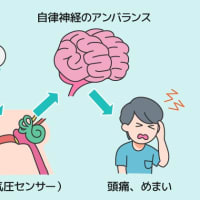

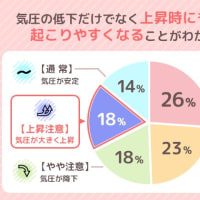
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます