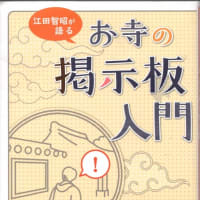お正月。神社や寺にお参りしてお札を求める方も多いでしょう。松岩寺でも三が日に祈禱したお札を檀家さんへ配ります。そのお札についての言葉を新年のことばとしました。
言葉の主であるベルナール・フランク(一九二七~一九九六)さんは、フランスの日本学研究者です。フランク氏は昭和二十九年に初来日して以来、四十年間にわたる幾度かの日本滞在で「北は青森から南は鹿児島まで、時間の許す限り精力的に歩き廻り、住職や参詣者と語り合い、雰囲気にふれ、お札を買って帰った」。
それらのお札が今も、パリのカルチェ・ラタンにあるコレージュ・ド・フランス(国立特別高等教育機関)には、保管されているというから楽しくなりませんか。
集めた札は千余、巡った寺社は二千にのぼるという。フランク氏の日本滞在は「統べればほぼ八年」だといいますから、おおかた毎日新しい寺を訪れて、お札を求めていた勘定になります。
お札は「お姿」あるいは「御影札」と呼ばれる絵札と、字句だけの文字札に二分されます。フランク氏は、神仏の図像がある絵札に興味をもちました。なぜそれほどまでにお札に魅了されたのか。フランク氏は記述しています。お札の無数とも思われるヴァリエーションは、「宗教に対する日本人の柔軟性、寛容性の証しであり、またその想像力の豊かさを示している」から、と。そして、コレクションから約二百点を載せて分類解説したベルナール・フランク著『「お札」にみる日本仏教』(藤原書店)は、仏教概論になっているから驚かされます。概論って、全体の内容を要約して述べることでしょう。全体をつかんでいないと書けないわけで、お札という身近な品物から仏教を論じているからわかりやすい。
さて、そうしたお札の効用はどこにあるのか。数年前の夏、私は京都の愛宕山に登りました。愛宕山には火伏せの愛宕神社があります。山頂の社務所には「火廼要慎」のお札の隣でシキビの枝を売っていました。竈(くど)を使っていた昔、毎朝最初に火をおこすとき、シキビの葉を一枚いれると火事にならないという慣わしからだといいます。緑色の葉一枚に防火の効能があるわけではない。葉を一枚手に取ることで、その日の安全を決意して点検したのです。
お札には、今の自分の状態を点検する効用があります。点検する機会を与えてくれる代物だから、よく見えるところへ置かなくては意味がない。この話、もっと詳しく知りたいと言う方は、花岡博芳著『またまたおうちで禅』の「カルチェ・ラタンにお札がある」(93ページ)を読んでみて!
「もう読んだ」という方は……、ありがとうございました。