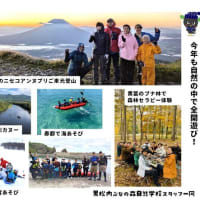まむがコーディネイトする「田舎の自然学校スタッフ養成・公開講座」の3回目は、
野山から畑から、草木が抱いている色をいただきます と題して、札幌の石川真代さんを講師に、草木染をテーマにした1泊2日の体験活動でした。
第1日目の今日は、野山や畑の植物を使ったに出した液で染める活動でした。もう九月になった秋のさわやかで柔らかな日差しの中で、スローな一日を過ごしました。田舎の大人の自然学校は、こうじゃあなくちゃあというような絶好なお日和でした。


まずは、ヨモギを皆さんで摘んできてというよりか、もはや刈り取ってきて葉っぱを取り外します。 クルミとキハダは山から事前に頂いてきました。時間があればそれも取ってきたかったなあ・・・。 事前に刈り取っておいた藍は醗酵をさせるために拡販し、ちょっとお酒や蜂蜜を入れて色合いを安定させました。こちらは明日使う予定です。

農家より手に入れていた大きな鉄鍋や鍋に湯を沸かし、染色材料をグツグツと煮出しました。火の番をする人、ヨモギの葉を摘む人、ビールを飲んでいる人・・ゆったりとした時間ですが、染物をするという目標がある共同作業は日ごろ知らない人であっても、打ち解けるのも早いような気がします。



大鍋はヨモギ、写真右から クルミ、キハダ、玉ねぎの皮の煮だし汁です。十分に煮出したところに、呉汁(大豆の汁、今回は豆乳)の植物性タンパク質をつけ色素を染まりやすくした木綿や絹を入れ一度乾かしておきます。
それから、紐や輪ゴムで石や棒を鋏んで絞った後に、15-20分くらい煮出した液で釜茹でします。その後、素材の色を定着・発色させる媒染液に浸した後に水洗いをします。今回は明礬と鉄釘を酢と煮た鉄漿(おはぐろ)液を使いました。



みなさん、なかかな芸術的に染まりました。 キハダの色合いにはビックリしました。古代社会の上層階級は、きっと想像する以上にカラフルな色合いの世界だったんだろうなあ・・・と思えるほどにくっきりと鮮やかでありました。
明日は藍染をします。
同じ仕事をした仲間同士・・・夕食も楽しかった。